RIM 環太平洋ビジネス情報 1998年10月No.43
アセアン4の電力インフラ整備の現状と課題
電力セクターを中心に
1998年10月01日 さくら総合研究所 川手潔
はじめに
今回の通貨危機が、アジアのインフラ事業に与えた影響は甚大であった。アセアン4(タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン)では、為替差損によって電力セクターの業績が悪化し、特に影響の大きかったタイやインドネシアでは、発電計画の下方修正が行われるに至った。
アセアン4では、1990年代にかけて、発電設備は急速に整備されてきた。しかしその一方で、送電・配電整備や、電力供給の効率化対策などの質的整備は、十分に施されてきたのだろうか。今後のアセアン4における電力インフラ整備の課題を検討するには、このような問題点を念頭に置きつつ、電力セクターに内在する構造的問題を理解する必要がある。そこで本稿では、アセアン4における電力インフラ整備の背景と現状を踏まえながら、各国の電力セクターが抱えている構造的問題を中心に検討し、今後の課題について言及したいと思う。
なお、アセアン4各国の電力セクターとして、タイのタイ発電公社(EGAT)、マレーシアのテナガ・ナショナル(TNB)、インドネシアの電力開発庁(PLN)、そしてフィリピンの国営電力会社(NPC)を対象とした。
I.電力インフラ整備の背景と現状
1.発電整備が拡大した背景
(1) 持続的経済成長と電力需要量の伸び
アジア諸国では、経済成長に伴う工業化、所得水準の向上、都市化の進展により、電力需要量が大幅に増大した。図1をみると、アジア諸国の電力需要量は、GDP成長率とほぼ均衡する形で伸び、アセアン4の中では、アセアン4の中では、マレーシア、タイ、フィリピンにおいて、需要量がGDP成長率より速いペースで伸びてきたのがわかる。各国とも、このような電力需要量の伸びに合わせ、発電設備の増強が図られた。図2の世界の発電設備の伸び率をみても、アジア諸国は相対的に高い値を示している。なかでも、アセアン4の発電設備は、全体で56ギガワット(GW)と、世界的にみて規模は大きいとはいえないが、その伸び率は9.4%と、顕著な伸びを示している。
(2) 民活インフラ整備の寄与
このような発電設備の増強に寄与したのが、民活方式による発電事業の導入である。90年代初頭、アジア諸国では、財政不足や、むやみに外貨資金調達の増加を図ることに対する警戒心があった。さらに、国内のインフラ事業を運営するのは国営企業などの公的部門で、そこには効率的なインフラ・サービスを提供する技術、人材、ノウハウが不足していた。その解決方法として、これまで公的部門が担っていたインフラ整備の一部を民間企業、特に外資に委ね、それによって事業効率化を図ることが民活インフラ整備のニーズとなり、民間外資の投資機会となった。
アセアン4をみると、フィリピンが90年にBOT(Build-Operate-and-Transfer)法を制定したのを機に、他の3カ国も 90~94年にかけて、独立発電事業体(IPP:Independent Power Producer)の導入に関するガイドラインを設定、民活発電プロジェクトが推進されてきた(表1)。すでに、操業しているIPPが国内発電設備の2~3割に達しているマレーシアやフィリピンに比べ、タイやインドネシアでは導入が遅れている。しかし、インドネシアでは、95年のパイトン I 石炭火力発電所の入札以降、矢継ぎ早にインフラ整備に民活方式を採用している。また、タイでも、95年にIPPの入札を開始して以降、3,800メガワット(MW)をIPPから調達する計画を立て、98~99年に第1号のIPPが操業する予定である。
他方、投資家サイドでも、ホスト国側の投資環境の整備が進むに従い、日米欧のコントラクターが自らの投資対象分野として、アジア発電市場の開拓に乗り出した。なかでも、欧米電力会社の進出が多い理由は、欧米諸国における公益事業の規制緩和・民営化や電力市場の成熟化の中で、企業間競争が激化し、海外発電市場に目を向けるようになったからである。
2.通貨危機の影響と対応
民活インフラ整備に支えられ、軌道に乗るかにみえたアセアン4の発電事業であるが、97年7月のタイにおけるバーツ切り下げ以降、アセアン4全体に波及した現地通貨の下落は、為替変動リスクとなって、電力産業全体に打撃を与えることになった。そこで、ここでは民活発電プロジェクトを中心に、通貨危機の影響と対応をみてみたい。
(1) 現地政府・電力セクターへの影響と対応
通貨危機によるアセアン4の電力セクターへの影響度は、当該国の(1)通貨の下落率、(2)電力セクターの外貨建て債務の比率、および買電契約(PPA:Power Purchase Agreement)上の基準通貨が何か、(3)燃料となる一次エネルギー資源の国内での調達度、またその国内燃料価格に対する政府補助金支給の割合、などによって国別に異なる。ただし、アセアン4のうち、タイだけはPPA上の基準通貨がバーツ建ての固定レートであり、契約上、為替変動リスクはIPP側に帰属する(表1)。しかし、バーツの下落率が大きく、今後のIPP事業に支障をきたす恐れから、EGATは、買電価格の8~9割を米ドル建てに変更するなど、相応のリスク負担に応じている。
結果として、アセアン4では、民活プロジェクトの為替変動リスクは、実質的に電力セクター側が被ることとなった。表2の通り、タイ、マレーシア、インドネシアでは、主要プロジェクトの延期がみられる。特に影響の大きいタイとインドネシアでは、電力需要の下方修正を行ったり、PPAに定めた条項に関し、IPPと再交渉せざるを得ない状況に陥っている。
(2) IPPへの影響と対応
IPPは、少なからず為替変動リスクを回避できたとはいえ、今後の現地政府・電力セクターとのPPAの再交渉が長引けば、IPP側にとっては、契約関係者との交渉コストの増加、借入条件の厳正化、さらにはプロジェクト自体の遅延による完工リスクが高まることになりかねない。インドネシアでは、電力需要の先行き低迷から、PLNが電力買い取り保証を、現行の80~90%から30%へ引き下げる方針である。また、このような状況の中で、IPPの売電収入に対する現地政府の外貨変換保証が維持されるのかといった懸念も出始めている。他方、タイでは、IPPの外資系スポンサーが出資比率を50%以上に増資することで信用力を強化し、国際シンジケート団やタイ産業金融公社から金融支援を獲得するなどの対応もみられ始めている。このように、通貨危機の影響の大きい両国でも、IPPの影響や対応には違いがみられる。
3.発電設備に偏重した電力インフラ整備
これまで、電力インフラ整備の中でも発電部門を中心にみてきたが、電力インフラ整備全体としての現状はどうなのだろうか。
本来、電力とは、発電、送電、配電という、垂直に統合された技術の集積であり、電力はこのような電力系統を通じて最終需要家へ供給されるものである。したがって、電力インフラ整備には、発電、送電、配電の各部門へのバランスのとれた設備投資が必要となる。発電部門は、民活方式を導入することによって、設備が拡充されてきた。他方、送電・配電部門は、電力の安定的供給と供給信頼性の維持が名目となり、その設備投資や事業運営は民間には開放されていない。
また、各国の財政事情を勘案すると、送電・配電整備は遅れ気味であると推測できる。例えば、地方村の電化率(注1)をみると、フィリピンでは52%(94 年)、インドネシアでは31%(93年)、さらにマレーシアでは、サラワク州が62%(94年)、サバ州が8%(94年)と、地方への送電網整備が遅れている。タイでは、地権問題、収用地に対する補償費の高騰、環境問題などに直面しており、送電・配電整備が計画通りに進んでいないのが実態である。実際、マレーシアやインドネシアの発電インフラに携わった日系エンジニアリング会社からのヒアリングでも、それらの国々では「昇圧用の変電所の設置や、既存設備の老朽化対策が不十分である」ことを指摘されている。
II.電力セクターにおける構造的問題
アジア諸国における民活インフラ導入の背景は、一つにはホスト国の資金不足、もう一つには電力セクター自体の非効率性にあった。では、電力セクターの非効率性とは何なのか。以下では、アセアン4の電力セクターにみられる非効率性を、組織面、財務面、技術面の3つの側面からとらえてみたい。
1.組織面
(1) 政府の直接的支援による非効率性
アセアン4の中では、タイ、インドネシア、フィリピンの電力セクターは、いずれも国営企業である。フィリピンやインドネシアでは、電力セクターに対し、政府補助金による補填が行われており、インドネシアのPLNは、政府への未払い金が未処理の状態にある(表3)。また、タイでも、EGATへのさらなる資本注入を行うなどの動きもみられる。
電力は公共財である。しかも、電力セクターは、電力の安定的供給を目指すもので、社会的インフラとしての外部経済性が高い事業分野である。そのため、このような政府補助金は必要であるという見方もある。しかし逆に、このような体制は、電力セクターに収支の悪化や損失が生じても、いざとなれば政府補助金などの直接的支援があるため、内部効率の改善、すなわち費用を削減して経営を効率化しようとするインセンティブが働きにくい面もある。
(2) 電力系統の垂直的統合による弊害
電力系統の垂直的統合は、日本、フランスなどの先進国や、他の開発途上国にもみられるもので、アセアン4の電力セクターに限った特徴ではない。電力セクターの多くは、公的規制の保護の下で、自然独占、地域独占が許容されている。電力という財の特殊性(注2)を考慮すれば、このような垂直的統合は、電力の供給信頼性を維持し、安定的供給を実現するもので、必ずしも非効率であるとはいい切れない。
ただ、逆に問題点として挙げられるのは、発電・送電・配電部門を一社が抱えることによって、各部門間における内部相互補助の体制が温存されることである。図4のように、アセアン4の発電市場は、民間のIPPに開放されている。しかし、電力市場の自由化が進んでいる英国と比較してもわかるように、アセアン4では、実質的に電力セクターはIPPの単独買電者であって、両者は競合関係にはない。電力セクターが、IPPに競争入札を行わせることによって発電コストを抑えたとしても、コストのかかる他の送電・配電部門との間で費用を内部調整すれば、各部門ごとの対費用効果は適正に行われない。また、タイやインドネシアには電力系統の分割・民営化構想があるが、内部相互補助体制の余地を残せば、市場開放された部門のコストを安くする一方で、他の部門のコストを高く設定することができるため、民間企業の新規参入を阻む要因ともなろう。
2.財務面
(1) 内貨収入・外貨支払いの収支構造
開発途上国の電力セクターの収支構造は、電力を含むインフラ・サービスの対価が内需による国内通貨収入であるのに対し、支出費用の大部分が輸入生産財(燃料費)、輸入資本財、外貨借入金の元利金支払い、およびIPPへの買電費など、外貨ベースで行われるという特徴を有する。アセアン4の電力セクターも、表3からわかるように、総じて、(1)営業費用の5割程度を燃料費が占めること、(2)通貨危機後の外貨建て債務(現地通貨換算)が膨らみ、長期借入金の3~10割を占めること、(3)通貨危機後の決算で為替差損を計上していることがみられる。なお、燃料費に関しては、マレーシアやインドネシアでは一次エネルギー資源の国内調達が可能とはいえ、国際価格での調達であるため、国際市況の影響を受ける。
このように、アセアン4各国の電力セクターは、典型的な内貨収入・外貨支払いの収支構造を有しており、為替変動リスクの影響を直接的に受ける財務構造となっている。他方、IPPも、PPA上の基準通貨が現地通貨建てであったり、外貨建てプロジェクト・ファイナンスの調達比率が高ければ、電力セクターと同様の収支構造を有することになる。
(2) 政府介入による政策的な電力料金
本来、為替変動リスクなどによるコストアップ分は、電力料金への価格転嫁によって吸収できる。しかし、電力料金は公共料金であり、公的規制を受ける。しかも、開発途上国では、産業育成、貧困層の生活水準の確保といった社会政策の観点から、電力料金を電力供給コストよりも低く抑える傾向がある。実際、アセアン4では、電力開発を工業化推進の重要な手段として、とりわけ、大口需要家である産業部門の電力料金に対しては割引制度を設けるなど優遇してきた。図5のアセアン4の電力料金の推移をみても、タイやマレーシアでは電力料金が据え置かれているし、フィリピンやインドネシアでは、名目上の電力料金は上昇しているものの、インフレ調整後の実質電力料金は低下しているのがわかる。
もとより、電力セクターは設備・装置産業である。アセアン4の電力セクターでは、90年以降、急速に拡張した発電設備に対する減価償却負担の増加や、設備投資の借り入れ調達に伴う支払利息負担の増加など、総費用に占める固定費部分の割合が高まりつつある。そのため、アセアン4の電力セクターは、今後、GDP成長率の低下に伴う電力需要量の低減局面を迎えた場合、収入減少に対して費用低減圧力が弱いために、さらなる収益悪化も懸念される。
3.技術面
(1) 送電・配電部門での電力ロスの大きさ
発電から最終需要家に至るまでに失われる電力の総合ロス率を、電力系統フローに従って作成したのが表4である。アセアン4では、総合ロス率は10~20%台に上る。内訳をみると、発電ロス率では日本と大差がないものの、送・配電ロス率での高さが目立つ。
表4 電力系統におけるロス率(単位:%)
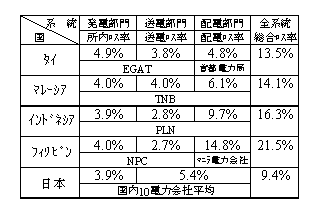
(注)データは94年当時のもの
(資料)ADB(1998)、電気事業連合会資料
送・配電ロスの生じる主な要因としては、(1)送・配電網における電圧の低さ、(2)既存設備の保守管理の不十分さ、(3)保守管理を行う技術力の未成熟さ、の3点が挙げられる。昇圧用の変電設備が不足している状態では、従前の低電圧の変電設備に頼らざるを得ず、それだけ電力のロス率は高くなる。加えて、変電所の設置数が少なければ、変電所間の送電線が長くなり、ロスの発生要因ともなる。
また、アセアン4では、人材育成が不十分であることも電力セクターの抱える問題となっており、それが運用・保守管理の技術力が未成熟である根本原因といえよう。ただし、以上のような内部的・技術的なロスがある一方、配電ロス率が高いインドネシアやフィリピンでは、盗電やメーターの不正改造といった外部的・非技術的なロスがあることも無視できない。
(2) 電力供給上の欠陥
図6をみると、マレーシア、インドネシア、フィリピンでは、供給予備率(注3)が、およそ40~80%の高さを占め、設備稼働率が40%台と低迷しているのがわかる。供給予備率は、将来的な需要増加や不測の設備事故への対応のため、ある程度の確保は必要となるが、(注4)逆に、高ければそれだけ不稼動設備が多くなる。つまり、ここから想定できるのは、第一に、マレーシア、インドネシア、フィリピンでは、発電設備が過剰気味か、有効稼動していないことが指摘できる。また、これは、計画時の需要想定が適正でなかったことにも一因がある。そして第二には、第一の要因とは逆に、需要想定通りの潜在的需要がありながら、送・配電整備の遅れから最終需要家への対応ができず、余剰の電力設備を抱えることになったとも考えられる。実際、マレーシア、インドネシアでは、高い供給予備率を維持していながら、最近でも大規模な停電が発生している。このような状況は、発電設備の不足ではなく、むしろ発電から最終需要家までの系統運用機能に原因があると考えられる。
図6 発電設備の稼動効率性の推移
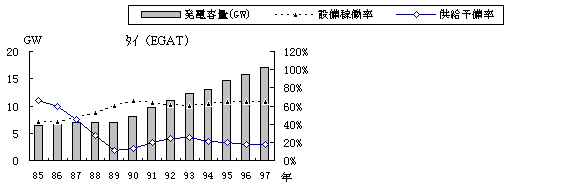
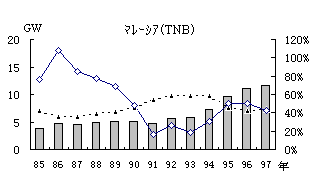
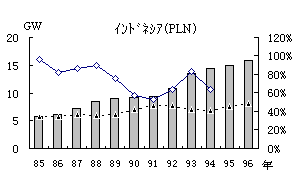
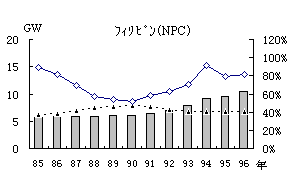
(注)
1.設備稼働率=発電量/(期中平均発電容量×24×365)、供給予備率=(発電容量-最大電力)/最大電力
2.EGAT、TNB、NPCのデータはIPPのデータを含む。
(資料)ADB(1998)、各社直近年次報告書
III.電力インフラ整備における今後の課題
このように、アセアン4の電力インフラ整備をみると、発電設備の整備が重視されてきた一方、送・配電整備、さらに電力供給の効率化対策など、ソフト面での整備は軽視されてきたといえよう。また、それは、アセアン4の電力セクターが抱える構造的問題に起因するものともいえるのではなかろうか。
そこで、以下では現在までの取り組み状況を踏まえつつ、今後の課題を、電力セクターおよび現地政府ごとに検討する。
1.電力セクターの課題
(1) 経営効率化対策
アセアン4各国では、経営効率化対策として、世界銀行の処方に基づいた民営化の動きがみられる。マレーシアでは、すでに92年にTNBの株式会社化が行われている。タイでは、98年中にEGATが発電子会社(EGCO)を株式公開することとし、将来的にはEGAT本体も、発電・送電部門を分割民営化する方向である。フィリピンでは、エストラーダ大統領が「10ポイント・アジェンダ」の中で、NPCの民営化を緊急課題として掲げている。さらに、インドネシアでも、民営化を前提に、発電・送電・配電部門ごとの社内分社化を検討していると伝えられている。
ただし、自然独占が維持されたまま、既存の電力セクターが民営化されたとしても、IPPと競合関係になく、また送・配電市場への新規参入が制限されている環境下では、どの程度の効果があるのか不明確である。また、発電、送電、配電ごとに分割民営化するにしても、技術力が未成熟な段階における電力系統の分断化は、全系統の統括部門あるいは統括機関が適正な需給管理を行えない限り、停電の発生など、供給信頼性の面で問題を残すことになりかねない。
アセアン4の電力セクターにとっては、このような「まず民営化ありき」といった対策よりも、系統運用の技術力向上、あるいは電力系統全体の管理機能の強化といったマネジメント部門の対策が先決だと思われる。
(2) 電力需給における技術的精度の向上
供給対策としては、まず、発電部門に偏りがちな投資配分を是正し、送・配電部門への投資額を増やしていくことが必要であろうと思われる。その上で、高電圧変電所の設置や送・配電部門のメンテナンスなどの管理面を強化し、同部門での電力ロスの低減化を図っていくことが早急の課題といえよう。それには、例えばマレーシアのTNBが、停電対策として東京電力に対し、電力供給信頼度に関するコンサルティングや技術者研修を依頼したように、先進諸国のノウハウを受け入れるのも有効な手だてである。
他方、需要対策としては、すでにアセアン4各国とも様々な方法を採用しているが、その中の重要な対策の一つに、ディマンド・サイド・マネジメント(DSM)がある。DSM手法とは、最終需要家に対し、(1)DSMに関する情報提供、(2)省エネルギーの推奨、(3)電力負荷の平準化を進めていくことである。例えば、タイでは、家計部門や商業部門における照明器具を熱効率の高いものに交換することを推奨したり、需要に応じた時間別料金の設定などを実施している。だが、必ずしも先進国で実施されているような技術的にも金額的にも高度なものではなく、まだ発展段階といえる。
(3) 財務体質の強化
財務体質の強化対策としては、収益源となる電力料金の価格決定システムの改善が優先課題と思われる。フィリピンのNPCは、長期借入金のほぼすべてが外貨建てであるため、為替変動リスクを受けやすい。そのため、NPCでは、最終需要家に対する電力料金に燃料費やプロジェクトコストの変動を反映させる料金調整システムが組み込まれるようになった。このような動きは、他の3カ国ではみられていない。
II.2(1)で述べたような収支構造を是正していくためには、外貨建て債務の比率を減少させ、同時に為替変動リスクに対するリスクヘッジ手段を絡めていくことが必要である。世界銀行、アジア開発銀行(ADB)などの国際金融機関、および先進国の輸出信用機関に働きかけ、現地通貨建ての借入比率を高めていくことも一つの手段となろう。だが、そのためには、具体的な収益計画、長期的な利益・投資計画を策定し、当該機関を納得させるような改善策を提示する必要がある。なかでも電力料金の見直しは重要事項といえよう。
2.現地政府の課題
(1) 当面の課題
まず第一には、IPP事業に対する政府方針の見直しである。現地政府には、総じて、政府保証は民活の基本理念に反するというスタンスがある。近年のアセアン4のBOTスキームの傾向をみても、現地政府・電力セクターは、(1)ポリティカル・リスクや、(2)燃料の供給リスク、価格変動リスクなどのコマーシャル・リスクを請け負いたがらず、IPP側に対し、リスク負担を要請するようになってきている。
しかし、通貨危機後、電力セクターの業績悪化から、IPPと締結するPPAの信用力低下が懸念され始めている。PPAの信用力低下は、販売・収入リスクとなり、IPPが資金調達を行う上で不利な条件を付されることにもなる。そのような状況を回避するためにも、現地政府は現状のBOTスキームに対する方針を見直し、政府保証、コンフォート・レターを追加的に認め、PPAに対する信用力を補完していくべきではなかろうか。
そして第二には、料金規制の見直しである。通貨危機後、電力料金の動向をみると、電力セクターの電力料金の値上げ申請に対し、政府が下方修正を要請したり、また値上げ時期を遅らせるなどの政府介入が行われている。電力料金は公共料金であるため、急激な為替変動に連動して引き上げるのは難しい。しかし、コストアップ分の価格転嫁がスムーズにいかなければ、電力セクターの収益悪化に拍車がかかり、それが国営企業であれば、結果として財政支出の負担につながることになる。アセアン4では、国営の電力セクターは民営化される方向にある。民営化が有効に機能するためには、料金規制の緩和、政府介入の排除は前提条件であろう。
(2) 長期的な課題
長期的な課題としては、電力セクターによる現地通貨建ての借入調達を可能とする、国内資本市場の整備・育成が挙げられる。電力セクターの収入が現地通貨であることから、本来は、資金調達も現地通貨建てが望ましい。しかし、アセアン4の資本市場をみると、資本市場に厚みがなく、巨額の資金を必要とするインフラ整備は、先進国の金融市場からの資金調達に頼らざるを得ない。さらに、通貨危機の影響から、タイ、インドネシア、マレーシアでは、不良債権の急増による銀行経営の悪化など、金融システムに問題が生じており、地場金融からの資金調達は難しい状況にある。しかし、当面は難しいながら、やはり為替変動リスクを極力抑えていくためにも、例えば国内の年金基金や保険会社、有力財閥からの投資など、現地国内で長期資金が供給できるよう、中長期的な視野に立った資本市場の整備が必要となろう。
おわりに
以上に述べてきたように、電力セクターの構造的問題を是正していくには、第一に、送・配電部門の整備拡充を軸とした電力系統での投資配分の是正が必要である。第二には、設備増強による電力確保よりも、むしろ全体として設備投資を抑えながら電力系統運用の効率化を図ることである。第三に、電力需要面において、前述したようなDSM手法の推進や、受益者負担に基づく価格設定によって、余剰な需要を抑制していくことも重要である。そして第四としては、電力セクターの自助努力を後押しするため、現地政府が補助金体制などの直接的支援を極力排除していくと同時に、環境整備など間接的支援を行うことが望まれる。電力料金設定への政府介入の排除は、緊急課題であろう。
現状のアセアン4の財政事情は厳しい環境下にある。特に、IMF主導の経済改革プログラムが進められているタイ、インドネシアでは、公的資金によるインフラ整備は難しい状況にある。国庫金負担を少なくするためには、やはり民活によるインフラ整備を前提に、IPPとの関係を良好に保ち、最大限に活用することではなかろうか。そのためには、現地政府として、第一にBOT法の整備拡充、第二に、環境変化によって突然変更されることのない法制度・政策の履行、そして第三に、相応のリスク負担に応じ、適切なセキュリティー・パッケージの組成に協力していくことである。
通貨危機以後、日本がアセアン域内のインフラ事業に対する貿易保険を拡大したり、日米欧の輸出信用機関が融資支援を継続的に行っている。このような時宜を得た先進国からの支援は、民間外資の逃避を抑えることにもなる。しかし、重要なことは、こうした先進国支援を土台にしつつも、電力セクター自身の事業効率化に向けた地道な努力が必要なのであり、民活インフラ整備や電力セクターの民営化をすべての解決手段とするのではなく、電力インフラ整備を効率化するための一つの手段と位置づけるべきであろう。
注
1. ADB(1998)
2. 矢島(1994、p. 32)では、電力という財の特殊性として、(1)生産と消費の同時性、(2)発電および送電の一元管理の必要性、(3)供給信頼性への社会的要請の強さ、を指摘している。
3. 供給予備率とは、最大電力(一定期間内におけるピーク需要時の電力負荷)に対して、現有 の発電設備が余分に保有する容量の割合。
4. 供給予備率の適正値は、当該国の電力需要の伸び率や電力系統の運用能力によって、一様で はない。ちなみに、日本では9%台を目標値としている。
主要参考文献
1. 植草 益編 (1994) 『講座・公的規制と産業(1)電力』 NTT出版 1994年
2. オーム社(1998)「OHM」 1998年1月号
3. 海外経済協力基金 開発援助研究所 (1995) 『開発途上国の電力セクターの効率化の在り方』 1995年
4. 海外電力調査会 (1993) 『海外諸国の電気事業 第1編』 1993年
5. 通産省 通商政策局 (1996) 『新時代のアジア協力』 1996年
6. 電力事業連合会 統計委員会編 (1997) 『電力事業便覧 平成9年版』1997年
7. 室田 武 (1993) 『電力自由化の経済学』 宝島社 1993年
8. 矢島 正之 (1994) 『電力市場自由化』日本工業新聞社 1994年
9. ADB(1998), Electric Utilities Data Book 1997, 1998.
10. APEC(1997), Manual of Best Practice Principles for Independent Power Producers, 1997.
11. Asia Law & Practice Publishing (1997), Power Project Documentation, 1997.
12. Financial Times (1998), Power in Asia No.242, 1998.
13. OECD-IEA(1997), Asia Electricity Study, 1997.
14. The McGraw-Hill Companies (1998), Standard & Poor's DRI World Energy Services (chapter "Viewpoint"), 1998.
15. The World Bank(1993), The World Bank's Role in the Electric Power Sector (chapter "New Approaches to Power Sector Development"), 1993.
16. The World Bank (1997), Choices for Efficient Private Provision in Infrastructure in East Asia, 1997.
17. The World Bank, Private Sector Monthly Review, various issues.
18. U.S. Department of Energy /Energy Information Administrationホームページ・各電力セクター Annual Report

