RIM 環太平洋ビジネス情報 1998年7月No.42
東南アジアにおける日系製造業の雇用と人材育成
1998年07月01日 さくら総合研究所 竹内順子
はじめに
東南アジアにおける人材育成の重要性は、しばらく前までは「持続的な経済成長」、現在では「経済再生」のための課題として、多くの場面で指摘されている。本稿はこの課題を、限られた範囲ながらも、具体性を持った問題として考えていくことを目的としている。
その材料として今回、取り上げるのは東南アジア(アセアン4=インドネシア・タイ・マレーシア・フィリピン)の日系企業における人材育成である。同じ設備を持つ工場でも、生産性はそこで働く人や組織の在り方によって大きく変化する(注1)。従業員の潜在能力を引き出すのは、企業の人材育成策であり、具体的には、企業がどのように従業員を訓練し、モチベーションを引き出しているかを検討する必要がある。
現地法人の訓練およびインセンティブ・システムはほとんどの場合、本社のシステムの影響を免れないと考えられる。積極的にとらえれば、本社のシステムは日本において長い時間と試行錯誤によって磨かれ、成功を収めてきたものであること、また消極的にとらえれば、有力な代替策が見当たらないことがその理由である。特に現在、東南アジアで展開されている大規模な輸出型企業では、製品は世界水準の品質とコストを求められる。よくいわれるように、製品の高品質と生産現場の効率性が日本企業の優位性であるとすれば、その優位性を支えるノウハウこそが重要な経営資源であり、現地法人においても、その適用が図られていると考えられる。
しかし、いうまでもなく、本社の人的資源開発のシステムが現地法人にそのまま適用されるわけではない。人事管理の方法は、ホスト国の労働関係法や雇用慣行などによってまず規定され、さらに質的・量的な労働力の需給状況への対応が必要となるからである。合弁企業であれば、現地側の出資企業のシステムとの兼ね合いもある。したがって、正確には、本社の人的資源管理システムが持つ目標に向けて、ノウハウの応用的な適用が図られていると考えるべきであろう。本稿では、こうした観点から、日系企業がノウハウを適用するためにどのような方法を採っているのか、適用を阻む要因は何なのかを考えていきたい。
通産省(1998)によれば、1995年度末現在、アセアン4で操業する日系製造業は1,114社であり、約59万人を雇用している。その約7割が87年度以降の進出である。87年からの10年間余りは、アセアン各国が高成長下にあり、経済、社会など雇用を取り巻く環境も大きく変化した時期である。さらに、先ごろの通貨危機を境に、再び、雇用環境が大きく変化しているのは周知の通りである。以下では、まず、東南アジアの雇用を取り巻く環境を概観し、生産現場と間接部門に分けて、日系企業の人的資源開発の現状をみていくこととしたい。
I.東南アジアの雇用を取り巻く環境
1.労働市場の変化
(1) 製造業の雇用拡大
まず、およそ過去10年にみられた労働市場の変化を振り返ってみたい。目覚しい変化としては、第1に、雇用創出に対する製造業の寄与の増大が挙げられる。雇用の増大に占める製造業の比率は、80~86年の期間にはマレーシアを除く各国で1桁台であったが、90~96年の期間には、フィリピンを除く各国において、新規雇用の約6~7割を製造業が生み出している(表1)。その結果、雇用全体に占める製造業雇用の割合は、フィリピンを除くといずれも上昇している。
第二に、専門人材の絶対数の増加が挙げられる。職種別の雇用を87年と96年(注2)とで比較すると、構成上の変化は小さいが(表2)、管理職および技術・専門職の絶対数は、おおよそタイで62万人、マレーシアで54万人、フィリピンで50万人増加している。ただし、職種別雇用構成を産業別にみると、管理職、技術・専門職の比率が高いのは金融等のサービス業であり、製造業における両職種の比率は若干低い。
第三に挙げられるのは、労働力の高学歴化である。80年代半ばと最近の数字を比較すると、従業員に占める未就学者の比率が各国において低下する一方、中等教育以上の学歴保有者の比率は一様に上昇している(表3)。
80年代後半から90年代半ばにかけて、外資系企業の急増、産業構造の変化などによる労働力需給のミスマッチ、とりわけ、技術者、管理職向けの人材の不足が深刻視されたことは記憶に新しい。この時期、国によって程度は異なるものの、機械セクターの拡大を中心に重工業化が進んだことによって、技能・技術職に対する需要が急増した点は共通している。また、新規に進出した企業は、大規模な生産体制を短期間で立ち上げる必要から、即戦力となり得る人材の獲得を望むが、経験者の数は限られている。需要が供給を上回れば、労働力の流動性が高まるのは自然のことであり、その流動性が企業の人材育成・蓄積を阻むという悪循環が生じた。
管理職、技術・専門職の予備軍となる高等教育の学歴保有者の絶対数は表3の期間に、インドネシアでは180万人、フィリピンでは159万人、タイでは82 万人、マレーシアでは70万人増加している。いずれも、同期間に増加した管理職および技術・専門職の数を大きく上回っている。もちろん、新卒者が管理職の役割を果たすことは不可能であり、短期的な不足感の解消を意味するものではないが、高学歴層の絶対数が増加したことで、企業側にとっては、新卒者の採用、選別が容易になり、内部育成の機会は増大するとみることができよう。しかし、大学生の供給力(ここでは在籍者数)は増大したが、大学生に占める理工および理数系学生のシェアは、最も高いフィリピンで14.7%(93/94年度)、最も低いインドネシアでは9.2%(92/93年度)と低く、技術系人材の供給不足という課題は、依然として残っている。
(2) 失業者の大量発生へ
97年7月のタイ・バーツの変動相場制移行を契機に発生した通貨危機は、東南アジア全体に波及し、各国はほぼ13年ぶりの不況に突入した。雇用も、刻々と不安定さを増している。直近の労働統計による失業者数は、インドネシアが442万人(96年)、タイが64万人(96年)であったが、インドネシアでは 98年6月の時点で失業者数は1,540万人に上り(「Jakarta Post」紙、98年6月19日付け)、タイでは年末までに230万人以上(「Bangkok Post」紙、98年5月18日付け)と過去最大規模の失業者の発生が予想されている。マレーシア、フィリピンでも失業率の上昇は避けられない見通しであり(注3)、雇用不安が消費の冷え込みを招き、内需型産業の低迷を促す悪循環が生じつつある。タイ、マレーシアでは、外国人労働者を帰国させることで、国民の雇用を確保する方針であるが、精米、水産、プランテーションなどの部門からは求人難を懸念する声が強い。一方、金融・不動産業等のセクターでは、企業の閉鎖、事業の低迷によって失業が増大している。今後、少なくともマレーシアでは重労働・低賃金層での求人難と高賃金層での求職難の併存という事態が生じよう。
しかし、労働力の高学歴化や、中長期的にみた場合の管理職、専門職層の需要の増大という趨勢には変わりはない。この調整期に、教育水準の向上や企業における人材の蓄積を進めることが、次の拡大期を左右するのであり、調整局面はミスマッチ解消に向けた猶予の期間ととらえたい。もちろん、現実的には、教育の普及水準の向上も、企業における人材蓄積も大きな脅威にさらされている。親の失業や賃金の低迷によって、中途退学、進学断念などのケースが発生してくるのは明らかであろう。また、解雇は企業にとっても、従業員にとっても、教育投資の損失を意味するが、様々な産業でレイオフが増加せざるを得ず、タイでは年初から4月までに労働裁判所で扱われた解雇に関する訴訟は約5,000件に上っている(「Bangkok Post」紙、98年4月23日付け)(注4) 。
日本政府は、アセアン4で操業する日系企業の雇用維持を支援するために、アセアン4の現地法人の従業員を、一時的に日本や第三国のグループ企業に移動させる際に発生するコストの一部を補助する方針を発表している(「日本経済新聞」98年4月24日付け)。
2.日系製造業における雇用
通産省(1998)によれば、95年度現在、日系製造業(注5)はアセアン4において約59万人を雇用している。これは、前回の第5回基本調査(注6)に比べると80%の増加であり、日系製造業の海外現地法人の雇用の 32%を占める。アセアン4では、雇用規模が大きい順にマレーシア(全体の32.3%)、タイ(同31.6%)となっている。
アセアン4の日系製造業における雇用の特徴としては、機械分野の雇用吸収が大きい点が挙げられる。雇用全体に占める電気機械のシェアが42.8%、輸送機械のシェアが18.7%と高い。各国ベースでみても、すべての国で電気機械と輸送機械が上位2業種に位置しており、インドネシアを除く各国では、この2業種が日系製造業の雇用の6割以上を占める(表4)。ちなみに米系製造業の各国における雇用をみると、電子産業の雇用規模が突出しており、アセアン4における米系企業の雇用の43.5%占める。電子のシェアに情報通信機器を内容とする機械のシェアを加えると、雇用の約6割に達するものと推計される。アセアン4の中では、タイのみが電子よりも機械の比重が高い。
表4 アジアにおける日系および米系製造業の従業員数
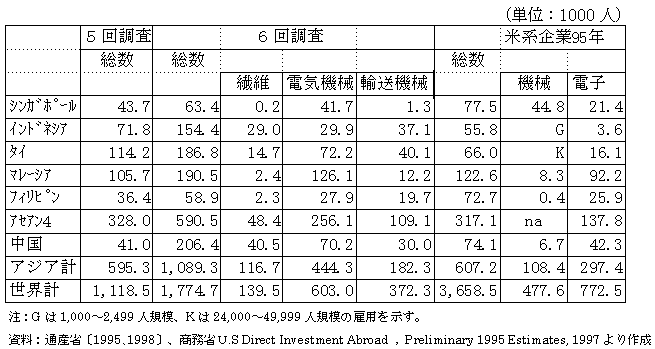
もう一つの特徴は、1社当たりの雇用規模が大きい点である。第6回調査ではアセアン4における1社当たりの平均社員規模(役員を含む)は546人であり、全地域平均の391人に比べて突出している。アセアンにおける雇用の大型化は、80年代後半以降の特徴である。第3回調査では、1社当たり336人で全地域平均を下回っていたが、第5回調査では同444人、第6回調査では同546人へと増大している。
職種別の雇用をみると、前回調査に比較して、管理職数は1.9倍、研究者数は1.4倍と、絶対数は増えているものの、社員全体に占める割合はあまり変化していない(表5)。北米の日系製造現地法人の状況と比較すると、社員全体に占める役員の比率は変わらないが、管理職、研究員の比率はアセアン4が低い。平均してみると、アセアン4の現地法人における1社当たりの役員数は5.2人、管理職数は10.6人、日本からの駐在員は5.6人である。
II.生産現場における人材育成
1.日本企業における熟練形成の特徴
東南アジアの現地法人の実態をみる前に、日本の生産現場における「熟練」の意味とその形成方法にみられる特徴について整理しておきたい。
(1) 「熟練」とは何か
生産現場における作業者の訓練の目的は、生産性の向上と、難しい技能の修得とに大別されよう。生産性を向上させるためには、(1)作業速度の向上、(2) 生産プロセスの改善、(3)歩留まりの向上、(4)稼働率の向上、(5)計画変更への迅速な対応などが行われる必要がある。(1)の実現は、基本的に、作業者各自の作業の習熟によってなされるが、(2)以下の実現のために作業者に求められる内容は多様である。例えば、生産プロセスを改善するためには、現場で工夫が生み出される必要があるが、そのためには、作業者が日常的な作業に目配りし、改善点を発見・提案することが必要である。改善の内容、効果は、作業者の製品、設備に関する理解や、生産工程の全体像の把握に大きく左右されよう。歩留まりの向上のためには、現場における品質管理の強化が必要となる。それには、各自が品質管理のための定型の手順を守る以外に、不良品が発生した際には原因を究明し、対応を記録するなどの関与も求められる。稼働率の向上についても、設備の保全自体は専門のスタッフが行うにしても、日常的な予防保全や異常の発見などに現場作業員が果たす役割は大きい。つまり、各作業者は、自分が担当する作業を円滑にこなすだけではなく、品質管理、保全、プロセス改善などへの関与をも求められているのであり、訓練の最終的な目的は、生産に関する理解を深め、問題発生への対応能力を高めていくことにあると考えられる(注7)。
機械加工などに携わる技能工については、生産性の向上に加えて、「難しい技能の修得」が重要となる。技能工に関する熟練の具体的な基準は、旋盤工、塗装工など職種によって多様であるが、小関(1985)では、機械加工の熟練工に要求される条件として「仕掛かり能力、段取り能力とか治具能力と呼ばれる知的な能力」を挙げ、「腕の器用さではなくて(中略)、その仕事のためにどんな注意が必要か、どこが急所か、どんな道具を用意すべきかを見抜く目を持つ」点を指摘している。経験によって培われた判断力や洞察力が技能内容の違いを超えて共通する熟練工の条件であると考えられる。
(2) 訓練とインセンティブ
こうした熟練は、どのように形成されてきたのであろうか。人材育成を進めていく上では、実効性のある訓練のシステムと併せて、従業員のモチベーションを高めるインセンティブが不可欠である。
労働省(1996)によれば、従業員数が300人を超える日本企業の8割以上が従業員訓練の方法として、計画的なOn-the-Job Training(OJT)を採用しており、特に生産現場については、その比重が高い。OJTとは、業務を行いながら仕事を覚えていくことであり、上司、先輩による演示と説明→訓練員による試行→上司、先輩による評価というプロセスを基本としている。こうした一連のプロセスによって習得した作業を担当替え(ローテーション)を繰り返しながら、容易な作業から難しい作業へと習得作業を多様化(多能工化)し、広範な仕事への理解を深めていく。
ローテーションが持つ意味は大きい。直接的な効果としては、ローテーションを通じた各作業者の多能工化によって、欠勤者の発生や生産量の調整への柔軟な対応が可能となる。また、演示から評価という作業ノウハウの習得をOJTの入り口とすれば、問題解決能力の向上がOJTのより深い目的であるが、そのための全体を見る目はローテーションによって養われる。
日本企業のOJTの特徴として、しばしば、そのローテーションの幅の広さが挙げられる。浅沼(1997)は、生産現場の業務を生産ライン・カテゴリーと熟練工業務カテゴリーに分け、日本の自動車工場では、両者の部門を越えたローテーションが観察できる点を、米国の自動車工場との大きな違いと指摘している。そして、日本方式の優位性を「型保全(金型修理)の経験を積んでいなければ、プレス加工ラインでトラブルが発生した際に、原因を敏速に検出し、適切な処方箋を書くことは難しい」という現場の意見によって示している。
米国では全米自動車労働組合が、各職務名称の責任範囲に含まれる任務の内容と時間当たりの基本賃金、職務間の異動に関するルールを厳格な協定として定めてきた。そこでは、職務は細分化され、明確な職務間の序列が形成されており、当然のことながら、上位職務ほど賃金は高い。上位職務への異動は、勤務期間の長い順に行われる、いわゆる先任権制度によって規定される。かつ、熟練工職種(Skilled trades)と定められた職種に就くためには、一度退職し、長い従弟訓練コースを受けて資格を取得する必要がある(注8)。「資格社会」のドイツでも、技能職務のための資格要件は厳密であり(注9)、こうした慣行の下で、日本的な幅広いローテーションを実施していくことは難しい。
OJTは仕事を習得する過程であると同時に、On-the-Job Screening(OJS:仕事を通じた評価)の過程でもある。日常的な仕事を通じて、作業者は作業能力や後輩への指導能力、人望などの評価を下されて昇格し、作業班の班長、さらにはその上の職階へと昇進していく。
OJTには終わりがない。班長になれば班長に見合った、職長になれば職長に見合った問題解決能力とその向上が求められるからであり、そうした能力は仕事を通じてしか得られないからである。しかし、職位が上がるにつれて、職場を離れた研修であるOFF-JTを実施する企業の割合も高まっていく(注10)。集合学習を中心とするOFF-JTには、日常業務で得た知識を体系化する効果が期待されており、OJTを補完するという役割を持つ。
日本のOJTをベースとする訓練は、作業者の長期的な育成を意図しており、長期の雇用を前提としている。したがって、企業にとっても、従業員にとっても、投資という意味合いが大きくなり、熟練の企業特殊性も大きくなる。また、勤務の長期化を促すために、賃金体系や昇進方式も、長期勤務に有利なように設計されている。小池(1997)は、日本企業の生産現場の賃金については、(1)年功カーブがみられること、(2)事務職との格差が小さいことを特徴として挙げている。そして、賃金の年功カーブは、ホワイトカラーについては欧米でも観察されるが、生産現場に及んでいる点が日本の特徴であると指摘している。これは、日本の生産現場では、仕事によって賃金が決まる職務給(Pay-for-Job)ではなく、「資格給」が基本とされ、「定期昇給」によって、年々上昇するためである。しかし、賃金は皆が一律に上昇していくわけではない。各自のモチベーションを喚起するために「査定」を通じた競争環境が維持され、昇格・昇給などに反映される。
(3) 生産システムと人材育成
上述したような日本的な訓練とインセンティブは、生産現場の変化に大きく影響されるのであろうか。生産システムは、市場の動向、技術革新などによって、当然のことながら絶えず変化している。特に、過去のME革命による自動化の進展の中で、メカトロニクス化が熟練労働を客観化、標準化することによって、生産労働者を二極分化させる傾向が指摘された。技術が機械に体化されることによって、誰でも可能な作業が増える一方、機械の保守内容が高度化すると同時に重要性を増し、作業の内容を機械向けに翻訳する業務が発生してくると考えられたためである。しかし実際には、生産システムの高度化は一般作業者の底上げをも迫ることとなった。一般作業者に要求される能力は、今後も高度化する傾向にある。機械振興協会(1997)は、一般作業者に現在、最も必要とされる能力は製品のチェック・調整能力であるが、将来的(5年後くらいを想定)には技能の客観化、保全能力、プログラミング能力の重要性が増す点を指摘している(注 11)。同時に、一般作業者の訓練方法や処遇制度は、今後も基本的には変わらない点を確認している。しかし、生産現場の技能形成の方法としてOFF-JTを重視する企業が、現状では1割に満たないのに対して、今後の方針では、約2割へと増大している。一般作業者に対する保全またはプログラミング能力の向上という期待が機械知識などの必要性を高め、企業のOFF-JT強化という方針を増大させているのであろう。
2.東南アジアにおける日本的熟練形成の現状と可能性
以下では、アセアン4の日系製造業の雇用の6割以上を占める機械およびその関連セクターを中心に、人材育成の問題をみていく。まず、日系企業における訓練とインセンティブの現状を、可能な範囲で整理する。次いで、タイで観察した3つの職場の事例を紹介する。
(1) OJTとローテーション
まず、数字の上から確認していこう。日系製造業における研修制度の有無については、表6の通りである(注12)。北米に比べて、アセアン4の現地法人では研修制度(=定型化したOFF-JT)を持つ企業の割合が高く、その比率は約7割に及ぶことがみてとれる。研修の形態として、最も多いのは親会社への派遣であるが、時系列で比較すると、現地社内および現地研修機関の比重が上昇している。マレーシア政府は、(1)訓練向けの投資(施設の建設、プログラム策定など)に対して税額控除を設ける、(2)外部研修機関への派遣費用を補助するなど、企業による労働者訓練の促進策を採用している。タイでも、経費の助成など企業内訓練を奨励する動きがあり、研修センターを設ける企業は増加している。表6にみられる現地研修の比重の上昇は、現地における研修体制強化の動きにも合致しているといえる。
ジェトロ(1992)では、生産職と経営スタッフに分けて、従業員訓練の方法を質問しているが、アセアン4については、生産職では83~89%、経営スタッフでは78~82%の企業がOJTを行っているという回答を得た。アセアン4においても、OJTを中心とし、Off-JTで補完するという訓練方法が広く採用されているとみられよう。OJTとOff-JTのバランスは、職種によって異なる。調査時点が少々古いが、マレーシアのエレクトロニクス企業のアンケート結果から、職種別に訓練の実施状況をみてみると、エンジニアでは親会社での研修などOff-JTを行う企業が多いのに対して、一般作業者では9割の企業がOJTと回答しており、Off-JTの採用比率は低い(表7)。また、一般作業者以外では、外部研修の採用比率が高いが、情報処理のように専門的かつ標準化が進んだ職務では、特に高いことがわかる。
ローテーションについては、日常的に行っている企業は多いが、どの程度、技能の多様化(多能工化)を意図したものかは判断できなかった(注13)。しかし、職務範囲の逸脱に対する従業員の抵抗感が、欧米系および現地企業に比べて日系企業では目立って小さいという調査結果(注14)は、従業員に職務範囲の弾力性に対する慣れ、あるいは意味の認識があることを示しているものとみられる。
(2) 長期の雇用を促すシステ
OJTをベースに、日本的な熟練形成を行おうとした場合、まず前提となるのは、長期の雇用である。離職率を示す数字はフィリピン(注15)しか得られず、東南アジアにおける雇用の流動性の水準や変化を数字から把握することは難しい。むしろ、ここでは、企業がどのように勤続のインセンティブを提供しているかをみてみよう。
まず、昇進の可能性である。日系企業が内部昇進を選好する傾向が強いという点は多くの事例で指摘されている(注16)。白木(1995)のインドネシアの調査(回答企業数162社)によれば、生産現場における監督職の「ほとんどを内部育成」する企業の割合は、欧米系の5.9%、地場の37.2%に対して、日系では65.2%と高い。
アセアン4のいずれの国においても、学歴に応じて職務が規定される傾向が強いことは広く知られている。前出のマレーシアのエレクトロニクス企業に対するアンケートから確認すると、エンジニアの7割以上を大卒者が、テクニシャンの7割以上を職業訓練校とポリテクニク(工専)の卒業生が占める(表8)。スーパーバイザーでは、最も多いのが高卒者であり、一般作業者からの登用がほぼ半分を占めるとみてよい。しかし、大卒者の19.6%、ポリテクニク(工専)卒業者の13.9%がスーパーバイザーになっているのに対して、高卒者でスーパーバイザーになっている人は2.9%に過ぎない。高卒者にとって、管理職である(注17)スーパーバイザーへの昇進は狭き門であるいえる。しかし、欧米系企業では監督職を外部から採用する企業が多い、すなわち、下からの昇進の余地が小さいという前出の調査結果を考慮すれば、日系企業においては一般作業者に、相対的に広い昇進の余地が与えられていると考えられる。
日系企業の多くは、生産職についても資格制度に類似した職階を設けて、資格(グレード)を賃金に反映させている。グレードは経験に応じて上昇するため、雇用が長期化すれば、それだけグレードが上昇する可能性も大きくなる。さらに、定期昇給を採用している事例の多さを勘案すれば、東南アジアにおいても勤続年数に比例して上昇する賃金体系を採っている日系企業は多いとみることができよう。日系企業においては、学歴による賃金格差が相対的に小さいという指摘がある(注18)が、高卒者と大卒者(技術系)には初任給の段階でも大きな賃金格差がみられる(表9)。高卒者と大卒者の賃金格差はフィリピンでは小さく、インドネシアでは大きいが、こうした格差の違いは、大卒者の希少性によるところが大きいと考えられる。
技能の修得に対するモチベーションを喚起する方法としては、社内における技能資格の認定制度が挙げられる。技能ごとにレベルを設けて評価し、資格として認定していく制度である。また、企業内研修でも、終了後に認定書を出すことが多い。こうした認定は転職の際のセールス・ポイントにもなるため、歓迎されるという側面もあるが、自己研鑚の機会自体が勤続のインセンティブとなる例もある。しかし、自己研鑚の最終的な目的はより良い処遇であり、研鑚の成果を処遇に反映する仕組みがなければ、転職の促進という性格が強く出ることになる。
(3) 事例としてのタイの生産現場(注19)
具体例に入ろう。半導体メーカーであるA社では、社員1,300人のうち、テクニシャン(短大卒)が200人、エンジニア(大卒)が100人と、技術系人材を多く抱えている。テクニシャンは、主として保全部門に配属される。現場の一般作業者でも高卒以上が採用要件である。
後工程(組み立て)に特化した東南アジアの半導体産業は、労働集約産業の典型のようにいわれるが、実際には工程のかなりの部分は自動化されており、資本集約型産業としての性格が強い。チップの切断や基板への搭載、ボンディング(配線)、パッケージの封止のいずれの工程も機械で行われ、現場作業者の主たる役割は、機械の作業を監視することである。組み立て過程の後に来る検査工程は、最も人手が必要とされるセクションであるが、検査装置でしか判断できない部分もあり、すべての工程を通じて機械への依存が大きい。つまり、A社で最も重要になるのは、固定費の大きい機械の稼働率を上げることであり、事故や故障を未然に防ぎ、異常が発生した場合には素早く対処できることであると考えられよう。機械の異常への対応は、保全部門が担当する完全な分離方式である。機械が複雑であるため、一般作業者の介在の余地は小さい。したがって、A社の訓練では保全担当者など、技術系人材の育成に重点が置かれているとみられる。一般作業者と技術系の従業員は別採用であり、分断された体制となっている。技術系でも、エンジニアとテクニシャンの間には職務・昇進上の垣根が存在するが、A社では両者の垣根を低くする試みを行おうとしている。A社の生産部門における職階は、オペレーター→リーダー(班長)→ジュニア・フォアマン→フォアマン(工長)→スーパーバイザー(職長)となっているが、高卒の一般作業者の昇進の上限は班長であり、昇進の天井は低い。
B社の一般作業者の採用要件はA社よりも低いが、一般作業者に開かれた可能性は大きい。B社は87年に操業を開始、VTRのメイン・シャーシやCDのシャーシなど、家電のセットメーカー向けに金属プレスおよびプラスチック射出成型部品と、それらを組み合わせた多様な部品を生産している。生産現場は、プレスおよび射出成型部門、組み立て・検査部門に大別されるが、96年に金型内製化のために金型製造部門が新設された。
B社では、(1)保全要員が一般作業者から登用される点と、(2)一般作業者にスーパーバイザーまでの昇進可能が開かれている点がA社と異なっている。初期の段階では、B社においても保全担当者の採用は一般作業者とは別枠にされ、技術系の男性を当てていたが、90年に女性作業者からの登用・育成を行ったところ、改善が著しかったために方針を変えた。金型製造部門でも、一般作業者から学歴を問わずに、適性ありと見込んだ女性社員を登用・育成し、準備期間として設けた1年余りで一号機の生産に漕ぎ着けた。
B社の生産現場における職階は、オペレーター→リーダー→スーパーバイザーであるが、全てが下からの昇進である。B社ではスーパーバイザーがタイ語の作業指示書を作成するが、現場を知っているだけに、わかりやすい指示書が作成できる。B社では子会社も含めると、2シフトで約5,000人の社員を雇用している。作業現場での取り扱い品目も多様であり、各所で作業指示書が必要となる。このため、一般作業者からスーパーバイザーを登用していくメリットが大きいのである。B社の組み立て部門では、班を越えたローテーション、応援がみられる
工作機械メーカーのC社にも様々な作業があるが、工程による作業内容が大きく異なるため、各部門は独立した工場のような印象である。C社の工程は大別すると、(1)電気系統のアッセンブル部門(PCB組み立て、ハーネスの束ねを含む)、(2)マシーンの台となる大型鋳物などの機械加工部門、(3)シャーシを製作する板金、表面処理の部門、(4)セラミック部品の焼結部門、(5)最終組み立て部門となり、それぞれの工場も別棟となっている。(4)の工程は 96年に導入した。従業員は500人で、そのうち約20人はエンジニア(大卒)である。一般作業者の採用要件は、高卒、工業専門学校卒である。保全は約 10人ほどの専任チームがあるが、各部門にも保全の担当者を置く混合方式となっている。C社の生産現場における職階は、オペレーター→リーダー→アシスタント・チーフ→チーフ→スーパーバイザーである。工専卒の昇進の上限はスーパーバイザーであり、一般作業者の一部には、管理職昇進への道が開かれている。
現状では、従業員の定着状況は良いが、90年の操業開始から3年間、人事システムが回り始めるまでの退職率は高かった。特に、大卒者についても、すべて現場勤務から始める日本方式を採っているため、入社後、半年以内に退職する人が多かった。体制が整ったこともあり、各工程の精度を上げていくために、1年半をかけて97年にISO9002を取得した。品質管理向上のためには何らかの「決め事」が必要であると考えて、ISOの取得を選んだのである。C社の製品は9割以上が輸出され、その約3分の2が欧米向けという事情も、ISOを選んだ一因であろう。
上記の3つの事例から、気がついた点を2つ挙げたい。まず第一に、一般作業者の熟練に対する要求は、業種や生産様式の特性に左右されるという点である。すなわち、(1)自動化の水準や設備の内容、(2)作業工程や取り扱い品目の多様性などによって、作業者の役割は変化する。例えば、A社では設備の複雑性、工程自動化の内容から、一般作業者の役割が限られているのに対して、手作業の工程が多く、作業内容が多様なB社では一般作業者を多能工化し、監督職へと成長させていく誘因が大きい。
第二に、作業員の管理・育成方法は、漸進的に定着・発展するという点である。C社では、設立当初の人事システム導入→抵抗(高い退職率)→定着という段階を経て、品質管理の強化や新工程の導入という次のステップを踏み出すことが可能となった。また、B社では、現地で通例となっている保全担当者の採用・育成方式を変更して改善に成功したが、変更に踏み切るまでに約4年間の試行期間があった。当然のことではあるが、制度の定着と従業員の能力の見極め→修正の繰り返しが、現地に適応した方法を生み出すのであろう。
(4) 熟練形成に対する選択的な対応
80年代後半以降、アセアン各国で急増した輸出向けの機械および機械部品の生産現場では、世界に通用する品質とコストで生産するという前提がある。したがって、品質管理の厳しさや設備の内容は、日本の工場に見劣りしないものも多い。しかし、こうした工場の運営を、日本からの短期出張者や、事前に日本で研修を受けた監督職予備軍といった限られたキーパーソンと、多くの未経験者という体制でスタートする場合、何らかの変更が必要である。例えば、作業の習得を速め、ミスを少なくするために1人当たりの担当内容を狭めて、ローテーションの範囲もごく限られたものとする。一般作業者の保全への参加は見込まず、品質管理についても、いわゆる「生産現場での作り込み」に注力するのではなく、人海戦術による全数検査で対応するという分離方式で臨むという選択である。この選択の下では、熟練形成は行われにくくなるが、短期の立ち上げが可能になる、流動性への対応が容易になるという利点がある。
一方、熟練を志向する場合には、長期の雇用の中で投資としての訓練を行っていくために、処遇上の配慮も行っていく必要がある(図1)。こうした選択は二者択一のものではなく、特定の部門について熟練志向を強化したり、段階的に熟練志向を強めることもできる。処理(コスト)と作業効果、企業の特性や労働市場の状況などから判断して目標を設定していくことが必要であろう。
III.間接部門における人材育成
間接部門の人材育成については、誌面の関係もあり、(1)今後、現地スタッフ(注20)の育成がどのような点で重要性を増していこうとしているのか、(2)現地スタッフの処遇を考える上でポイントとなるポストの現地化の2点について、簡単に述べたい。
1.現地法人におけるスタッフ育成の意味
80年代後半から、シンガポール、香港を中心に、地域本部を開設する動きが日系企業の間にも広まった。地域本部の役割として、多くの場合挙げられるのは、(1)財務・法務、(2)人事・研修、(3)マーケティング、(4)システム開発などであり、国際調達事務所(IPO)や物流子会社を併設して、域内関連会社の物流を一括管理する例もある。換言すると、地域本部設置の動きは、間接部門を特定拠点へ集約する動きであり、周辺国で展開するグループ企業において、こうした機能への重複投資を防ぐための動きであるともみられる。アセアン4の日系製造業のうち、地域本部の機能を持つ企業は全体の8%に過ぎず(注 21)、間接部門の役割は限られた企業が多いと考えられよう。
しかし、アセアンでも90年代に入り、(1)現地市場の拡大や貿易自由化に起因した地域マーケティングの必要性の増大、(2)コスト削減に向けた現地調達活動の活発化、(3)主力工場化に伴う地域拠点化などによって、非製造機能の拡充が求められる傾向にあった。さらに、グローバル経営という点からみれば、コストと付加価値の2つの面で、現地の人材育成の重要性が増している。コストについてはいうまでもなく、本国からの管理責任者の駐在経費の節約である。日系企業は欧米企業に比較し、本国スタッフの駐在が多いといわれる。職務・ポストの現地化を推進し、駐在員の削減を行うことは、コスト上も意味がある(注 22)。また、ポストの現地化は後述するように、現地スタッフの士気にも大きく影響してくる。
付加価値の面では、現地市場の拡大で現地向けの製品開発がクローズアップされたために、市場情報の収集や分析の価値が大きくなった点が挙げられる。また、日本企業の海外進出に関する最初のブームの引き金となったニクソン・ショックからは27年、最大のブームの引き金となったプラザ合意からも13年が経過している。操業年数が長期化した現地法人には、現地法人運営のノウハウが蓄積されているはずであり、こうした情報を形式化して、共有する意味も大きくなっている。激しいグローバル競争下においては、世界中に張りめぐらされた現地法人のネットワークから情報やアイデアを吸い上げ、活用していく必要性が増していくと考えられる。
アジアへの進出時期が早く、現地市場に密着してきた欧州系の消費財メーカーでは、現地のマーケティング・企画をヒントに、アジア発の世界的なヒット製品を生み出した例もある(注23)。また、同社では、(1)一工場で発生した問題への対処方法を、通信ネットワークを通じて世界中のグループ企業から募る、(2)新製品の開発・販売に関する一貫情報をデータベース化して、グループ企業による利用を可能とする、などのノウハウの相互活用を図っている(注 24)。情報化の進展によって、即時的な情報の共有が可能になったことが、情報源としての在外子会社の価値を高めていると考えられよう。在外子会社の活動の高度化に伴い、付加価値の発生が期待されるようになると、間接部門のスタッフ育成も大きな意味を持つようになる。
2.東南アジアの日系製造業におけるスタッフの現状
図2は、各国の大企業における採用と昇進の特徴を示している。通常、間接部門においても、管理職への昇進の可能性は、学歴によって分断されている。II. 2(3)章の事例でみたA社においても、間接部門の職階は、ジュニア・スタッフ→スタッフ→シニア・スタッフ→オフィサー(課長相当)となっているが、まず、入職時の職位が短大卒はジュニア・スタッフであるのに対して、大卒はスタッフであり、短大卒はスタッフが昇進の上限であるという明確な分断がみられた。
生産現場の監督職を除けば、管理職への昇進要件を大卒としている企業は多い。
(1) 現地化の動向
アセアン4の日系製造業の平均的な構成は、従業員総数546人で役員5人、管理職(部長クラス)11人であり、現地スタッフに限れば、役員は3人、管理職は9人となる。しかし、間接部門の人員を仮に全体の1割とすれば(注25)、55人であり、ホワイトカラーの役員・管理職比率は意外に高いことになる。
東南アジアにおいても、日系企業では管理職の内部育成志向が強いが、末廣(1997)は、タイの大企業および官庁においても内部昇進が用いられている点を指摘している。当センターでも地場の大手企業グループ数社の調査を行ったが(注26)、管理職はほとんどが大卒であり、内部昇進が重視されている点が確認された。問題は昇進の上限であろう。図2のタイ、インドネシアの大企業では、経営者層は下からの昇進が難しい、分断された構造となっている。これは、両国の大企業の多くが基本的には所有と経営が未分離なファミリー・ビジネスであり、経営者の多くがオーナー一族から輩出されるためである(注27)。日系企業の場合も、最高責任者および役員の一部が日本からの派遣員で占められていることを考慮すれば、地場の大企業と構造的には類似している。
日系製造業の役員、管理職に占める日本人の割合をみると、通産省(1998)では、役員については39.6%、管理職については14.4%となっている(表10)。この数字は、北米の現地法人に比較して低いが、アセアン4では外国人ポストについて、制限や削減のための行政指導を行っている国が多いことが一つの理由であろう。役員・管理職に占める日本人比率は、過去の調査と比べてもほぼ変化がない。しかし、企業の形態によって、役員の日本人比率は大きく異なるとみられる。ジェトロ(1997)(注28)によれば、現地側役員が皆無の日系企業の割合がマレーシアの56.4%、フィリピンの44.8%、タイの 34.8%、インドネシアの21.6%の順の大きく、マレーシアでは5割以上の企業において、すべての役員が日本人という結果になっている。役員の日本人比率は、出資比率と密接な関係にあり、現地側役員が皆無の企業のほとんどが日本の100%出資企業である。一方、合弁企業では、出資比率に応じて現地側から役員が出されるが、多くの場合、出資者が役員ポストについており、内部昇進者からの登用は遅れている例が多い。内部昇進者の役員登用には、操業期間も大きく影響する。
各部門の責任者の現地化の度合いをみてみよう。表11の1は、各部門の責任者として、日本人を派遣している企業の比率を示している。第6回調査の結果をみると、アセアン4の現地法人で、相対的に責任者の現地化が進んでいるのは、(1)人事、(2)仕入れ、(3)企画の部門であることがわかる。過去の調査との比較でみても、最高および次席責任者を除けば、日本人の派遣比率は低下しており、現地化を進める企業が増えていると考えられる。北米の現地法人の状況をみても、同様の傾向がみられるが、北米においては、次席責任者、販売および仕入れ責任者の現地化の度合いが若干高い。
次に、どの分野で現地法人への権限委譲が進んでいるかをみよう。仮に「本社による事前承認義務」がない事項を権限委譲(=決定の現地化)が進んだ部分と考えれば、人事に関する項目では、雇用・解雇、賃金引き上げについては、かなりの企業が決定を現地化している(表11の2)。3回調査、5回調査の結果からそれ以外の項目をみると(注29)、生産、販売に関する項目で比較的、現地化の度合いが高く、利益、投資などお金に関する項目では本社による事前承認要求が強い。北米の現地法人においても、こうした傾向は共通している。
表11 日系製造業における決定・人事の現地化
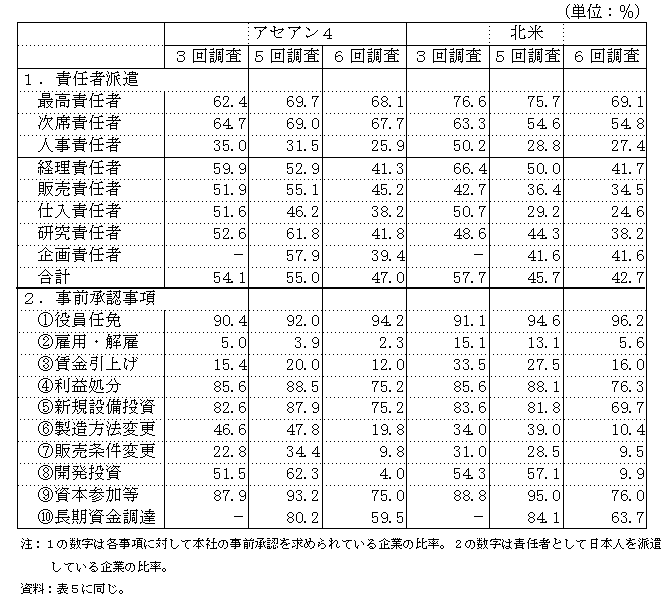
(2) 就職先としての日系企業
岡本(1998)では、東アジアの日系企業で働く現地マネージャー273人に対して、人事政策に関するアンケートを行っているが、満足度が最も高いのは「雇用の安定」で約8割が満足している。一方、最も低いのは「給与」であり、満足している人の割合は4割を切った。企業側は離職対策として「将来の可能性を示す」旨の回答をしているところが最も多かったが、昇進の可能性に満足している人は約5割であり、評価が分かれるところである。企業によっては、外国人社員の幹部候補生(ボード・メンバーの養成プログラム(注30)という形で、役員レベルまでの昇進可能性を示しているが、将来的な昇進のモデルを何らかの形で提示していくことが必要であろう。さらに、日系企業の大卒者の入職時の職位が相対的に低く、昇進・昇給の速度が鈍いというデメリットを、雇用の安定というメリットが相殺し得るか、という検討も必要であろう。生産現場の作業者では、相対的に長期の昇給が期待できることに加えて、一部の国を除けば、労働力に余剰感があることが雇用の安定というメリットを大きく感じさせた。しかし、需要過多の職種にあっては、雇用の安定に対する評価は相対的に小さなものとなる。
おわりに
総じていえば、東南アジアの日系企業は、日本方式の熟練形成方法を踏襲しつつも、「幅の縮小」という変更を加えることによって、即効性が望める人材育成を推進していると考えられる。幅とは、重点的な訓練の対象となる職層の幅(広さ)であり、従業員に求める能力の幅(技能・関与の多様性)である。こうした幅は、生産体制や製品の多様性など、企業の持つ特性によっても変化する。幅の縮小が必要になった理由としては、一つは、操業の初期段階からのアウトプットに対する要求水準の高さであり、もう一つは流動性への対応であろう。
東南アジアは技能・専門人材の絶対的な蓄積の小ささからみて、外部労働市場が発達した社会とはいい難いが、少なくとも、転職に対する抵抗感や転職に伴う経済的な損失が小さい社会であるということはできよう。高成長期には、製造業、非製造業を問わず、複数の産業が並行して成長し、同業者間だけではなく、金融業と通信産業、通信産業とエレクトロニクス産業など、セクター間でも人材獲得競争が激しく展開された。企業は内部昇進を重視しつつも、急速な拡大や新分野への進出に対応するために、スカウト人事を行わざるを得ない。こうした環境下では、従業員は自己の市場価値に敏感になり、需要の多い人材ほど流動性が高まり、企業側の損失感も深まる。自己の市場価値への意識が強まることによって、研修自体が勤続のインセンティブとなり得るが、ある期間を経て外の市場と報酬上の乖離があれば、離職が生じるというリスクも伴う。こうした傾向が、80年代後半の高度成長の中で強まったと考えられる。
幅の縮小された熟練形成は全体像を理解する人材の育成に不十分なため、ブラックボックスが生じ易く、日本人スタッフがその欠落部分を補うという必要につきまとわれる。今後は、中長期的な人材育成を目指して、幅の広い熟練形成を推進していく必要がある。雇用不安が高まり、流動性の低下が見込まれる現在の苦境を生かしていくことが望まれる。
注
1. 小池・猪木(1987)では、日本とほぼ同じ設備を持ちながら、生産性はその3分の1であるマレーシアのセメント工場を事例として、作業者の熟練が生産性を左右することを検証している。
2. ただし、タイについては87年と95年、フィリピンについては86年と95年である。
3. EUIが予測した98年の平均失業率はマレーシア4.8%、フィリピン9.1%であったが、4月の段階でフィリピンの失業率は13.3%に達した。
4. 例年より多いこの数字は、8月19日に発効する新労働法における退職金規定の変更(最高額を従来の月給6ヵ月分から10ヵ月分へ引上げ)に先立つ駆け込みレイオフとする見方もある。マレーシアでも、まもなく行われる雇用法の改正で、企業の賃金支払い遅延に対する罰金の増額が行われるなど、雇用不安を前に、従業員保護は強化の方向にある。
5. ここでの日系企業とは、本社が直接出資する子会社であり、孫会社の数字は入っていない。
6. 通産省が実施する海外事業活動調査のうち、3年に1度実施されるものを「基本調査」と呼ぶ。第1~5回は「海外投資統計総覧」として発表されていたが、第6回基本調査に当たる今回から、毎年実施の調査に名称が一本化され、『第26回我が国企業の海外事業活動調査』として発表されている。本稿で使用した各調査の対象時期は以下の通り。第3回調査:87年3月、第5回調査:93年3月、第6回調査:95年3月。
7. 小池(1995)は、仕事の内容を「ふだんの作業」と「ふだんとちがった作業」とに分け、後者に該当する「変化と異常への対応」能力を「知的熟練」と呼び、生産現場の作業者が広くこの能力を高めている点を、日本の職場の効率性の基盤としている。
8. 浅沼(1997)P.99~102。
9. ドイツの労働事情については、高橋俊夫、大西健夫『ドイツの企業』早稲田大学出版会 1997年、第3章を参照。
10. 労働省(1996)P.130。
11. 同報告書では、一般作業者の技能は、(1)機械の監視作業→(2)製品のチェック・調整→(3)段取り替え→(4)自らの技能を客観化する→(5)設備の保全→(6)プログラミングまたはティーチング、の順で難しいとされている。
12. これは、一般作業者のみを対象とした研修制度ではないことに留意。
13. 継続的な単純作業による能率低下を防止するためのローテーションというケースもある。タイについては、日系企業の約6割がジョブ・ローテーションを行い、約4割は教育のためにジョブ・ローテーションを採用しているという調査結果がある(労働研究機構『タイの労働事情』日本労働協会、1988年)。
14. 白木(1995)P.13。
15. フィリピンの製造業における離職率は、95年で5.0%であった。製造業の離職率は全産業平均(3.2%)に比べて高く、91年以降、上昇傾向をたどっている(『Yearbook of Labour Statistics Philippines』 1996年)。
16. 今岡(1987)も、日系企業が雇用の安定のために賃金引キ上げではなく、内部昇進を重視している点を指摘している。
17. 企業によって職位構成には違いがあるが、スーパーバイザーに至るまでに1~3の職位があり、スーパーバイザーからを管理職(課長相当)としている例が多い。
18. 白木(1995)P.24。
19. いずれの企業のヒアリングも、97年8月下旬から9月上旬にかけて行った。3社とも、100%日本の出資による輸出型企業である。関係者の皆様に謝意を表したい。
20. ここでのスタッフとは、将来的な管理職予備軍である短大・大卒の事務職を指す。
21. 通産省(1998)によれば、アセアン4の日系製造業のうち、地域本部機能を有していると回答している企業は90社であった。
22. 通貨危機による経営環境の悪化から、すでに日本人駐在員を削減する動きが進んでいる。
23. ユニリーバは、アジア子会社が開発した美白化粧品を世界市場に投入して成功した(「日本経済新聞」98年3月24日付け)。
24. ユニリーバ会長インタビュー(「日経産業新聞」98年3月23日付け)。
25. 労働統計上、製造業の雇用全体に管理職、技術・専門職、事務職が占める比率は、アセアン4で最も高いマレーシアでも13.2%(93年)である。
26. 98年5月中旬から下旬にかけて、アジア7カ国、28社に対してヒアリングを実施した。
27. 加藤秀樹編『アジア各国の経済・社会システム』東洋経済新報社、1996年、P.61~63参照。
28. 86 年以降、アンケート形式で毎年実施されている調査であるが、設問が変化している点が惜しまれる。この第10回に当たる調査は96年11月から97年1月にかけて実施されている。92年に実施された調査では、現地スタッフの役員への登用がみられる企業、現地役員の比率が50%を超える企業という設問が設けられており、いずれもその割合が最も大きかったのはフィリピンであった。
29. 6、7、8の項目については、6回調査と過去の調査との乖離が大きすぎるため、何らかの問題があると考え、言及を控えた。
30. 松下電器では、外国人社員を対象に、将来的な海外現地法人のボード・メンバーの育成を目的とする「シニアエグゼクティブ・ディベロップメント・プログラム」を開始した。約1年間の研修で、第1期生として15名が参加(「日経産業新聞」98年5月18日付け)。
主要参考文献
1. 浅沼萬里(1997)『日本の企業組織-革新的適応のメカニズム』東洋経済新報社 1997年
2. 伊丹敬之・加護野忠男・伊藤元重(1993)『日本の企業システム 第3巻人的資源』有斐閣1993年
3. 今岡日出紀(1987)「アジア諸国の熟練形成と日本企業の役割」(アジア経済研究所『アジア経済』1987年10月号 所収)
4. 岡本康雄編(1998)『日系企業in東アジア』有斐閣 1998年
5. 尾高煌之助編著(1989)『アジアの熟練』アジア経済研究所 1989年
6. (財)機会振興協会経済研究所(1997)『90年代の生産システム革新と人材活用』1997年
7. 小池和男・猪木武徳編著(1987)『人材形成の国際比較』東洋経済新報社 1991年
8. 小池和男(1991)『仕事の経済学』東洋経済新報社 1997年
9. 小池和男 (1994)『日本の雇用システム』東洋経済新報社 1994年
10. 小池和男 (1997)『日本企業の人材形成』中公新書 1997年
11. 小関智広(1985)『鉄を削る』太郎次郎社 1985年
12. 白木三秀(1995)『日本企業の国際人的資源管理』日本労働研究機構 1995年
13. 末廣昭〔1997〕「タイにおける労働市場と人事労務管理の変容」東京大学『社会科学研究』第48巻、1997年所収)
14. 田坂敏男編著(1989)『東南アジアの開発と労働者形成』ケイ草書房 1989年
15. 通産省(1989)『第3回海外投資統計総覧』 1989年
16. 通産省-(1995)『第5回海外投資統計総覧』 1994年
17. 通産省-(1998)『第26回我が国企業の海外事業活動調査』 1998年
18. 日本貿易振興会(1993)『アセアンの日系製造業活動実態調査1992年』日本貿易振興会 1993年
19. 日本貿易振興会(1997)『アジアの日系製造業活動実態調査1996年』日本貿易振興会 1997年
20. 労働省編(1996)『労働白書』日本労働研究機構 1996年

