RIM 環太平洋ビジネス情報 1998年7月No.42
調整局面を迎えたインドネシアの繊維産業
1998年07月01日 さくら総合研究所 大八木智子
はじめに
インドネシアの繊維産業は、外資系企業や地場企業の積極的な設備投資や、それを反映した化合繊(注1)を中心とする繊維生産量の増大など、その成長ぶりが語られて久しい。世界における同国の繊維産業の位置づけをみると、綿織物の生産量では世界第4位、ポリエステルなど合成繊維の生産量では世界第8位と、世界有数の生産国としての地位を築きつつある。また、他のアジア諸国と比較すると、化合繊の生産量では先発の韓国や台湾には追い付いていないものの、紡機設置錘数や織機設置台数においてはすでに両国・地域を上回っている。また、繊維輸出額は、1992年にはタイをしのぎ、アセアンの中で首位となるなど、インドネシアはアジアの代表的な輸出国としての地位も獲得した。
しかし、繊維産業の発展を支えてきた繊維輸出が93年以降、伸び悩んでいる。繊維産業は、雇用面や外貨獲得などの面において、インドネシア経済で大きな役割を果たしてきたことから、近年の繊維輸出の伸び悩みの要因を探り、解決の糸口を見つけ出すことは、今後の同国経済を考える上で意義があることであろう。また、97年7月のタイ・バーツの下落に端を発するアジア通貨危機はインドネシア・ルピアにも波及し、同国の繊維産業にも多大な影響を及ぼしている。本稿では、インドネシア繊維産業の現状と同国が抱えている問題について通貨危機の影響にも触れながら概観し、同産業の長期的な発展に向けた課題を考察してみたい。
I.インドネシア経済における繊維産業の重要性
1.雇用創出効果の大きい繊維産業
国連工業開発機関(UNIDO)の資料で、インドネシアの製造業全体に占める各産業の事業所数、就業者数、付加価値額の割合をみると(図1)、85年時点では、事業所数、付加価値額において食品産業が首位であったが、95年には繊維産業が食品産業を抜き、すべての項目において首位となっている。特に、就業者数は85年の37万人(全体に占める比率22%)から、95年には100万人(全体に占める比率24%)へと著しく増加している。これは II で後述するように、86年以降、政府の輸出振興策によって、輸出志向型企業を中心に数多くの企業が繊維産業へ新規参入を果たしたことが一要因であろう。このことから、雇用創出を通じ、繊維産業がインドネシア経済に大きく貢献しているといえるだろう。
2.工業品輸出のトップを占める繊維
繊維産業は、輸出面においても重要な役割を果たしている。87年の工業品輸出に占める各製品のシェアをみると(図2)、トップの加工木材に続き、繊維は第2位であった。当時、加工木材は工業品輸出全体の35%を占めており、その中でも合板は工業品輸出全体の26%という大きなシェアを占めていた。しかし、繊維が90年に合板を上回り、さらに91年には加工木材全体をも上回り、第1位となっている。
最近の輸出に占める繊維のシェアをみると、96年には66億米ドルと、工業品輸出全体の2割を占めていたが、97年にはアジア通貨危機の影響を受け、 15%へと低下している。しかし、依然として繊維が工業品輸出のトップであることには変わりなく、繊維産業が非石油・ガス製品部門において外貨獲得上、代表的な役割を果たしている。
以上から、石油・ガス部門以外では、繊維産業がインドネシア経済において最重要産業であるといえるであろう。
ただし、工業品輸出全体に占める電気機器の比重が近年高まっている。その背景には、同国政府が電気・電子産業の育成に力を入れていることがある。繊維産業は引き続き重要な外貨獲得産業であり続けようが、同国政府が繊維産業を今後、インドネシア経済の中でどう位置付けていくか、明確な「ビジョン」の確立が求めらている。
II.インドネシア繊維産業の構造と生産状況
1.インドネシア繊維産業の発展の経緯
インドネシア繊維産業の発展は、外資系企業の存在なしには語れない。特に、日系企業による資本・技術の導入がなければ、近年の同産業の発展にあり得なかったであろう。
インドネシア繊維産業の歴史を紐解くと、1960年代までの伝統的な綿織布と国営企業による綿紡績に限定された生産体制から、近代的な紡織一貫体制や化合繊生産体制への移行が可能になったのは、60年代後半から70年代にかけてインドネシアへ進出した日系企業によるところが大きい。具体的には、鐘紡、東洋紡、大和紡績(現ダイワボウ)といった綿紡績メーカーが紡織一貫企業を設立し、東レ、旭化成工業、帝人などの合繊メーカーが化学繊維や化合繊紡績の生産を開始したのである。
70年代を通じて、これらの日系企業と国内民間企業により、紡績、化学繊維の輸入代替化が推進され、さらに織布の輸入代替化も進められていく。80年代には、アルゴ・マヌンガルやバティック・クリス、スリンダフィンなどのインドネシア華人を中心とした繊維企業グループによって、化合繊化が一層進められていくことになる。
その後、70年代半ばから80年代前半にかけて講じられた政府の輸出振興策と、86年のルピア切り下げにより、インドネシアの繊維産業は、輸入代替型から輸出志向型へと一転する。その結果、輸入代替化によって生産が拡大し、輸出競争力を付けた紡績・織布企業に加え、日本や韓国などの外資系企業や国内企業の新規参入が活発化した川下の縫製部門に至るまで、積極的に輸出拡大が行われるようになった。
2.インドネシア繊維産業の構造
インドネシア繊維産業の構造の特徴は、第一に、紡績部門への外資参入度が最も高いことである。(表1)。同国繊維産業の生産主体は国内民間企業で、外資系企業(合弁企業を含む)は200社弱と、繊維産業全体の4.5%を占めるに過ぎない。部門別にみると、織布部門、編立部門、縫製部門では、国内民間企業が 9割を超えているのに対し、紡績部門では国内民間企業が77%、外資系企業が15%と、他の3部門と比較して、最も外資系企業の参入が進んでいる。これは、前節で述べた通り、70年前後から外資系企業のインドネシア進出が活発化したためである。このように、インドネシア繊維産業の生産主体としては国内民間企業が多いが、同国繊維産業への生産設備の持ち込み、特にAJL(注2)やWJL(注3)をはじめとする革新的生産設備の持ち込みや技術移転という役割を考えると、外資系企業の存在意義は非常に大きいといえるだろう。
なお、参考までに、部門別の雇用・生産概況を以下に示した(図3)。紡績部門は205社と、繊維産業全体の5%を占めるに過ぎないが、粗産出額、付加価値額では全体の34~35%を占めている。一方、縫製部門は2,110社と同産業全体の5割を占めているものの、付加価値額・粗産出額ともに2割程度である。これは、紡績部門が他の部門と比較して、いかに資本集約的であるかを示している。
図3 インドネシアの繊維企業の部門別概況
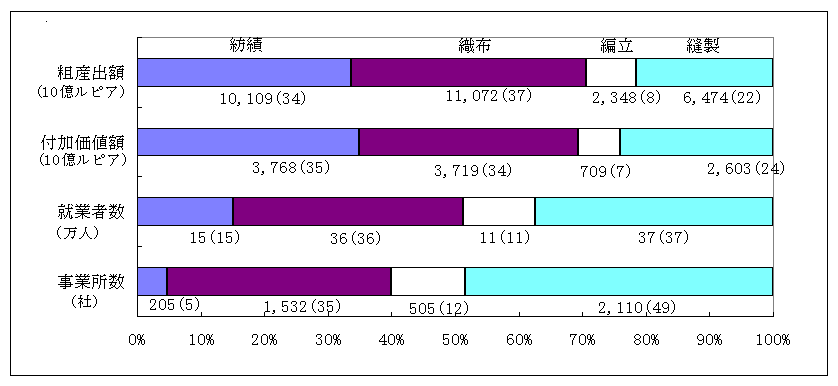
(注)
1.分類はISICに準じる。紡績(32111~32113)、織布(32114~32129)、編立(32130~32190)、 縫製(322)
2.カッコ内の数字は繊維産業全体に占める割合
(資料)Biro Pusat Statistik 『Statistik Industri』1995
第二に、大手企業においては、川上(注4)から川下にかけての生産統合が進んでいることが挙げられる。日系企業や繊維企業グループの中には、一つの生産部門に特化せず、紡績と織布部門の統合や、紡績と織布に縫製部門を統合するなど、複数の部門を持った企業が少なくない。グループ内で川上から川下までを一貫生産できる体制が整っていることは、同国繊維産業の特徴の一つとなっている。
第三に、川下よりも川中、川中よりも川上の設備規模が大きいことから、川上は川中に対し、川中は川下に対し、恒常的に生産過剰が発生する構造になっていることである[ジャカルタ・ジャパン・クラブ(1996)]。そのため、国内で消費しきれない糸・織編物などは輸出せざるを得ず、結果的に在庫調整的な大量輸出や安値輸出が行われてしまうようである。
第四に、縫製部門の能力不足が指摘できる。川上に比べ、労働集約的な川下の縫製部門には小企業や零細企業も多く、品質管理や納期対応などの面で遅れている企業が多い。また、同部門で生産されているものは、ジャケットやシャツ、パンツ、ジーンズなどの「軽衣料」であり、中国で生産されているような冬物用のコートをはじめとする重衣料は生産されていない。同部門では衣類の付加価値を高めることが求められているが、ウールなどの素材が国内調達できないことや、熱帯性気候の同国で、日常使用しない「重衣料」の生産ノウハウを定着させることは難しいことから、重衣料の生産はなかなか困難とみられている。
第五に、合繊原料の一部国産化が進められていることである。ポリエステルやナイロンの原料であるPTA(高純度テレフタール酸)やEG(エチレングリゴール)、カプロラクタムの製造、あるいは製造が計画されており、これによって企業は原料の国内調達が一部可能となる。これは、川上の強化に大きく役立つであろう。
3.インドネシアの主な繊維・繊維製品
インドネシアで主に生産されている繊維・繊維製品は、綿糸や綿織物に加え、化合繊(化学繊維+合成繊維)(注5)および同糸・織物などである。衣類では、先述した通り、いわゆる「軽衣料」が主流となっている。
日本化学繊維協会『繊維ハンドブック1998』によれば、インドネシアの綿糸生産量は、96年では86万トンと、世界第5位で(表2)、綿織物の生産量は 83万トンと、世界第4位となっている(表3)。80年代後半から90年代前半にかけて、綿糸、綿織物とも2桁の伸びを続けてきたが、93年には綿花生産国の虫害の影響などによる綿花減産を要因に、綿花輸入が減少、それに伴い生産量も減っており、それ以降も、生産の伸びが鈍化している。
その一方で、化合繊生産の伸びが著しい。これは、近年の新規参入メーカーおよび既存メーカーによる積極的な生産設備拡大の結果である。同国で生産されている化合繊には、ナイロンF(フィラメント(注6))、ポリエステルF、ポリエステルS(ステープル(注7) )、レーヨンSがある。アクリルSについては生産開始計画があるものの、現在のところ全量輸入に依存している。
生産量をみると、合成繊維の生産は、その9割を占めるポリエステルを中心に70万トンと、世界で第8位となっている(表4)。なかでもポリエステルFは、 93年以降、生産が急拡大している。その結果、ポリエステルFは国内で供給過剰となり、輸出の急拡大が進められたため、EUとの間でダンピング問題が浮上し、96年にはアンチダンピング税賦課の決定がなされた。また、90年代前半に生産が急増したレーヨンSは現在18万トンと、世界第3位の生産量となっている(表5)。これは、公害規制の強化などから先進国での生産が縮小されていることや、レーヨンの質感が高温多湿なインドネシアの国民に好まれていることが背景として考えられる。さらに、綿花の代替素材として注目されていることも要因の一つである。
III.インドネシア繊維産業の貿易動向
1.繊維原料と糸・織編物を中心とした繊維輸入
まず、インドネシアの繊維(繊維原料+糸・織編物)輸入についてみると、後述する輸出拡大期に伴い、86年以降、年々2桁の伸び率となっており(図4)、 85年の4億ドルから、90年14億ドル、95年26億ドルへと拡大している。ただし、93年には一時的に、綿花生産国の綿花減産を要因として、繊維輸入は減少した。
繊維輸入の内訳をみると、繊維原料が全体の50%、糸・織編物が49%と大勢を占め、衣類は1%程度と非常に少ない(図5)。繊維原料は8割弱が綿花であり、主に米国と豪州から輸入されている。残りの15%強はアクリルSやポリエステルSなどの化学繊で、日本と韓国からの輸入が多い。繊維原料の輸入額全体でみると、米国、豪州、日本からの輸入がその過半数を占めている。
一方、糸・織編物輸入の内訳をみると、特殊織物(フェルトなど)が全体の28%、糸が21%、化合繊織物と編物がそれぞれ15%、綿織物は11%を占め、韓国、日本、米国からの輸入が多くなっている(図6)。
2.伸び悩む繊維輸出とその要因
(1) 繊維輸出の動向
次に、インドネシアの繊維輸出をみると、全体の55%が衣類、43%が糸・織編物、残りの2%が繊維原料となっており、繊維原料の多い輸入とは対照的である(図5)。内訳をみると、96年の糸・織編物輸出は化合繊織物のシェアが41%で首位を占め、次に糸、綿織物が続いている(図7)。91年当初はチュール(注8)レース等が第2位、綿織物が第3位で、糸は第4位であったが、昨今の紡機増設による生産拡大により、糸の供給が増え、糸の輸出が増加した。一方、衣類は96年には男性衣類(布帛(注9))が32%を占めて最も多く、次に女性衣類(布帛)が続いた。
II でも述べたように、インドネシアの繊維産業は、70年代初頭に輸入代替が進んだ後、86年のルピア大幅切り下げや、政府の非石油・ガス輸出部門の輸出振興により輸出シフトが行われ、以降、92年まで繊維輸出(衣類+その他繊維製品)は毎年30%超の伸び率が続いていた(図8)。
しかし93年以降、繊維輸出は60億ドル前後で頭打ちとなっている。特に、94年は落ち込みがひどく、前年比マイナス7%の58億ドルへと低下した。
インドネシア政府は第6次五カ年計画(94~98年度)において、最終年度の繊維輸出目標額を当初120億ドルとしていたが、このように輸出が伸び悩んでいるため、目標額を120億ドル100億ドルへ、さらに100億ドルから80億ドルへと度にわたり下方修正を行ってきた。しかし、97年にはアジア通貨危機の影響を受けさらに落ち込んだため、現在では再下方修正後の目標額80億ドルの達成さえも危ぶまれている。
なぜ、80年代後半から90年代前半にかけて好調だった繊維輸出がこのように低迷しているのであろうか。次節でその要因を探ってみたい。
(2) 輸出低迷の要因
輸出を糸・織編物と衣類とに分け、それぞれの動向を仕向け国・地域別にみてみよう。
92年まで2桁の伸びを維持してきた糸・織編物輸出は、93年に前年比7%減の26億ドルへと落ち込み、94年も前年比5%減の25億ドルへと低下している。その後もかつてのような勢いはみられない(表6)。
品目別にみると、綿織物や化合繊織物において、輸出数量の減少・鈍化がみられている(表7)。インドネシアでは生機(注10)輸出が多く、同分野で競合関係にある中国との単価引き下げ競争が激しくなっていることが、その一因と考えられる。
また、全般的に韓国が低価格攻勢をかけていることも、インドネシアの糸・織編物輸出が落ち込んでだ原因の一つとなっている。さらに、ポリエステル長繊維織物に関しては、インドネシアでは薄地を中心に生産・輸出してきたが、近年、仕向け先において生地の中肉厚地化が求められており、薄地需要が減少していることも、同国の輸出伸び悩みに拍車をかけている。
主要仕向け国としては、首位の香港、日本、シンガポール、英国、アラブ首長国連邦が挙げられ、そのうち輸出の減少や大幅な伸び率鈍化がみられたのが、シンガポール、英国、アラブ首長国連邦であった。なかでも、英国をはじめとする欧州への輸出低迷は、93年以降、EC(現EU)がインドネシアの繊維に対し、輸入規制を開始したことが主因と考えられる。主要仕向け先であったEUの輸入規制(クォータ制)の実施は、インドネシアの繊維産業にとって大変大きな打撃となった。
一方、衣類の輸出も伸び悩んでいる。92年に前年比40%増の32億ドルを計上した衣類輸出は、93年に前年比11%増とやや伸び率が鈍化し、94年には32億ドルと前年を8.5%下回った。その後、95年、96年も35億ドル前後で低迷している(表8)。
衣類輸出の主要仕向け国をみると、米国が全体の3割超を占め首位となっており、以下、ドイツ、日本、英国、アラブ首長国連邦と続いている。特に93年以降に激しい落ち込みがみられたのは、日本、ドイツ・英国・フランスなどの欧州、シンガポールであった。米国、欧州、日本向けの輸出額に注目すると、輸出単価の低下がみられる。その背景には、同一の市場をターゲットとする、低賃金を売り物にしたベトナム、バングラデシュなどの後発国の台頭や、中国やインドの輸出急増などがあり、インドネシアの輸出環境は大変厳しくなっている。
日本と英国の衣類輸入先国の変化をみると(図9)、日本のベトナムからの衣類輸入は、91年当時は3,400万ドルと、輸入国の順位では10位以下であったが、96年には91年の15倍へと急増、インドネシアを抜き第6位となっている。また、91年当時、8,000万ドルだった英国のバングラデシュからの衣類輸入は、96年には4.3倍の3億ドル強へと増加、第9位のインドネシアを抜き、第8位となっている。
3.アジア通貨危機のインドネシア繊維産業への影響
このように、90年代前半からすでにインドネシアの繊維産業は輸出低迷に苦しんできているが、さらに追い討ちをかけたのがアジア通貨危機である。97年7月のタイ・バーツ下落に始まったアジア通貨危機は、インドネシア・ルピアにも波及し、97年6月まで1米ドル=2,400ルピア程度で推移していた対米ドルレートは、98年初めに1万ルピアまで落ち込み、さらに98年6月末現在では1万4,900ルピアと、前年同月末比83.7%下落している(図10)。今回のインドネシア通貨の大幅な下落は、同国経済に多大な影響を与えており、繊維産業も例外ではない。
繊維産業への具体的な影響をみると、(1)原料など輸入価格の高騰、(2)国内需要の落ち込み、(3)生産の減少、(4)設備投資の削減・凍結、(5)輸出低迷、(6)外貨建て債務返済負担の増加など、マイナス影響が目立っている。
影響が最も大きかったのは、国内販売を主とする地場企業である。まず、川上においては、海外の銀行がインドネシアの地場銀行が発行したL/Cの受け取りを拒否するケースがみられ、綿花を中心に繊維原料の調達難に陥っている企業が出ている。また川中では、原料価格高騰の影響を受けて糸値が急騰し、その結果として、生産減少や操業停止に追い込まれる企業が増えている。さらに、原料の高騰による製品への価格転嫁は、川上から川下へと下りるに従って難しくなっているため、川下の企業ほど操業維持が困難になっている。また、ルピアの価値が低下したため、自国取引においてもドル決済が一般的になっているが、地場銀行と取引の多い地場企業の中には、ドル手当てが困難になっているところも少なくないという。
一方、日系企業は輸出志向型企業が多いこともあって、影響は地場企業に比べ比較的軽微であり、通貨危機後のリスク・ヘッジ対応も早かった。為替や与信リスク策の回避を徹底している企業も多く、販売金額の大半をドル決済に切り替えたり、国内販売も売り掛け期間を短縮し、ルピア決済の場合でも、当月決済や現金決済に切り替えることなどで対応している。また、国内需要の落ち込みにより、川上から川下に至るまで全部門で輸出志向が強まっている。
例えば、現地の有力縫製企業であるグレート・リバー・インダストリーズと組んでソックスを生産しているグンゼは、製品の大半を輸出、一部を地場向けに販売していたが、通貨危機後は、販売価格の上昇による国内需要の低迷などを受け、国内向け商品を輸出向けに切り替えている。また、大手商社の中には、インドネシアで生産している製品の7割を輸出、3割を国内向けに販売していたが、100%輸出向けにしたところもある。
このように、企業の国内向け製品を輸出に転化する動きが活発化してはいるものの、97年の繊維輸出額は、8月以降、数量・金額ともに大幅に落ち込み(図 11、図12)、97年全体では前年比20%減となった(図8)。その背景には、先述した通り、原料価格高騰の影響を受けた企業や、L/C受け取り拒否のため原料の確保ができなかった企業が、当初予定していた生産ができず、輸出も落ち込んだためと考えられる。
図8 インドネシアの繊維輸出動向
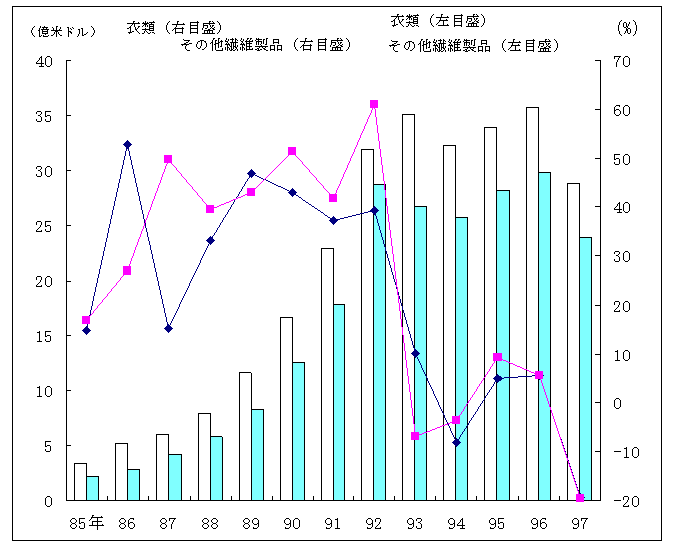
(注)
1.輸出額(棒グラフ)と前年増減率(折れ線グラフ)
2.図7、表6、表8とは出所が違うため、分類が異なる(衣類<garments>とその他繊維製品<other textile>)。その他繊維製品には、糸・織編物を含む。
(資料)Biro Pusat Statistik 『Indikator Ekonomi』 Maret 1998
98年になり、衣類以外の繊維製品(糸・織編物を含む)の輸出が急増している。同年6月30日付けの繊研新聞によれば、この動きは3月まで続いており、輸出回復の兆しかと期待されたが、5月には公共料金の値上げや失業の増大に対する国民の不満が反政府デモとなって表れ、その結果、地場銀行の信用低下による輸入原料の調達難、海外バイヤーのインドネシア離れが加速し、繊維輸出は減少した模様である。
IV.インドネシア繊維産業の今後の課題
このようにインドネシアの繊維産業は、近年の輸出低迷に加え、今般の通貨危機によって非常に厳しい状況に追い込まれている。今後、同国の繊維産業が長期的に発展していくためには、次のような対応が必要であろう。
まず第一に、政府による同国繊維産業に対するビジョンの明確化である。I でも触れたが、繊維産業はインドネシア経済において雇用創出や外貨獲得の面で大きな役割を果たしているが、育成の重点はに電気・電子産業に移っているように思われる。そのため、繊維業界の中にも、同産業は斜陽産業としてみられているのではないかと危惧する声も聞かれている。同産業をインドネシア経済の中で今後、どのように位置づけていくのか明確化することを政府に期待したい。
第二に、企業の生産品目と生産体制の見直しである。まず、III で触れたように、インドネシアで生産・輸出されている織物は生機が中心であるため、単価を低めに設定せざるを得ない。したがって今後、付加価値のより高い製品へのシフトが喫緊の課題となろう。また、同国では薄地生産がメインであるが、世界的に薄地需要が減り、中肉厚地生地の需要が増加している。インドネシアでも同生地の生産に対応すべく、レピア織機の導入が進められているが、生地生産に使用する国産の糸の品質が中級品であるため、結局、輸入糸を使用する動きが出ているという。これから生地の中肉厚地化の対応に向け、川中部門が国内で良質な糸を調達できるよう、いかに川上の紡績部門と協力し、地場で良質な糸を生産していくかどうかが、他国との差別化を図る上での鍵となろう。
さらに、川下における生産体制の見直しが必要である。同国の縫製部門では従来、スーパーや大型小売店で売るような定番品と、ややその上の中級製品の大量見込み生産を行ってきた。しかし、後発国の追い上げがあり、従来のモノを生産してから売るという「プロダクト・アウト」型生産体制を続けていては、世界での生き残りが難しくなってきている。縫製部門に限らず他の部門でも、市場の求める製品を生産するという「マーケット・イン」型へと切り替えることが急務になっているといえよう。また、同国の縫製部門は、品質管理、納期対応などの面で遅れていることも、同部門の発展のネックとなっている。繊維産業の担い手である華僑が中心となり、日系企業をはじめとする外資系企業の協力を得ながら縫製部門の強化を図ることが求められている。この縫製部門の強化は、設備・生産規模が川上で大きく、川下で小さいという同国繊維産業のインバランスを改善することにも役立つであろう。
第三に、輸出仕向け国の半分を占める非クォータ地域への輸出拡大である。アジア通貨危機の影響により、国内のマーケットが縮小している現在、ルピア安を追い風とする本格的な輸出拡大が、繊維産業の成長にとって必要不可欠となっている。しかし、主要仕向け国である欧米は、クォータ制を導入(2005年に廃止予定)しているため、輸出拡大にも限界があることから、ミッション派遣や見本市・展示会の利用んなどを通じて、いかに日本や東欧など、非クォータ地域において、新たな販路を開拓できるかがポイントになろう。
以上、インドネシアの繊維産業の現況をみてきたが、同産業には様々な問題があり、その解決は一朝一夕にはいかないであろう。しかし、こうした問題の対応なしには、インドネシア繊維産業の今後の発展はないと思われる。
注
1. P.45 (注5)参照。
2. Air Jet Loom(エア・ジェット織機)。空気流を利用して緯入れを行う織機。
3. Water Jet Loom(ウォーター・ジェット織機)。水流を利用して、緯(横糸)入れを行う織機。
4. 川上(化合繊製造、紡績、および素材流通)、川中(織布、編立、染色、および中間製品流通)、川下(縫製、製品流通)
5. 化学繊維の原料はパルプで、代表的なものはレーヨン。一方、合成繊維の原料は石油で、代表的なものは、ポリエステル、ナイロン、アクリルが挙げられる。
6. 生糸のように連続した糸のこと。長繊維ともいう。
7. 木綿や羊毛のようなわた状の繊維のこと。短繊維ともいう。
8. ベール等に用いる網状の薄絹のこと。
9. 織物のこと。
10. 加工されていない、織ったままの織物のこと。
主要参考文献
1. アジア経済研究所 編 (1980)『発展途上国の繊維産業』1980年
2. 北村かよ子 編 (1995)『東アジアの工業化と日本産業の新国際化戦略』アジア経済研究所1995年
3. ジャカルタ・ジャパン・クラブ (1996)『インドネシア・ハンドブック1995/1996年版』1996年
4. 末廣昭・保田靖 編 (1987)『タイの工業化 NAICへの挑戦』アジア経済研究所 1987年
5. 繊維産業構造改善事業協会 (1994)『2000年におけるアジア繊維産業』1994年
6. センイ・ジヤァナル (1996)『繊維関連のアジア進出企業一覧』1996年
7. 通商産業省生活産業局通商課監修(1996)『WTO繊維協定と繊維セーフガード措置』(財)通商産業調査会1996年
8. 通商産業省生活産業局 編(1994)『世界繊維産業事情』(財)通商産業調査会1994年
9. トラン・ヴァン・トゥ 編(1992)『産業発展と多国籍企業』東洋経済新報社 1992年
10. 日本化学繊維協会 (1997)『繊維ハンドブック 1998』1997年
11. 日本化学繊維協会 (1997)「調査レポート インドネシア・タイの繊維産業動向」1997年
12. 三平則夫、佐藤百合 編 (1992)『インドネシアの工業化 フルセット主義工業化の行方』アジア経済研究所 1992年
13. 安中章夫、三平則夫 編 (1995)『現代インドネシアの政治と経済』アジア経済研究所1995年

