RIM 環太平洋ビジネス情報 1998年4月No.41
悪化するタイ経済と日系企業
1998年04月01日 さくら総合研究所 黒田恵三
はじめに
1997年7月2日にタイ・バーツが突如、変動相場制へ移行してから9ヵ月余りが経過した。この間、バーツが大幅な下落と乱高下をたどる一方、景気後退が加速する中で、日系進出企業は輸入部材のコスト増、売り上げ不振、外貨建て負債の膨張という、かつて経験したことのない三重苦に直面して苦闘を続けている。本稿では、日系企業の置かれた状況、対策、業績回復の課題、タイの投資環境の変化などに焦点を当ててみたい。
1.低迷続くタイ経済、98年は成長のマイナス幅が拡大
97年のタイ経済は前年を下回り、わずかだが40年ぶりにマイナス成長に落ち込んだ模様である(図1)。8月にIMFなどから国際資金支援を受けるにあたり約束した、厳しい包括的経済再建策をベースに、経済運営を実施したことが影響したものである。民間消費は、所得の伸び悩み、付加価値税率の引き上げ、金利高、インフレ加速の中で一段と冷え込み、工業生産指数は8月から前年同月比マイナスへ、民間投資指数も10月からマイナスへ転落した。
一方、バーツ下落の中で輸出はにわかに息を吹き返し、バーツ建てでは7月以降の下半期に52%増と、目覚しい回復を遂げた。他方、輸入は景気低迷を受けて同期間に15%増にとどまり、貿易収支は黒字へ転じた。貿易収支が改善を続けるなか、バーツ下落の引き金となった経常収支も大幅に改善し、ドルベースに引き直した貿易収支、経常収支ともに9月から黒字に転じた。経常収支の月刊黒字計上は、実に14年ぶりである。
98年のタイ経済は、さらに落ち込んで97年に引き続き前年を割り込み、しかもマイナス幅は大幅に拡大する可能性が濃厚になってきた。IMFとの約定に基づく包括的経済再建策ならびに金融再建策の両再建策を順守するのに伴い、景気低迷の持続は免れ得ない状況である。ことに緊縮財政堅持のため、98年度(97年10月~98年9月)歳出予算は3度にわたりカットが繰り返された結果、8,000億バーツ(前年度比13.5%減)に抑制され、財政面からの景気浮揚効果はほとんど望み薄の状況である。さらに気掛かりなことは、貿易収支および経常収支の改善が、ドル建て表示の輸入の減少に大きく依存しており、長続きすると思えないこと、さらに、物価の上昇、失業者の膨張、倒産の増加などはこれから本格化すると見込まれることである。チュアン首相は去る3月の訪米時に、「タイ経済は最悪期を脱した」と宣言したが、タイ経済のファンダメンタルズはむしろこれから、なお悪化するとみられる。
現政権にとって経済再建に向けての最大の課題は、金融機関の不良債権処理の問題であろう(本誌掲載の「タイの金融システム改革」ご参照)。不良債権処理に必要とされる資金をどのように捻出するのか、間もなく回答を要求されることになろう。
2.落ち着きどころが見えてこないバーツ相場
変動相場制移行後のバーツ相場の動きを振り返ると、それまでの1米ドル=25~26バーツの水準から、移行と同時に下落、その後じりじり下げて97年10 月末には40バーツ台を突破し、年明け早々には50バーツ台に乗った。1月12日には最安値の57バーツをつけ、通算して54%の下落を記録した(図2)。しかしながら、1月末のバーツ国内・国外二重相場制の廃止や、近隣諸国の落ち着きに加え、チュアン政権の信頼度の向上とともに、バーツ相場は大きく戻し、3月30日には37.60バーツをつけるに至った。現在は40バーツを挟んだ動きとなっている。
政府当局は現時点での最優先課題としてバーツの安定に力点を置き、バーツの安定こそが、その他の経済課題の克服に資することになるとしている。政府当局は、3月下旬のバーツ相場の水準でもタイ経済のファンダメンタルズの実態からみてまだまだバーツが安い、とする見解を示し、企業の債務負担およびインフレ圧力の軽減の観点から、バーツ安是正を歓迎すべきとしている。しかるに経済界には、せっかく増加基調をたどり始めた輸出にブレーキをかけ、ひいては経済回復に水を差すことになりはしないか、と懸念する向きも多い。
今後のバーツ相場の行方については、経済回復の時期をどうみるかはさておいて、タイ国内には外貨建て債務返済のためのドル買い需要が根強いことから、中長期的にはバーツ安基調が続くとする見方が有力だ。さらに、2月末現在でなお163億米ドルに上るドル先物売り残高の存在も、バーツ相場の上昇を抑える要因となる恐れなしとしない。
いずれにしても、バーツ相場がどの辺りのレベルで落ち着きそうなのか、皆目みえてこないのが実情で、日系企業の間でドル建て債務のヘッジ、あるいは他国通貨建てへの乗り換えが目にみえて進行しないことの理由にもなっている。
3.日系企業のタイにおける高いプレゼンス
タイへの日系進出企業数は3,000社に及ぶとする説もあるが、バンコク日本人商工会議所(JCC)の加盟数は、97年6月末現在で1,144社を数え、プラザ合意を受けて外資の進出ラッシュが起こった86年の3月末における424社に比べ、10年余の間に2.7倍に急増している(表1)。業種別にみると、電気・機械(8.9倍)、金属(5.9倍)、化学・窯業(4.2倍)で増加率が高い。
日本からタイへの直接投資は、日本の大蔵省の統計では、1951年度から95年度までの累計で件数が3,253件、金額が1兆1,737億円、アジアの中では(1)インドネシア、(2)香港、(3)シンガポール、(4)中国に次いで5番目、アジアでのシェアは9%弱を占める。タイにおける外資系企業の登録資本金に占める日系企業のシェアをみると、1960年から96年までの累計で45.7%と、2位の台湾8.3%を大きく引き離して第1位である。
タイに進出した日系企業のタイ経済に対する貢献度は極めて大きい。その実態については、JCCの「日系企業の貢献度調査報告書(95年度)」(97年6月発表)によると、次の通りである。すなわち、日系企業の占める比率は、タイ全体の輸出の21.8%で、うち製造業では17.9%(日本向け47.5%、第三国向け11.9%)、また輸入の29.6%で、うち製造業では23.1%(日本から56.5%)に上っている。製造業について、タイ全体の雇用者に占める日系企業雇用者比率は7%であった。なお、日系製造業企業の原材料調達比率は、(1)現地調達比率38.7%、(2)日本からの調達比率 43.4%、(3)その他17.9%となっている。
いずれの統計も、日系企業のタイにおけるプレゼンスの高さを如実に物語るものといえよう。
4.内需不振、バーツ下落で日系企業に大きな打撃ー特に深刻な自動車業界
このようにタイにおいて高いプレゼンスを誇る日系企業ではあるが、長年にわたる通貨バスケット方式に基づくバーツ相場決定方式のもと、外貨建て債務を有する企業の大半が為替リスク回避のためのヘッジを行ってこなかったため、今回のバーツ下落により、巨額の為替差損を余儀なくされた。損失の規模について全貌をとらえるのは極めて困難であるが、日系企業全体では膨大な規模に達するのは間違いのないところで、例えば、A自動車メーカーでは外貨建て債務の評価損が 390億円に上ると報じられた。為替差損を被ったのはタイの地場企業の一部も同様で、国内最大の産業コングロマリッドであるサイアム・セメントでは、97 年末の連結決算で、ヘッジなき42億ドルの外貨借り入れにかかわる為替差損を主因に、526億バーツの赤字計上のやむなきに至った。
バーツ下落により日系企業が被った影響に関し、JCCが97年10月に日系企業を対象に行った「バーツ下落の影響調査報告」によると、悪影響と回答した企業が80%、好影響が17%、影響なしが3%となっており、大半の企業が悪影響を受けたことが再確認された。
図3によれば、非製造業の方が製造業よりも悪影響を受けた割合が大きく、また、製造業の中でも業種によって影響の濃淡がかなり明瞭に表れている。「輸送用機械」においては全回答企業が悪影響としており、とりわけ日本企業の独壇場である自動車産業では、大変な苦境に置かれている。タイの自動車販売台数は、 96年には58万9,000台のピークに達したが、97年はバーツ下落に内需不振が重なって36万3,000台と、前年に比べ38.4%も減少し、 92~93年の水準に落ち込んでしまった。自動車生産能力は80~100万台と推計されるので、設備稼働率は4割前後に落ち込んだことになる。IMFとの合意事項である健全財政の堅持を目的とした自動車消費税の5%引き上げも、売れ行きにさらに水を差す結果になった。最大手のB社では、11月中旬から2つある工場の操業を全面的に停止したほか、他のメーカーもいっせいに生産調整に踏み切っている。C社では部品の多くを輸入により調達しているため、調達コストの上昇が3割以上に達していると伝えられる。またD社のように、いち早くバーツ下落を予知し、ドル建て借入金を全額予約に切り替え、影響を回避した企業もある。E社では需要の急減に対処して、ノックダウン生産委託を中止し、ひとまずタイ市場から撤退することを決めたが、日本のメーカーで現地生産を打ち切るのは初めてのケースとなる。前記A社では、2つある工場のうちの一方を閉鎖する計画だ。
なお、バーツ下落に需要低迷があいまって、自動車部品メーカーへの影響は組み立てメーカーを上回って深刻化しており、自動車業界は裾野の広い業界だけにタイ経済に及ぼす影響も極めて大きいことが憂慮される。
自動車販売市場については、金融機関の不良債権処理の問題が大きくかかわっており、オート・ローンを扱う金融証券会社(ファイナンス・カンパニー。いわゆるノンバンク)が多数清算に追い込まれ、また新規にオート・ローンが組みにくい状況にあり、金融面でも苦境を余儀なくされている。
5.検討進む外貨借り入れの現地通貨への乗り入れと先物ヘッジーただし実行例はまだ少数
バーツ市場の先行きが不透明ななか、為替差損を回避するため、(1)ドル建てあるいは円建て資金調達からバーツ建て調達への乗り換え、(2)ドル建て借り入れの先物ヘッジ、を検討する日系企業が増えてきている。ただ、実行例はまだ少数にとどまっており。大きなうねりには至っていない。
タイの日系企業を実情として、「一部企業を除き、多くの企業がヘッジ率20~30%以下であり、ノーヘッジの企業も多くみられる。ヘッジをしない理由として、(1)今のバーツの水準で損失が出ているため、さらに高いスワップコストを負担してヘッジすることに躊躇している、(2)損失が多額に上り、バンコクの現地法人(または支社)で決断できず、放置されている」との指摘もある。日系企業の多くは97年末に決算期を迎え、1ドル=47バーツのもとに巨額の為替差損計上を余儀なくされた。その後、乱高下を経てバーツ高に向かい、前述のように40バーツを挟む水準にあり、もし今、ドル建て借り入れをバーツ建てに乗り換えれば、為替差益が確保できる状況にある。それでも企業が実際に乗り換えに踏み切れない大きな理由の一つは、20%近い高水準のバーツ金利にあるようだ。
6.景気回復の時期に対し、慎重な見方の日系企業
タイの景気はいつ頃回復に向かい、また回復を遂げるのかについては、日系企業ならずとも大いに気になるところだが、日系企業はかなり慎重にみているようだ。
現地の経済紙「バンコク週報」が10月に実施した日系製造業アンケート調査(対象:JCC加盟の日系製造業462社、うち回答企業162社、回答率 35.1%、実施期間:9月30日~10月7日。以下「調査」)と、同紙が「調査」に先立って9月22日~30日にバンコク都民を対象に実施したアンケート調査(以下「都民」)の2つの調査結果を評価すると、以下のようになる(表2)。
表2 景気回復までにかかる時間
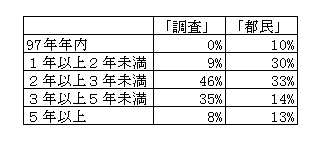
(資料)「バンコク週報」
この「調査」によれば、景気回復まで3年以上必要とみる日系企業が43%も占めるのに対し、「都民」では景気回復は2年未満のうちに実現するとみる比率が40%に達しており、景気の先行に関して慎重な日系企業と楽観的なバンコク都民との間で、対照的な結果が出ている。
なお、地場企業の間では資金流動性の不足、あるいは金融機関の貸し渋りの問題が深刻化してきたが、邦銀と取引する日系企業にはさしたる影響はなさそうだ。
7.日系企業が重視する今後の課題・対策
日系製造業企業が今後の業績立て直しの方策として重視すべき課題は、(1)「製品輸出比率の拡大」と、(2)「現地調達比率の向上」の2点となろう。
(1)について「調査」では、タイからの輸出は「今後横ばい」とした企業が22%であるのに対し、「増やす」と回答した企業が67%に上っている。特に、電子・電機、繊維、食品産業では80%の企業が、また自動車では54%、金属では57%の企業が増やすと答えている。輸出に活路を見出だしたい日系企業の意向が如実に示されており、国内市場への依存度を減らし、いかに輸出比率を高めるかが今後の課題となろう。ただ、タイの近隣諸国でも大幅な通貨下落に見舞われている状況のもとでは、アセアン域内への輸出拡大には困難が伴うと見込まれ、新規市場の開拓や、中東や東欧などへのシフトに苦心している企業もある。(2)については、「現地調達比率が80%以上の企業の場合、97年下半期の経常利益が減ると回答した企業が58%(増えるは17%)」であるのに対し、「現地調達比率が20%未満の企業の場合、下半期の経常利益が減るが81%(増えるは9%)」に及ぶ。さらに、製品価格を値上げする(値上げした)と回答した企業が「現地調達比率が80%以上の企業では41%」、「20%未満の場合は71%」と対照的な結果が出ている。
一方、バーツ下落の経営への影響が回復する時期については、1年未満5%、1年以上、2年未満21%、2年以上、3年未満31%、3年以上31%という割合になっており、日系企業が業績回復までに長い期間を要するとみていることが読み取れる。
日系企業のバーツ下落への対応策を、前記JCCの「バーツ下落の影響調査報告」でみると、表3のように、原材料・部品の輸入から国内調達への転換、製品販売価格の値上げ、為替予約などのリスク・ヘッジが上位にランクされている。
8.投資委員会(BOI)の外資導入政策の改定により、日系企業へ好影響
タイでは投資政策上、全土を3つの地域に分け、バンコク首都圏を第1地域、その近県を第2地域、遠隔地を投資奨励地域の第3地域に指定し、この第3地域に進出する企業に最も手厚い投資優遇措置を付与し、投資の地方分散と地域開発の推進を図っている。
BOIではバーツ下落を踏まえ、8月に発表した包括的経済再建策に呼応する形で、10月下旬に投資政策の改定を決めた。改定の内容は、(1)農業、アグロインダストリー分野の重視をはじめとする外貨獲得のための輸出拡大、(2)国産化推進のための特別奨励業種の拡大など、外貨保持のための輸入代替、(3) 外資による産業支援を促すための外資優遇策、を柱とするものである。日系企業は今回の改定を高く評価しており、これまで様々な制約に悩まされてきた経緯に鑑み、歓迎する声が強いと伝えられる。なかでも外資優遇策に盛り込まれた「外資出資規制の緩和措置」が大きな評価を受けており、バーツ下落で為替差損を被った企業がバランスシート改善を図るには増資が最も効果的だが、タイ側パートナーの資金力不足がネックとなっていたとする企業もあり、今後は日系企業が増資について弾力的に対応可能となった。
9.なお有望視される投資先国としてのタイの将来性
これまでタイの外資導入に占める日本のシェアは、群を抜いて第1位を占めてきており、したがって日本企業がタイを投資先国としてどう評価するかは、今後ともタイへの外国投資の動向を展望する上で極めて重要な判断要素となろう。
日本の企業が諸外国を投資先国としてどう評価しているかについては、日本輸出入銀行が89年から毎年実施している「海外直接投資アンケート調査」が貴重な情報を提供してくれている。この調査は原則として「生産拠点1社以上を含む海外現地法人を3社以上保有している製造業の企業」全部を対象に行っており、いわば海外事業展開の経験豊富なわが国有力製造業企業を広く網羅したユニークな調査といっていい。
公表された最新の「97年度調査結果」(調査対象企業743社、調査期間は97年の7~9月、回答企業445社、回答率59.9%、「海外投資研究所報」 98年1月号)によれば、タイをはじめインドネシア、マレーシア、フィリピンの4カ国は、94年度調査以来、中期的(今後3年程度)に有望な投資先国にも、長期的(今後10年程度)に有望な投資先国にも、例外なく揃ってベストテンにランクされた(表4)。
タイの位置づけをみると、中期的有望性ランキングはそれまで3年連続で2位を占めてきたのが、97年度は4位へ下降するとともに、タイを選択した比率も低下し、長期的ランキングでは94年3位、95年5位、96年6位、97年6位にランクされている。総じていえば、タイの通貨危機、経済・金融危機を経験後といえども、日本企業は投資対象国としてのタイを引き続き高く評価している、といって差し支えないのではないか。さらにいえば、このアンケートの調査時期が7~9月ということで、(1)インドネシアのルピアの暴落、ならびにIMFなどとの支援条件にかかわる確執、(2)チュアン政権の誕生、などの情勢が折り込めなかったことを考慮すれば、タイの順位が低めに表れているといえるかもしれない。
なお、最近の外資導入状況については、95年をピークとする外国投資の「第3の波」も、96年の景気後退、97年のバーツ危機を経て、さすがに縮小傾向が鮮明になってきた。
97年の外資導入実績(BOIの投資申請ベース)は607件、3,444億バーツで、NIEsや日本の落ち込みを主因に、件数で6.3%、金額で 17.5%減少した(表5)。日本からは件数が216件で32%減、金額が983億バーツで27%減となり、金額では欧州、NIEsに次いで3位に下降した。日本からの投資は通貨危機以降の落ち込みが急で、BOIによれば、タイ国内市場向けが中心の自動車、家電製品用の部品メーカーなど、いわゆる裾野産業への投資申請の減少が目立つと伝えられている。投資家の主体が組み立てメーカーから部品メーカーへ移行する過程で、1件当たり投資額の小型化が定着したのが特徴だ。
投資地域別にみると、97年上半期のBOI認可証発給件数426件(国内・外資を合算)のうち、第1地域が55件、13%、第2地域が83件、19%、第3地域が288件、68%となっており、引き続き第3地域へ立地する比重が高くなってきている。
なお、今年1月のBOI発表によると、すでに投資奨励を受けた案件について、経済落ち込みの影響のうち最も大きなものは、投資資金の確保であるという。 93年以降97年10月までに投資奨励を認可した投資規模10億バーツ以上の大型案件286件(投資総額1兆3,352億バーツ)の追跡調査を行ったところ、中止決定、または中止の可能性大が24件(1,160億バーツ)、景気回復や合弁相手との交渉待ち、または資金確保の遅れといった理由から延期が41 件(3,251億バーツ)あることが判明した。中止・延期の案件を業種別・部門別にみると、多いのは鉄鋼、石油化学、製紙、逆に少ないのはサービス、公共事業、軽工業、農業、アグロ・インダストリーで、輸送機械および部品製造、電気・エレクトロニクス製造の部門では、中止・延期されることなく進捗中である。ここへきて内外投資家が一層慎重な姿勢を示し始めたことがうかがえる。

