RIM 環太平洋ビジネス情報 1997年10月No.39
アジアにおける高度情報化への取り組みの現状と展望
シンガポール、台湾、マレーシアを中心に
1997年10月01日 さくら総合研究所 大木登志枝
はじめに
アジア各国は1980年代以降、輸出志向の工業化と海外からの直接投資によって飛躍的な経済発展を遂げたが、それを支えたのが海外とのコミュニケーションを可能にした情報通信インフラであった。経済発展に伴い、情報通信インフラ整備は急速に進展し、アジアNIEsでは、ユニバーサル・サービス(すべての国民に、あまねく安価に電話サービスを供給すること)を達成した。
しかし、アセアン、中国などの発展途上国では、依然として都市と地方の電話回線普及率において格差が残っている。
90年代に入って、世界情報基盤(GII)やアジア太平洋情報基盤(APII)など、国際的に高度情報化に対応した情報通信インフラを整備しようという動きが出てきた。近年、アジア各国でも、21世紀における持続的成長を目指して、来たるべき高度情報化社会を視野に入れ、情報通信インフラ整備を推進している。
本稿では、アジアがどのように高度情報化に取り組んでいるのかを明らかにし、将来を展望することを目的とする。
まず I では、高度情報化社会とその成立要件について述べ、II ではアジア全体の動きを概観し、III ではシンガポール、台湾、マレーシアのケースを取り上げて、高度情報化に各国がどのように取り組んでいるかをインフラ、アプリケーション、技術開発および関連人材の育成、環境の各面からまとめる。IV では、これらを踏まえて、アジアの情報通信基盤整備の展望、高度情報化社会への課題について考える。
なお、本稿でいうアジアとは、NIEs、アセアン、中国を指すものとする。
I.高度情報化社会とその成立要件
アジア各国の高度情報化への取り組みを分析するにあたり、ここでは、高度情報化社会と過去の社会との相違点、高度情報化社会が成立する要件について簡単に述べてみたい。
1.高度情報化社会とは
70年代には、通信といえば、電話、テレックス、電報によって音声か文字を伝送することを指し、インフラは主として銅ケーブルおよびアナログ無線であった。80年代に入って情報化が浸透し、メインフレーム・コンピュータ、デジタル通信を利用して、企業やVAN業者がLANを構築し、データなどを伝送するようになった。
現在到来している高度情報化社会とは、情報通信ネットワークを利用し、音声、文字、データ、画像など多様で大量の情報を相互に交換することにより、企業やVAN業者だけでなく、政府、教育機関、一般市民が、ビジネス、医療、教育、福祉、娯楽など様々な分野の活動を電子ネットワーク上で行えるような社会のことである(図1)。このような社会は、高度情報化社会、または電子ネットワーク上での情報交換により成立することから、サイバー社会とも呼ばれる。
情報化は、なぜ重要なのだろうか。情報化は「産業の情報化」および「情報の産業化」により、産業の高度化と社会生活の質の向上をもたらすものと期待されている。
「産業の情報化」とは、生産性を向上させることや(在庫の減少、開発リードタイムの短縮化、作業の効率化など)、付加価値を生み出すこと(R&D、マーケティングに情報化を組み込むことによってもたらされる製品品質の向上など)をいう。
「情報の産業化」とは、バーチャル・ショッピング、電子マネー、電子商取引(Electronic Commerce:EC)、遠隔教育、遠隔医療など、情報通信技術を利用して新サービスを創出することをいう。実際、米国では、高度情報化によってインフレなき経済成長(ニュー・エコノミー)がもたらされているという説があるほどである。
アジア各国でも、21世紀における持続的成長を目指し、情報通信基盤の整備、高度情報化を推進している。ほとんどのアジア諸国では、低下するコスト面での競争力を産業の高付加価値化によって補うことが重要課題となっているが、高度情報化はその鍵を握っているといえよう。
2.高度情報化社会の要件
高度情報化社会が成立する主たる要件として、次の4点を指摘したい。
まず第一に、高度情報通信インフラの整備である。現在、情報通信インフラは、固定回線(銅/同軸/光ファイバー・ケーブル)、移動系回線(地上系無線、衛星系)から、放送(地上波系、衛星系)、CATVと多様化している。マルチメディアに対応するには、加入者線にも1.5Mbps(注1)以上、画像が入れば10Mbpsが必要であり、既存の電話回線(64Kbps)の高速大容量化もしくは高度インフラの新設が求められる。そして、その実現のためには技術と資金が必要である。
第二に、利用者のニーズに合った多様なアプリケーション(電子マネー、遠隔教育などの応用技術)が導入されていること、第三に、端末、ネットワークなどのハード技術の導入、データベースなどのアプリケーション、コンテンツなどソフトの開発を行う人材を擁していること、第四に、高度情報化社会を支援する環境が整備されていることが挙げられる。
高度情報化社会においては、技術を開発する以上にそれを導入する環境整備が重要であり、その割合は技術:環境=20%:80%との指摘もある(注2)。ここでいう環境とは、(1)規制緩和の推進、(2)国際標準の採用、(3)法制度の整備、(4)商慣習の見直し、(5)ITリテラシーの向上を意味するが、その内容については表1に記載した。
II.アジアにおける高度情報化の概観
ここでは、アジア全体におけるインフラ整備状況、および新しい動向、高度情報化計画について概観する。
1.国内インフラ整備と規制緩和
高度情報化社会を支える支柱の一つはインフラ整備である。80年代以降、経済活動のグローバル化がもたらす通信需要の増加、技術革新による通信サービスの多様化に対応するため、世界的に通信インフラ整備が推進された。
特に、アジアにおける通信インフラ整備の増強ぶりには目をみはるものがあり、84~95年の11年間に、中国が15倍、タイ、インドネシアが6~7倍、マレーシアが4倍の伸びを示した。NIEs諸国は2~3倍であるが、日本・米国が1.4倍であったことを勘案するとその伸びは高いといえよう。
アジア各国の電話回線普及率(人口100人当たりの電話回線数)をみると(表2)、95年において、香港、シンガポールでは52.8%、46.9%、韓国、台湾でも40%以上と、すでに先進国レベルに達している。マレーシアは16.6%であるが、タイ、インドネシア、フィリピン、中国は2~6%と低い。
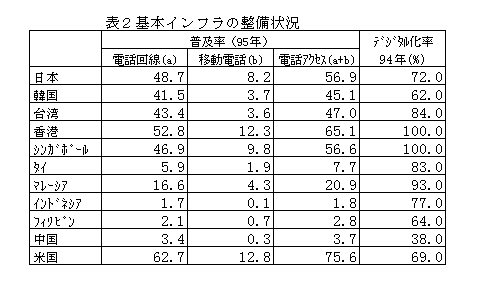
(資料)ITU(1995a),ITU and TeleGeography Inc.(1996)
普及率が低い国では、都市と地方との電話回線普及率の格差が大きく、社会的な問題となっている。例えば、インドネシアの場合、ジャカルタの普及率7.7%に対し、地方は0.7%、またフィリピンの場合、マニラの6.7%に対し、地方は0.5%といった状況である(93年、表3)。
しかし、逆説的ではあるが、途上国では既存の通信インフラが不足しているがゆえに、開発当初から最新技術を導入し、いわゆる「後発の利益」を獲得できるという面もある。その例として国内の固定回線のデジタル化率をみると、タイ、マレーシアでは80%を超え、インドネシアも77%と、日本の72%より高くなっている。
また、固定回線の普及が遅れていたアセアン各国や中国では、移動電話が当初から一般用として利用されるケースが多い。経済発展に伴って急激に増加する通信需要に、莫大な資金と長期間を要する固定電話回線の整備では対応しきれなかったため、より安価で短期間に整備できる移動体通信が普及するようになったのである。
アジア各国における移動電話の普及率をみると、香港、シンガポールではそれぞれ12.3%、9.8%と日本より高く、韓国、台湾では約4%である。アセアン各国、中国では、4.3%のマレーシアを除き、0.1~2%と高いとはいえないが、加入者数は著しく増加している。91~95年の4年間に、アセアンでは6~26倍、中国では76倍の伸びを示した。ちなみに、NIEsでは3~10倍、日本では7.4倍である。
この伸びを可能にしたのが、規制緩和である。先進国において電気通信サービスの規制緩和が始まったのは、電話回線普及率が40%を超え、ユニバーサル・サービスが実現した後であったが、アセアンにおいては、電話普及率が1%に満たない、かなり低い段階で規制緩和が導入された。
具体的には、国営企業の民営化が進み、競争導入が図られ、外資参加枠が拡大した(表4)。特に、移動体通信分野では、固定通信分野に比して規制緩和が進んでおり、外資を含む民間企業の競争が促進された。
2.アジアにおいて期待される移動体通信
さらに、21世紀に向けて、移動体通信は新しい動きをみせている。その一つは、国際ローミング(注3)によるグローバル地上波移動体通信システム、もう一つは、衛星利用の移動体通信システムである。
前者は、FPLMTS(Future Public Land Mobile Telecommunication Systems)またはIMT-2000(International Mobile Telecommunications: 次世代移動体通信)と呼ばれるシステムで、2000年頃の導入が計画されている。このシステムでは、1台の移動端末で全世界と通信でき、その伝送速度は2Mbpsで、固定回線と同等の品質を持たせることを目指している。日米欧の企業は、このシステムの国際標準を獲得するため、目下、し烈な戦いを展開中であるが、最終的に99年に、国際電気通信連合(International Telecommunications Union:ITU)によって決定される。
後者の衛星を利用した通信システムは、アジアでは島嶼国であるインドネシアで70年代後半より運用されていた。現在では、GMPCS(Global Mobile Personal Communications Satellite)と呼ばれる全世界をカバーするシステムの整備が推進中で、98年から次々と実用化される。
表5は、アジア企業が参加する、移動電話サービスを提供する衛星利用の移動体通信システムをまとめたものである。欧米企業主導のシステムとしては、イリジウム、グローバルスター、アイコ、オデッセイなどがある。これらは、地上波移動電話と接続できるほか、地方の交換局や公衆電話へのアクセスも想定されている。
シンガポール企業および中国企業主導のエーピーエムティー、インドネシア企業主導のエーセスは、サービス地域をアジアに限定し、国内の地方への通信アクセスの改善も目指している。これらの通話料金は、サービス域内ならどこへかけても一律で、しかも0.5~1米ドルと、かなり安価に設定される模様である。
加入者線に移動電話やPHSなどのデジタル無線技術を適用するシステム(Wireless Local Loop:WLL)も開発され、途上国の市内網整備に導入されている。このように移動体通信は、途上国において未整備状態にある長距離・市内網の固定回線を補完していく役割を担っていくと予想される。
3.不足する技術開発の人材
アジア各国は、インフラ整備に要する資本のみならず、技術も先進国企業に依存している。各国は、自国でハード関連の技術を開発する力はなく、先進国と比肩する技術開発力を持とうとは考えていないようだ。シンガポールでさえ、回線、端末、伝送・交換設備などの基礎技術は、海外から導入すると決めている。
この理由には、(1)技術革新のスピードが速く、自国で開発していては国際水準に追い付かない、(2)自国で開発したとしても、標準化されなければ機会費用が大きすぎる、(3)標準化された技術を導入した方が国際需要に対応できるし、コストが安価である、といった点が考えられる。
ここで鍵となるのが、標準化が世界の趨勢になっていることである。今日、情報通信のハードの新技術を開発しているのは、日米欧の企業に限定されてしまっている。したがって、アジア各国に求められているのは、日進月歩で変化する技術を理解し、活用し得る人材であるが、現段階ではアセアン、中国では不足している。
一方、アプリケーション、コンテンツといったソフトは、アジア各国の独自の開発力が生かせる分野である。当然、先進国から輸入する技術も多いが、その場合でも、自国の言語へ転換したり、自国の市場・産業に合うように修正を加える必要が生じてくる。また、自国独自のニーズに合ったアプリケーションを開発することもあり得る。
例えば、シンガポールにおけるEDI(Electronic Data Interchange:電子データ交換)やデビットカードシステム、マレーシアにおけるスマートカードなどである。このようなソフト開発能力を持つ人材はニーズが大きいが、アジアでは全般的に不足している。
4.各国における高度情報化関連政策
高度情報化に取り組むため、レッセフェールを標榜する香港を除くすべてのアジア各国では、高度情報化に向けた計画が策定され(表6)、進捗の差はあれど、それぞれ実行に移されている。
表6
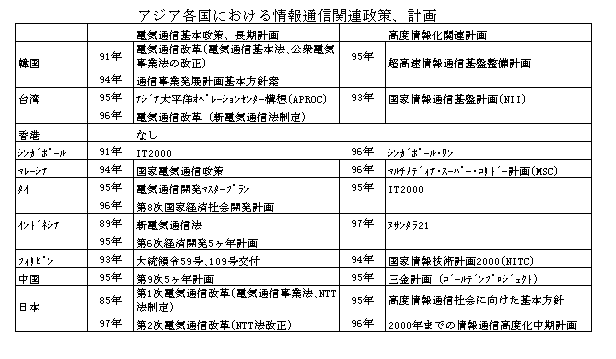
(資料)さくら総合研究所作成
どの国も、自国経済の高度化には高度情報化が重要であることを認識し、情報化によってもたらされる技術革新を産業の各部門に組み込み、生産性を向上させ、製品・サービスの高付加価値化を図り(産業の情報化)、かつ新サービス業を創設する(情報の産業化)ことを目指している。
III.アジア各国における高度情報化への取り組み
ここでは、アジアにおける高度情報化への対応をみるために、情報通信基盤整備が進んでいるシンガポール、またNIEsから台湾、アセアンからマレーシアを取り上げて、各国の(1)高度情報化戦略、(2)インフラ、(3)アプリケーション、(4)技術開発および関連人材の育成、ならびに(5)法整備などの環境の各分野について現状を概観したい。
なお、アプリケーション例としては、各国ですでに導入され、比較がしやすい貿易EDIの状況および高度情報化計画の進捗状況をみることとする。
1.シンガポール
(1) 戦略
シンガポールは、86年に国家情報技術計画、92年に「IT2000インテリジェント・アイランド構想」を発表し、アジアの中では最も早い時期から高度情報化を意識した政策を進めてきた。96年には「シンガポール・ワン」というアクション・プランを打ち出し、2005年には家庭、オフィス、教育機関をネットワークで結び、多様なマルチメディア・サービスを提供し、高度情報化社会を他国に先駆けて実現することを目指している。
21世紀をにらみ、シンガポールは、情報化により国民の生活水準を向上させるとともに、情報通信関連の技術、ノウハウを輸出し、情報通信産業を自国の基幹産業とする方針を持っている。
(2) 審議結果
電話回線の普及率は47%(95年)で、そのデジタル化率は100%である(前出表2)。
97年にはFTTC(fiber to the curb:カーブ[日本では電柱または電話局に当たる]まで光ファイバーを敷設すること)の完成、2005年にはFTTH(fiber to the home:家庭、オフィスまで光ファイバーを敷設すること)の完成が計画されている。
しかし、光ファイバーが高価であることから、加入者線においては既存ケーブルの有効利用(銅ケーブル・同軸ケーブル(注4)とのハイブリッド使用(注5)、ADSL(注6)技術の導入など)で対応することが検討されている。また、次世代インフラとして、広帯域マルチメディアに対応するWLLも視野に入れている。
(3) アプリケーション
1) 貿易EDI
シンガポールでは、89年よりトレードネット(TradeNet)という自動通関用EDIが貿易開発庁(TDB)により導入された。目的は、貿易関係者と政府機関の間を流通する書類の準備、伝送、処理に要するコストと時間を削減することであった。実際、官庁や関連企業で人員削減、オフィススペースの節約が可能となったほか、貿易業者は年間約10億米ドルのコスト削減に成功したという(注7)。
トレードネットは、365日24時間フル稼動で、TDB、関税局、航空局、貨物取り扱い業者、航空貨物業者、貿易業者、フォワーダー、船会社、港湾局など約1万社が結ばれ、輸出入関連の申請手続きが2分以内で処理され、申請書類は関連政府機関へ自動転送されるシステムになっている。また、トレードネットはポートネット(港湾情報システム)や米国の自動通関システムと接続されている。
貿易EDIの実現化のためには、諸手続きが電子ネットワーク上で処理できるような仕組みになっていることが重要である。シンガポールでは、もともと申請書類が10種類と極めて少ないこと(日本は40~45種類(注8))、導入にあたり輸入は事前通関、輸出は事後報告と、手続きが簡素化されたことがトレードネットの成功の一端を担っている。
2) シンガポール・ワン
IT2000では、(1)教育、(2)建設、(3)ヘルスケア、(4)製造・物流業、(5)デジタル図書館、(6)行政サービス、(7)ニューメディア・インターネット、(8)観光・レジャーをアプリケーションの重点分野としている。そのアクション・プランである「シンガポール・ワン」のアプリケーション実施予定は以下の通りである。
i) 第1フェーズ(96~2001年):遠隔教育、電子図書館などのテストベッド・プロジェクトを、97年第1四半期に300世帯で、同年第4四半期に5,000世帯で実施の予定。
ii) 第2フェーズ(99~2004年):ビデオ・オン・ディマンド(VOD)、電子ショッピング、ホームバンキング、遠隔教育、ビデオ会議、テレコミューティング、ECなどのアプリケーションを実用化する。
なお、経済開発庁(EDB)により、シンガポール・ワンへの参加企業には、補助金や税制面での優遇措置が適用されるスキームが策定されている。
(4) 技術開発および関連人材の育成
シンガポールでは、ハードインフラ関連の新技術については先進国企業より入手するケースが多く、新技術のパイロット・プロジェクトを歓迎している。
97年には、情報通信の研究開発機関とハイテク企業を誘致・育成するため、衛星通信施設を備えたインテリジェントビル、テレテックパーク、通信のバックアップセンターであるテレパークを設立した。ソフトウェアに関しては、政府が補助金を支給し、政府系研究機関が中心になって開発を行っている。
科学教育のレベルは高く、米国留学経験者も多いが、人口が絶対的に少ないことから、開発研究要員の数も少ない。表7に、多国籍企業および国内企業の管理職層に実施したアンケート結果を掲げているが、「有能なエンジニアの調達」は46ヵ国中32位となっており、シンガポールに対する他の技術開発関連の評価に比べ低い。
(5) 環境整備(法整備など)
シンガポールは、常にグローバル市場を念頭に入れているため、国際標準の採用に積極的である。例えば、89年には、国際標準として認可されたばかりのEDIFACT(注9)をトレードネットに導入した。
サイバー法は現在整備中で、商慣習の面では、国民の開放性、柔軟性が比較的高いと評価されている(表7)。一方、シンガポールには、インターネットの検閲など情報規制が存在するため、将来、自由な情報の流れを阻害する可能性があると危惧する声もある。
政府は情報技術(IT)教育を重視し、初等教育段階から教育を実施している。現在、小学校以上の児童・生徒3人に1台の割合でパソコンが提供されている。また、コミュニティーでも公民館などにパソコンで遊べるスペースを確保し、幼年期からのIT教育を実施している。
パソコン普及率、インターネット普及率はアジアの中で最も高く(表8)、さらに政府は98年までに全家庭の50%にパソコンを設置する予定である。英語も公用語として広く普及している。
2.台湾
(1) 戦略
台湾は、アジアの中で電気通信政策面における自由化が遅れていたが、高度情報化社会を目前に控え、96年、新通信法を制定し、規制緩和を開始した。
まず、移動体通信分野が開放された。基本通信分野は、96年にようやく会社化された中華電信の独占となっているが、98年には競争導入が予定されている。台湾における規制緩和は、開始時期が遅かった分、他国に追い付くため速い速度で進捗しているようだ。規制緩和の成否が台湾の情報通信の将来を握っているといえよう。
台湾では、95年より、アジア・太平洋地域における製造、海運、航空、金融、情報通信、メディアの6分野に関するセンターを建設するという「アジア太平洋オペレーションセンター(APROC)」構想が推進されている。情報通信は、その目標6分野のうちの一つで、台湾がアジア・太平洋における情報通信の基地となることによって、経済を活発化させることを目指している。
また、高度情報化社会に向けて国家情報通信基盤(NII)計画が策定され、B-ISDN(光ファイバーとATM(注10)による広帯域デジタルネットワーク)の建設、インターネットの普及、アプリケーションの実施を関連官庁が連携して推進している。電信総局長によると、NIIではパソコンやインターネットなどのIT教育に最も重点が置かれているということである。
(2) インフラ
電話回線の普及率は43%(95年)で、そのデジタル化率は84%と高い。中華電信では、普及率を2000年には60.5%に向上させる計画を持っている。
94年にNIIが発表された当初は、台湾全土にB-ISDNを敷設することが最大の目標であり、伝送速度を64kbps~1.5Mbpsから 45Mbps~155Mbpsに加速させ、光ファイバー敷設率を24%(96年)から2000年には100%とし、FTTCを完成させる計画であった。現在もその方向性は変わらないものの、既存回線の利用、インターネット普及率の向上に重心が移ってきている。
また、双方向アプリケーション対応のため、CATV、無線・衛星による移動体通信を統合したインフラも検討中である。新法成立後、98年に初めての通信衛星をシンガポールと共同で打ち上げることとなり、台湾域内のテレビ番組の送信、企業内通信に加え、中国との通信に利用する方向を探っている。
(3) アプリケーション
1) 貿易EDI
台湾における貿易EDIには、90年以降財務部(大蔵省)によって開発されたトレードVANがある。税関、通関業者、海運・航空業者、銀行、FISC(Financial Information Service Center)など、約4,500社がこれによって結ばれている。24時間フル稼動で、航空貨物の約90%、海上貨物の約50%が15分間で自動的に通関業務を処理することができる。金融EDIと結合された関税支払いシステムが94年に開発され、輸入税関業務の3分の1がこのシステムで処理されている。
台湾では、トレードVANを他の業界VANとつないだ統合VANを、国際標準を採用のうえ実用化する計画がある。
2) NII
NIIでは関連官庁の協力のもと、次のようなアプリケーションが台湾全域で推進されている。
1. 遠隔教育:台湾、中央、精華、交通、成功、中正、中山の7大学において、各大学の授業がオンラインで受講できる。また、各大学間の単位交換制度も整備する。すでに3大学と4大学の2グループで実験を実施、今後、7大学間をすべてネットワーク化する予定。
2. 遠隔医療:医療施設が不足している島と大都市の5病院を結び、島の医療サービスの向上に努める。現在は病院間ネットワーク用のISDNを建設中である。
3. VOD:テストベッド・プロジェクトを経て、97年1月よりサービス実施。
4. EDI:他のアジア諸国と比較して進んでおり、貿易、製造業(自動車産業)、商業(小売、電子産業)、金融、出版、公共工事入札の分野で実施中。
5. オンライン・データベース:既存3,000のデータベースをオンライン化する。例えば行政部門では、戸籍、国民健康保険などのデータベースをオンライン化して、諸手続きの簡素化を図る予定。
6. インターネット・プロモーション:インターネットのユーザーを2000年までに300万人(現在の5倍)に増加させる計画である。
(4) 技術開発および関連人材の育成
エレクトロニクス製品の生産額が世界第3位である台湾では、情報通信機器の生産も増加しつつあるが、新技術は、現時点では海外より導入することが多い。 96年の規制緩和も、海外企業の誘致を視野に入れたものである。近年、新竹科学工業園区の成功が注目されているが、ここには、大学、政府系研究所、海外・域内のハイテク企業が集中し、研究開発の成果が短期間で商業化できる仕組みになっている。
現段階では、開発研究要員は日本と比較し少数であり、ソフト関連の開発要員が育っていないとの台湾企業からの指摘もある。しかし、大学では理工系学生の比率が6割と高いうえ、欧米留学経験者も多く、米国との間に人的ネットワークが築かれているため、多国籍企業は開発要員は潜在的には豊富とみている(前出表7)。また、人材が豊富な中国に、ソフト開発を業務委託するケースも増加しつつあるという。
(5) 環境整備(法整備など)
台湾では、国際標準と域内の商慣習に合った標準を開発・採用する方針である。すべてのEDIはEDIFACT準拠である。台湾のEDIは、異業種間でのデータ交換も可能である。
制度面をみると、NII委員会では、NII関連の諸規制を見直した上で、その修正のための申請を行っている。また、知的所有権に関する法律の変更など、高度情報化社会にあった法整備を行う予定である。多国籍企業などからは、台湾人は対応が早く、柔軟性があると認識されており(前出表7)、情報化に伴う変化の速さにもうまく対応していくとみられている。
パソコン普及率およびインターネットの普及率がまだ低いため(前出表8)、NIIでは普及率向上を図る計画がある。中学校以上の教育機関については 100%、小学校については60%をネットワークで結び、また初等教育にインターネットのカリキュラムを開設する。日本と同様、一般市民の間では英語の普及度が高くないことが情報化へのネックになると懸念する声もある。
3.マレーシア
(1) 戦略
マレーシアは、アセアン(シンガポールを除く)の中で最も情報通信インフラが充実している。
電気通信分野における政策面での規制緩和を80年代から進めていたが、90年代に入り、「ビジョン2020」(2020年までに先進国入りするという構想)達成のため、産業の高付加価値化を図る上での原動力として、情報通信産業育成に重点を置き始めた。
94年には、高度情報化社会の樹立を目指した国家電気通信政策を、96年には「マルチメディア・スーパー・コリドー(MSC)」計画を発表した。MSCは、マレーシアが将来の自国経済の命運を賭けて、世界から資金、技術、人材を結集し、関連官庁が一丸となって推進している国家プロジェクトである。
MSCはシンガポール・ワンと似ているが、コストがより安く、情報がより開放的である点でシンガポールより優位性を持つといえよう。しかし、産業の集積度、情報産業の進展度など、総合的にみればシンガポールに一日の長があることは否めない。
(2) インフラ
電話回線の普及率は17%(95年)ではあるが、そのデジタル化率は93%と極めて高い。基本通信業者であるテレコム・マレーシアでは、電話回線普及率を2005年には30~35%、2020年には50%に向上させる予定である。
MSC内には、信頼性が高く高速大容量(2.5~10Gbps)で、国内外と円滑に接続できる広帯域ネットワークを構築する予定である。当初は100%光ファイバーとする計画であったが、コスト削減のため、ADSLやWLLの利用を検討しており、現在、実用化に向けて実験中である。MSC内のインフラ整備には、日本のNTTがマスタープラン作成時から積極的に協力している。
(3) アプリケーション
1) 貿易EDI
95年より政府主導で海上貨物通関処理システムとしてダガンネット(Dagang Net)が導入され、その際、EDI関連の法律も改正されるなど環境も整ってきた。利用者は急増しており、貨物情報の60%、輸入申告の70%、輸出申告の80%がダガンネットにより電子処理されている(注11)。96年には、金融EDIと結合され、関税支払いについても電子化が可能となった。
2) マルチメディア・スーパー・コリドー
MSCでは、2000年までに、4つのインフラプロジェクト(クアラルンプール・シティ・センター、プトラジャヤ、サイバージャヤ、クアラルンプール新国際空港)の完成、7つのアプリケーション(電子政府、多目的カード、スマートスクール、研究開発センター、世界製造拠点、マーケティング拠点、遠隔医療)(注12)の実施が予定されているが、現在、具体的に進んでいるのは次の2つである。
1. 電子政府:官庁間の事務、行政手続を電子化するもので、98年よりプトラジャヤにて実施する。
2. 多目的カード:一つのカードが、ID、電子財布、医療カルテなどに使用できる多機能のカード・システムで、98年に一部実用化の予定である。マレーシアは国レベルでこの種のカードを導入する最初の国になる。
金融危機の後の97年9月10日、マレーシア政府は経常赤字削減策の一環として、プトラジャヤ建設の第2・第3フェーズの延期を発表した。MSCは民活プロジェクトが多いため、金融危機は株式市場の低迷、金利の上昇により、民間の資金調達面で影響を与え、短期的にはMSC全体の進捗を遅くする可能性がある。しかし、長期的な方向性を変えるものではないと思われる。9月下旬、NTTはMSCにおける研究開発の本格化を表明し、各進出予定企業による変更の発表もなされていない。
(4) 技術開発および関連人材の育成
マレーシアは、他の途上国と同様、情報通信技術を先進国から輸入している。MSCでは日本のNTTが情報通信技術を全面的に支援し、欧米、アジアの優良ハイテク企業のトップがMSCのアドバイザーとなっている。そのほか、シンガポールと同様、新技術の実験の場を提供しているためか、多国籍企業による「新情報技術の実施」に対する評価は46ヵ国中4位と高い。
マレーシアでは、開発研究要員が不足しているため(前出表7)、MSC実現にあたり、短期的には人材を海外から誘致し、関連産業に従事させる予定である。そのため、MSC内の海外雇用者にはビザを免除し、外国人にとって住みやすい住環境の整備を行うことを計画している。
自国の人材が育つまでは(政府によると2005年頃まで)海外の頭脳に依存するが、長期的には、スマートスクールなどを通して自国の人材育成を図る方針である。多国籍企業による「義務教育における科学教育」および「技術開発・導入環境」に対する評価は途上国としては高いが、技術開発の人材育成には時間がかかるだろう。
(5) 技術開発および関連人材の育成
EDIは、95年に導入されたため、後発の利益を享受し、EDIFACTを採用している。
制度面では、EDI関連法を94年に成立させた。97年に入って、サイバー法のうち、電子署名法、コンピュータ犯罪法、遠隔医療法、修正著作権法が成立し、現在、電子政府法、マルチメディア集約法が審議中である。サイバー法への取り組みは先進国と比べても早い。MSC構想が96年8月に公式に打ち出されてから、マハティール首相をトップとする政府の意思決定の早さが、海外企業より高く評価されている。
マレーシアには、強力な政治的リーダーシップが存在し、国民は柔軟性があることから(前出表7)、商慣習の変更への抵抗は少ないとみられる。
パソコン普及率、インターネット普及率はまだ低く、スマートスクール・アプリケーションによるインターネットの普及、初期教育段階におけるIT教育の導入などにより、市民のITリテラシーを高める計画がある。なお、在マレーシア日系企業からは、従業員のパソコンの利用能力は日本人より高いとの指摘があった。英語は公用語として広く普及している。
IV.アジアにおける高度情報化への展望と課題
以下、21世紀のアジアにおける高度情報化社会を展望するとともに課題を述べることとする。
1.アジアにおける高度情報化への展望
II、III でみたように、アジア各国では、高度情報化に向けて着々と準備を進めている。
21世紀初頭に向け、アジア各国では、自国の経済発展に見合ったレベルで情報化を推進していくだろう。アセアン各国および中国の国内における都市と地方の格差は、移動体通信の導入などにより徐々に縮小していくだろう(もっとも国によっては、かなりの時間を要するだろうと思われる)。
そして、アジア各国の大都市は、情報通信産業のグローバル化、標準化の影響で、インフラ、アプリケーション分野においては先進国のレベルに達する可能性がある。
技術開発分野では、先進国と比肩するレベルに達することは難しいが、規制緩和など環境整備に注力すれば、世界的な高度情報化に少し距離をあけて走っていくことが可能となろう。
(1) 次世代インフラは何か
現在、固定回線、移動系回線、放送などの情報通信インフラがある。
固定回線をみてみれば、B-ISDNは次世代インフラの一つの候補であるが、建設費用が高いため、ADSL技術を導入し既存インフラを有効利用しようとの動きが各国で出てきている。
次世代インフラは、加入者線で2000年には6Mbps、2010年には150Mbpsが必要との予想もあるが、ADSLを導入した場合の速度は 1.5Mbpsであり、既存インフラを利用するだけでは限界がある。B-ISDNもしくはそれに代わる新技術が必要である。インターネットの普及にも、加入者線の増強が必要なことには変りない。
移動体通信をみてみると、II で述べた新移動体通信システムにより、短期的には、2Mbps程度の速度ならば、途上国といえども先進国レベルまで回線が普及する可能性がある。このシステムは、途上国にて未整備状態にある固定電話網を補完する機能を持つといえよう。
一方、日本では、マルチメディア対応衛星システムや、マルチメディア移動アクセスシステムといった広帯域デジタル無線通信技術が開発中で、これらが導入されれば、かなり高度なレベルまで、光ファイバーを敷設せずにインフラ問題が解決できる。これらを適切に導入すれば、広帯域インフラでも先進国に接近する可能性があるが、それは大分先のこととなろう。
様々なインフラの中で、何が次世代インフラとなるかは現段階では不明である。21世紀には、利用者がニーズとコストの組み合わせによって自由にインフラが選べるように、多様なインフラが共存し、それらがシームレスに接続するネットワークが構築されるだろう。現在、先進国では、次世代インフラをめぐっては試行錯誤の段階にある。アジア各国では世界の動向を見ながら、自国のインフラ整備計画に修正を加えて進めている。
(2) 高まる海外への依存
海外からの資金、技術に依存することなく、アジアにおける高度情報化社会は成立しない。次々と開発される新技術を導入するため、資金、人材面で先進国企業への依存は一層高まると予想される。
先進国企業は、アジア市場をどうとらえているのか。
近年、情報機器、電気通信などのハイテク産業は、収穫逓増の性質をもっており、市場の拡大により利益がより拡大するとの説がある(注13)。その説の通り、ウィンドウズやGSM(デジタル移動電話のシステム)を販売したマイクロソフトやノキア、エリクソンは、極めて高い利益を計上している。収穫逓増の法則と、国際標準化の動きを併せて勘案すると、投資リスクが残るとはいえ、情報通信分野における先進国企業の投資意欲は、当分低下することはないと思われる。今回の金融危機でも、現段階では特に目立った影響は出ていない(注14)。
(3) 高まる海外への依存
アジア各国が自国で開発し、今後、独自の技術を生み出す可能性があるのは、EDIやECといったアプリケーションの応用分野やコンテンツであろう。
例えば、シリコンバレーの「スマート・パーミット」がシンガポールのトレードネットのノウハウを導入しているように、EDIやMSCで開発中のスマートカードのサービスは先進国に先行している部分もあり、輸出できる可能性もある。アジアは、日米欧とは異なる土俵でニッチを狙った開発が有効となろう。
アプリケーションの導入状況をみると、様々なアプリケーションが実験段階にある。現在、実用化が進んでいるのはビジネス分野であるが、その代表例として貿易EDIをみると、シンガポール、台湾、マレーシアの3ヵ国とも、(1)EDIFACTを採用し、国際的にデータの交換が可能である、(2)貿易EDIと他産業のEDIの統合を推進中で、台湾、マレーシアでは、すでに金融EDIと結合されている、(3)EDIの効用を高めるため、法律の改正・制定、手続きの簡素化(商慣習の見直し)が行われるなど、日本よりも環境が整備されている。
ちなみに日本の貿易EDIは、税関はSea-NACCS、港湾オペレーターはSHIPNETSといったように、各システムが連結しておらず、国内標準を採用しているため、その利用率は低いといわれており(SHIPNETSは対象業務の20~30%)、現在、EDIFACT導入に向けて整備中である)。
加えて、海外企業はアジア各国の国民の柔軟性を評価しており、Iで述べたように技術:環境=20%:80%に倣えば、アジアでは80%の環境部分が優れており、高度情報化にも有利に働こう。
2.アジアにおける高度情報化への課題
(1) 規制緩和
アジア各国では、今後増加する海外企業を誘致するため、一層の規制緩和が必要となってこよう。海外企業の国内産業への経営・資本面での参入を規制していては、海外からの技術導入が滞る可能性がある。国内の情報通信企業の育成とのバランスをとりながら、規制緩和をいかに進めていくがが、アジア各国にとって大きな課題となろう。
(2) 技術開発関連の人材育成
II.3および III で述べたように、早いスピードで変化する技術を導入できる人材とソフト開発能力を持つ人材は、アジアでは全般的に不足している。
しかしながら、こうした人材は一朝一夕には育たず、長期的な自国における教育の向上によって生まれる。海外での研修制度や国際機関のセミナーへの参加を支援するとともに、自国の初等教育、高等教育分野での教育の高度化、企業内での技術者の育成が必要である。高度な技術を有する産業へ移行する際、教育が重要なのは、どの国の場合でも同じである。
シンガポールでは、インドのバンガロールにソフト開発の業務委託をするケースが増えているが、このように外国人を活用することにより開発要員を補っていくことも一案である。
(3) 市民のITリテラシーの向上
途上国では、パソコン普及率、インターネット普及率の低さが象徴するように、市民のITリテラシーが低い。たとえ、利用者が限定されるビジネス面でのアプリケーションでは成功していても、教育、医療、コミュニティーなど市民が参加するアプリケーションの場合には、実用化に時間がかかるものと予想される。そのため、現段階からIT教育、パソコン普及率の向上を図ることが望まれる。この分野でも、教育機関での訓練が重要となってくる。
おわりに
情報通信分野は、日進月歩で開発が進み、この分野に関する企業の合併や提携が日々報道され、混沌とした状況にある。本稿では、要件を4つに分けて、3ヵ国について概観することを試みてみたが、アジア各国では自国の経済発展に合わせて、情報化を徐々に進めているといえる。
97年夏、タイに端を発した金融危機は、近隣諸国に飛び火した。国内企業は、金利上昇と株価の値下がりで、資金調達面で苦難を強いられるほか、輸入価格の上昇、国内需要の縮小などの影響により、当面は投資の縮小・延期など停滞を余儀なくされる可能性がある(97年9月時点では、タイ以外では実体経済には大きな影響は出ていない)。
しかし、(1)アジア各国では、情報化による技術革新が今後の経済発展の原動力になるとみており、情報通信関連企業の誘致には熱心であること、(2)海外の情報通信関連企業がアジア進出へ熱心であること、(3)海外企業がアジアをグローバル・ネットワークに取り込み他の国と同レベルの情報化を望んでいることなどにより、情報通信分野の海外からの直接投資には大きな影響はでないと思われる。
最近、「日本はアジアより情報化が遅れている」としばしば耳にすることがある。その理由は、高度情報化社会成立の要件の一つである環境整備、つまり、法制度、慣習、市民のITリテラシーにおいて日本が問題を抱えていることを意味すると思われる。
特に、商慣習の面で、旧来の仕事の仕方・組織維持への執着、なわばり侵害への抵抗などが日本人には強く、これらを払拭していかなければ将来のサイバー社会は成立しない。前出の表7にあるように、多くの企業家たちも日本人の「柔軟性と適応性」を46ヵ国中42位と極めて低く評価している。日本は、アジアの人々から柔軟性を学ぶべきだろう。
注
1. bpsは伝送速度の単位であるbit per second(ビット/秒)の略で、M(メガ)は100万を指す。Mpbsは、1秒間に100万ビットのデータを送信できることを意味する。kbps、Gbpsのk(キロ)は1,000、G(ギガ)は10億を指す。
2. 社団法人 港湾物流情報システム協会(1995)
3. 加入者が契約している国だけでなく、他国においても同じ端末で、他国の事業者の基地局を使って通信サービスを享受できること。
4. テレビ伝送やLANに使用されるケーブル。普通の銅ケーブルより伝送能力が大きく、強度が高く、雑音が少ない。光ファイバーが普及する前は、大容量の伝送路(長距離、局と局の間など)に使用されていた。
5. 異なるケーブルを幹線、加入者線などで組み合わせて使うこと。通信では、光ファイバー+銅ケーブル、通信では、光ファイバー+同軸ケーブルの組み合わせのことを指す。
6. Asysmmetric digital subscriber line(非対称デジタル加入者線)の略。この技術を使うと、銅ケーブルでも1.5Mbpsの高速伝送が可能。米国で実用化されているが、日本では実験段階である。
7. Rajendra S.Sisodia "Singapore Invests in the Nation-Corporation," (『Harvard Business Review』 May-June 1992所収)
8. 社団法人 港湾物流情報システム協会(1995)
9.
10. Asynchronous transfer mode(非同期転送モード)の略。B-ISDNに使用される信号の伝争・交換技術のこと。
11. 財団法人金融情報システムセンター(1996)
12. マレーシア・テレコム資料
13. 収穫逓増とは、より多く生産するほど、限界的な1単位から得られる利益が逓増すること。Arthur(1996)に詳しい。
14. ただし、タイでは、公共投資、直接投資とも全体的にかなり冷え込んでいる模様で、情報通信関連も影響を受けている可能性がある。
主要参考文献
1. (財)金融情報システムセンター(1997)「アジアにおける貿易金融EDIに関する研究会報告書」 1997年
2. 経済審議会21世紀世界経済委員会(1997)「進むグローバリゼーションと21世紀経済の課題」 1997年
3. KDD総研『R&A』各号
4. (社)港湾物流情報システム協会(1995)「港湾物流情報トップフォーラム講演録」 1995年
5. サイバー社会基盤研究推進センター他編(1996)『サイバー社会の展望』野村総合研究所 1996年
6. (財)新日本ITU協会『ITUジャーナル』各号
7. 通産省情報政策企画室編(1995)『産業情報ネットワークの将来』日刊工業新聞社 1997年
8. 電気通信審議会通信政策部会(1997)「情報通信21世紀ビジョン中間報告」 1997年
9. 電子決済グループ国際F-FDIチーム(1996)「国際フィナンシャルEDI構築に向けての現状と課題」((財)金融情報システムセンター『金融情報システム』1996年7月~9月号所収)
10. 西垣通(1996)『インターネットの5年後を読む』光文社 1996年
11. 日経コミュニケーション編(1997)『新情報早わかり講座』日経BP社 1997年
12. 日経BP社(1996)『情報・通信新語辞典』 1996年
13. 増野大作(1996)「ASEANの通信産業」(野村総合研究所『財界観測』1996年7月10日号所収)
14. 松原能文(1996)「アジアの通信サービス産業の動向」(海外投融資情報財団『海外投融資』1996年3月号所収)
15. 郵政省編(1996)『平成9年度通信白書』大蔵省出版局 1996年
16. 郵政省通信政策局監修(1996)『通信衛星年報平成8年版』(財)国際衛星通信協会 1996年
17. Arthur, Brian W.(1996), "Increasing Returns and the New World of Business" in Harvard Business Review, July 1996.
18. IMD(1997), The World Competitiveness Yearbook, 1997.
19. ITU(1995a), Asia Pacific Telecommunication Indicators, 1995.
20. ITU(1995b), ITU Statistical Yearbook, 1995.
21. ITU and TeleGeography, Inc.(1996), Direction of Traffic; Trends in International Telephone Tariffs, 1996.
22. TeleGeography, TeleGraphy 1996/97; Global Telecommunications Traffic Statistics and Commentary, 1996.

