RIM 環太平洋ビジネス情報 1998年10月No.39
アジアにおける欧州企業の動向
1997年10月01日 さくら総合研究所 真崎修、川手潔
はじめに
1997年9月27~28日、第1回アジア欧州会合(ASEM)経済閣僚会合が、幕張で開催され、欧州とアジアの経済的結び付きの推進などをテーマに議論がおこなわれた。この結果、市場経済の重視、最高経営責任者(CEO)レベルの円卓会議の開催など、民間企業の活躍を前提にした投資促進行動計画(IPIP)などが合意された。このように欧州とアジアの経済関係の緊密化にあたって、民間企業の活動が重要性を増してきていることに鑑み、本稿では欧州企業のアジアにおける動向に焦点をあてて、日本企業のアジア戦略を考える上での参考としたい。
欧州のアジアに対する直接投資は、90年代から本格化し、94年末時点では、直接投資の残高ベースで、日本762億米ドル、米国478億ドルに対し、欧州は459億ドルと、投資残高において日米に遜色ない水準に達している。業種としては、発電、通信などインフラ関連産業、金融などサービス産業、およびハイテク産業の投資が目立つ。その投資戦略は、アジアの労働コストの低さをあてにしたものというより、アジア域内市場の持続的な発展を前提にしたものである。
I.貿易と投資の動向
1.輸出が先行した欧州企業のアジア市場開拓
アジアは近年、直接投資先として重要な地域となっているが、日本や米国に比較すると、輸出によってアジアの市場に参入する傾向が強い。図1に示す通り、 90年にはEU諸国の対アジア輸出額は対アジア直接投資額の5.4倍で、日本の1.9倍、米国の2.5倍に比べ、輸出の規模が相対的に大きかった。その後、アジアに対する直接投資が増加し、94年は輸出が直接投資額の3.7倍(日本、米国はそれぞれ2.1、1.9倍)と日米並みに近づいてある。しかし、依然として輸出の占める割合が多い。
図2を見ると、EU諸国の輸出全体に占めるアジア向け輸出の割合は、80年には3%台に過ぎなかったが、90年代になってから急増し、93年には6%を超え、96年には7%に達している。アジアの市場が欧州にとって重要な地位を占めてきていることがわかる。なかでも自国の国内市場が小さい北欧諸国の伸び率が高く、例えばフィンランドは80年に2%にも満たなかった対アジア向け輸出の割合が、96年には10%近くに増加している。これには携帯電話器などのエレクトロニクス製品の貢献度が大きい。
2.直接投資の動向
欧州企業の対アジア投資は、アジアが欧州の植民地であった歴史的経緯もあり、半世紀以上も前にアジアに進出した例も多い。反面、70~80年代を通じ、欧州企業の対アジア直接投資は積極的であったとはいい難く、最近まであまりその動向は注目されていなかった。
しかし、図3に示すように、90年代に入ってからの欧州企業の対アジア投資は急増しており、アジアにおけるプレゼンスは大きくなっている。90年以降の欧州企業の対アジア投資の年平均伸び率をみると、全体として日本や米国の企業より高い伸び率を示した(図4)。
図3 欧州諸国の対アジア直接投資額の推移
(単位:億米ドル)
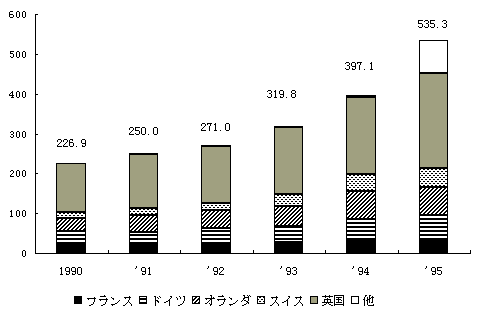 (資料) OECDほか
(資料) OECDほか図4 欧州諸国の対アジア直接投資残高の年平均伸び率(1990~95年)
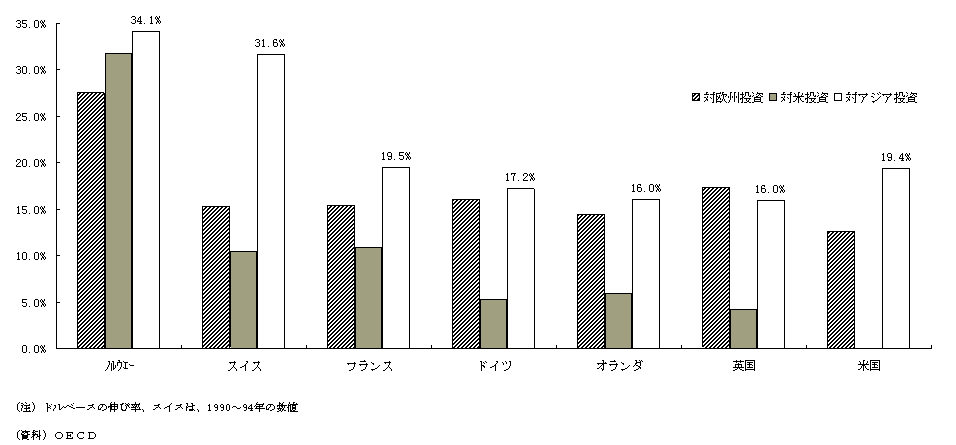
欧州の中でも、北欧諸国やスイス、オランダといった国内経済規模の小さい国の対アジア進出は積極的である。こうした国は、国内経済規模(GDP)に比し、対外直接投資の割合が高い。欧州企業の直接投資にとって、母国の経済規模が重要なファクターとなっているといえる(図5)。
3.欧州企業のアジア進出を支えた要因
欧州企業のアジアへの投資、輸出が活発化した根本的な要因はいうまでもなく、アジアが長期的な成長路線に乗り始め、今後ともその発展が続くと考えられているからであるが、ここではそれ以外の要因についてみてみたい。
(1) 欧州域内の構造変化
日米のいずれの企業も、産業構造の転換期に対外直接投資を急増しているが、欧州の場合も同様である。
欧州企業の対外直接投資は、90年代に急増し、同時期にアジアへの投資も本格化したが、この背景には、90年代初頭にかけての欧州諸国、特に大陸諸国の景気低迷があり、欧州企業としては、国際戦略の再検討を迫られていたことが挙げられる。
ただ、欧州の場合はドイツマルクを除き、ドルに対して上昇している欧州通貨がほとんどない。米国企業は80年代中頃にドル高によって、また日本企業が90 年代前半の円高によって海外生産比率を増加させたが、日米のケースと異なり、通貨が対外直接投資の大きな要因となったとはいえない。
(2) 国際規格
アジアをはじめ世界に生産拠点を展開する際、品質基準など世界共通の規格で生産をすることが重要になってきているが、代表的な国際規格決定機関である「国際標準化機構」(International Organization for Standardization: ISO)における国際規格の決定方法は、基本的に1国1票の多数決であるため、欧州諸国は数の上で優位に立つといわれている。またアジアでは、携帯電話の欧州規格であるGSM(Global Standard of Mobile Communications)が支配的になりつつあるが、この点において欧州企業は優位に立っている。今後、デジタル家電製品の普及が予想されるアジアにおいても、欧州規格が一般的となる可能性がある。
なお、97年9月に幕張で開催されたASEM経済閣僚会合では、基準認証において参加各国の国際規格への整合化がうたわれ、貿易円滑化行動計画の中に織り込まれた。
(3) 通貨変動の少なさ
通貨の変動は貿易・投資面での為替リスクを増大させるものである。この点、図6に示すように欧州通貨とアジア通貨の変動率は、日本通貨とアジア通貨間の変動率に比べれば小さく、この意味でも欧州企業はアジアにおいて活動しやすい環境にあるといえよう。
(4) 政府の支援体制
民間レベルでの経済交流の活発化に伴い、欧州主要国政府およびEUは、93から94年にかけて本格的にアジアをターゲットとした輸出・投資促進政策をスタートさせている(表1)。
まず英国では、英国貿易産業省が発表した輸出振興政策の中で、アジアを日本、中国、東アジア(中国を除く)および東南アジア、インド、南アジア(インドを除く)の5つに地域に分けて、それぞれ輸出振興機関を設置、相手国別に輸出重点分野を選んでセミナーの開催やミッション派遣等を行っている。特に中国、インドといった将来の市場規模の拡大が見込まれている国への期待は大きく、95年5月の中国ミッションは、自動車メーカーのローバーや通信事業のブリティッシュ・テレコムなど大手企業を含めた大ミッションとなった。また同年12月のインド・ミッションは通信分野に的を絞ったもので、インドにおける通信インフラの将来性に大きな期待をかけているようである。
ドイツでは、93年10月にアジア諸国との政治・経済関係の緊密化を目的に「アジア・コンセプト」を政府が発表、在外ドイツ商工会議所のネットワーク活動や、在外公館の商務的役割の強化などを具体策として示している。95年のアジア・ミッションにはコール首相自らが加わり、相手国政府に対し、トップ・セールスを積極的に展開した。
さらにフランスでも、政府が対アジア向け輸出と投資促進を目的とした「対アジア政策」を発表し、93年以降、外交関係正常化を契機としてベトナムや中国などへ産業ミッションを組み、フランス企業のアジア市場への参入を後押ししている。
96年以降、頻繁に開催されているASEM会合は、本来、経済協力と政治関係の緊密化を目的としたものであるが、アジアの人権問題や民主化、さらに環境問題に関し、アジアと欧州の間で足並みが揃わないこともあって、経済・ビジネス中心に話し合いが進んでいる。
(5) 欧州ビジネスセンター
94年以降、主として民間の主導により、アジアの現地情報の提供などを行う機関として、シンガポールを中心に欧州ビジネスセンターが設立されている。欧州ビジネスセンターは、英国、フランス、ドイツが主に設立しているが、北欧諸国も近く開設する予定である。設立地は、現状のところシンガポールに集中しているが、アジア各地への拠点展開も検討されている。
欧州ビジネスセンターの特徴としては、まず第一に、欧州の中小企業を支援対象としていること、第二に、既存の現地商工会議所と異なり、情報提供やコンサルタント業務に加え、主要業務としてオフィス・フロアの提供といったサービスを行っていることが挙げられる。オフィス・フロアの提供は、現地進出直後の中小企業の経費を節減し、事業の立ち上がりをサポートするインキュベーター機能を備えている点で興味深い。
II.アジアにおける欧州企業の業種別動向
以下では、アジアにおいて欧州企業の活躍が特に目立つ自動車、通信、重電、および金融の各産業分野を取り上げ、アジアでの事業展開の具体例をみることにする。
1.自動車
日本と欧州の自動車産業のアジアにおける生産拠点展開戦略は明確に異なっている。日本企業はアセアンのBBCスキーム(注1)を活用した形でアセアン域内での分業体制構築を重視する一方で、中国、インドなどでも生産規模を拡大していく方向にある。一方、欧州企業は、主として将来の国内市場規模が大きい中国やインドなどへ集中して生産拠点を置く傾向にある。アセアン4ヵ国における欧州企業の生産規模は95年時点で5万5,000台と、日本企業の138万 4,000台に比べて圧倒的に小さい。しかも、拡張計画をみても、アセアンにおいてはインドネシアを除き積極姿勢はみられない。これに対し中国では、今後変更があり得るとはいえ、2000年には欧州系自動車メーカーのアジアにおける自動車生産の65.1%が行われる計画になっている(図7)。なかでもVW/Audiの生産計画は、中国において2000年には61万台と、中国進出自動車メーカーの中で最大規模となる。
自動車産業の育成に不可欠である自動車部品産業が、生産量が増加すればするほど単位あたりの製造コストを引き下げることができる産業、すなわち規模の経済が強く作用する業種であることを考えると、中国やインドを生産拠点に選ぶことに合理性がある。
2.通信
日米欧の通信サービス産業がグローバルな事業展開を開始した背景としては、自国の公益事業の民営化・自由化により競争原理の導入が図られ、競争力強化が必要になったこと、および新たな市場を求めるようになったことが挙げられる。欧州の中では、英国が80年代に先んじて公益事業の民営化・自由化を進めたが、EUの政策である電気通信の完全自由化や市場統合を前提に、他の欧州各国も、これまで規制業種であった通信サービス産業に競争原理を導入し始めた。そのようななか、アジア各国も情報通信事業の民営化政策を導入し、市場開放が進んだこともあり、日米欧の通信サービス産業の参入が相次いでいる(表4)。ただし、アジア各国は香港以外、外資に対しては外資規制を設けており、したがって日米欧の通信事業者は現地通信事業者への資本参加の形で市場参入を図っている。欧州企業の中で積極的にアジアに進出しているのは、英国、ドイツ、フランスの欧州主要3ヵ国の通信事業者である。アジア各国の通信市場への参入状況をみると、米国企業がアジア全域に多数参入しているのに対し、欧州企業は進出相手国によって事情が異なる。英国企業は主として旧植民地への参入が多い。一方、ドイツ・テレコムとフランス・テレコムはコンソーシアムを組み、通信回線の相互相乗りで国ごとに棲み分けを図っている。
このように通信サービス事業が拡大するのと同時に、それに付随する通信機器の需要も急増した。通信機器市場では、携帯電話などの規格の標準化が競争戦略上の武器となっている。アジアでは、多くの国・地域がデジタル式携帯電話の規格として欧州規格のGSMを採用しており、アジアの通信機器市場において欧州企業のプレゼンスは高い。そのGSM規格のデジタル携帯電話の供給会社であるノキア(フィンランド)、エリクソン(スウェーデン)、シーメンス(ドイツ)など欧州企業のアジア市場における競争優位性は高く、『日経エレクトロニクス』誌によると、95年時点の世界の携帯電話の市場占拠率は、ノキアが28%、エリクソンが16%、シーメンスが7%と欧州企業3社でほぼ5割の市場占拠率を有している。だが、携帯電話は製品サイクルが短く、価格競争が激しい。そのため、エリクソンやノキアなどは単品供給よりもGSM規格の携帯電話基地局システムの受注獲得に注力し始めている。特に、中国ではエリクソンが広東省、遼寧省、四川省、ノキアが福建省、北京市の基地局システムの受注に成功している。いったん基地局システムを受注すれば、その携帯電話機の納入業者としても参入できる可能性が高い。
こうしたビジネス機会の増大に伴い、これまでエリクソンはアジアへの製品供給をもっぱら本国などからの輸入に依存していたが、近年になって合弁の生産拠点を相次いで設立し、現地需要に対応しようとしている。これに対し、ノキアは、すでにアジアでの生産拠点を韓国、台湾、中国に設置している。また、ノキアは中国における販売戦略として、日本商社の現地販売ネットワークを活用するなど戦略的提携を組むケースもみられる。
3.重電
アジアの発電プラント需要増大の背景には、工業化の進展に伴い電力供給のための関連設備増強が必要になったことと、政府の財政逼迫から民活型の発電プラント事業を積極的に導入されてきたことがある。したがって、これまで東欧や北米・中南米の発電プラント事業に注力してきた欧州企業や米国企業も、矛先をアジアに転じ始めた。いまや日米欧の大手重電機メーカーや日本商社が、国際的なコンソーシアムやジョイント・ベンチャーを組成して、アジア各国の発電所建設の受注をめぐり、熾烈な獲得競争を展開している。最近では、中国の大型プロジェクトである三峡ダム水力発電所の発電設備納入業者として、ABBアセア・ブラウン・ボベリ(スイス/スウェーデン)、シーメンスなどの欧州連合が、日本企業のコンソーシアムを敗り、総額7億4,000万ドルの落札に成功した。このプロジェクトにおいて欧州勢は、早くから自国の輸出信用機関の公的融資を絡め、自国政府との連携して中国側に商談を持ち掛けるなど対応がすばやく、コスト競争力においても優れていたとされる。また、ABBアセア・ブラウン・ボベリは中国、インドをはじめとするアジア市場へ攻勢を強める方針であり、発電所、各種プラントなどの年間受注額を、95年の80億ドルから2000年にはその約2倍に当たる150億ドルに拡大する計画で、このため現地の雇用者数を2万人から4~5万人に倍増する予定である。
民活型発電プロジェクトの成約事例をみると、日本企業は重電機メーカーが商社と組んで受注を獲得しているのに対し、欧州企業は単体かメーカー同士で獲得している(表5)。ただし、通常インフラ・プロジェクトにおけるコンソーシアムはプロジェクトごとに別々に結成され、ある案件で敵対関係であった企業同士が、別の案件では共同して受注獲得を行うといった合縦連衡を繰り返すため、欧州企業と日本企業あるいは米国企業との混合のコンソーシアムとなるケースもある。欧州企業が日本企業をパートナーとして選ぶ場合、案件発掘力、ファイナンス力、機材販売力のある日本商社と組むケースが多い。
4.金融
近年のアジアでの金融サービス業の事業展開においては、特に欧州系銀行の動きが顕著である。93年末には、欧州系銀行の対アジア融資残高は585億ドルと、中南米や東欧向け融資残高を下回っていたが、96年末には1,371億ドルと、対外地域別融資残高で最大となったばかりでなく、これまで対アジア融資残高でトップだった邦銀を上回るまでになった(図8)。邦銀との国別融資残高の対比では、タイとインドネシアを除くアジア各国において欧州系銀行がトップであり、93年以降、とりわけ韓国、中国、インドネシアへの融資増加額が大きい。このような対アジア融資額の増加要因としては、主として欧州企業のアジア進出に伴い、その資金供給機関として融資残高を伸ばしたこと、アジアのインフラプロジェクトに協調融資団の幹事として積極的に参画し、プロジェクト・ファイナンスなどを手掛けてきたことなどが考えられる。さらに、香港やシンガポールのアジア・オフショア市場においても、財務基盤が比較的強固な欧州系銀行は、安定した自己資本比率を維持しながら運用残高を増加させている(注2)。
一方、邦銀はアジア地域の高度成長を背景に95年まで融資額を拡大してきたが、96年になって伸び率は落ち込んだ。また、オフショア市場においても、第2次BIS規制といわれる市場リスク規制を念頭において、利鞘の薄いオフショア市場での運用を控える動きが出てきた。さらに、95年央以降、ジャパン・プレミアムなどの影響により資金調達コストが上昇したこともあり、邦銀はアジアのオフショア市場における運用残高でも欧州系銀行に抜かれることとなった。
III.欧州企業の投資戦略の特徴
1.アジアの市場拡大を前提にした大型投資
欧州企業は、投資相手国の将来性や、国内市場規模を重視した戦略を採用しており、その結果一件当たりの投資額も大型で、産業基盤の整備に貢献するものが目立つ。
発電事業においては、前述のようにABBアセア・ブラウン・ボベリとシーメンスから成る欧州企業連合が約7億4,000万ドルの中国の三峡ダム水力発電設備を受注した。このほか、今後の大規模プロジェクトとして、マレーシアが計画しているサラワク州のバクン水力発電所プロジェクト(総事業費約55億ドル)においても、欧州の有力電機メーカーがコントラクターとしての参加交渉を行っている。
通信インフラの整備に欠かせない通信ケーブル敷設事業においては、フランスのアルカテルが大規模通信回線の敷設事業に本格的に取り組んでおり、98年にはドイツとシンガポールを結ぶ3万キロメートルにおよぶ光ファイバーを利用した海底ケーブルが完成する予定である。このほか、インドネシア、中国においても大規模なケーブル回線敷設計画が進んでいる。またドイツ・テレコムは上海とフランクフルト間の光ファイバー通信網敷設を97年末に完了する計画である。
中国のように、将来的に市場の規模が巨大となることが予想される国においては、自動車、化学など規模の経済が作用しやすい分野での大規模な投資が目立つ(図9)。自動車については前述の通りだが、このほか化学についても、ロイヤル・ダッチ・シェルが、25億ドル規模の大型エチレンプラントの建設に向けて動き出し、ドイツのBASF、英国のBPケミカルズも大型化学プラントを計画中であると報じられている。
以上の例からわかるように、単に賃金の安さなど製造コストの低さに魅力を感じて労働集約的な産業の生産拠点をアジアに配置し、そこから世界に輸出している例は少ない。日系家電メーカーの場合は、マレーシアなどに大規模な工場を設立して世界にその製品を輸出しているが、白モノ家電の分野で欧州最大手のエレクトロラックスは、家電製品の生産拠点をアセアン諸国ではなく、中国、インドに置いている。将来の中国やインドの国内市場規模の発展性を重視した結果であろう。
2.経済環境の変化に即応した投資
一般に欧州企業の特徴であるハイテク、国内市場志向型は、アジアを取り巻くさまざまな経済環境の変化に対処しやすい。例えば、一般労働者の賃金の上昇は、労働集約型の産業にとっては大きなリスク要因となっているが、ハイテク産業においては、賃金上昇の影響は緩和される。特にシンガポールのような一部アセアン諸国においては、一国当たりの労働人口が少なく、賃金上昇率も高いので、欧州企業の投資もハイテク産業や知的サービス業の分野に重点が置かれている。
欧州型直接投資のもう一つの強みは、最近問題となっているアジア通貨の変動の影響を受けにくいことと思われる。インフラ整備など国内市場志向型の産業は輸出に多くを依存していないので、ドルに対して投資相手国の通貨が上昇しても直接的な影響は少ない。また通信、発電、金融などのサービス産業においては、通常の製造業と異なって材料や中間財に依存する度合いが小さい。したがって、いったん初期投資が行われれば、その後、対ドル相場下落によって材料や中間財等の輸入品の価格が上昇しても、すぐに製造コストが上昇することはないわけである。
3.今後の見通し
以上述べたように、欧州企業は投資相手国の市場規模を重視しているが、今後、通貨統合により欧州に共通通貨を使用する単一市場が形成された場合の影響はどうであろうか。少なくとも、自動車、鉄鋼など規模の経済が作用しやすい産業は、欧州域内生産を重視してくる可能性がある。
欧州の共通通貨となるユーロが、ドイツ企業などの実力に比べ低く評価されれば、ドイツ企業はアジアに生産拠点を設置せず、輸出によって市場ニーズに対応するという戦略を採る可能性もあろう。ただ、シーメンスなど大手の欧州系多国籍企業は、すでに世界市場をにらんだ生産拠点の展開をしており、欧州域内だけの企業としてとどまることはないものと考える。
国内市場規模を重視している結果、欧州企業は、いままで中国への関心が高く、また投資も活発に行ってきた。ただし、カントリーリスクなどの点でアセアン諸国に比べて中国が特に低いわけではないことに留意する必要がある。したがって、欧州型のアジア進出戦略の是非を問うのはまだ早いと思われる。しかし、これまでの欧州企業の対外直接投資収益率からみれば、その対外直接投資戦略は注目に値するといえよう(図10)。
注
1. Brand to Brand Complementationの略。88年10月に制定された、アセアン域内の完成車メーカー間で相互に補完される部品に対して、関税などが通常の50%免除となる制度。
2. Financial Times 『The Banker』誌96年7月号によると、世界ランキングのトップ50銀行のうち、95~96年の決算期の自己資本比率が10%を超えているのは、欧州系銀行で22行中13行、邦銀では13行中2行のみとなっている。
主要参考文献
1. UNCTAD, World Investment Report, 1994~96各年版
2. European Commission(1996), Investing in Asia's Dynamism: European Union Direct Investment, 1996.
3. International Monetary Fund(1997), International Financial Statistics Yearbook 1997, 1997.
4. International Monetary Fund(1996), Direction of Trade Statistics Yearbook1996, 1996.
5. OECD(1996), International Direct Investment Statistics Yearbook 1996, 1996.
6. BIS(1997), The Maturity, Sectoral and Nationality Distributuion of International Lending, 1997.
7. 長銀総合研究所『日米欧多国籍企業の東アジア戦略』No.44、45 1995年
8. 日本貿易振興会 『ユーロトレンド』1995年4月号~97年2月号
9. 電子ジャーナル(1997)『半導体データブック1997』1997年
10. FOURIN(1996)『アジア自動車産業 1995/96 』1996年
11. 重化学工業通信社『プラント貿易年鑑』 1996,97各年版
12. 中垣 昇(1993)『グローバル企業の地域統括戦略』文眞堂 1993年
13. ジョルダン・D・ルイス著(中村元一・山下達哉訳) 『アライアンス戦略』ダイヤモンド社 1993年
14. P.ラセール、H.シュッテ著 (長谷川 啓之訳)『西欧企業の対日・アジア戦略』 学文社 1997年
15. 郵政省郵政研究所(1997)『成長するアジアの電気通信と日本のあり方』 1997年
16. Siemens, Annual Report 1996, 1997.
17. Nokia, Annual Report 1995, 1996.
18. LM Elicsson(1997), Annual Report 1996, 1997
19. ABB Asea Brown Boveri, Annual Report, 1992~96各年版、1993~97年
20. Alcatel Alsthom(1997), Annual Report 1996, 1997.
21. Daimler-Benz(1997), Annual Report 1996, 1997.
22. Dun & Bradstreet, '96 Asia Directory Electronics Manufacturers, 1996.

