RIM 環太平洋ビジネス情報 1998年7月No.38
第2次工業化マスタープランにみるマレーシアの新工業化戦略
1997年07月01日 さくら総合研究所 竹内順子
はじめに
マレーシアにおける今後10年間の工業化の青写真ともいうべき第2次工業化マスタープラン(IMP2、1996~2005年)が96年末に発表された。IMP2は95年に終了した工業化マスタープラン(IMP、86~95年)を引き継ぐものである。
86年に発表されたIMPは、10年という長期的展望を持った同国初の工業化政策であったが、個別セクターの育成方向を具体的に明示したという点においても画期的であり、注目を集めた。IMPは誘導的計画(Indicative Plan)という位置づけながら、その後の投資政策、政府系企業の行動に大きな影響を及ぼし、いわゆる産業政策に近い役割を果たしたと考えられる。
皮肉なことに、IMPが発表された86年を境に、マレーシアの製造業を取り巻く環境は大きく変化した。すなわち、外資系企業による投資ブームの到来である。この偶発的な追い風もあり、IMPが設定した定量的な目標は、ほとんどの産業で達成された。
しかし、投資ブームはマレーシアを労働力不足経済に移行させるともに、グローバル経済に、より深く組み込むことにもなり、工業化戦略は曲がり角を迎えている。
本稿ではまず、IMPのレビューを中心に工業化の進展を整理する。次いで、IMP2で描かれた工業化の目標と実現のための施策を紹介し、マレーシア政府の工業化戦略がどのような方向を目指しているか述べてみたい。
I.工業化マスタープラン(1986~95年)のレビュー
IMPでは、80年代半ばの時点でマレーシア製造業が抱える構造的な問題として、(1)労働集約型および資源加工型産業への偏向、(2)公営企業、外資系企業といった大企業への偏向、(3)輸出における電子および繊維製品への過度の依存、(4)中間財・資本財産業の発達の遅れによる産業連関の欠如を指摘している。これらはマレーシアが採用してきた工業化戦略の影響を如実に示しているといってよい。
1.工業化戦略の変遷
(1) 輸出加工区の功罪
工業化に着手するにあたって、他の多くの国同様マレーシアにおいても、輸入代替政策が採用された。人口が2,000万人に満たないという国内市場の制約から、60年代の終わりには行詰まりが明らかとなり、輸出志向型工業化が採用された。ただし、輸入代替政策からの全面的な転換というわけではなく、輸入代替産業と併存させる形で輸出型産業の育成が図られた。
具体的には、70年に自由貿易地域(FTZ)法が施行され、韓国、台湾の輸出加工区に範をとったFTZが全国に建設された。外資系企業誘致のための一種の飛び地である。製品の8割以上を輸出する企業はFTZに入居するか、保税工場のステータスを得れば、輸入資本財・中間財の関税免除という恩典を供与された。輸入代替期に導入された投資促進のための税制上の優遇措置についても、輸出型産業への優遇が強化され、外国投資を誘致する環境が整った。
こうした措置により、外資系企業の進出は急速に増加し、雇用の創出、製品輸出の増大という点で大きな成果を上げた。
一方、中間財を輸入して加工し、輸出するという輸出加工区には、(1)加工工程が分割しやすく、輸送しやすいという特性を持った産業が集中する、(2) 加工コストの削減が目的だけに企業の活動が労働集約性の強い工程に特化する、(3)国内経済とのリンケージが発生しない、というデメリットもあった。急速に増大した製品輸出の大宗をなした電子・電気製品と繊維製品に、その傾向が顕著に現れている。80年には、電子・電気製品と繊維製品の輸出額は製品輸出全体の約6割を占めた。輸入中間財への依存が高まったことから、輸入が急速に膨んだが、保護的政策下におかれた国内産業からこれらを代替する動きは生じなかった。
(2) 政府主導の重工業化
80年代に入ると、FTZ型の産業発展に対する限界が強く意識された結果、第2次輸入代替の必要性を説く声が高まり、公営企業、州政府開発公社などを実施主体とした重工業プロジェクトが計画・実行された。
重工業化にあたって政府資本が実際の推進役となったのは、一つには投資額が大きい重工業プロジェクトに対する民間資本の躊躇が予想されたためであるが、マレーシアに固有の事情もあった。
周知のように、マレーシアは複合民族間の調和を維持する方法として、70年に新経済政策(NEP、70~90年)を導入し、民族間経済格差の是正を推進してきた。その眼目は、経済的に劣勢にあるブミプトラ(土地の子の意。マレー系マレーシア人を指す)の経済活動への参加促進であったが、ブミプトラ民間資本家が育っていない段階では政府資本がそれを代替せざるを得なかった(注1)。
重工業化における政府資本の参加にもこうした側面が強い。オイル・ショック以降の石油収入の膨張による財政的な余裕も、こうした方針をバックアップしたと考えられる(注2)。
当時、商工相であったマハティール現首相のイニシアティブによって、80年に重工業公社(HICOM)が設立され、同公社と外資系企業の合弁プロジェクトが重工業分野で相次いで実行された。HICOMが出資した分野は自動車、自動二輪車エンジン、鉄鋼、工業団地など多岐に及ぶ。特に、自動車産業についてはその裾野の広さから、マレーシアに欠けている産業連関の形成に寄与することが期待され、国民車構想が推し進められた。
しかし、公的資金の投入による重工業化の推進は、プロジェクトの操業開始を待たずに曲がり角を迎えた。一次産品価格の下落である。歳入が細る一方、財政赤字の拡大、対外債務の増大が深刻化したが、重工業の投資は懐妊期間が長く、なかなか収入には結び付かなかった。また、民業圧迫という批判が経済情勢の悪化とともに高まり、財政縮小の必要性からも重工業化政策はトーンダウンした。
さらに、85年には原油・一次産品価格の暴落、半導体不況などが重なったため、不況感は一気に深まり、マレーシアは独立以来、初めてのマイナス成長を経験した。一次産品輸出・財政主導による経済成長の限界はいよいよ明らかになり、工業製品輸出・民間主導による経済成長への切換えの必要性は切実さを増した。
(3) IMPの登場
今後、経済成長の原動力となるべき製造業の長期的な発展を見直すべき時期であった。その一つの解答が86年に発表されたIMPである。
IMPは83~85年にかけて韓国の経済学者をヘッドに、国連工業開発機構(UNIDO)およびマレーシアの関係省庁・団体によって策定された。IMPはその序文で明示されたように「誘導的計画」であり、日本や韓国の産業政策にみられたような直接的な立法、予算措置を伴わない。
IMP策定の目的は、一つは民間セクターに対して政府の目指す方向性を示すことであり、もう一つは工業関連の施策を担当する各省の政策立案・調整の根拠となることであった。
IMPの最大の特徴は、個別セクターの育成の方向と処方を明示したことであったが、その全編を貫いていたのは外向きの工業化(outward industrialization)という方針であった。
工業化の重点は、輸出に効果を持つ奨励策を講じることによって、輸出産業の成長を加速させることに置かれた。重工業は輸出産業を支援するセクターと位置づけられ、輸出産業に負担をかける保護措置は極力回避することが提言された。市場だけでなく、資本の面でも外向きの姿勢が強まり、外資導入をより積極化させたことも特徴的である。
具体的な対応としては、従来の「産業創始法」にかわる「1986年投資奨励法」が制定され、民間投資を促進する措置が矢継ぎ早に打ち出された。
最も効果が大きかったものとしては、同年10月に発表された外資出資比率の規制緩和が挙げられる。同措置では90年末を期限として、比較的緩やかな条件下で外資の全額出資を認めた(注3)。
そのほか、パイオニア・ステータスの期間延長、投資手続きの簡素化、投資規模に応じた外国人ポストの留保が導入されるなど、外資系企業誘致のための環境整備が進められた。
(4) 投資ブームの到来
86年以降、マレーシアが民間投資の促進を目指して投資環境の改善を進めたのはすでにみた通りであるが、折りからの円高を背景とする日本企業の海外生産の拡大と、それに続くNIEs企業の海外進出の波を受け、マレーシアの外国投資受け入れは急速に拡大した(図1)。輸出比率の高い投資案件が多いのが特徴である。
各年の投資認可額(払込み資本金+ローン)の推移を部門別にみると、設備投資額の大きい素材産業の比重が高いが(図2)、個別業種としてみると電気・電子産業が常に大きな位置を占め、87~96年の投資認可額の累計上のシェアでは(1)電気・電子産業(19.0%)、(2)石油(16.2%)、(3)基礎金属(14.5%)となっている。
製造業の活況に先導され、マレーシア経済は急速に回復した。さらに、国民の所得水準の向上、拡大する経済活動を支えるインフラ需要の増大等を背景に消費、建設投資が活況を呈して好景気は循環的に持続した。IMPが想定した期間中の平均経済成長率は6.4%であったが、実績は7.7%と70年代の高度成長期の再来を思わせる高さであった。IMPが想定した95年の目標工業化率(23.9%)を88年の時点で上回ったことからも、80年代後半の製造業の急成長がいかに不測の事態であったかがわかる。
2.加速する構造変化
工業化の進捗を工業化率、雇用工業化率、製品輸出比率からみると、80年代前半ではいずれの点についても停滞感が強い(表1)。これを一変させたのが投資ブームであり、86、87年を境に工業化の加速が顕著になっている。
86~94年の8年間で工業化率は12.1ポイント上昇した。86年以前には工業化率が10ポイント上昇するのに20数年を要したことを考慮すると、変化の速さがしのばれよう。
製造業人口の増加の加速は89年から顕著になり、92年まで対前年比2ケタで伸び続けた。同時に、農業人口は89年以降、減少を続け、製造業人口は92年に農業人口を逆転した。労働人口が少ないことから、雇用工業化率の変化は著しく、86~94年の間に9.7ポイント上昇した。同期間の雇用創出に対する製造業の寄与は50%を超えている。この時期、マレーシアは労働力需給の転換点(注4)を超え、労働力不足経済という局面に移行したとみられる。
製品輸出比率は85年の31.5%から86年に38.8%へと著増したが、これは原油・一次産品の価格低下を受け、相対的に製品比率が高まったという側面が大きく、製品輸出の本格的な拡大は88年以降と考えられる。製品輸出比率は86年の38.8%から94年の74.7%へと劇的に上昇した。
製造業を食品等、軽工業品、機械加工業、素材産業の4部門に分けて、付加価値額の推移をみると、87年を境に部門間の格差が拡大している(図3)。食品等が伸び悩む一方、他の3部門は急速に成長している。とりわけ、90年以降の機械加工産業の成長は著しく、93年には機械加工業の付加価値額は食品等の4倍弱の規模へと拡大している。
マレーシアの重工業化率は70年代前半の時点で約4割に達しており、83年には5割を上回り、90年には6割に達した。重工業化率が92年でやっと4割を超えたタイとは対照的である(注5)。
しかし、その内訳をみると、83年時点でも重工業の52.1%を機械加工業、その55.4%を電子・電気産業が占めるという構成であった。機械加工業への投資の急増を経て、その傾向はますます強まり、93年には重工業に占める機械加工業のシェアは66.1%、うち電子・電気産業のシェアは63.2%へと上昇した。
電子・電気産業のシェアの突出は、輸出構成をみると、さらに明らかである(表2)。機械類の輸出は製品輸出の約7割を占めるが、約5割が電子・電気製品である。輸送機器、化学、鉄鋼が製品輸出に占めるシェアは、1~3%と小さい(94年)。
3.IMP期間中の成果
IMP期間中の工業化は、製造業の成長率、製品輸出の増加率などいずれも目標を上回った。主要産業に関する目標と実績を比較してみても、目標を大きく下回ったのは鉄鋼産業の輸出、機械産業の投資額など、ごく一部の分野であり、定量的には評価すべき成果を上げたといえる(表3)。
表3 主要産業におけるIMPの目標と実績
(単位:%、億リンギ)
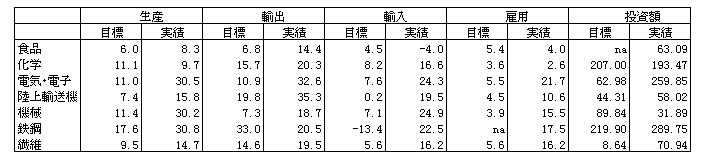
(注)生産、輸出、輸入、雇用については86~92年の平均増加率。投資額については86~95年の投資認可額累計
(資料)『Review of Industrial Master Plan』、その他の資料より作成
特に、期間中の投資額は電気・電子産業で目標の4倍、繊維産業で同8倍という金額に上った。
ただし、輸入は食品産業を除いては目標をはるかに上回る速度で拡大し、貿易収支の悪化を招いている。
一方、定性的な目標はどのように実現されたのであろうか。ここではマレーシアにとって積年の課題であり、多くの産業に共通する問題である産業連関の形成と製造業に対する国内資本の参加の2点をみておきたい。
(1) 産業連関の形成
FTZが工業化推進の核となってきたマレーシアでは、産業間リンケージの欠如がしばしば指摘される(注6)。87年と時点は古いが、産業連関表からも簡単に確認しておこう。
表4はマレーシア、韓国、日本の各産業における輸入誘発係数である。輸入誘発係数とは、1単位の生産によって生じる輸入を示しており、例えば、マレーシアの機械産業では1の生産のために0.5以上の輸入が必要であることを意味する。
マレーシアは一次産品に恵まれていることから、食品、木材などの産業においては輸入誘発係数は低いが、機械部門における輸入誘発係数は日本はもちろん、韓国に比べても著しく高く、これらの産業が輸入財に大きく依存していることがわかる。
個別の製品でみた場合、80年代後半の企業進出によって、現地調達率が大きく上昇したものも散見される。当然ではあるが、生産が集約され、生産規模が一定段階に達したものについてはその傾向が強い。例えば、カラーテレビ、エアコン、VTRなどである。
しかし、輸入に占める資本財および製造業向けの中間財の比率の上昇は80年代後半から著しい(表6)。
理由として、第一に考えられるのは、新規投資および投資拡大のための設備・資材の輸入である。これらは本来、一過性の需要であるが、投資ブームの長期化に連動し、高水準の輸入が続いている。
第二に、産業高度化の影響である。マレーシア政府による高付加価値産業の奨励、多国籍企業の域内拠点間の生産調整などの影響を受け、マレーシアで生産される製品の水準は相対的に上昇している。需要産業の水準が上がれば、供給側への要求水準も上昇することになるが、国内供給が不可能な段階では輸入に依存せざるを得ない。
第三に、投資奨励で重点が置かれたこともあり、投資ブームの主役が輸出型企業があったことである。マレーシアにおける機械部門の資本財・中間財生産が製造業全体の生産に占める比率は、81年の15.8%から91年には26.3%へと上昇しているが、逆に同資本財・中間財の国内調達率は24.6%から 10.0%へと低下している(注7)。
これらの数字は、機械部門における新たな資本財・中間財の生産が国内供給よりも、輸出により多く結び付いたことを示している。
(2) 国内資本の参加
93年末現在、操業中の製造業企業における資本構成は表6の通りである。投資ブームを経て、外資のシェアは87年の31.2%から44.7%へと上昇している。
業種別にみても、この2時点間で外資のシェアは、飲料・タバコ、紙・紙製品、基礎金属の3業種を除く全業種で上昇した。特に、家具、プラスチック、機械、電気・電子の4業種では、20ポイントを上回る大幅な上昇がみられた。現状、飲料・タバコ、石油および輸送機器を除く機械3業種では、外資比率が50%を超えている。このうち、飲料・タバコ、石油では欧米のシェアが高く、機械3業種では日本のシェアが過半を占める。
国内資本の区分が87年と93年では異なるため 、民間資本と政府系資本の比重の変化が確認できないが、ブミプトラ個人+公営企業としてみたシェアが87年の35.5%から29.4%へ、華人のシェアが19.1%から14.4%へといずれも縮小している。
具体的な案件からみると、鉄鋼産業における政府系資本のプレゼンスの後退 、国民車事業の民営化など、総じて、政府系資本による直接的な関与の縮小が目立った。
石油化学産業では国内側パートナーとしての公営石油会社ペトロナスの位置づけが明らかになり、エチレン・センターを含む複数の大型投資に同社が参加したが、化学産業全体としてみると外資のシェアが上昇している。
IMPにおいては、国内民間資本の参加促進が非資源立脚型の産業で強調されたが、鉄鋼、自動車などの分野を除くと目立った動きはなく、外資系企業のプレゼンスがより拡大する結果となった。
輸出面でも外資系企業の影響力は増大している。「Report of the Financial Survey of Limited Companies」によれば、85年と92年の製造業の輸出に占める外資系現地法人のシェアは39.8%から68.3%へと大幅に上昇している。
同時期に外資系現地法人の売上高に対する輸出額の比率は41.8%から69.7%へと上昇しており、外資系企業の絶対数と同時に、輸出志向型企業の増大が輸出に対する外資系企業の影響力を増大させていることがわかる。
II.第2次工業化マスタープラン(1996~2005年)
96年11月、IMP2は予定より約9ヵ月遅れて発表された。中央銀行傘下のシンクタンクであるマレーシア経済研究所(MEIR)と米国のマグロウヒルが実施した調査に基づいている。
すでに述べたように、前回のIMPの全編を貫いていたのは「外向きの工業化」という戦略であったが、IMP2のキーワードは「マニファクチャリング++(プラス・プラス)」と「クラスター」である。
IMP2もIMP同様、個別産業の発展の方向を示しているが、産業はセクターではなくクラスターとして採りあげられている。
以下では、(1)IMP2の総論的な狙い、(2)国内最大のクラスターである電気・電子クラスターの現状とIMP2で提示された開発戦略、(3)開発戦略を実現するための施策の3点についてみていきたい。
1.IMP2の狙い
(1) マニュファクチャリング
製造業の活動を、研究活動から販売までを含めた一連の価値創造のプロセス(バリュー・チェーン)と考えた場合、生産以前のプロセスとしては研究開発、商品開発など、また生産以降のプロセスとしてはロジスティックス、販売などが存在する(図4)。このバリュー・チェーンでは、両端に近づくほど労働者1人当りの付加価値生産は大きい。
IMP2では、マレーシアの製造業においては生産活動の比重が高く、企業活動が付加価値の小さいプロセスに集中しているという認識に立っている。そこで、「マニファクチャリング++」という言葉で今後、研究開発、関連サービスなど、付加価値が高いプロセスを強化していく必要性を提言している。
こうした非製造プロセスの強化には生産活動自体を高度化する効果もあり、結果としてバリュー・チェーン全体の付加価値生産を上方にシフトさせると考えられている。
IMP2に先立って発表された7MP(96~2000年)では、「(資本・労働力の)投入量の増大による成長から、生産性の向上による成長へ」の転換が打ち出された。こうした路線はIMP2にも反映されており、生産性向上のための手段の1つがマニファクチャリング++であると考えられる。
(2) クラスター開発
クラスターという言葉は元々は房、群れなどを意味し、産業という文脈で用いられた場合は、産地、産業群などと訳されている。
国の競争力に対するクラスターの重要性はマイケル・ポーターの『国の競争優位』で大きく取り上げられており(注8)、IMP2におけるクラスター概念の導入は同著の影響を受けているとみられる。
ただし、ポーターが貿易統計をベースに選出した「優位性のあるクラスター」には多国籍企業の影響下にある産業は含まれない。企業戦略、研究・開発を主として受け持ち、イノベーションを起こす「本国」の競争優位が論じられているからである。この条件の下では、マレーシアには一部の資源立脚型産業を除くと、優位性のあるクラスターは存在しなくなる。
IMP2がイメージするクラスターは関連産業が密接な関係を持ちながら発展している日本的な「産業集積」に近いものと考えられる。
近年、マレーシアでは組み立てメーカーを中核に、ベンダー企業を組織化して育成するスキームが採用されているが、こうした企業の地理的な集約も試みられている。国民車メーカーであるプロトン社を中核とする「プロトン・シティ」はその代表的な例である。
産業集積には、(1)分業の調整コストの低減、(2)企業経営資源の相互利用、(3)柔軟な要素技術の組み合わせによる創造などのメリットがあり(注9)、有機的な結合を生み出す「場」としての力が見直されている。
IMP2における「クラスター」は、コア産業とそれを取り巻く関連産業(キー・サプライヤー。サービス産業も含む)、そしてこれらをサポートするインフラおよび制度的な支援基盤によって構成されている(図5)。
コア産業と関連産業は相互に成長を促進し合うシナジー効果を発揮するが、特に関連産業の層の厚みはコア産業の新陳代謝を可能にしていく。支援基盤はこうした産業の成長を促進する環境であり、政府の役割は支援基盤を充実させることにある。
IMP2では国内に存在するクラスターを、(1)国際経済リンク型クラスター、(2)政策主導型クラスター、(3)資源立脚型クラスターの3つに大別している。
(1)は当該クラスターにおいて多国籍企業の役割が大きい電気・電子クラスター、繊維クラスター、化学クラスターから構成される。
(2)は輸送機器クラスター、素材クラスター、機械クラスターから構成される。必ずしも比較優位はないが、国内における技術基盤形成や輸出産業支援のために開発が必要とされるセクターである。いずれも短期間に収益ベースに乗せることが難しく、育成のためには政策介入が必要と考えられている。
(3)は国内に豊富に存在する資源を活用する産業で、木製品クラスター、アグロ・クラスターなどから構成される。
2.電気・電子クラスターの現状と開発戦略
電気・電子産業は、生産高787億リンギ、雇用数34万5,000人、輸出額923億リンギの実績を持つ国内最大のクラスターである(95年)。以下では、IMPで設定された開発目標の達成という面から現状を検証し、IMP2においてどのような発展の方向性が提示されたのかを述べる。
(1) 進む構造変化
電気・電子産業は80年代半ば以降、最も投資が集中した分野であり、大きな変化にさらされた産業である。
86~95年の間に、件数にして、電子部品で766件、家電で245件、産業用機器で286件の計1,297件の投資案件が認可された。こうした案件は順次、操業を開始しており、同産業における操業企業数は87年末の212件から95年末には850件へと激増している。操業企業の増加によって、生産、輸出、雇用が目覚ましい拡大を遂げているのはすでにみた通りである。
一方、IMPが設定した開発目標である(1)国内資本主導の産業育成、(2)輸出志向の民生機器および産業機器の成長促進、(3)部品・材料の輸入依存軽減のうち、目覚ましい成果が得られたのは(2)のみであった。
すでにみたように、マレーシアにおける電気・電子産業の発展の牽引役はFTZに立地する半導体産業であり、電気・電子産業を輸出額構成でみた場合、86年時点では電子部品:民生機器:産業機器の比率は84:14:2という偏った構造にあった。特定分野への過大な依存は市場の変動に対する脆弱性を意味しており、事実、84~85年の半導体不況では大きな打撃を受けた。
そこで、IMPでは民生機器と産業機器の成長促進による、均整がとれた産業構造への転換が目指されていた。
マレーシアにおける家電製品の生産は、80年代初頭に貿易摩擦に直面した日系企業が欧米向けの迂回輸出拠点を設立するに伴って本格化した。投資ブーム以降は、日系・NIEs系企業が本国のコスト上昇を回避し、海外生産によって輸出競争力を増強する動きがマレーシアに幸いした。
世界的に適地生産が追求された結果、すでに電気・電子産業の集積があり、投資環境が整備されていたマレーシアに家電製品の大型輸出拠点が次々に設立され、カラーTV、VTRなどの生産が飛躍的に拡大した。また、コンピュータ・周辺機器の生産についても、シンガポールからの生産移転、台湾企業の進出などによって急速な拡大がみられた。
結果として、電気・電子産業の輸出額構成は、95年には電子部品:民生機器:産業機器が43:25:32へと目覚ましく変化した。マレーシアの家電輸出が世界の輸出に占めるシェアは、95年では17.9%に及んでいる。
開発目標のうち、(1)の国内資本の育成については投資ブームによって、むしろ大きな後退がみられた。電気・電子産業の払い込み資本金に占める外資の比率は87年末の54.4%から93年末に86.6%へと増大しており、地場資本による有望企業の成長もみられなかった。
(3)については I.3でもみたように、輸入財への依存の軽減は進んでいない。
(2) IMP2における目標設定
IMP2では、電気・電子クラスターの特徴として、(1)多国籍企業主導の発展、(2)高い輸入財依存を挙げており、IMPにおいて提示された開発目標は依然として、同産業における最大の課題であり続けている。
(1) 有力国内企業の成長(マレーシア・ブランドの育成)と(2)輸入財依存の軽減化は、IMP2においても中心的な開発目標に挙がっている。
新たな目標としては、国際経済にリンクしたという同クラスターの特性を強く意識して、(3)多国籍企業の統合生産センター(Integrated Manufacturing Center:IMC)化と(4)国境を超えたクラスター形成の促進という方向性が打ち出されている。
(3)のIMCは、IMP2で初めて登場した言葉であり、IMCとしての具体的な振興策は存在しないが、その内容はマレーシアにおける外資系企業の活動を研究開発からマーケティングまで、一貫性の高い活動へと誘導していこうとするものである。すでに、80年代後半時点で研究開発活動、地域本部(OHQ)、 95年には国際調達センターに対する優遇措置が導入されたが、こうした動きを総称したものと理解されよう。
マレーシアがアジアの、製品によっては世界の主力工場となったために、設計・開発部門を併設する企業は増加している。日系企業の海外拠点における研究開発費支出に占めるアジアのシェアは、製造業全体では5.7%であるが、電気機械については9.1%と相対的に大きく、その63.7%がアセアン4に集中している(注10)。開発拠点の配置からみて、その大部分はマレーシアで支出されていると考えられる。
販売・マーケティングの面では、国内流通というよりも企業内貿易のハブになることに力点が置かれている。具体的には、前出の国際調達センターの設置振興である。さらに、IMP2では付加価値の高い活動の移転を促進する上で障害となる出資比率規制、輸出比率規制などの見直しが提言されている。
(4)は、近年の労働力逼迫を緩和し、国内の企業活動をより高次のものに移行させるために、周辺国への生産移転を積極化する動きである。マレーシアの電気・電子産業はシンガポールに隣接することによって部品調達、物流などの面で大きな利益を受けてきたが、同様にマレーシアにおける電気・電子産業の成長もシンガポールに好影響を及ぼしている。今後はマレーシアも周辺国の電気・電子産業の成長に寄与しつつ、その中で相対的に高度な役割を担っていくことで利益を得ようとしている。
移転先の具体的な候補の1つは、北方の三角地帯である。マレーシアの電気・電子産業の国内集積地帯としては、(1)ペナンを中心とし、対岸のケダ(注11)へ広がる半島北部(93年の同産業における雇用規模は約12万人)、(2)セランゴール、ネグリセンビランを中心とする半島中央部(同10万人)、(3)ジョホールを中心とする半島南部(同8万人)が3大地域であるが、半島北部では今後、タイ南部とのリンケージ強化による拡大が目指されている。
(3) マルチメディア・スーパー・コリドー
1) 計画の概要
電気・電子クラスターの開発戦略におけるもう1つの方向性は、情報技術産業(IT産業)を、今後10年間の電気・電子クラスターの成長の核と位置づけている点である。電気・電子クラスターのコア産業として、新たにデジタル機器という分野が登場し、ソフトウェアやマルチメディアといった知識集約型の産業が具体的に挙がっている。
こうした知識集約型産業の振興のために建設が進められているのがマルチメディア・スーパー・コリドー(MSC)である。
MSCは指定地域に高度な情報通信網、インテリジェント・ビル、快適な居住区など、世界最高水準のインフラを整備し、税制、出資比率、雇用面での恩典を提供することによって世界的なマルチメディア関係の企業を誘致、IT産業の一大集積地にしようとする試みである。
クアラルンプールの南方25kmに、シンガポールより若干広い750平方キロメートルの地域を対象に開発が進められている。MSCの一部として、飛び地的にクアラルンプール市内および近郊に立地するクアラルンプール・シティセンター(KLCC)やテクノロジー・パークはすでに完成し、入居が開始されている。
地域内のプロジェクトとしては、最初に完成するのはクアラルンプール国際空港(KLIA)で、98年初頭に開港予定、次いで、行政都市プトラジャヤへの主要官庁の移転が98年から順次行われる。今後は空港に隣接するエアポート・シティ、MSCにおける企業活動の中心部になるIT都市(サイバー・ジャヤ)の建設が着手される。第1期完成のめどは99年である。
高度情報インフラの整備は徐々に対象地域を広げ、マレーシアの先進国入りの目標年である2020年には国内全土に及ぶ計画である。電子承認やネット上の知的所有権保護、コンピュータ犯罪などにかかわる新しい法律(通称サイバー法)の策定も進められており、ハードのインフラだけではなく、制度面の整備も行われる。
2) 実験場としての価値にメリット
MSCに立地するメリットとしては、良質なインフラ、進出企業に対する各種の優遇措置(後述)などがあるが、マレーシアという1つの国を対象に、政府の全面的なバックアップの下で実験的な試みが可能であるところに最大の意義があると考えられる。更地からの立上げであり、政府による全面的な支援があるため、活動の自由度は大きい。
表7には今後、実用化が予定されているアプリケーションとそれぞれに関係が深い業種が挙げられている。
最初に実用化されるのは「電子政府」で、免許書き換え、登録などの各種手続きのペーパーレス化が新行政都市への官庁移転後、首相府を皮切りに開始される。アプリケーションの具体化に関しては、外国企業にも参加が求められており、ハードのインフラ建設と並ぶ当面のビジネス機会はここにある。規制の多い環境ではできない実験的な活動を行い、良いプロダクトが得られた場合は海外に売り込んでいくことも考えられる。こうしたアプリケーションの導入は今後、世界的に進むことが見込まれる。
こうしたインフラとしてのITの充実は、生活における利便性の向上、産業の効率性の向上という効用をもたらすと同時に、IT産業の需要創出を意味する。需要の拡大と環境の向上が企業の集積を呼び、クラスター化することによって、新たなビジネスやベンチャーを生み出すという循環が発生することが期待される(図6)。
MSCは「マレーシア版シリコン・バレー」と称されるように、将来的には産学協調による技術革新、ビジネス、企業の発生の場としての機能が考慮されている。年内に創設が予定されるマルチメディア大学、誘致が進められている海外の大学の研究所分室などがその中核となる予定である。
3) 人材の供給が課題
問題は、「入れ物」以外のところでどのようなメリットが提供できるかという点であろう。
IT産業にとっての環境としてみた場合、現状ではインフラ面でも人材面でもマレーシアの優位性は必ずしも大きくない。特に人材面では、コストこそ相対的に小さいが、絶対数が少なく、充足感に対する評価は極めて低い(表8)。
表8 IT産業にとっての環境比較
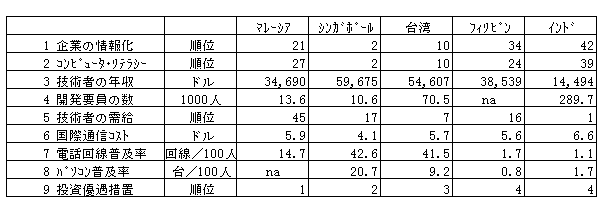
(注)1、2、4は94年、その他は95年の実績。1、2、5は48カ国中の評価順位、9については表中の5カ国における順位。通信コストはピーク・アワーの対米通話料(3分)
(資料)「The World Competitiveness Report 1995&1996」より作成。ただし、9については筆者の私見
今後、5年間でもIT人材の量的な需給ギャップは拡大が見込まれている(表9)。
知識集約型産業であるIT産業にとって最大の資源は人材である。MSCでは外国人の雇用が自由化されているが、先進国からのスタッフ派遣では企業のコスト負担が大きい。インド、フィリピンなどの近隣諸国から技術者を導入することも予想されるが、構想の規模・範囲に差こそあれ、現在、アジア全体でIT産業振興の動きが活発化しており(注12)、企業の誘致だけではなく、人材獲得の面でも競合が増している。自国にない内容かつ報酬の良い「仕事」を提供できなけれぱ、優秀な人材を招くことは難しい。
データ処理や単純なソフト開発であれば、コスト的に優れた国に発注するという選択肢もあるし、「実験場」としてのMSCのメリットを生かそうと思えば、ある程度の水準の技術者が必要となる。
企業がマレーシアに立地する必然性を高めるためには、自前の人材供給が必要である。国外からの供給をも含めた人材供給が MSCの発展に大きく影響する。
3.目標実現のための施策
(1) 優遇措置・制度の見直し
1) 投資政策の変化
投資ブームによって生じた産業構造の変化や新たな課題の出現で、投資政策は90年前後から変化している。傾向としては、(1)投資の選別強化(高付加価値産業志向)、(2)国内資本の参加促進が指摘できよう。
投資の選別色は91年頃から強まり、投資優遇措置の供与状況が厳しくなった。優遇措置を受けた案件は87~89年には投資認可案件全体の6割を上回ったが、年々、減少しており、93年以降は全体の3割前後で推移している。
また、I で述べたように、外資出資比率の規制緩和措置の期限が91年10月で切れたため、全額外資出資の案件が投資全体に占める比率も90年をピークに低下傾向をたどっている。業種によっては輸出型企業でも合弁が義務づけられたこと、「輸出」の再定義が行われたことも影響している(注13)。
7MPでは、さらに従業員1人当りの投資額が5万5,000リンギ以下の案件を労働集約型産業と位置づけ、優遇措置の適用を中止する方針を明らかにした。ただし、(1)付加価値率(付加価値額/生産額)が30%以上の企業、(2)半島東海岸およびサバ、サラワク州に立地する企業、(3)管理職・技術職・監督職の数が雇用の15%以上の企業、(4)「1986年投資促進法」の振興対象とされる技術・知識集約型の産業については例外とされる。
IMP2においては、(1)FTZと国内産業間のリンケージ強化のための制度変更、(2)WTOの動きに合わせた制度見直し(輸出義務、国産化規制、出資比率規制など)、(3)技術・知識集約型産業への転換を促進する優遇策パッケージ、(4)既存の各種優遇制度の運用利便性などが検討課題に挙げられている。
2) 新たな投資振興策
上記の検討課題のうち、97年度予算から制度変更が実施されたものもある。国際調達センター(IPC)の設置、およびマルチメディア・スーパー・コリドー(MSC)への進出企業に対する振興策の導入である(表10、11)。また、中間財の国産化推進を目的とした関税率の変更なども行われた(注14)。
今後、活発化が予想されるのは、96年に組織された中小企業開発公社(SMIDEC)が中心となるインダストリアル・リンケージ・プログラム(ILP)である。同プログラムは、すでに実施されている中小企業育成策であるベンダー・ディベロップメント・プログラム(VDP)を発展させたもので、国内中小企業を「工業化のメイン・ストリームに組み込む」ことを目的にしている。サプライヤーとして、中小企業の役割が大きいと考えられる機械部門から開始される。
VDP同様、セット・メーカー(VDPではアンカー企業)によるサプライヤー(同ベンダー)の支援・育成を基本としている。ILPにおける恩典としては、セット・メーカー(同リーディング・カンパニー)には出資比率規制の免除、サプライヤー育成に際して生じた支出の税額控除など、サプライヤーには投資優遇措置、低利融資などが供与される。
(2) 国内資本企業の育成
1) 第三市場創設
マレーシアでは91年に、中堅企業向けに第2株式市場を創設したが、さらに上場基準の緩いハイテク産業向けの店頭市場(MESDAQ)の創設が97年内に予定されている。最低資本金は200万リンギ、業種としては電子、バイオ産業、情報技術、新素材、環境技術、航空産業などを想定、過去の業績ではなく、技術の有望性を評価する。外国企業でもマレーシアで操業する企業であれば、調達した資金の7割を国内で投資することを条件に上場を認める。MSCの計画ともリンクさせ、技術力、アイデアを持ったベンチャー企業の生成を促進する方針である。
2) 政府系資本の関与
マレーシアの場合、国内資本の製造業への参加という面では、政府系資本が大きな役割を果たしてきた。近年、従来型の重工業投資への関与が縮小されてきたのはすでにみた通りであるが、製造業の大規模案件への参加では、政府系資本は依然として最も有力なプレイヤーであり、戦略性を持った案件に出資する傾向を強めている。
投資主体としては、94年に改組があり、政府の出資企業を管理・運営するために大蔵省傘下に全額出資の投資会社、カザナ・ナショナルが設立され、HICOM、テレコム・マレーシア(旧電電公社)、テナガ・ナショナル(旧電力公社)など多くの公営企業株が移管された。
同社は戦略産業への投資活動を積極化しており、輸送機器関連 、電気・電子関連で目立った動きがある。
後者については、従来、政府系資本の関与はまれであったが、90年代半ば以降、カザナ・ナショナルによる出資が開始された。具体的には、MEMCエレクトロニクス・マテリアルズ(米)との合弁によるシリコン・ウエハーの生産、「国民家電」(注15)を生産するマレーシア・エレクトリック・コーポレーション(MEC)への出資である。
資本参加の理由としては、(1)国内技術基盤形成の上からも国内資本による関与が必要という判断と、(2)投資資金およびリスク負担という企業支援の両面があると考えられる。
シンガポールでは、政府系資本が出資した半導体メーカーが順調に業容を拡大しているが、設備投資負担が大きい半導体の前工程を誘致するためには政府による出資という「呼び水」が必要であった。
7MPでは、前工程プロジェクト向けに1億リンギの予算が計上されており、マレーシア政府も今後、資金負担という「呼び水」の提供を意図しているとみられる。
前工程の導入は電気・電子産業の輸入財依存軽減化の目玉とされ、IMP2でも操業4年目以降、貿易収支に対してプラスの効果をもたらすと試算されている。ケダ州で計画されていた日立製作所とLG電子による合弁の前工程プロジェクトは市況悪化により中止されたが、現在、数件が投資認可を受けている(注 16)。
海外技術の獲得と国内開発技術の商業化の促進機関としては、94年にマレーシア技術開発公社(MTDC)が設立された。実際の活動はベンチャー・キャピタルとしての性格が強い。
(3) 人材育成
ハイテク産業の誘致にしても、サポーティング産業の発展にしても、あらゆるクラスターを通じて、キーとなるのは人材の育成であり、産業構造の転換に合わせた人材供給のための対応が急がれている。
大きな変化としては以下の2点が挙げられる。
第一に、人材供給機関の増大である。まず、96年に「1996年私立高等教育機関法」が成立したことによって、海外の大学の分校も含めた私立教育機関の設立が可能になった。ペトロナス、テナガ・ナショナル、テレコム・マレーシアは社内訓練所をエンジニアリング関係の学位(ディグリー・レベル)を出せる教育機関へと格上げする。今後、こうした私立の教育機関の増加によって需給調整が進むことが期待される。
また、89年に設立されたペナンの技術開発センター(注17)に範をとった官民合同型の技能訓練施設の増加、人材育成基金による従業員訓練コストの補助金支給対象(注18)の拡大など、就労者の訓練についても工夫がみられる。
第二は外国人雇用政策の変化である。未熟連労働者の雇用が農業、建設、メイド等に限定され、労働集約型の製造業における外国人労働者の雇用が本格的に制限される。一方、専門職の雇用については緩和の方向にある。すでにみたように、MSCでは外国人技術者の雇用は完全に自由化されている。
III.今後の展望
1.2005年の製造業
(1) 特化傾向の強まる産業構造
IMP2では各クラスターの成長率と構成比を予測している(表12)。この予測に基づくと、2005年では、現状でも製造業のほぼ1/3を占める電気・電子クラスターのシェアがさらに拡大するなど、既存有力クラスターへの特化傾向が強まっている。
製造業を4部門に分けてシェアの推移をみると、86~93年の間に機械加工産業への特化傾向が著しく進んだことがみてとれるが、2005年の製造業構成はその延長線上にある(図7)。
経済規模の小さいマレーシアにとっては、総花的な産業育成は政策的なコストの負担を意味する。IMP2では、自由化と企業のグローバル化の進展という環境の中で、既存のクラスターを強化していくという現実的な方向が打ち出されたものと理解されよう。
(2) 新たな成長産業
しかし、野心的な試みがないわけではない。例えば、新たな成長産業として、航空産業が挙げられている点である。IMP2でもFTZ的な専門の開発地域(アビエイション・パーク)設置による育成を提示している。
98年開港予定のクアラルンプール国際空港は最終的には現在のシンガポールの空港の6倍の規模に達する計画であり、航空機の整備・保守などのサービス需要の増大を見越した動きであろう。
また、MSCに立地するエアポート・シティの別名はエコメディア・シティであり、将来的にはバイオテクノロジー産業の育成拠点となる構想が描かれている(注19)。
MSCにしても、従来型の「モノ」づくりのための産業集積と並行して、知識集約型産業による産業集積を政策的に推進するという点では、十分に野心的な計画である。IMP2の予測では、現在のリーディング産業である半導体産業の成長速度は鈍化するが、航空産業、医薬品などの産業が期間を通じて、高率で成長すると予想されている。
2.グローバル経済下の産業政策
80年代後半以降の工業化に対するマレーシア政府の関与をみると、第2国民車、国民家電など、ナショナリズムの発露がみられる場面もあったが、総体としてはグローバル経済に深く組み込まれた自国の状況を意識した現実的な対応が目立ち、政府主導色は後退している。
IMP2においても、有力クラスターへの傾斜が強まれば強まるほど、企業のグローバル化戦略に深く組み込まれるという構図の中で、その動きを最大限に活用すべきであるという認識と、フルセット型の産業育成を諦めきれないナショナリズムの責めぎ合いがみられる点が興味深い。クラスターを大別する際に、あえて国際経済リンク型クラスターと政策主導型クラスターを置いたところなどはその顕著な例である。
しかし、貿易自由化が進展する現在、国内市場の保護にる産業育成は困難になりつつある。加えて、ウルグアイ・ラウンドの妥結を受け、国産化規制、輸出比率規制は2000年、出資比率規制は2003年を目標に撤廃が予定されるなど、政策手段はますます減少していく。こうした環境下で競争力のある産業を生成・発展させていくために国ができることは何かという問いかけの回答が「クラスター開発」であったと考えられる。
クラスターの発生自体に対しては、政府が行い得ることは少ない。しかし、形成が始まった段階ではそれを強化する役割を果たすことが可能であり、大学の付属研究所、訓練センター、専用インフラなど「専門的な要素」を創造する投資の重要性が指摘されている(注20)。
マレーシアではまさに、こうした投資への取り組みが本格化されているのである。専門的な要素とは、技術や創意またはそれが体化された人材や企業であり、さらに問題となるのはこれらを持続的に生み出していく社会・経済的なシステムであるともいえる。
輸出加工区を設け、外資系企業を誘致するタイプの工業化は、しばしば「テナント・インダストリー(貸し間産業)」と揶揄されてきたが、いまや、そのテナントの質を問うものは、工業団地などの「入れ物」ではなく、ホスト国が提供できるトータルな経営資源となっている。前出の「専門的な要素」こそが、その土地を単なる一時的な生産の場か、発展性のある創造の場にするかを決定していくと考えられよう。
注
1. 拙稿「マレーシアの企業」(『RIM』19号、1992年所収)参照。
2. 4MP(80~85年)における開発支出の対GDP比は、1MP~7MPの中でも抜きん出て高い。
3. 具体的には、(1)輸出比率50%以上、(2)250人以上の雇用創出(常勤)のいずれかを満たせばよい。同措置は実際に91年10月末まで延長された。
4. 転換点については、南亮進『日本の経済発展』東洋経済新報社、1981年、p.244~252。
5. タイの産業構造変化については、拙稿『変容するタイ工業化』(『RIM32号』、1996年所収)参照。
6. 青木(1992)など。
7. 竹内文英「東アジア各国における資本財・中間財の外部依存について」JCERディスカッションペーパー、1995年。
8. 一国の競争力における成功は、相互に連結した産業のクラスター全体で起こるなど。この場合の競争力とは、生産性およびその持続的な向上を可能にする種々の要因を指す。
9. 清成・橋本編著(1997)、p.191
10. 通産省『第5回海外投資統計総覧』、1993年。
11. ケダ州には国内初のハイテク・パークが設立されており、政府系資本の出資するエレクトロニクス企業などの入居も決まっている。ペナンの工科大学などとも連携したハイテク産業の集積地として育成が図られている。
12. シンガポール、フィリピン、タイ、インド、台湾などがそれぞれ振興策を持っている。
13. 91年にはプラスチック射出成型、金属プレスなどについては、輸出型企業でも原則、合弁となった。また、93年7月から間接輸出(FTZなどへの販売)を輸出にカウントしなくなったため、輸出型企業(製品を8割を輸出する企業)として単独出資が可能な企業が減少した。
14. 具体的には、日本貿易振興会『通商弘報』96年11月12日号参照。
15. トースターからエアコンまでと幅広い家電製品の生産が予定されている。現状ではほとんど優遇措置を受けておらず、また、製品の大半を輸出する計画である(『Far Eastern Economic Review』April 24,1997)ことから、国民車プロジェクトとは性格が異なる。
16. サラワク州では州政府出資、シャープの技術供与による、ジョホール州ではシンガポールのチャータード・セミコンダクターによる前工程プロジェクトが計画されている。
17. 同センターは、主として州開発公社が土地、建物を、ペナンに立地する民間企業が運営費、機材、トレーニーを分担することによって運営されている。91~95 年の間に延べおよそ2万人が利用した。こうしたタイプのセンターが新たにジョホール、セランゴール、ケダなど8州で設立されている。
18. 97年度から中小企業および特定のサービス産業が新たに補助金支給の対象となった。
19. 黒川紀章事務所ホームページ「Ecomedia-City」。
20. ポーター(1992)下巻、p.360
主要参考文献
1. 青木健『マレーシア経済入門』 日本評論社、1992年
2. 清成忠男・橋本寿郎編著『日本型産業集積の未来像』日本経済新聞社、1997年
3. マイケル・ポーター『国の競争優位 』ダイヤモンド社、1992年
4. Economic Planning Unit, Prime Minister*s Department, Malaysia ,Seventh Malaysia Plan 1996-2000,1996.
5. Ministry of International Trade and Industry, Malaysia, Industrial Master Plan 1986-95, 1986.
6. Ministry of International Trade and Industry, Malaysia, Second Industrial Master Plan 1996-2005, 1996.
7. K.S., Jomo Industrialising Malaysia -Policy, Performance,Prospects Routledge,1995.

