RIM 環太平洋ビジネス情報 1998年7月No.38
アセアン諸国の消費市場の現状と展望
1997年07月01日 さくら総合研究所 坂東俊輔
アセアン諸国は輸出主導で順調な経済成長を遂げてきたといわれている。近年、アセアン諸国の国内消費市場の規模は拡大してきており、先進国企業から有望なマーケットとして重視され始めている。
そこで本稿では、アセアン諸国の消費市場の現状を概観した上で、主に過去20年間(1976~95年)について、(1)国民所得統計などのマクロ経済指標からみたとき、アセアン諸国の消費がどの程度拡大しているのか、(2)経済成長が輸出主導型から内需主導型に移行しているのか、さらに、(3)消費市場の今後の動向について分析を行った。
その結果、以下のようなことが明らかになった。
1. 自動車を典型的な例として、アセアン諸国の国内消費市場は順調に拡大している。その経済的な要因として一人当たりGDP(国内総生産)の増加、社会的な要因として中間層の台頭と情報化の進展が挙げられる。
2. マクロ経済指標から分析を行った結果、アセアン諸国において、
1)実質額でみた消費は順調に拡大している。
2)実質GDPの構成をみると、民間最終消費支出の比率は安定している。一方、輸出の比率は年ごとのばらつきが大きい。
3)限界消費性向に構造的な変化はみられない。
したがって、最近のアセアン諸国の経済成長は従来通り輸出主導型のものである。これを確認するために、
4)世界経済の成長率に対するアセアン諸国の実質経済成長率の弾力性をみると、80年代に入り弾力性が上昇しており、世界経済の動向にアセアン諸国の経済成長率が左右される度合いが高まっている。
3. アセアン諸国の消費の将来を展望すると、(1)その人口規模、世界経済を上回る経済成長率から消費の絶対額が拡大すること、(2)中間層の増加、消費者信用サービスの充実、現地の消費を喚起する商品の開発・生産の本格化、人口の高齢化の進展といった理由から限界消費性向が上昇することにより、消費市場の一層の拡大が予想される。
はじめに
1980年代、特に後半以降、先進国市場の順調な拡大、積極的な外資導入政策、円高などを原因に、アセアン諸国の輸出はエレクトロニクス関連製品を中心に目覚ましい勢いで拡大した。その結果、アセアン諸国は総じて高い経済成長率を持続した。
89年には、経済協力開発機構(OECD)によりタイ、マレーシアがアジアNIEsとともにDAE(Dynamic Asian Economies)と称されるようになった。
現在、マレーシアは西暦2020年に先進国の仲間入りを果たすという目標を掲げている。大国インドネシアも石油・天然ガス等一次産品依存型経済から脱却している。フィリピンも一時の政治的・経済的混乱から立ち直り、2000年にはNIEs入りすることを目標にしている。このような輸出主導の目覚ましい経済成長は、輸入代替化政策を重視したラテンアメリカ諸国の経済パフォーマンスとは対照的なものであった。
アジア諸国の経済成長は、これまで先進国市場向けの輸出に依存したものであるといわれてきた。しかし、近年、NIEs、アセアン諸国の経済成長は輸出主導によるものから個人消費を中心とした内需主導型に移行しつつあるとの意見が聞かれる。
先進国においては、消費市場が飽和しつつあるといわれていることや、潜在成長力が過去の実績と比較して低下している現状から、国内市場の拡大が望めない。このため、日米欧の先進国企業は消費市場としてのアセアンに注目し始めている。
そこで、本稿では第一に、アセアン諸国の消費拡大の現状とその要因を考える。具体的は、消費がどの程度拡大しているのかを自動車の販売台数などで確認し、その経済的および社会的要因を考える。
第二に、アセアン諸国の消費拡大の現状を、国民所得統計を中心にマクロ経済の視点から分析する。具体的には、消費の実質額推移を概観し、実質経済成長に対する輸出や民間最終消費支出の寄与度をみる。それによって、アセアン諸国の経済成長が輸出主導型であったのか内需主導型であったのかを検証する。さらに近年、経済成長の牽引役が輸出から内需に転換したか否かを確認する。
また、輸出に関し、世界とアセアン諸国の実質経済成長率の関係を、その弾性値を計測することにより時系列で概観する。
最後に、アセアン諸国の消費市場が今後も拡大を続けるのか否かについて考察する。
なお、本稿におけるアセアン諸国とは、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピンの4ヵ国を指すものとする。一人当たり国民所得が高く、通常NIEsに分類されるシンガポール、小国ブルネイ、95年にアセアンに加盟したが統計のアベイラビリティに問題のあるベトナムについては、今回の分析対象から除いている。
I.アセアン諸国の消費拡大の現状と要因
1.アセアン諸国の消費の現状
アセアン諸国は、一時期のフィリピンを除き世界経済の平均成長率を上回る高い経済成長を持続し、その経済規模を順調に拡大している(図1)。日本経済研究センターの資料「経済のグローバル化と地域主義の相克」(96年3月)によると、全世界の名目国内総生産(GDP)に占めるアセアン4ヵ国の比率は、90 年の1.3%から95年には1.6%へ拡大している。さらに2000年には2.0%に拡大し、2010年には3.1%、2020年には4.5%に拡大すると予想されている。
個人消費に大きな影響を与える要因の一つに人口規模がある。国際連合『世界人口予測1950→2050』によると、世界総人口に占めるアセアン諸国の人口の比率は95年で6.0%に上っている。この比率は2000年、2010年にも変わらないと予想されている。
発展途上国では、一人当たり所得が一定水準に達すると急激に購買力が高まるため、耐久消費財の需要が急拡大するといわれている。
アセアン諸国においても、代表的な耐久消費財である自動車の販売台数が顕著に増加している。86~95年の10年間で、アセアン各国の自動車販売台数はタイで7.2倍、マレーシアで4.2倍、インドネシアで2.3倍、フィリピンでは実に29.6倍に拡大している(図2)。
一般に、一人当たりGDPが3,000米ドルを超えると、急激にモータリゼーションが進展するといわれている。
95年末時点での一人当たりGDPは、タイ2,800ドル、マレーシア4,100ドル、インドネシア1,000ドル、フィリピン1,000ドルである。3,000ドルを超えているのはマレーシアだけであるが、その他の国でも自動車販売台数は急激に拡大している。
また、自動車のみならずカラーテレビ、VTRなどの家電製品も、急速に普及率が高まっている(表1)。アセアン諸国においては、高い経済成長率が持続した結果、所得が増加し、消費も拡大した。しかも国民の消費の選択の幅も広がりつつあるのである。
こうしたことから、日系企業など先進国企業を中心に近年、アジアの消費市場が注目されている(注1)。また、アセアン諸国の経済成長は、輸出主導型から民間最終消費支出を中心にした内需依存度を高めているのではないかともいわれ始めている(注2)。
2.市場としてのアセアン諸国の重要性
アセアン諸国の消費市場の拡大に注目し始めた日系企業は、アセアン進出に際し、第三国市場向けの輸出拠点という従来からの位置づけに加え、現地市場での販売を進出動機として今まで以上に重視し始めている。
通商産業省政策局国際企業課が80年度以降3年ごとに発表している『海外投資統計総覧』(注3)で日系企業のアセアン進出状況を振り返ってみよう。
日本企業現地法人のアセアンへの進出動機に関し、現地ヘの販路拡大を目的とすると回答した企業は全体の61.8%(90年3月末時点調査)から63.3%(93年3月末時点調査)へと増加している。製造業に限った統計では、その比率は同時期に58.9%から60.9%に増加している。
また、日本輸出入銀行が89年から実施しているアンケート調査の最新版(95年末実施)においても、国別投資理由のうち、進出先マーケットの維持拡大がタイ、マレーシア、インドネシアで1位、フィリピンで2位となっている。
具体的な例として、日系自動車メーカーが現地の所得水準に合わせ、アジア・カーと呼ばれる低価格のアジア向け自動車の生産を本格化するなど、現地の消費を喚起するようなマーケティング戦略を本格化し始めている事例も挙げられる。
先進国市場においては、新しい機能を付加した製品や、画期的な新製品に関しては目覚ましい需要の伸びがみられるケースもある。しかし、普及品や耐久消費財全般については、近年、消費市場が飽和状態にあることが指摘されている。さらに、先進国の潜在成長力が伸び悩んでおり、将来的にも先進国の経済成長率に関し、アセアン諸国ほどの高い伸びは期待できない。一方、アセアン諸国の一人当たり国民所得は先進国と比較すると低いとはいえ、経済成長率は高く、その人口規模も無視できない。
このような理由から、日系企業は消費市場としてのアセアン諸国を、従来にもまして重視し始めていると考えられる。
3.消費拡大の要因
ここでは、アセアン諸国において消費が拡大した経済的な要因と社会的な要因について考えてみたい。
(1) 経済的な要因
アセアン諸国において消費が拡大している経済的な要因は、高い経済成長率に伴う一人当たりGDPの増加と物価の安定である。
すなわちアセアン諸国では、高い経済成長率を背景に、賃金が上昇し、雇用者所得が増加する一方で、インフレが比較的低位にとどまっているため、民間最終消費支出が拡大しているのである。
アセアン諸国の購買力の上昇は通常、一人当たりGDP(時価ベース)の増加によって議論されている。しかしながら、時価ベースで米ドル換算した一人当たりGDPは、実質的な購買力や生活水準を正確に表すものではない。一人当たりGDPを時価ベースでドル単位で測りその国の国民の購買力を比較すると、実際の購買力を過小評価する危険がある。
実際の為替レート(時価ベース)は、貿易財に対する購買力の比率により決定される。しかしながら、GNP(国民総生産)やGDPを構成する生産物には、住宅やサービスなど多種多様な非貿易財が含まれている。一般に発展途上国では、先進国よりも非貿易財の価格は低い。途上国の購買力平価は貿易財と非貿易財を含んで計算されることから、実際の為替レート(時価ベース)より割高となる。
そこで、実際の為替レート(時価ベース)で米ドル換算した一人当たり名目GDPと実質購買力を比較したものが図3である。国連開発計画(UNDP)の『人間開発報告』による、購買力平価で測った一人当たりGDPは、実際の為替レートで米ドル換算した一人当たりGDPよりかなり大きい。前者の後者に対する比率は、タイで2.6倍、マレーシアで2.7倍、インドネシアで4.0倍、フィリピンで3.3倍となっている(注4)。すなわち、アセアン諸国の購買力は、実際の為替レートで測ったものより相当高いものである。
加えて、現在の所得だけが現在の消費を規定するわけではないことにも留意しなければならない。将来の経済成長率に関する期待の形成に際しては、過去の実際の成長率および現在の経済状況に左右される面が強い。この10年間に高い経済成長率を実現したアセアン諸国の国民は、将来の所得も上昇すると期待することとなろう。
消費の恒常所得仮説(注5)によれば、潜在成長力の上昇に伴い、将来確実に獲得できると予想される所得が増加すれば、その所得の増加部分は恒常所得と考えられ、現在の消費は増加することとなる。
インフレ率をみても、86~95年の10年間でアセアン諸国の平均インフレ率(GDPデフレータ上昇率)は5.9%と、発展途上国の中では極めて低いものであった。物価上昇率が低い中で雇用者所得が上昇した結果、アセアン諸国において消費拡大が促進されたのである。
(2) 経済的な要因
上述した経済的な要因の他に、消費拡大に関する社会的な要因として、アセアン諸国における中間層の台頭(注6)と情報化の進展が挙げられる。
1) 中間層の台頭
アセアン諸国においては、経済成長に伴い雇用が拡大し、個人の所得が増加した。その結果、都市に住む中間層(ミドル・クラス)が増大したと考えられる。
中間層についての明確な定義はなく、また各研究者によってその定義は異なっている。ここでは、主に都市に居住するホワイト・カラーあるいは専門職に従事する階層を念頭に置いている。
このような中間層については、従来の生活嗜好とは異なる生活・行動パターンをとることが指摘されている。アセアン諸国では目覚ましい経済成長の過程で、都市住民を中心に、従来の伝統的な生活パターンからライフスタイルの欧米化がみられている。具体的には、中間層の増加は都市化の進展、核家族化、共稼ぎの増加などを引き起こしている。
都市化の進展度合いをみると、都市に居住する人口の全人口に対する比率は着実に増加している。85年と95年の2時点比較で、タイでは17.9%から 20.0%へ、マレーシアでは45.9%から53.7%へ、インドネシアでは26.1%から35.4%へ、フィリピンでは43.0%から54.2%へと増加している(注7)。また、核家族化は世帯数の増加を意味し、耐久消費財に代表される消費需要の増加をもたらしたと考えられる。共稼ぎ夫婦の増加は、白物家電製品(例えば冷蔵庫や洗濯機など)の需要拡大につながる。
このように所得が比較的高く、しかも消費性向の高い中間層世帯の増加は、企業の製品に対してマス・マーケットを提供する。したがって、中間層の増加はアセアン諸国における消費市場の拡大に大きく寄与したと考えられよう。
事実、都市部の中間層の比率は増加しつづけているのである。例えば、インドネシアにおいてはジャカルタ、バンドン、スラバヤ、メダンの四大都市において、中間所得層に相当するとみられる層は90年には全体の18%であったが、94年には24%に増加している(注8)。また、90年代初めに600万人前後であった年収6,000~12,000米ドルの中間層は、経済発展で1,500万人に増えたという(注9)。
金融面においても、中間層は金融機関にとって消費者金融の中心的なマーケッティング対象である。中間層の多くはクレジットカードを所有しているものと考えられる。例えば、タイにおいて、現地の中間層を対象にしたJCBカードの保有者は96年初頭には約5,000枚であったが、96年中には6万枚に達する見通しであるという報道もある(注10)。消費者金融やクレジットカードの普及は消費を拡大すると考えられる。こうした金融の側面からも、アセアン諸国の中間層の台頭は消費の拡大につながっていると考えられる。
2) 情報化の進展
一方、マスメディアの発達により、多種多様で大量の情報がアセアン諸国の国民に広範かつ即座に伝達されるようになってきた事実も見逃すことはできない。多くの途上国においてテレビの普及が消費意欲をかきたてていることが指摘されている。
近年、既存のテレビについてはチャンネル数が増加しているうえ、新規の媒体としてスターTVに代表されるような衛星放送、あるいはCATVも急速に浸透し始めている。その結果、欧米先進国の消費生活のみならず、日本やNIEsなど近隣アジア諸国の消費動向もアセアン諸国の国民にリアルタイムで伝達されている。マスメディアの発達は、アセアン諸国の人々の購買意欲を大いに刺激していると考えられる。
これらの要因に加え、家電や自動車などに関して割賦販売が普及し始めたこと、流通・小売業が地場、外資を問わず積極的に店舗展開しており、流通面から消費を促進していることなども消費拡大に寄与していると考えられよう。
以下では、マクロ経済データにより、民間最終消費支出と実質GDPへの寄与度の推移を概観した上で、近年指摘されているようにアセアン諸国の経済成長が輸出主導型から内需主導型に移行したのか否かを検証する。
次いで、アセアン諸国における消費の拡大が、主に所得の増加によるのか、それとも限界消費性向に構造的な変化が生じているのかといった視点から分析する。
ただし、マクロの民間最終消費支出は、あくまでマクロでとらえられたデータである。マクロで得られる統計とミクロレベルでの経済主体である消費者の消費に関する実感との間に乖離はあることには留意しなければならない。
II.経済成長と消費動向
1.民間最終消費支出と輸出の動向
最初に、アセアン諸国の支出国民所得の構成を各国ごとに時系列で追ってみた(図4)。この図からわかる通り、実質値でみたアセアン諸国の民間消費支出額は順調に拡大している。
各国ごとにみると、タイでは86~95年の間に民間最終消費支出は7,489億バーツから1兆6,328億バーツ(88年固定価格)へと2.2倍に、また、マレーシアでは263億リンギから581億リンギ(78年固定価格)へと2.2倍に、インドネシアでは114兆7,530億ルピーから206兆 3,220億ルピー(93年固定価格)へと1.8倍に、フィリピンでは591兆4,230億ペソから802兆8,660億ペソ(85年固定価格)へと 1.4倍に拡大している。
次に、GDPに占める民間最終消費支出の構成比率を時系列でみたものが表2である。総じて、アセアン諸国のGDPに占める民間最終消費支出の割合は安定していることが読み取れる。これは、特に個人の所得水準が短期的に変動したとしても個人は消費水準を即座に変えることはない習慣効果に起因する。
ただし、もう少し詳しくみてみると、各国ごとにそれぞれの特徴がみてとれる。
タイにおいては、趨勢的に民間最終消費支出のGDPに占めるウェイトが低下してきているが、近年は56%で安定している。
また、マレーシアについては、80年代後半に同ウェイトが低下したものの、90年に入ると若干上昇し、93年以降再び低下してきている。
インドネシアについては、80年代前半は同ウェイトは上昇傾向を示しているが、後半に入ると前半の値よりも総じて低いものになっている。
フィリピンでは、70年代後半から80年代前半にかけて若干低下したが、84年を契機に上昇している。また、フィリピンにおいてはGDPに占める消費の比率が80%近くにも達しており、マクロ経済でみた貯蓄率の低さにつながっていると考えられる。
マレーシアを除き、アセアン諸国では各需要項目のGDP構成比の中では民間最終消費支出が最大である。ただし、GDPに占める輸出の構成比はインドネシアを除いて趨勢的に上昇傾向にある。
インドネシアについては、70年代後半から80年代央にかけてそのウェイトが低下している。当時、インドネシアの主要輸出品が石油・天然ガスであったことを考えると、世界向けの資源輸出がその輸出の中心であり、一次産品価格の低迷が輸出の構成比を低下させたと考えられよう。インドネシアの輸出のGDP構成比は85年に底を打ち、その後、非石油・天然ガスが輸出の中心となるのに伴い、上昇している。
2.寄与度の動向
次に、アセアン諸国の実質経済成長率の需要項目別寄与度を求めたのが表3である。便宜的に76~85年を前半、86~95年を後半(ただし、タイについては図4(注)の理由により86~94年)として、民間最終消費支出の寄与度をみてみよう(注11)。
同寄与度は経済成長率の変動に伴い、年ごとに大きく変動している。前半と後半の平均値をみると、タイが3.4%から4.9%へ、フィリピンが2.0%から 3.0%へと増加している。一方、マレーシアは3.6%から3.4%へ、インドネシアは4.3から3.6%へと減少している。
また、前半と後半について民間最終消費支出の寄与率を計算すると、タイが52.7%から51.6%へ、マレーシアが51.9%から44.4%へ、インドネシアが67.5%から48.5%へ、フィリピンが91.4%から74.0%へと、すべての国で減少している(注12)。
次に、需要項目の寄与度のばらつきをみるために、ばらつきの大きさを測る指標である変動係数(標準偏差を平均値で除した比率)を需要項目別に算出し、比較してみた。
アセアン諸国における民間最終消費支出の変動係数は、86年にその寄与度が-5.1%となったことが影響しているマレーシアを除き、輸出、輸入の変動係数よりも小さくなっている。すなわち民間最終消費支出は安定的な動きを示しているのである。
昨年来、タイでは輸出の伸び悩みを主因に、経済成長率が鈍化している。96年にはタイの輸出は13年ぶりに前年比伸び率がマイナスとなった。需要項目に占める消費の割合が高まることは、内需主導型の安定した経済成長につながるとも考えられよう。
タイに限らずアセアン諸国の間では、繊維製品など労働集約的な製品に関しては中国、ベトナム、インドなどに急追され、国際競争力が低下している。一方で、自動車関連製品やエレクトロニクス製品など比較的高付加価値製品の輸出は、十分に国際競争力を持ち得るレベルまでには発展していないのが現状である。
高付加価値製品が輸出市場で国際競争力を持ち得るまでに国内産業が高度化するまでの間、既存の労働集約的製品が輸出の中心であると、国際競争力の低下から輸出が伸び悩み、成長率が鈍化する可能性がある。
タイのケースでは、96年に輸出が減少したのはエビやプラスチック製品、繊維製品など、一次産品や労働集約的な商品であり、エレクトロニクス関連の輸出は増加している。そこで、アセアン諸国にとっては、中長期的な視野から内需主導の経済成長を、産業の高度化を実現するための短期的な「構造変換のための過渡期」と考えることも必要となろう。
3.限界消費性向
マクロでみた消費に関しては、限界消費性向という概念も重要である。
限界消費性向とは、1単位の実質所得(GDP)が増加した時、実質消費が何単位増加するかを示すものである。
限界諸費性向を時系列でみて、それが構造的に変化したのか否かをみることにより、限界消費性向が上昇して同じ所得に対する消費額が増加したのか、それとも消費性向自体はあまり変化していないのか、実質GDPつまりパイが拡大して消費が増加しているのかを確認できる。
そこで、76~95年の20年間について、実質民間最終消費支出を実質GDPで回帰分析することにより、アセアン諸国の限界消費性向を求めた。
限界消費性向を算出する際、説明変数としては実質可処分所得を使用することが望ましいが、ここではデータの制約から実質GDPでその傾向を追うことにした。
また、限界消費性向を算出する際、実質民間最終消費支出と実質GDPをそれぞれ人口で除して一人当たりの数字を求めて回帰分析するケースもある。しかしながら、一人当たりベースで回帰分析を行った結果、フィリピンでは経済成長率が84年、85年に-7.3%と極めて低く、ばらつきが極めて大きいため、係数が有意でないうえ、当てはまりが極めて悪くなってしまった。そこで、本稿では一人当たりの数値は使っていない。
フィリピンでは出稼ぎ労働者による送金など、海外からの要素所得(労働への対価と投資収益、特にフィリピンのケースでは前者)がかなり大きなものとなっている。
そのため、フィリピンにおいてはGNP(GDPに海外からの要素所得を加えたもの)がGDPを大きく上回っている。GNPとGDPの比率をみると、95年時点でタイ0.97、マレーシア0.94、インドネシア0.96、フィリピン1.03となっている。
したがって、フィリピンの場合には、民間最終消費支出は海外からの要素所得に大きな影響を受けているものと考えられる。そこで、フィリピンに関しては限界消費性向の推計に際し、実質GDPではなく実質GNPを説明変数とした。実際、フィリピンの実質民間最終消費支出を実質GDPで回帰分析すると、限界消費性向が1.01と、1よりも大きなものとなり、所得以上に消費するという現実離れした結果となってしまう。
76~95年の20年間に関する(タイについてはデータのアベイラビリティの問題から94年まで)限界消費性向を求めた結果は、表4の通りである。
表4 回帰分析結果
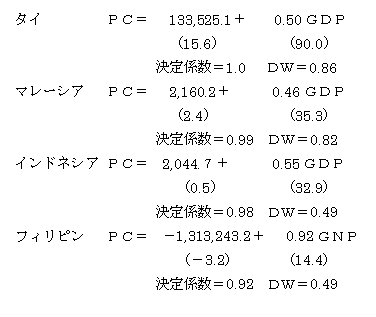
(注)PC=民間最終消費支出、GDP=実質国内総生産、( )内はt値
回帰分析結果について、DW比が低く、誤差項に正の相関があると考えられる。しかし、ここでは決定係数が高いこと、限界消費性向を求めることが主目的であることから、消費関数を単回帰にとどめている。
限界消費性向はタイが0.50、マレーシアが0.46、インドネシアが0.55、フィリピンが0.92であった。フィリピンの限界消費性向の高さが際立っているが、これがマクロでみた貯蓄率の低さにもつながっていると考えられる。
また、マレーシアの消費性向の低さ、すなわち貯蓄性向の高さは、強制的に加入が義務づけられている従業員退職積立基金(EPF:Employees Provident Fund)により、所得の一部が強制的に貯蓄させられているためとも考えることができる。
限界消費性向に変化が生じているか否かを視覚的に確認するために、横軸に実質GDP(フィリピンは実質GNP)、縦軸に民間最終消費支出をとって、そのトレンドをみたのが図5である。
図中の直線は回帰式を表している。この図からわかる通り、アセアン諸国の限界消費性向はこの20年間安定しており、限界消費性向が変化した兆候は見いだせない。
また、93年から94年にかけてエマージングマーケット・ブームといわれるほどアセアン諸国の株式市場が活況を呈したが、それに伴う資産効果による消費の拡大もみられなかったことがわかる。
以上をまとめると、アセアン諸国において実質GDPに占める消費のウェイトは安定しており、その一方で、輸出の割合は上昇傾向にある。
実質経済成長率に対する輸出の寄与度をみると、その値のばらつきは大きい。過去20年間(76~95年)に関していうと、前半10年よりも後半10年について民間最終消費支出の寄与率がすべての国で低下している。
したがって、GDPに占める民間最終消費支出のウェイトは、水準自体は大きなものではあるが、アセアン諸国の近年の経済成長の牽引役は、内需というよりもむしろ輸出であると考えられる。
また、アセアン諸国の限界消費性向はほぼ一定で、消費の拡大は限界消費性向の上昇によるものではない。すなわち、アセアン諸国の消費の増加はGDPの拡大によるもので、限界消費性向の構造的変化によるものではないと考えることができる。
4.弾力性でみた輸出依存度の動向
前述のように、アセアン諸国の経済成長が依然として輸出主導型ならば、世界経済の成長率とアセアン諸国の経済成長率がいったいどの程度連動しているかを、その弾力性を推計することによって考えてみたい。
推計は、世界の経済成長率に対するアセアン諸国の弾性値を計算したものである(注13)。図6は、世界経済が1%成長したときアセアン各国が何%の経済成長するか(弾力性)を、76~85年から85~94年までの各10年について、計10期間の時系列で示している。具体的には、世界経済の実質GDPとアセアン各国の実質GDPの自然対数をとり、前者を説明変数、後者を被説明変数にして回帰分析を行い、その係数を求めたものである。
図6が示すように、世界経済に対するアセアン諸国の経済成長率の弾力性は76~85年以降、低下傾向を示していた。
しかし、タイでは78~87年、マレーシアでは80~89年、インドネシアでは80~89年、フィリピンでは79~88年の各期間以降、それぞれ上昇傾向に転じている。これは貿易や投資を通じたアセアン諸国の経済と世界経済との結び付きが80年代に強化されたことを反映しているといえるであろう。
アセアン諸国にとっては米国、日本が主要な輸出産品の仕向け先となっている。図6は、米国、日本を中心にした輸出あるいは投資を通じた世界経済の動向がアセアン諸国に影響を及ぼす度合いが近年高まっていることを反映したものといえよう。このことは、前述のアセアン諸国の経済成長が輸出主導型であったことと軌を一にしている。
直近のデータである85~94年の10年間をみると、世界経済が1%成長するとタイは3.0%、マレーシアは2.4%、インドネシアは2.0%、フィリピンは1.0%の経済成長を遂げていることになる。
タイが世界経済の影響を最も大きく受けることになり、フィリピンではその影響が最も小さい。フィリピンの弾力性の低さは、GDPに占める民間最終消費支出の高さに現れている。
このように、アセアン各国のGDP成長率が世界経済の動向に左右される度合いは近年高まっているのである。
III.今後の動向
以上では、順調に拡大してきたアセアン諸国の民間最終消費支出の動向をみてきたが、ここでアセアン諸国の今後の消費の動向に目を転じてみたい。
結論を先取りすると、今後アセアン諸国においては、GDPの拡大に伴い消費が増加すると予想される。さらに、構造的に限界消費性向が上昇すると予想され、この面からも消費が拡大すると考えられる。
ただし、フィリピンに関しては、GNPに占める消費の比率が高いこと、および限界消費性向も0.92と高いこと、さらに経常赤字が深刻な問題になっていることを考えると、消費拡大による貯蓄率の低下、経常赤字の拡大といった制約要因があることから、消費がさらに拡大することに関して若干の懸念がある。
1.GDPの増加による消費の拡大
GDPが増加することにより消費規模が拡大する理由は、以下の2点である。
第一に、人口規模が大きいことが挙げられる。95年のデータでアセアン諸国の人口はタイ6,000万人、マレーシア2,000万人、インドネシア2億人、フィリピン7,000万人と総計3億5,000万人であり、世界の総人口の約6%を占めている。今後、この比率はさほど変わらないと予想されているが、その絶対的な人口規模の大きさは消費の拡大を予想させるに十分なものである。
第二に、アセアン諸国において、今後も世界の平均成長率を上回る経済成長が予想されることである。図7に示されるように、今後アセアン諸国は世界経済の平均成長率を大きく上回る経済成長率を実現すると予想されている。経済成長の結果、実現される経済規模(GDP)の拡大は消費の増加を意味する。先に述べた恒常所得仮説に基づけば、経済成長が継続した結果、将来も引き続き所得の伸びが期待され、その所得の増加が恒常所得と国民に認識されれば、現在時点での消費が増加すると考えられる。
2.限界消費性向の上昇による消費の拡大
限界消費性向の上昇をもたらすと考えられる主な要因としては、以下の4点が考えられる。
第一に、消費の中心的な担い手と考えられる中間層が増加していくと考えられることである。中間層は、都市部を中心に物質生活の浸透に伴い、強い購入意欲を有する大量の需要を形成すると考えられる。近年、アセアン諸国において中間層が増加しているといわれてはいるが、現状ではアセアン諸国において中間層と分類できる層はいまだに少数である(図8)。しかし、前述したように、アセアン諸国は今後も高い経済成長率を持続する結果、中間層に属する人口比率は上昇していくものと考えられる。
第二に、アセアン各国において金融市場の整備・自由化がさらに進展し、消費者信用サービスが拡充することが予想されることである。商品、サービスの販売と直結した販売信用と消費者金融が一層充実すれば、手元に資金がなくても大きな支出が可能となることから、限界消費性向が上昇すると考えられる。
現在、タイにおいては自動車の購入者の6割がローンを利用しているといわれている。地場銀行はアセアン諸国においてリテール部門の拡充に努めている。最近では地場銀行に加え、邦銀もアセアン諸国の地場でリテール部門の拡充を図っている。消費者信用の充実により、ローンの利用比率が高まることも予想される。
しかし、注意すべき点もある。タイの例にみられるように、消費者向け貸し出しの中には、不良債権化している資産もある。一部のタイの金融会社は、不動産向け融資と自動車の割賦販売向け融資の不良債権化で経営が悪化している。例えば、経営危機に瀕している地場のファイナンスカンパニー、ファイナンス・ワン(F1)の場合、融資額の24%が割賦販売向けであった。今後、消費者信用制度がより一層充実するためには、消費者信用に関する法律の整備、個人信用情報制度の整備、金融機関のノウハウの蓄積などが必要となろう。
第三に、アジア・カーに代表されるように、現地の消費を喚起する商品の開発・生産が本格化することが予想されることである。今後見込まれる経済成長の結果、アセアン諸国においては購買力が高まり、消費市場としての潜在的な可能性が一層顕在化しよう。従来、外資系企業の商品は、先進国での販売商品をそのままアジアの地場市場で販売していたケースが多かったと考えられる。しかし、今後は購買力の上昇を背景に、現地仕様の商品の販売が増加してこよう。マレーシアではすでに実現しているが、インドネシアにおいても国民車構想が具体化しつつある。
耐久消費財に関しては、普及率の上昇による消費の伸び悩みも将来的には懸念される。しかし、アセアン諸国では現在の普及率が比較的低いことに加え、現地仕様の商品の増加が予想されるため、中期的には限界消費性向が上昇するものと考えられる。
また、アセアン諸国においては、先進国でも最新商品と考えられている商品が、先進国にさほど遅れることなく販売・消費されることとなろう。例えば、VTRが普及している先進国では、むしろDVDの普及のスピードは緩慢なものかもしれない。これに対し、VTRの普及率が先進国より低い発展途上国では、VTRを購入せずに一気により高価なDVDを購入するケースも考えられよう。
第四に、アセアン諸国においても先進国ほどではないにしろ、人口の高齢化が進展することが予想されることである。国際連合の『世界人口予測 1950→2050』に基づき、95年と2020年の2時点比較で、全人口に占める65歳以上の人口の比率をみてみよう。65歳以上の比率はタイで 5.0%から9.2%、マレーシアで3.9%から7.0%、インドネシアで4.3%から7.0%、フィリピンで3.4%から6.1%に上昇すると見込まれる。ミクロに関する消費のライフ・サイクル仮説(注14)を国民経済全体に適用すれば、高齢者の全人口に占める比率が上昇することにより、国民経済全体でみた貯蓄率は低下し、消費が増加することになる(注15)。
また、今回の分析では資産効果はみられなかったが、アセアン諸国においても徐々にではあるが個人の資産が蓄積されてきており、将来、資産効果による消費の拡大も見込まれよう。
そのほか、労働条件が改善し、労働時間が減少して余暇に充当する時間が増加すると予想されることや、流通・小売業の一層の発展も、消費拡大の要因と考えられる。
以上から考えると、アセアン諸国の消費は今後も拡大すると考えられる。また、特に長期的には上述の4つの理由から、限界消費性向も高まるのではないかと考えられる。したがって、経済成長に関しても、輸出依存の経済成長は続くものの、徐々に消費の寄与率、すなわち内需の寄与率が高まってくると予想される。
おわりに
これまでみてきたように、アセアン諸国の消費市場は順調に拡大してきた。近年においても消費は拡大してはいるが、経済成長の原動力となっているのは従来同様に輸出である。
今後を展望すると、アセアン諸国は経済成長が急激に低下することがないという前提のもと、長期的には限界消費性向も上昇しながら、民間最終消費支出は拡大していくことが予想される。
アセアン諸国において国民所得が増加するに伴い、先進国が経験してきたように大量生産、大量消費の時代から消費者の嗜好が多様化し、消費に関して量から質への変化がみられるのではないかと考えられる。
それによって、アセアン諸国に進出している日系企業のマーケッティングもマス・マーケット戦略から、消費者をセグメント化し、販売する商品を多様化する多品種少量生産に変わるのではないかと予想される。加えて、アセアン諸国の消費の内容も、中間層の拡大により、モノの消費からサービスの消費に移行するのではないかとも考えられる。
最後に、今後の課題として、(1)将来予想される限界消費性向の変化の定量的な検証、(2)交易条件の改善に伴う内需主導経済の本格化の検証、(3)マクロレベルでのより精緻な消費関数の推計などが挙げられる。
注
1.例えば、榊原(1996)では「最早アジアにおいては低収入、低消費は過去のものとなりつつある」と論じている。また、『通商白書』平成8年版は「アセアン4については90年代に入り本格的な大衆消費社会を迎えたといわれる」と論じている。
2.例えば、95年5月1日付け日本経済新聞では「アジアの人口大国のインドネシアやタイなどでは、輸出が経済成長のけん引役なら、中間所得層に引っ張られたおう盛な消費は経済の強力な下支え役。構造転換を進める役割も果たし始めている」としている。
3.『海外投資統計総覧』はアジアの日系企業の現地法人(日本側出資比率10%以上の外国法人<海外子会社>と日本側出資比率50%超の海外子会社が50%超の出資を行っている外国法人)2,597社からアンケートに対する回答を得ている。指定統計ではなく承認統計であるため、回答を強制できず有効サンプル数が限られているというカバレッジの問題はあるが、大まかな傾向をつかむにはさほど問題はないと思われる。
4.ちなみに日本の場合、0.6倍である。
5.恒常所得仮説(permernent income hyopothesis)とは、M.フリードマン(M.Friedman)が唱えたものである。ここでは消費の主要説明変数である実際所得Yが、定期的に収入として入ることが確実に予想される恒常所得Ypと、臨時に得られる変動所得Ytとに分けられる。このとき、消費CについてはC=kYpという関係が成立する。ここで恒常所得からの消費性向kは、消費者の選好が変わらない限り、所得水準とは無関係に一定であると考えられる。上の両辺をYで割ると、C/Y=kYp/Yを得るが、これは現実の消費C/Yが、実際所得に占める恒常所得の割合に比例することを表す。フリードマンの仮説によると、実際所得の中の恒常所得の割合が大きいと消費が増加する、ということになる[高橋・増田、1984]。
6.アジアの中間層の動向に関しては、さくら総合研究所環太平洋研究センター(1995)およびRobinson and Goodman(1996)が詳しい。
7.都市人口比率の増加が中間層の拡大につながると考えることは必ずしも正確ではない。都市人口比率の増加の原因には、周辺の貧しい地域からの人口流入も考えられることも割り引いて考えなければならない。
8.日本経済新聞 95年5月1日
9.日本経済新聞 97年5月26日
10.日本金融新聞 96年10月9日
11.寄与度とともに寄与率も、支出項目別の経済成長率への影響度を測る指標として使われるが、経済成長率がマイナスであった年に関しては、たとえ民間最終消費支出が増加していたとしても民間最終消費支出の寄与率がマイナスとなるため、ここでは、寄与度を使った。
12.この期間で民間最終消費支出の寄与率がマイナスとなったのは、マレーシアの85年(-26.6%)、86年(-413.3%)とフィリピンの91年(-288.3%)であった。したがって、両国においては後半10年に民間最終消費支出の寄与率が低下した点には若干の留意を要する。
13.世界経済とNIEs、アセアンの平均成長率の弾性値を計測した先駆的研究には関・佐々木(1993)がある。
14.F.モディリアーニ(F.Modigliani)等によって提唱されたライフサイクル仮説(life-cycle hypothesis)とは、消費者の所得・消費・貯蓄の関係が生涯の各段階において異なることに着目して構成された理論である。個人は将来の消費に備えるべく貯蓄を増やすため、賃金等の上昇により所得の増加する若年期から壮年期にかけては、所得以下に消費する。老年期に入り、退職等により所得が低下したときに、若年期から壮年期に備えた貯蓄を消費して生活する[高橋・増田、1984]。
15.この場合、高齢化の進展による供給面でのボトルネックは、技術および資本集約的産業の進展、女性および高齢者の雇用促進により解決されるという前提に基づいている。
主要参考文献
1.関志雄、佐々木史子(1993) 「自力成長に転換するアジア経済」(野村総合研究所『財界観測』93年11月号 所収)
2.木村福成(1997) 「海外直接投資と企業活動の国際化」(日本評論社『経済セミナー』97年6月号 所収)
3.国際連合(1996) 『世界人口予測1950→2050』 原書房、1996年
4.小浜裕久、柳原透(1995) 『東アジアの構造調整』 日本貿易振興会、1995年
5.榊原芳雄(1996) 「域内市場の拡大と消費革命~生産し消費するアジアへ~」(日本貿易振興会『ジェトロセンサー』96年11月号 所収)
6.さくら総合研究所 環太平洋研究センター(1995) 『新世紀アジアの産業を読む』 ダイヤモンド社、1995年
7.高橋泰蔵、増田四郎(1984) 『体系 経済学辞典』 東洋経済新報社、1984年
8.通商産業省編(1996) 『平成8年版 通商白書』
9.通商産業省 産業政策局国際企業課(1994) 『海外事業活動基本調査 海外投資統計総覧』 1994年
10.日本経済研究センター(1996) 『経済のグローバル化と地域主義の台頭 - 2020年の世界経済』1996年
11.日本輸出入銀行 海外投資研究所(1997) 「1996年度海外直接投資アンケート調査結果報告」(『海外投資研究所報』97年1月号 所収)
12.速水佑次郎(1995) 『開発経済学』 創文社、1995年
13.原洋之介(1996) 『アジアダイナミズム』 NTT出版、1996年
14.山本拓(1995) 『計量経済学』 新世社、1995年
15.吉田和男(1989) 『マクロからみた日本経済』 日本評論社、1989年
16."The Asia Car: Ready to Rev" in ASIA, INC., March 1997.
17.Euromonitor, Consumer Asia 1995.
18.Richard Robinson and David S.G. Goodman, The New Rich in Asia, Routledge, 1996.

