RIM 環太平洋ビジネス情報 1997年7月号No.38
ベトナムの社会主義市場経済体制における外資政策
選別的外資導入の特徴と「国家資本主義」セクターに関する考察
1997年07月01日 さくら総合研究所 大泉啓一郎
はじめに
ベトナムでは1996年11月、4年ぶりに外国投資法が改正され、97年2月その施行細則が公布された。今回の改正の特色は、従来の改正とは異なり、徹底的な議論が繰り広げられて全面的な改正となったことである。
本稿では、この改正外国投資法およびその細則を中心にみて、近年のベトナム外資政策が外資に何を期待しているのかについて焦点を当てるとともに、党大会で用いられた「国家資本主義」セクターという言葉の意味を考え、ベトナムの外資政策の特徴を明らかにしたい。
1.外国投資法改正の背景
ベトナムは、80年代後半以降、「ドイモイ」のスローガンのもと、経済改革を推進してきた。
ドイモイ当初は、東側諸国からの援助削減を始めとする国際環境の悪化もあって、インフレの高進、自国通貨の減価など、経済は危機的な状況にあったが、90年代に入ると経済改革の効果が表れ、インフレは抑制され、為替レートも安定的な動きをみせるようになった。
また、92年以降は実質経済成長率も8%を上回るようになり、経済はあたかも高度成長期に入ったかの印象を与えている。
このような好調な経済パフォーマンスを受けて、経済政策もドイモイ当初とは質的に大きく変化しており、単純に市場経済化・対外開放政策であると規定することはできなくなっている。
例えば、市場経済化については、計画経済への逆戻りは考えにくいものの、「国家主導の市場経済メカニズム」と命名されたベトナム独自のメカニズムの下で推進されているし、経済政策の焦点は、経済の安定重視から、94年4月開催の共産党中央委員会以降は、「工業化・近代化」のスローガンに象徴されるように経済の加速を重視する方向へ変わってきている。
また、この「工業化・近代化」は、同時に近隣諸国へのキャッチアップを目標として、国際競争力の強化を意図しているものでもあることはいうまでもない。
96年7月に開催された第8回党大会では「工業化・近代化を通じて、2020年にはGDPを90年水準の8~10倍の水準にまで高め、工業国の仲間入りを果たす」という野心的ともいえる経済目標を発表した。この目標を達成するためには、年平均8%程度の成長を25年(四半世紀)間、維持しなければならない。
このような経済政策の変化は、当然のことながら外資政策にも反映している。ドイモイ当初は、ともかく外資を導入し、経済危機から脱出を図ろうとする無差別的外資導入政策を基本としていたが、92年以降は、国家計画に沿うように外資を選別的に導入しようとの姿勢が強まっている。(注1)
たしかに、ベトナム政府は、外資がベトナムの経済開発に不可欠な存在であり、今後も重要なことは認識しつつも、その一方で「外資といえども国家が管理すべき」との官僚の発言が頻繁になされるようになったり、第8回党大会では国営企業と外資企業の合弁企業が民間セクターとしてではなく、「国家資本主義(shunghia tu ban nha nucc)」セクターとしてとらえられるようになるなど、外資政策に新しい動きがみられる。
2.外資導入の現状と外国投資法改正の変遷
まず、これまでの外資導入の現状を確認しておこう。
図1は、88年以降の外資の受け入れ件数および総額(いずれも認可ベース)の推移をみたものである。受け入れ額は、87年12月に外国投資法が制定されて以来、現在まで一貫した増加を続け、96年には86億米ドルの水準に達した。
投資国・地域別では、投資法制定当初はベトナム国内に特別な人脈を持つ台湾、香港からの投資が圧倒的に多かったが、90年代に入ると、シンガポール、日本、韓国、米国などがベトナム投資に本格的に参入、世界的な「ベトナム投資ブーム」が起きた。投資分野は、石油開発、ホテル・観光から、現在では建設資材、家電、自動車組み立てなど、多岐にわたるようになった。投資額も大規模化し、1件当たりの平均投資額は88年の990万ドルから96年には2,560万ドルに拡大した。
88年から96年末までに、投資受け入れは累計で1,633件、総額は284億ドルとなった。もちろん、認可された投資がすべて実行に移されたわけではなく、実行ベースでは約80億ドルと、全認可額の30%程度と低水準にとどまっている。しかし80億ドルといえど、同期間の国家基本建設投資額が30 億~40億ドルであったことを勘案すると、ベトナム経済に与えた影響が大きかったことは明らかである。
外国投資法は87年に制定されて以来、今回の改正を含め3回改正された。1回目の改正は90年で、複数の出資者による合弁企業設立の承認、輸入代替産業の優遇などが盛り込まれた。2回目は92年の改正で、事業期間の延長、海外からの資金借入の承認などが新たに加えられた。
今回の改正は3回目にあたり、内容としては、国内の行政改革にあわせた行政手続きの簡素化が進められ、審査期間の短縮化(90日から60日へ)、投資認可書と営業登録書の一本化など、これまでの煩雑な手続きにメスが入れられた。また、地方分権化の一環として、投資認可権限の一部を特定地方に移譲することが明記されたことも特徴的であった。(注2)
3.選別的外資政策の強化
それでは、本題であるベトナムの外資政策がどのような分野に外資を導入しようとしているのかについてみることとしたい。
具体的な投資奨励分野および地域については、「投資奨励地域リスト」「投資奨励分野リスト」「条件付き投資分野リスト」「投資を認可しない分野のリスト」として随時発表される(外国投資法細則第3条)が、大まかな奨励分野・地域については、投資法の第6条、および投資法細則の第54条から推測することができる。
今回の改正で明確となった選別の動きは、(1)地域間経済格差の是正、(2)基幹産業の育成、(3)公共部門への投資の奨励と、(4)奨励しない投資への優遇措置の縮小・廃止に大別できる。以下に、それぞれについてその背景を明らかにするとともに具体的にみてみよう。
(1) 地域間経済格差の是正に貢献する外資を優遇
外国投資法における投資奨励分野に関する記述が、制定以来初めて書き直された。図2は、従前の奨励分野と改正法に記載された奨励分野を比較したものであるが、カテゴリーが分野と地域の2区分となり、地域が重視されるようになった。
図2 奨励分野の変化
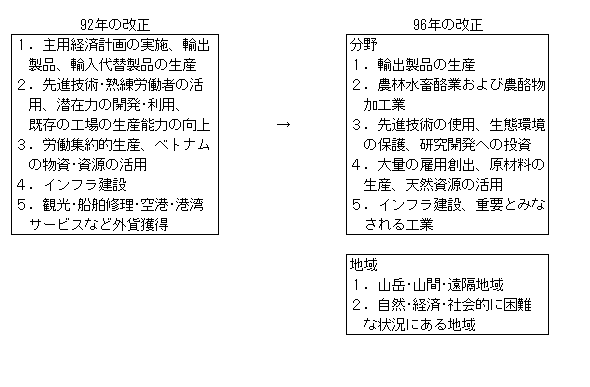
具体的には、山岳・山間・遠隔地域、および自然・経済・社会的に困難な状況にある地域への投資が奨励されることが明記された。このほか、山岳地域の場合、最低出資比率を特別に20%まで引き下げる(一般は30%)こと、土地のリースに関して有利な条件を設定することなどが定められた。
これは、90年代に高い経済成長を達成した一方で、地方間の経済格差が拡大し、開発の遅れた地域からの不満が高まったことへの配慮とみることができる。一人当たりGDPでみると、最も高いホーチミン市と最も低いハジャン省の間では、10倍もの格差が存在している(94年実績値)。
このため、ベトナムでは、従来から地方政府の権限が強い上に、社会主義体制の基本として経済格差の是正は常に中心的命題であったことから、極度に開発の遅れた地域に対する投資が、財政配分を含め優先される傾向にある。
また、今回の改正にあたり、農林水産業への投資が奨励されるようになったのも同様の理由からである。
(2) 基幹産業に対する外資を優遇
前述のように、近年の経済政策は「工業化・近代化」をてことした経済成長の加速を目論んでおり、そのための資金・技術を外資から導入したいとしている。この「工業化・近代化」と外資導入の関係については、外国投資法の前文でも、「国家基盤となる近代化、工業化を進めるため」と明記されている。投資法の第3条では、重要とみなされる工業・製造業を奨励することが明記されている。
では、具体的にはどのような産業を指すのだろうか。表1では、冶金、基礎科学、製造機械、石油化学、肥料、電気部品、自動車部品などが列挙されている。これは重工業であると同時に原材料関連の産業といえ、ベトナムはこのような基幹産業の育成に外資を用いようとしていることがわかる。
表1 利潤税率の適用基準にみる優遇分野
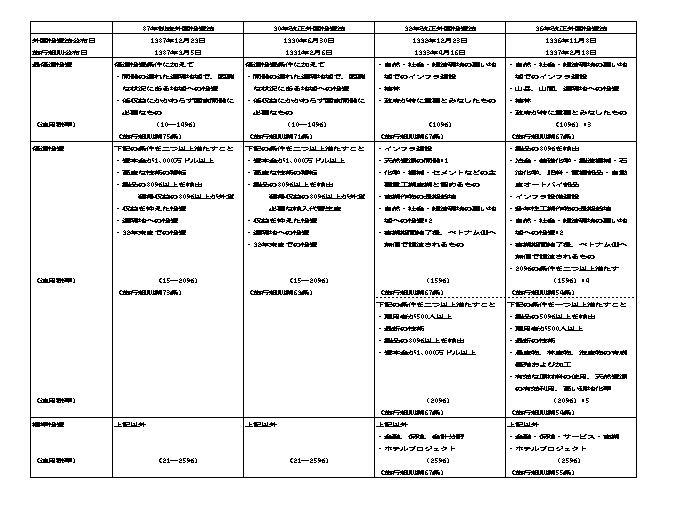
(注)
1.石油・ガス開発および希少鉱物資源開発を除く。
2.ゴム、ジュートなど、製品の原材料となる作物
3.ホテルプロジェクトを含み、希少鉱物資源開発を除く。
4.適用期間は15年間
5.適用期間は12年間
6.適用期間は10年間
(資料)各外国投資法、施行細則よりさくら総合研究所作成
注目すべき点としては今回、部品産業が新しく明記されたこと、また逆に、基幹産業であっても外資の進出が顕著だったセメントが対象から外されたことが挙げられる。このような基幹産業は重要な産業であり、後述する現地の出資比率引上げの対象となることが予想され、100%外資の進出は難しい。
(3) 公共部門への外資導入
ベトナム政府の外資に対する期待は、上述の基幹産業だけでなく公共部門を含め広範囲にわたっている。96~2000年までの5年間に必要な投資総資金(約 400億ドル)の4割に当たる160億ドルを、外国からの直接投資に依存するという計画からも明らかなように、本来は国家財政が負担すべき公共部門への外国投資を認め、その傾向は今回の改正でより明確となった。
代表的な例は、インフラ整備に対する外資の導入である。インフラ整備に対する投資は、優遇措置を受けられるだけでなく(開発の遅れた地域では、より一層の優遇措置)、92年の改正で正式に認められたBOT方式(建設・運営・譲渡)に加え、今回BTO(建設・譲渡・運営)、あるいはBT方式(建設・譲渡)が認められた(外国投資法第2条12、13項)。また、外資企業にメリットの少ないBT方式によるインフラ投資については、その他の投資分野において便宜を図るという特別措置も設定された(外国投資法第2条13項)。
この公共部門に対する外資を導入しようとする姿勢は、インフラ整備にとどまらず、学校や病院、研究機関への投資に対しても積極的に受け入れていくことが明記されたことは注目される。(注3)
(4) 一般投資に対する優遇措置の縮小・廃止
上述のように、地域間経済格差の是正、基幹産業の育成、公共部門への投資が奨励される一方で、特に奨励されない一般投資に対しては、優遇措置の縮小・廃止の動きがみられたのも、今回の改正の特徴である。
表2は、各投資に対する利益税の減免期間および再投資の還付率をみたものである。特に奨励されない分野への投資(一般投資)については、92年の改正法では利益税の1年間の免除と2年間の減税がインセンティブとして講じられていたが、今回の改正で減免措置が廃止された。また、再投資分の利益税の還付についても受けられないこととなった(細則第54条)。
このような税制面での優遇措置の縮小・廃止は、財源基盤を強化する目的に加えて、国内産業の保護を目的とするものと考えられる。
実際、近年、国内産業の保護を意図した政策が採られるケースが多くなっている。国内において鉄鋼、セメント、製紙などの在庫がかさむような状況になると、政府は一時的な同製品の輸入禁止措置を講じることが多く、現地の小規模企業が存在する産業においては「過当競争」を理由に、外資の進出を制限する動きも出ている。例えば、タクシーやホテル、清涼飲料水、繊維・靴加工産業などへの外資制限がある。今回の改正において、商業分野が利益税の優遇の対象から外れたのも、同じ趣旨と考えられる。
今回の改正を通じて、選別的外資導入の動きはより明確になった。その中には、国内産業の保護を意図した制限もみられ、「対外開放」とは逆行しているとみることも可能である。このような輸入代替政策は、東アジア一般に採られてきた政策ともいえるが、AFTAに加盟することをすでに宣言したベトナムにとって、正当な行動といえるだろうか。
4.「国家資本主義」を掲げた外資政策
3では、選別的外資導入の目的や意図などを明らかにしたが、それだけではベトナムの外資政策をみるうえでは不十分と考えられる。国家計画に沿った選別的外資導入や国内産業の保護は、他の発展途上国でもみられる政策であり、必ずしもベトナム特有のものとはいえないからである。そして、何よりも、第8回党大会で合弁企業を「国家資本主義」セクターとしてとらえた意図を解く鍵にはならないからである。
ここでは、「国家資本主義」セクターをキーワードとして、ベトナムの外資政策を考えてみたい。第8回党大会の政治報告によれば、「国家資本主義」セクターとは、国営セクターと国内外の民間セクターとの合弁事業、協力事業を指す。
しかし、外国投資の8割以上が国営企業との合弁企業であること、国営セクターとベトナムの民間企業の合弁が少ない現状を考えると、「国家資本主義」セクターという名称は、外資との合弁事業に冠されたといっても過言ではなかろう。
「国家資本主義」セクターを考える上で、ベトナム政府が目指すマクロ経済コントロールのスローガンとなっている「国家が主導する市場経済メカニズム」を手がかりとしたい。このメカニズムとは、従来の計画経済のような政府の直接的な経済への関与を否定しつつも、市場への政府の間接的な関与は認める枠組みとみなすことができる。例えば、貸し出し上限金利内での金利決定の自由、国営企業における人事権の行使による統制などがそれに当たる。(注4)
これと同様に「国家資本主義」セクターを考えると、政府が合弁企業の意志決定に直接関与しないものの、合法的な経路を通じて合弁企業の活動に関与するととらえることができる。もちろん、合弁企業の国有化はおよび経営に関する直接的な関与は、当然のことながら禁止されている(外国投資法第21条、細則第46 条)。
ここではその一例として、ベトナム側パートナーである国営企業の意見が、合弁企業の最高意思決定において、どの程度反映するものかについてみてみたい。(注5)
(1) 経営管理評議会の全会一致原則
合弁企業の最高意志決定組織は、経営管理評議会(Hoi Dong Quan Tri)(注6) である。経営重要事項については全会一致で、それ以外の一般事項については過半数(従来は3分の2)によって決定される。
まず、経営重要事項についての経営管理評議会の全会一致原則に着目したい。ここでいう経営重要項目とは、社長、副社長、経理部長の任命・解任、企業定款の改訂、年次財務報告の承認、投資資本の借り入れである(外国投資法第14条)。
この全会一致原則は、制定当初から問題視されながらも、今回も改正されることはなかった。これは、多くの場合にマイノリティーとならざるを得ないベトナム側の発言権を守ったものと考えられる。(注7)そして事実上、合弁企業の現地側パートナーのほとんどが国営企業であることを考えると、親会社である国営企業やその管轄省庁、あるいは地方政府の意思が反映するシステムともみなされよう。
今回の改正では、合弁会社が子会社として設立した合弁会社(以下、新合弁会社と呼ぶ)にも、このシステムが拡張された。具体的には、新合弁企業の経営管理評議会の役員として、親会社から役員を最低2人を送り込むが、その際1人はベトナム側パートナーとすることが義務づけられたのである(外国投資法細則第 21条3項)。これにより、親会社が国営企業である場合、孫会社、曾孫会社に至るまで国営企業から管理評議会メンバーを派遣することができ、全会一致原則を通じて経営に対する意志の反映できるシステムが構築された。
(2) 現地側出資比率の引き上げ義務と経営管理評議会の一般事項の決定
全会一致の原則はあるものの、一般事項については過半数の賛成によって決定される。よってマジョリティーの確保は、依然重要な問題である。これに対して、 92年の改正により、政府が重要とみなす産業については、合弁企業はもちろんのこと、100%外資であっても、一定期間後に現地側出資比率を引き上げることを義務づけられている(これは、100%外資企業に対する「国家資本主義」セクターヘの移行措置といえる)。
それでは、ベトナム政府が重要とみなす分野とは何であるか。外国投資法および施行細則に具体的な記述はないが、外国投資法細則草案では石油・ガス、電力、機械、インフラ整備、セメント、ホテルが挙げられており、これは前述の奨励すべき投資分野と一致している。現地側出資比率引き上げ義務と併せて考えると、今回、一般事項の決定を従来の3分の2から過半数としたことは、現地側出資比率の引き上げを早め、早い段階でベトナム側に意思決定権が移行できるようにしたシステムともいえよう。
現地側出資比率の引き上げを資本譲渡によって行う場合、合弁におけるベトナム側パートナーを優先することは従来と変わりがないが、譲渡の際に得られる利益に課せられる資本譲渡税は、一般には25%であるのに対し、ベトナム側パートナーの場合には10%、国営企業の場合は免税とする(細則第64条)との優遇措置が盛り込まれた。これも「国家資本主義」セクターへの移行措置と考えることができる。
5.「国家資本主義」セクターは国営セクターか、民間セクターか
4では、「国家資本主義」に対する私見を述べてきたが、最後にこの「国家資本主義」セクターが今後、どのように変化するかについてみてみたい。
最大の関心は、「国家資本主義」セクターは国営セクター的性格なのか、それとも実際は民間セクター的性格が強いのかということである。
統計上では、国営企業との合弁企業は、長らく国営企業としてカウントされてきた。党大会で発表された政治報告の草案で、2020年の国営企業のシェアを現在の40%から60%に引き上げるとしたのは、おそらく国営企業との合弁企業をも、国営セクターとしてカウントしているからであろう。ここから読み取れるメッセージとして、ベトナム政府が「経済の牽引力は国営セクター」と主張する限り、国家資本主義セクターは国営セクターに近い存在とみなされていることといえよう。
「国家資本主義」セクターに対する国家のかかわりおよび国営企業と「国家資本主義」セクター企業との関係は、今後どのように展開していくのだろうか。
現在、国営企業改革が進められているが、95年に公布された「国営企業法」では、国営企業の定義を「国家がシェアの半分を占める企業」としている。では、例えば国家が51%を占める国営企業と、国家が70%を占める「国家資本主義」セクター企業では、どちらが純粋の国営企業に近いのであろうか。それとも、国家のシェアが過半数を超える「国家資本主義」セクター企業は、国営企業法の適用を受けるのであろうか。
さらに細かくみて、国営企業のグループ(総公司)に属する合弁企業の経営の扱いはどうなるのであろうか。総公司の定款では、総公司のメンバーは物価高騰時に国内価格の安定に寄与することが義務づけられているが、それは合弁企業にも適用されるのか。今後、特に基幹産業を中心に、合弁企業に対するベトナム側の要求が、どのように具体化されるかには留意しなければならない。
おわりに
これまで、改正外国投資法における選別的導入の特徴を明らかにし、さらに「国家資本主義」セクターに対する私見を述べてきた。
これらの外資政策の変化が外資導入にどのような影響を与えるか、結果はまだ出ていない。また、「国家資本主義」セクターについても、正式な定義は与えられていない。
しかし、市場経済化には「国家が主導する市場経済メカニズム」が、「対外開放政策」には「国家資本主義」なるベトナム独自の路線が示され、ベトナムの経済政策は、いまや単純に市場経済化、対外開放を目指す政策とはとらえられない性質への質的変化を遂げているということに注意を払う必要があろう。
注
1. 92年の外国投資法改正の評価については、拙稿「転換するベトナムの経済政策」(『RIM』31号、1995年、p.38~47)を参照。
2. 97年6月、ハノイ市、ハイフォン市、ホーチミン市、ダナン市、ビンズン省、ドンナイ省、バリアブンタウ省、クアンニン省に移譲された。
3. トラン・ホン・クァン教育大臣は、外国資本による職業訓練校、大学(特に自然科学)およびその分校の開設を認める方針を発表した。
4. 「国家の主導する市場経済メカニズム」下における国営企業の管理については、竹内郁雄「規制された市場メカニズム」(五島文雄・竹内郁雄編『社会主義ベトナムとドイモイ』アジア経済研究所、1994年、p.65~151)が詳しい。
5. そのほか、外資企業にも共産党の組織を設置すること、全国労働同盟に属する労働組合を設置することで関与することもある。これについては、渡辺英緒「国家資本主義経済形態と合弁企業」(白石昌也・竹内郁雄編『ベトナム共産党第8回大会とドイモイの現段階』アジア経済研究所、1996年、p.65~84)が詳しい。
6. 経営管理評議会は株主総会と取締役会の機能を併せ持つ。
7. 合弁における平均出資比率は、外資:地場=7:3。

