RIM 環太平洋ビジネス情報 1997年1月号No.36
アジア諸国の経済成長率と経済発展の相対評価
1997年01月01日 さくら総合研究所 環太平洋研究センター 坂東俊輔
要旨
本稿は、高い経済成長率を持続しているアジア諸国(韓国、台湾、香港、シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、中国、インド)の「経済成長率」(量的変化:経済規模拡大のテンポ)と「経済発展の度合い」(質的変化:経済水準や国民生活の充実度)を定量的に相対比較しようとするものである。
具体的には、まず過去20年間にわたるアジア諸国の実質経済成長率を統計的に分析した。
次いで、国民の経済的な豊かさ、工業化・国際化水準の度合い、国民生活の充実度といった視点から、アジア諸国の「経済発展の度合い」を相対評価した。
その結果、以下のような3点が観察された。
1. 過去20年間のアジア諸国の実質経済成長率は非常に高いものの、その安定性の指標となる変動係数(=標準偏差/平均)を見ると、ばらつきが大きく、成長率の変動が一様でなかったことがうかがわれる。
20年間のうち、後半10年間(1986~95年)の変動係数は、前半10年間(76~85年)より低く、後半の10年間の経済成長率が比較的安定していたことを示している。
また、アジア諸国の中では、インドネシアの変動係数が低く、成長率が相対的に安定していたと考えられる。
2. アジア諸国の実質経済成長率の相関関係をみると、後半10年間の方が前半10年間よりも相関関係が高まっており、アジア諸国間の雁行型発展の広がりや相互依存関係が深まっていることを示している。
3. 「経済発展の度合い」を測る指標としては、一人当たりGDPが比較的よく用いられている。
「経済発展の度合い」を国別に比較するために行った、国民の経済的豊かさ、工業化・国際化水準の度合い、国民生活の充実度についての簡単な主成分分析によれば、一人当たりGDPの順位と比較して、中国が国民の経済的豊かさで、またマレーシアが工業化・国際化水準の度合いで、より上位に位置するなど、一人当たりGDPの順位とは異なる結果が得られた。
はじめに
この10年間、アジア諸国の実質経済成長率[実質国内総生産(GDP)成長率、以下、経済成長率]は非常に高いものであった。今後も、当分の間は高水準の経済成長が続くとの見通しから、21世紀は「アジアの世紀」になるともいわれている。
しかし、「経済発展の度合い」(質的変化:経済水準や国民生活の充実度)を評価するには、「経済成長率」(量的変化:経済規模拡大のテンポ)ではなく、国民の経済的豊かさ、工業化・国際化水準の度合い、国民生活の充実度などを考慮する必要がある。
以下では、第一に、1976~95年の20年間にわたるアジア諸国の経済成長率を概観し、また、各国ごとに経済成長の要因などを振り返る。
第二に、貿易や投資を通じたアジア諸国間の経済関係の緊密化を考慮して、アジア諸国の経済成長率の相関関係を分析する。
第三に、経済成長率以外の様々な経済・社会指標を用いて簡単な主成分分析を行い、アジア諸国の「経済発展の度合い」を測定し、各国を相対的に比較する。
分析対象は韓国、台湾、香港、シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、中国、インドの10ヵ国・地域とし、本誌に掲載されている経済予測対象国のうち、ベトナムを除外している。
その理由は、統計の定義などが他の諸国と異なるケースが多々あること、ドイモイ(刷新)政策が86年に導入され、市場経済化が進展したのがこの10年のことであるため、統計のアベイラビリティの問題があること、の2点である。
I.アジア諸国の経済成長率
1.過去20年間の経済成長率概観(注1)
(1) 分析対象データと分析の方法
現在のところ、経済成長率が経済指標として最も頻繁に使用されている。経済成長率とは、そらぞれの国の経済主体の経済活動が生み出した付加価値の総和[=国内総生産(GDP)]の増加率のことである。
経済成長率が意味する経済的なパイ(国内総生産)の拡大は、そのパイが最終的には国民に分配されることから、極めて重要なものである。
以下では、過去20年間を10年ずつ2期間に区切り、各国ごとに経済成長率の単純平均により、長期的な経済規模拡大のペースを評価する。
ただし、いくら経済成長率が高くても、成長率が乱高下していては健全な経済とはいえない。一般的に経済成長率は、前年の急激な物価上昇への対応策として実施された過度の引き締め政策、あるいは一次産品価格など主要輸出産品価格の低迷などといった外的なショックによって大きく変動するケースがある。だから、経済成長率の高さに加え、経済成長率の安定性も考慮する必要がある。
経済成長率の安定性(振幅の度合い)を表す指標としては、標準偏差が使われることがある。標準偏差は、データの平均から散らばり度合いを示す指標としては有用であるが、平均値の絶対値を考慮していない。
そこで、変動係数(=標準偏差/平均値)を計算することにより、各国の安定性を比較する。変動係数が高いことは、その国の経済成長が不安定であったことを意味する。
(2) 前半10年間(76~85年)の動向
まず、76~85年の前半10年間のアジア諸国の経済成長率の動向を見てみよう(表1)。
表1 アジア諸国の実質経済成長率(1976~85年)
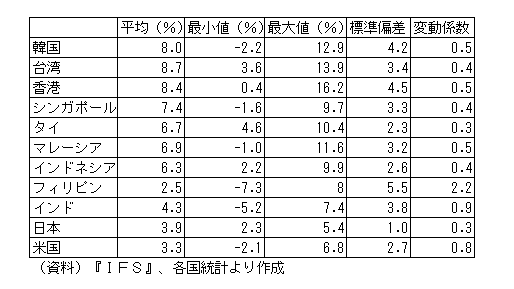
NIEs(注2)全体の平均成長率(単純平均、以下同様)は76~85年の10年間で8.1%と、非常に高いものであった。なかでも台湾が8.7%、香港が8.4%、韓国も8.0%と際立っている。韓国は、80年には経済成長率がマイナスになったにもかかわらず、平均で8%の成長率となっている。
経済成長率の変動係数についてみると、韓国と香港がともに0.5と、高いものとなっている。これは、韓国においては朴大統領の暗殺や光州事件などにみられる政情不安、香港においては中国情勢などを反映した経済成長率の変動と考えることができよう。
アセアンの平均成長率は、NIEsよりもかなり低い5.6%である。しかしながら、この中には、平均成長率が2.5%と極めて低いフィリピンの数字が含まれている。フィリピンを除いたタイ、マレーシア、インドネシア3ヵ国の平均は、6.6%である、
マルコス政権からコラソン・アキノ政権への政権移行時の政情不安を背景にしたフィリピン経済の低成長が、アセアン諸国全体の足を引っ張ったといえよう。
変動係数を見ると、政情不安が続いたフィリピンが2.2と、極めて不安定な経済であった。ベニグノ・アキノ氏暗殺とその結果生じた外資の引き揚げを主因に、84年、85年と2年連続して-7.3%のマイナス成長を記録したことがフィリピンの平均成長率を引き下げ、変動係数を高めた大きな要因である。
また、マレーシアの変動係数が0.5と、フィリピンに次いで大きいものとなっている。これは、80年代前半まで錫、ゴム、パームオイルなど主要一次産品の輸出が総輸出の50%以上を占めるなど、一次産品輸出に依存した経済構造となっていたマレーシア経済が、85年の一次産品不況の影響を受け、同年の経済成長率がマイナスとなったことが大きく響いている。
(3) 後半10年間(86~95年)の動向
86~95年までの10年間を見てみると、NIEsの平均成長率は7.9%と、前半10年間と比較して若干低下したものの、ほぼ同水準を維持している(表2、図1)。この結果、NIEsは過去20年間にわたり、平均8%近い経済成長率を維持してきたのである。
表2 アジア諸国の実質経済成長率(1986~95年)
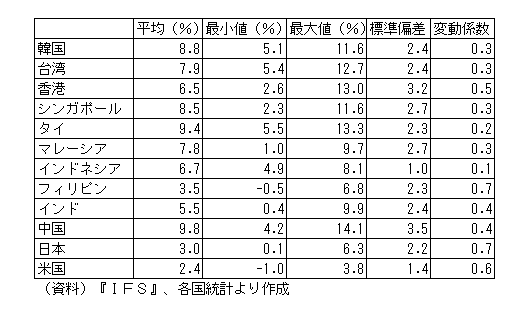
個別に後半10年間の平均成長率を見ると、韓国が8.8%、シンガポールが8.5%と、9%近い数字を達成している。台湾も7.9%と、NIEs平均の成長率と同じ水準となっている。
唯一香港のみが6.5%と、他の国と比べて成長率が低い。これは、中国で発生した天安門事件の影響で、89年の成長率が2.6%にとどまったことが大きく影響している。
一方、シンガポールは、85年のマイナス成長に加え、翌86年も2.3%という低成長を記録したにもかかわらず、10年間平均で8.5%の経済成長率を実現したことが注目されよう。
変動係数を見ると、0.4と比較的高かった中国との経済的な結び付きが強化されるに従って、中国の政治・経済動向の影響を受ける度合いが一層強まった香港が0.5と最も高かった。韓国、台湾、シンガポールは0.3であった。
アセアンを見ると、全体の平均成長率は6.8%と、前半10年間の平均成長率を上回っている(表2、図1)。すべての国の経済成長率が前半10年間の実績を上回っており、アセアンが総じて順調な経済成長を遂げていたと結論づけられよう。
個別に見ると、タイ、マレーシアがそれぞれ9.4%、7.8%と高い成長率を遂げ、インドネシアも6%を越えている。前半10年間同様、フィリピンの平均成長率が3.5%とアセアンの中で最低で、アセアン全体の平均成長率を引き下げている。
また、特にタイ、マレーシア両国においては、85年のプラザ合意以降の円高を契機に、日本からの直接投資が経済成長に大きく寄与したともいわれている(注3)。
変動係数を見ると、インドネシアでは0.1と、極めて低いものとなっている。この期間に、インドネシアでは石油・天然ガスを中心とした一次産品輸出に依存する経済構造から、繊維や合板など製造業を中心とした輸出構造への転換が進んだことに伴い、安定的かつ高い経済成長率を維持している。スハルト大統領の長期政権による政治的安定が経済的安定に結び付いたともみることができよう。
また、タイの変動係数も0.2と、NIEsのいずれよりも安定した数字となっている。
フィリピンでは、最高の成長率6.8%に対し、最低の成長率が-0.5%と変動幅が大きいことを反映して、変動係数はアセアンの中では最も大きくなっている。
これ以外では、中国の平均成長率が9.8%と、二桁近くに達していることが注目される。
また、インドも前半10年を上回る経済成長を続けている。
このように、アジア諸国が総じて80年代後半以降、高成長を遂げた要因としては、
1. 85年9月のプラザ合意による円高とその継続により、アジア諸国製品の国際競争力が向上したこと、
2. 日本を中心とした海外からの資金・技術を有効に活用すべく各国で進められた外資規制緩和や金融・資本市場の整備が進展し、外資が流入したこと、
3. 一次産品依存経済から脱却して工業化を図る過程で、原油などの原料価格が低位安定傾向にあったこと、
4. アジア諸国製品の主要な輸出先である米国を中心に、先進諸国で順調に景気拡大が続いたこと、
などが挙げられよう。
また、この20年間の大きな特徴は、NIEs、アセアンとも、変動係数が前半10年間と比較して後半10年間に低下していることである。
世界経済が比較的安定的に推移したことも一因ではあるが、アジア諸国がこの10年間に自国経済を取り巻く外的なショックに対して、総じて政策面でうまく対応してきたとも評価することができよう。
2.相関係数による分析
(1) 過去20年間(76~95年)の動向
近年、アジア各国間では、経済的な結び付きの強化を通じた相互依存関係が強まっている。
アジア各国間の経済的リンケージが緊密化すれば、各国の経済成長率の動きは連動したものになると考えられる。
そこで、過去20年間について、各国の経済成長率間の相関係数マトリックスを作り、その動向を見てみよう(表3)。二国間の経済成長率の相関係数が1に近ければ、その理由の一つとして、両国が非常に強い経済的結び付きを持っていることが考えられる(注4)。
表3を見ると、台湾と香港、シンガポールとマレーシアで相関係数がそれぞれ0.79、0.80と高い値を示している。台湾は、中国との直接的な貿易取引ができないため、香港経由で中国と取引を行っている。シンガポールは、主に自国内の労働コスト上昇に対処する目的で、隣接するマレーシアを中心に積極的に生産拠点を移転している。
このように、台湾と香港、シンガポールとマレーシアの間の経済関係は、輸出入や直接投資などを通じて極めて緊密なものである。その結果、経済成長率の間に極めて高い相関関係が表れていると考えることができよう。
また、インドについては、他のアジア諸国と異なり。他国の経済成長率との相関係数がマイナスであるケースが多い。プラスの場合でも、その絶対値は小さいものとなっている。
これは、インドでは47年の独立以降、重工業を中心に国内産業の保護・育成を進めてきたため、貿易・投資などを通じたアジア諸国との経済関係が希薄であったことが影響していると考えられる。
(2) 後半10年間(86~95年)の動向
アジア諸国が目覚ましい経済成長を遂げ、しかもアジア諸国間での直接投資や間接投資を通じた資本移動も活発化してきた86~95年の10年間の相関係数を示したのが表4である。
韓国と香港(0.60)、台湾と香港(0.85)、シンガポールとタイ(0.75)、シンガポールとマレーシア(0.75)、タイとマレーシア(0.63)、マレーシアとインドネシア(0.63)などの間で高い相関関係がみられる。
また、91年のラオ政権成立以降、ドラスティックな経済自由化・規制緩和に着手しているインドにおいても、他のアジア諸国の経済成長率との相関関係は高まりつつある。
このように、最近10年間の相関係数は、アジア経済の間のリンケージが高まったことを示している。
ただし、相関関係が高まるということは、相関関係の高い国同士が同時に好不況を経験することも意味しており、アジア全体の経済成長がいっせいに停滞する危険性も高まっているといえる。
今までのところ、アジア諸国間の経済的なリンケージは、EU成立を契機に資本自由化にまで経済的な統合が進展している欧州諸国と比較すると、商品貿易、つまりモノの流れがその中心となっている。
しかし現在、NIEsからアセアンに向けての直接貿易が急増しており、今後モノの流れに加え、カネの流れも緊密化すると考えられる。APEC、AFTA、WTOといった多国間協議の中で、貿易・資本移動に関する規制緩和・自由化が進展し、アジア諸国の経済的なリンケージは近い将来、ますます強固なものになることが予想される。
その結果、アジア諸国の経済成長率の連動性(相関関係)が一層高まろう。このことは、現在高い成長を維持しているアジア諸国の経済成長率がいっせいに鈍化する、いわゆる共倒れの危険も一層高まっていることを意味している。
たとえば、本誌の前半で述べられているように、96年のアジア各国の経済成長率(落ち着き見込み)はフィリピンを除き、エレクトロニクス関連商品の輸出の伸びなどを理由に、総じて95年の成長率よりも鈍化している。
II.主成分分析によるアジア諸国の「経済発展の度合い」(質的変化:経済水準や国民生活の充実度)の相対比較
1.経済発展を測るための指標
「経済成長率」(量的変化:経済規模拡大のテンポ)は経済の一面をとらえているに過ぎず、「経済発展」(質的変化:経済水準や国民生活の充実度)を測るものではない。しかも、経済成長は必ずしも国民生活の向上を意味していない。
ここでは、経済成長と経済発展の意味の違いについて考えてみたい(注5)。
通常、経済成長とは、経済産出量の全体的な(あるいは一人当たりの)増加と考えられる。しかし、経済発展という概念は、経済学においてさえ必ずしも明確に定義されているとはいえないのが現状である。
具体的に経済成長と経済発展について定義した経済学者をみると、キンドゥルバーガーはその『経済発展論』の中で、「経済成長という言葉が、産出量の増加を意味するのに対して、経済発展というのは、その他に、技術的・制度的な生産方法の変化をも併せて意味する言葉である」と述べ、経済発展とは産出量の増加にとどまらず、投入量の増加、効率の向上、生産物構成と生産要素の部門別配分の変化と関連しているとする。
また、フランソワ・ペルーは『20世紀の経済』において、経済成長を、一定期間における一経済次元指数の増加であると定義し、これに対して経済発展を「住民に自らの総実質生産物を、累積的かつ継続的に成長させる適性を与えるような精神的・社会的変化の結合」と定義している。
これらの見解は、成長をとりわけ経済の量的変化ととらえ、発展を質的変化と結び付けて考えるものである。国連も、62年に発表した「開発の10年」に関する事務総長報告で、発展を「成長プラス社会的・文化的経済的総体」と定義している。
このように経済成長と経済発展は同一のものとはいえない。高い経済成長率は、経済発展の必要条件ではあるが、十分条件ではないのである。
例えば、国連開発計画(UNDP)は『人間開発白書』の90年版において、(1)出生時平均余命、(2)成人識字率、(3)購買力平価による一人当たり実質GDPの対数値、の三つの指標から成る人間開発指標(HDI:Human Development Index)を作成している。その中で同書は、HDIによって世界各国の順位づけを行い、GNPの順位づけとHDIの順位づけが大きく異なることを示している。
したがって、アジア諸国の「経済発展の度合い」の評価は、「経済成長率」以外の様々なマクロ経済指標や社会・文化指標をも組み合わせたものでなくてはならないと考えられよう。
2.主成分分析とは
前述のように、経済発展は経済のみならず社会発展などを含めた多元的なものである。
現在までのところ、アジア諸国の経済発展を完全に説明する経済発展理論やマクロ・モデルは確立していない。理論やモデルが明確であれば、それを実証できるデータ・統計の選択は比較的容易である。
理論やモデルがない現状においては、経済発展という概念に関係がありそうだと考えるデータを可能な範囲で集め、分析する以外に方法はない。
さらに、このようにして集めたデータを整理し、十分な説明力を持った情報(特性)に収斂する必要がある。
そこで用いられる方法が、多変量解析手法の一つである主成分分析である。
多変量解析とは、そもそも多種類のデータ(多次元データ)を分析するための統計的手法である。なかでも、主成分分析の目的は「いくつかの要因を総合化すること」にある。数学的には、主成分分析とは、新しい座標軸(主成分)を見つけ、その座標軸の特徴(総合的特性)を読み取ることである(注6)。
このように主成分分析は、何種類かのデータを、より数の少ない特性に総合する手法であり、また主成分スコアを計算することにより、サンプルの順位づけをすることができる。
3.アジア諸国への主成分分析の適用
以下では、NIEsおよびアセアンに中国、インドを加えた10ヵ国・地域を対象に、「経済発展の度合い」(質的変化:経済水準や国民生活の充実度)を国別に比較する目的で、多様なマクロ経済指標および社会に関する指標を主成分分析により統合しようと試みた。
具体的には、(1)国民の経済的豊かさ、(2)工業化・国際化水準の度合い、(3)国民生活の充実度、といった特性のそれぞれについて、互いに相関関係の高いデータを集め、主成分分析を実施した。
また、一人当たりGDPが経済発展の度合いを測る指標として使われることが多いことから、一人当たりGDPの順位と国民の経済的豊かさ、工業化・国際化水準の度合い、国民生活の充実度に関する主成分スコアによる順位の相違をみる目的で、図2にアジア諸国の一人当たりGDPを示した。
(1) 使用したデータおよび統計上の留意点
ここでは分析対象に台湾を含めているが、社会や文化に関する豊富な統計を掲載する国際連合教育科学文化機構(UNESCO)のデータなど国連関連のデータ、および『IFS』などの国際通貨基金(IMF)のデータには台湾のデータが収録されていない。
そこで、分析対象国のデータをほぼ網羅しているアジア開発銀行(ADB)の『Key Indicatoers of Developing Asian and Pacific Countries』により分析を行った。
データは、基本的にすべての国の統計が利用可能となっている94年のものを採用しているが、データが得られない場合は、直近の最新データを使用している。
また、経常収支に関する指標は、分析に際しては不可欠と考えられるが、香港政庁が経常収支統計を発表していないため採り上げていない。
失業率についても、失業者についての各国の定義が異なることから比較が不可能であり、割愛した。
データの加工に関しては、各国の人口やGDP総額の規模が異なることから、各国間のデータ比較が可能となるように、一人当たり、対GDP比率、対人口比率などに変換している。
現地通貨単位で測定されている指標については、各年の対米ドル年平均相場で米ドルに換算している。
また、各特性については、対象国の数が10ヵ国と限られているため、主成分分析に利用できるデータ数にも制約がある。
そこで、多様なアジア諸国を相対的に点数評価するという趣旨から、国民の経済的豊かさ、工業化・国際化水準の度合い、国民生活の充実度それぞれについて、9個のデータにより主成分分析を行った。主成分スコアは各主成分について、平均が0、分散が1になるように標準化されている。
なお、主成分を決定する際の固有値(主成分の分散、この値が大きいと情報損失量が少ない)については、1以上を基準に主成分を抽出した。ただし、工業化・国際化の度合いに関しては、この基準では2つの主成分が得られたが、第2主成分の説明力が極めて弱いので、第1主成分だけを選んでいる。
(2) 各特性の評価
1) 国民の経済的な豊かさ
国民の経済的な豊かさとして考えた9個の指標を用いて主成分分析を行った結果が表6(表6、8、10に使用されている略称については表5参照)である。
消費者物価指数と、金融深化の度合いを示す指標であるM2(広義のマネーサプライ)の対GDP比率の2つ以外の指標の因子負荷量(主成分との相関係数)の絶対値は0.9以上となっている。
また、消費者物価指数は因子負荷量の記号が負であり、その上昇率が高いほど主成分スコアは小さくなる。すなわち、物価上昇率の高い国ほど、国民の経済的豊かさの度合いは低くなる。
導き出された主成分は、経済的豊かさを総体でとらえている指標ということができよう。累積寄与率は0.79であり、この主成分で元の9個の経済指標の持つ情報の79%を説明している。
主成分スコア(表7)をみると、シンガポール、香港、台湾、韓国、マレーシア、タイ、中国、インドネシア、フィリピン、インドの順位となっている。一人当たりのGDP(米ドル建て)の順位(図2)と比較すると、インドネシアとフィリピンの順位が逆転していること、一人当たりGDPでは10ヵ国・地域中9位であった中国が7位になっているのが特徴である。
これは、中国の一人当たりの貯蓄、一人当たりの電力消費量、M2の対GDP比率が大きいためである。
2) 工業化・国際化水準の度合い
工業化・国際化水準の度合いとして考えた9個の経済指標を用いて主成分分析を行った結果、得られたものが表8である。
GDPに占める農業部門の比率、海外からの資金フロー総額の対GDP比率の2つを除き、各経済指標と主成分の因子負荷量は0.8以上である。
GDPに占める農業部門の比率の因子負荷量は負となっており、この数字が高ければ主成分スコアも低くなる。つまり、工業化・国際化水準の度合いも低くなる。
この主成分の累積寄与率は0.77であり、この主成分で元の9経済指標が持つ情報の77%を説明している。
主成分スコア(表9)の順位は、シンガポール、香港、台湾、マレーシア、韓国、タイ、フィリピン、インドネシア、中国、インドとなっている。一人当たりのGDPの順位と比べると、マレーシアの順位が上がっている。
これは、マレーシアの輸出入の対GDP比率がともに80%を超え、韓国(輸出25%、輸入27%)よりも大幅に高いこと、一人当たり外貨準備高が韓国の 961ドルに対しマレーシアが1,311ドルであること、海外からの資金フロー総額の対GDP比率が5%と韓国の1%よりも高いこと、などによる。
3) 国民生活の充実度
国民生活の充実度として考えた9個の指標から得られた主成分分析の結果が表10である。
一人当たりGDP、平均寿命、都市人口比率の因子負荷量の符号は負、その他の指標の因子負荷量の符号は正となっている。したがって、この主成分スコアは小さければ小さいほど優れたものと評価される。
因子負荷量の絶対値は、医師一人当たり人口、都市人口比率を除き、0.8以上である。この主成分の累積寄与率は0.75で、元の指標の持つ情報の75%を説明している。
主成分スコア(表11)の順位は、香港、シンガポール、台湾、韓国、中国、マレーシア、タイ、フィリピン、インドネシア、インドの順となっている。
この中で、特に中国の順位が一人当たりGDPと比較して優れたものになっている。これは、病院ベッド当たり人口、医師一人当たり人口においてNIEsに匹敵する数字を示していることにみられるように医療面が充実していること、人口抑制策の結果、出生率が低くなっていることが影響している。
また、国民の経済的豊かさ、工業化・国際化水準の度合いではシンガポールが第1位であったが、この指標では香港が第1位となっている。その原因は、平均寿命が香港の方が長いこと、病院ベッド当たり人口の面で香港がシンガポールに勝っていることにある。
以上の3つの主成分スコアを各国ごとにプロットしたのが図3、4である。この図は、国民の経済的な豊かさ、工業化・国際化水準の度合い、国民生活の充実度について、主成分スコアが第1位の国を10、第10位の国を1として座標軸をとっている。
一人当たりGDPの順位と比較すると、総じて、一人当たりGDPの順位と国民の経済的豊かさ、工業化・国際化水準の度合い、国民生活の充実度の順位との間には顕著な相違はみられなかった。
ただし、NIEsについては、一人当たりGDPの順位と国民生活の充実度の順位に関し、シンガポールと香港が入れ替わっている。
また、マレーシアが主に貿易依存度(輸出入の対GDP比率)の高さから、工業化・国際化水準の面で順位がアップしているのが特徴的である。
国民の経済的な豊かさにおいて、フィリピンとインドネシアの間で順位の入れ替えがみられるが、両国の一人当たりGDPはほとんど差がないことから、この順位の差に大きな意味はないと考えられる。
インドはすべての面で10ヵ国中最下位になっている。
中国については、一人当たりGDPに比較して、国民生活の充実度の面で相対的に高い順位となっている。これは中国が社会主義のもと、国民生活の向上に尽力した結果ともいえよう。
おわりに
アジア諸国の過去20年間の経済成長率は、総じて高いものであり、前半10年間(76~85年)ではNIEsが平均8.1%、アセアンが5.6%、後半 10年間(86~95年)では、NIEsが7.9%、アセアンが6.8%であった。また、後半10年間の中国の経済成長率は9.8%と、著しく高いものであった。
一方、成長の安定性を示す指標である変動係数を見ると、すべての国が前半10年間と比較して後半10年間に安定した経済成長を実現している。
また、経済成長率の相関係数は、後半10年間にその値が高くなっており、アジア諸国間の経済的な相互依存関係が強まっていることがわかる。
「経済発展の度合い」を相対評価するため、国民の経済的豊かさ、工業化・国際化水準の度合い、国民生活の充実度について主成分分析を行い、主成分スコアを見ると、総じて一人当たりGDPの順位と同じような順位であったが、マレーシアと中国が一人当たりGDPに比較して、それぞれ工業化・国際化水準の度合い、国民生活の充実度の面で高い順位となっている。
本稿の主成分分析に関する最大のボトルネックは、データの制約であった。
今後の課題としては、データの数を増やした分析が必要となろう。国の数を大幅に増やすとともに、それに応じて経済指標や社会関連指標の数を増やした分析が必要であろう。
採用すべき具体的な経済指標の例としては、技術や効率性に関するデータが挙げられる。
米スタンフォード大学のポール・クルーグマン教授は、『まぼろしのアジア経済』(The Myth of Asia's Miracle,1994)の中で、アジア諸国の経済成長は生産要素である労働および資本の投入によるところが大きく、技術進歩や効率性などに代表される総要素生産性の上昇が伴っていないため、長期にわたる成長の持続は不可能であると述べている。
アジア諸国の将来を予測する上でも、従業員教育などを含めた教育関連支出や、R&Dに関する指標なども考慮すべきであろう。
また、今回の特性として考えた国民の経済的豊かさ、工業化・国際化水準の度合い、国民生活の充実度といった3つの特性の間の相関関係を明らかにしていくことも今後の大きな課題である。
注
1. アジア諸国の多様性や経済成長率の動向の概観については、さくら総合研究所 環太平洋研究センター(1996)が簡潔にまとめている。
2. 以下では、NIEsを韓国、台湾、香港、シンガポール、アセアンをタイ、マレーシア、インドネシア、フィリピンとする。
3. マレーシアにおいては、このような日本からの直接投資ブームが一次産品依存経済からの脱却の好機ととらえられ、「歴史的日本機会」ともいわれた。
4. 相関係数は因果関係を示すものではないので、一国の経済成長率と他の国の経済成長率との相関関係が大きいことをもって、一国の経済成長が他国の経済成長の原因であると結論づけることはできない。因果関係については、定性的な分析を含め、別途詳細な検討が必要である。
5. 経済成長と経済発展の相違については、西川(1976)に負うところが大きい。同書においては、「経済発展とは総実質生産物の変化に影響を与える文化的・技術的・社会的変化の組み合わせ、およびこれらと実質生産物の変化との相関関係」と定義されている。
6. 石村(1992)
主要参考文献
1. アジア経済研究所『発展途上国経済発展の数量的分析(I)』1984年
2. アジア経済研究所『発展途上国経済発展の数量的分析(III)』1985年
3. 有馬哲、石村貞夫『多変量解析のはなし』東京書籍 1987年
4. 石村貞夫『すぐわかる多変量解析』東京書籍 1992年
5. 奥野忠一ほか『多変量解析法』日科技連 1971年
6. さくら総合研究所 環太平洋研究センター『早わかり 図で読むアジア経済』プレジデント社 1996年
7. 高橋克秀「MACで実践!統計学」(日本評論社『経済セミナー』1993年11月以降10回連載)
8. 通商産業省『経済協力の現状と問題点 1983年』1983年
9. 西川潤『経済発展の理論』日本評論社 1976年
10. 日本開発銀行「緊密化する環太平洋地域の経済リンケージ-貿易・直接投資・技術」(『調査』1990年所収)
11. 福田公正「豊かさを明らかにする経済学」(日本評論社 『経済セミナー』1996年11月号所収)

