RIM 環太平洋ビジネス情報 1999年1月No.44
わが国繊維産業を取り巻く環境と中小繊維企業にみる国際化の取り組み
1999年01月01日 さくら総合研究所 大八木智子
はじめに
わが国繊維企業の海外進出が本格化したのは、1960年代後半以降である。特に、近年の経済グローバル化に伴い、若年労働者不足や人件費高騰への対応に加え、海外の消費地への直接的な立地を目的とした繊維企業の海外進出が活発化した。このような進出は、進出企業に対し、人件費などのコスト削減や、適地・適品生産といった経営の効率化、国際競争力の強化をもたらした反面、国内への逆輸入を増加させ、産地を苦境に追い込んでいる。また、旧態依然とした生産・流通構造や、92年以降続いている消費不振などの問題も深刻化しており、わが国繊維産業は解決すべき数多くの問題を抱え、非常に厳しい環境に置かれている。繊維産業は、日本経済において雇用を創出する重要な産業の一つであり、生産面でも地域経済社会への貢献度が非常に高い産業であることから、状況の改善に向け、早急に新たな方策をとる必要がある。
このような実情を踏まえた上で、本稿では繊維企業の9割超(注1)を占める中小繊維企業、なかでも織・編物企業や縫製・アパレル企業に焦点を当て、以下の点を探ってみたい。すなわち、(1)近年、繊維企業が「国際化」に向けてどのような取り組みを行ってきたか、(2)進出した日系繊維企業からの逆輸入の増加や、アジア諸国の台頭による輸入の急増が、国内の産地へどのような影響を与えているか、(3)産地の活性化に向け、企業はどのように対応しているかの諸点である。さらに最後に、繊維産業の国際化を展望するとともに、このような厳しい環境を生き抜くための課題が何であるか、海外進出企業だけでなく、国内にのみ生産拠点を置く企業も視野に入れて考察してみたい。なお「国際化」とは、海外進出や海外との輸出入、海外企業との技術提携などを指すが、本稿では主に「海外進出」を指すことを付記しておく。
I.わが国繊維産業を取り巻く厳しい環境
わが国繊維産業は非常に厳しい環境に置かれている。同産業が現在抱えている問題は数多くあるが、大きく分けると次の3つに集約される。すなわち、(1)若年労働者不足と従業員の高齢化、(2)個人消費の落ち込みと多様化する消費嗜好への対応、(3)増大する繊維輸入圧力と低迷する繊維輸出である。
1.若年労働者不足と従業員の高齢化
繊維産業は、わが国経済の雇用創出に貢献している。96年の繊維産業(繊維工業、衣服・その他の繊維製品製造業、化学繊維製造業の合計。推計含む)の従業者数は93万人と、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、一般機械器具製造業に続き、製造業では第4位の雇用数となっている(通商産業省『工業統計表』)。しかし近年は、事業所数、従業員数に加え、製造品出荷額等が年々減少している(図1)。90年に13万あった繊維産業の事業所数は、96年には10万弱へと減少、それに伴い従業者数も127万人から93万人へと大幅に減少した。また、製造品出荷額等も14兆円から10兆円へと低下している。理由は先述の通り、国内消費の低迷と海外からの輸入品との競合が、主な理由として考えられる。加えて、若年労働者不足が顕著になっている。その要因としては、繊維産業の賃金が低いこと、潜在的な成長性が期待できないことなどが考えられる。さらに、同産業では、従事する従業員の高齢化も進んでいる。通産省の調べによると、繊維の主要な産地では高齢化が急速に進んでおり、50歳以上の構成比が過半数を超える産地も少なくないという。同時に、主要な産地では企業の後継者不足も深刻化しており、企業の存続が危うくなっている所もある。産地企業の廃業が増加すれば、産地としての機能低下につながるため、無視できない問題となっている。
2.個人消費の落ち込みと多様化する消費嗜好への対応
第二の問題点としては、国内個人消費の落ち込みと、多様化する消費嗜好への対応が挙げられる。百貨店やスーパーにおける紳士服・洋品、婦人・子供服・洋品の販売額は、92年以降、前年比減少もしくは横ばいで推移している(表1)。97年には、消費税引き上げや特別減税の廃止、金融機関の経営破綻などが、消費者の購買意欲を抑制する方向に働いたと考えられる。
さらに、消費者の嗜好の多様化も、繊維企業の業況を厳しくしている理由の一つである。「バブル期」と呼ばれていた80年代半ばには、DCブランドやイタリアン・ブランドなど、有名デザイナーやメーカーが打ち出す「流行」を消費者が追いかける時代風潮があった。しかし、ここ数年は、消費者が自分の価値観に応じて衣類を購入する傾向がみられ、ブランド品や高級品離れという「価格コンシャス」志向が高まっているといえる。そのためアパレルメーカーは、引き続き多品種・小ロット生産とQR(クイック・レスポンス)(注2)対応に迫られている。
3.増大する繊維輸入圧力と低迷する繊維輸出
第三の問題点は、わが国繊維輸入の急増である。わが国繊維輸入(繊維原料、糸、織物、二次製品の輸入合計)の動向をみると(図2)、87年以降、基本的には右肩上がりで増加しており、85年の1兆4,100億円から97年には2兆8,200億円へと倍増している。なかでも、二次製品(衣類含む)の増加が著しく、85年の5,000億円から約5倍の2兆2,500億円へと拡大した。ちなみに、繊維輸入の内訳をみると、8割が二次製品、繊維原料と織物が各7%、糸が6%となっている。これは、織物を日本から輸出し、それを海外で縫製した後、日本へ逆輸入するという貿易構造になっていることが一因である。
国別にみると(図3)、中国が全体の55%と圧倒的なシェアを占め、イタリア(8%)、韓国(6%)、米国(5%)、インドネシア(3%)が後に続いている。中国が断然トップである理由は、活発化した日系繊維産業の中国進出が背景にある(II.2参照)。
また、輸入急増に伴い、繊維製品(糸、織物、二次製品)の輸入浸透率(輸入/内需。糸ベースで換算)も上昇し、85年の26%から、97年には過去最高の61%に達している(図4)。近年、繊維輸入が急増した背景には、(1)縫製業を中心とした日系繊維企業が、製品の持ち帰り(逆輸入)を目的とした海外進出を活発化させたこと、(2)生産技術や生産能力を向上させた中国をはじめとするアジア諸国が、円高を利用して日本向け輸出を増加させたことなどがある。97年は、日本国内の消費低迷の影響により繊維輸入に減少がみられたが、国内景気が回復すれば、再びアジアからの対日繊維輸入が増加することも予想される。
一方、わが国繊維輸出は、基本的に減少傾向にある(図2、4)。85年の1兆4,800億円から97年には9,700億円へと減少、特に糸と織物の輸出の落ち込みが加速している。一時、89~92年にかけて、委託加工用の織物輸出が増加した時期もあったが、最近では一部の日系企業が現地で生地を調達するようになったこともあり、再び輸出は減少している。
輸出先国別の動向に目を転じると(図3)、97年は中国が全体の3割強を占め首位となっており、香港(12%)、米国(8%)、韓国(7%)、台湾(6%)が後に続いている。
輸出の内訳をみると、5割が織物で、3割が二次製品、残りが糸および繊維原料となっている。これは、二次製品が8割を占める輸入とは対照的である。なお、日本の繊維貿易を総合してみると、87年に輸出と輸入が逆転し、その後も入超幅は年々拡大している。このことから、わが国の繊維供給構造は、すでに輸入が組み込まれた体制に移行しているといえよう。
以上、わが国繊維産業が非常に厳しい環境に置かれていることを示した。次に、先に指摘した若年労働者不足や従業員の高齢化などの問題を克服するため、わが国繊維企業が行ってきた海外進出への取り組みに焦点を当ててみよう。
II.中小繊維企業にみる国際化の取り組み
1.繊維企業の国際化の流れ
通商産業省生活産業局(1994)では、戦後の繊維企業の海外進出を次の4期に分類している。まず第1期である1955~69年には、紡績業を中心とした企業によって、原料の調達基地の設立や関税障壁の克服を目的とする、中南米や東南アジアへの進出がみられた。また、65年以降には、合繊企業による海外進出も活発化した。続く70~74年の第2期には、テキスタイル(糸、織物、染色加工)企業を中心に、NIEs(韓国、台湾、香港)、アセアン、中南米への進出が増加した。この時期の進出は、現地での販売が主な目的とされ、輸出代替が進められたことが特徴である。その背景としては、わが国経済の輸出主導型成長に陰りがみえ始めたこと、さらに輸出先国で輸入代替工業化政策がとられたことが指摘できる。テキスタイル企業の進出形態は、合弁企業の設立が主ではあったが、技術指導のみのケースもみられた。次に、第3期である75~86年には、発展途上国企業による自給化と第二次オイル・ショックの勃発によって現地法人の見直しが行われ、進出テキスタイル企業の体質強化やスリム化に加え、撤退する企業もみられた。そして第4期(87年~現在)には、国内労働者不足の深刻化、円高の進行、さらに中国の改革・開放政策の推進などを要因に、縫製・アパレル企業を中心とした中国およびアセアンへの進出が急増した。第4期の進出目的としては、主に国内への製品持ち帰りであったことが特徴として指摘できる。進出形態は、テキスタイル企業に比べても多様化されており、合弁企業の設立に加え、委託加工(注3)、専用ライン(注4)、補償貿易(注5)、単純企画輸入(注6)、技術指導など、さまざまな形態が取られた。
テキスタイル分野の進出は、基本的に投資額やリスクが大きいため、中小企業の織物業者や染色業者が中心となって進出するケースは少なく、大手原糸メーカーの主導もしくは商社を仲介役として、比較的少ない出資比率で参加するという形態にとどまるケースが多かった。一方、縫製・アパレル企業では、商社や問屋などと協力して進出するケースも多くみられたが、投資額が比較的小さいため、中小企業自らが進出するケースも少なくなかった。
2.近年における海外進出の経緯と進出地域の変遷
第4期の進出について、もう少し掘り下げてみよう。85年のプラザ合意以降、若年労働者の確保や、現地市場の将来性を考慮した、繊維企業のアジア進出が活発化した。
わが国繊維企業の海外直接投資件数をみると(図5)、87年度以降、円高の影響もあいまって新規進出件数は年々拡大し、85年度に40件だった進出件数は、95年度には約9倍の376件に達した(大蔵省『国際金融局年報』)。進出先の内訳をみると、89年度時点では、アジアが全件数の64%、欧州が22%、北米が14%というシェアであったが、95年度時点では、アジアが90%、欧州が4%、北米が3%のシェアを占め、アジアが占める比率が圧倒的に高くなっている。アジアの内訳をみると、中国が75%と大半を占め、ベトナム(6%)、インドネシア(5%)が後に続いている。しかし、96年度以降、海外進出件数は減少しており、97年度には139件となっている。97年度のシェアをみると、アジアは74%へと低下し、欧州、北米はそれぞれ14%、9%となっている。海外進出が減少した理由は、新規投資が一巡したこと、また、日本市場がすでに供給過剰であるため、新規に進出して日本向け製品を生産しても、メリットが少ないと企業が感じていることも一因であろう。
以上、繊維企業による海外進出の動きをみてきたが、併せて、同企業の9割以上を占める中小繊維企業の進出の動きもみておこう。94年3月以降、対象案件が3,000万円から1億円超へと変更されたため、データは連続しないが、93年以降、中小繊維企業(大企業との共同投資、個人投資も含む)による投資件数の大幅な上昇がみられた(図6)。地域としては圧倒的に中国が多く、93~95年にかけて中国は9割前後のシェアを占めていた。しかし、97年になり、新規投資は前年の180件から42件へと大幅に低下、それに伴い、中国の比率も6割へと下がった。理由としては先述の通り、新規投資の一巡と、日本への持ち帰りを目的とした海外進出のメリットが薄れたことが指摘できる。
3.進出企業が抱える問題点
では、中小繊維企業は、海外進出を果たす前、果たした後にどのような問題を抱えているのであろうか。ヒアリング調査(注7)(97年9~10月、98年11月)を参考にしながらまとめたい。
第一に、情報収集面での問題を抱えている。特に進出前の段階で、中小企業一社では、現地の経済情勢や投資国における制度、進出の手続きなどの情報を単独で収集することが難しいため、商社や問屋などと協力して進出するケースが多くみられる。
第二に、人材育成面である。言語、価値観、宗教などの異なる従業員を教育することには、大変な困難が伴う。例えば、日本的な互助精神を身につけさせようとしても、現地の従業員は与えられた仕事以外は一切行わず、自分の仕事が終了しても他人が忙しければ手伝うという意識が薄いため、互助精神を身につけさせるのは難しいようである。
第三に、製品の品質面と生産性向上の問題である。進出当初、日本市場が求めるような水準の製品化が困難だった企業も少なくなく、操業1年目は、縫製方法の指導に終始したという企業もあった。企業の多くでは、品質を第一に考え、徐々に生産性を上げていくのが一般的な方針のようである。
その他の問題点としては、パートナーに操業開始年度からの利益計上を期待されたこと、97年に発生したアジア通貨危機の影響を受け、現地の消費意欲が急速に減退し、現地で製品が売れなくなったことなどが指摘された。しかし現在は、何よりも日本の景気が低迷し、日本国内での受注が減少したあおりを受け、国内と海外での生産体制の見直しを迫られていることが、最も深刻な問題のように思える。
4.海外進出の利点
このように、繊維企業は海外進出前後に問題を抱えてはいるものの、海外進出は、進出企業はもちろんのこと、日本経済や進出相手国経済に対し、プラス効果を与えている。
まず第一に、進出企業の利点としては、(1)若年労働者の確保、(2)人件費などコストの削減、(3)新規納入先の獲得、(4)新規市場の開拓、(5)国際分業体制の推進、といった効果が挙げられる。また、進出後に、国内従業員が海外従業員の成果に負けられないという意識を持つようになり、人材の活性化が進んだ企業もみられた。
第二に、日本経済への影響としては、輸出誘発効果が挙げられる。輸出誘発効果とは、海外進出に伴い、進出企業が日本から原材料を調達することから、日本の輸出増加をもたらすことである。89~92年にかけて、委託加工用の織物の輸出が増加したことは、先述の通りである。第三に、進出相手国経済に対しては、技術移転、雇用創出に寄与するといった効果がみられている。
5.進む東アジアとわが国との生産分業体制
前節でも、進出企業の利点として「国際分業体制の推進」を挙げた通り、アジアへ進出した繊維企業は、わが国と現地との間で生産分業を進めている。生産体制の特徴としては、高級品や多品種・小ロット生産、短納期が要求される製品は基本的に日本国内で生産し、納期に比較的余裕のある製品や低価格品など定番品は海外で生産するという、生産期間や製品価格別の分業が行われている。
それでは、海外へ進出した中小繊維企業へのヒアリング調査(98年11月)(注8)を基に、具体的な分業事例を挙げてみよう(図7)。
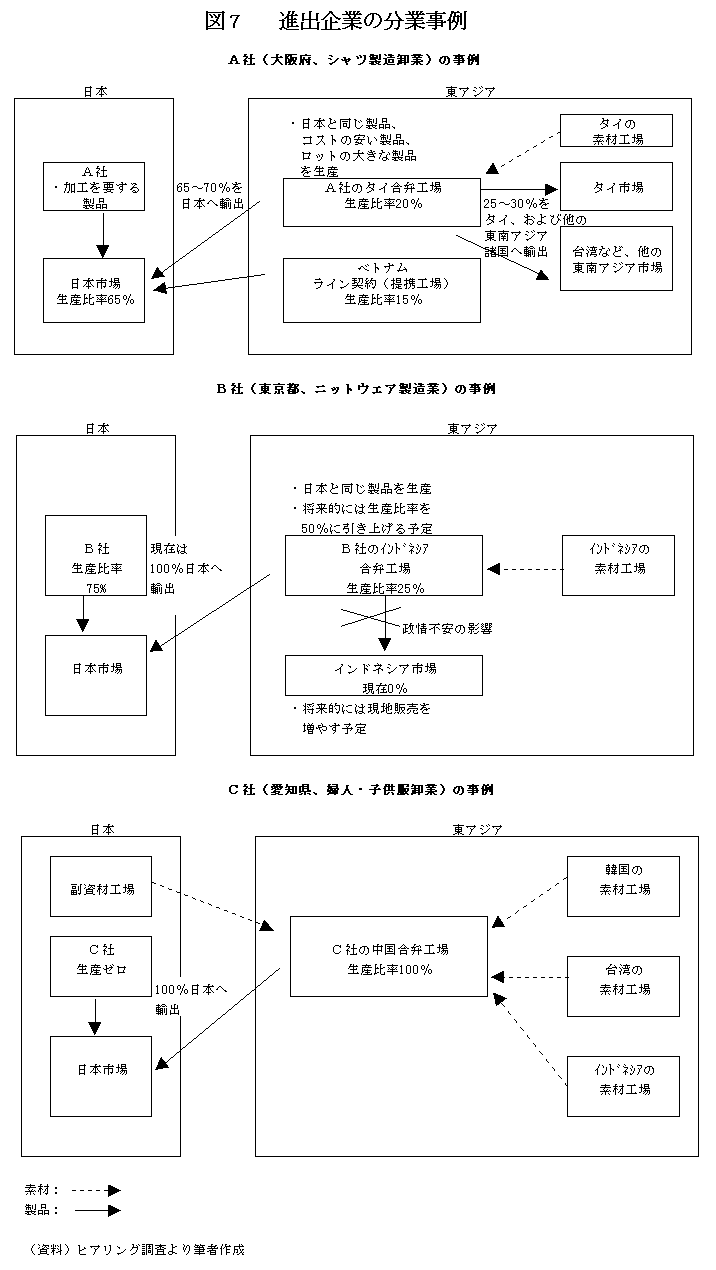
まず、シャツの製造・販売を行っているA社(大阪府、シャツ製造卸業、従業員291名)は、80年代後半に日系商社の協力を受け、タイへ進出した。進出理由には、(1)国内での労働力確保が困難になってきたこと、(2)安定した技術者と品質を確保すること、(3)国内市場が低廉な製品を望んでいたことなどを挙げている。タイを選択した理由は、(1)国情が安定していること、(2)現地での素材調達が可能であること、(3)現地で日系の商社や紡績企業の支援を得られるとの情報を得たことである。タイでは日本で生産している製品も多く生産しているが、一方で、形態安定シャツなど加工を要する製品は日本で、コストの安い製品、ロットの大きな製品はタイで生産するといった分業も行っている。製品は、7割近くを日本へ持ち帰り、残りを現地や他の東南アジア諸国に輸出している。
次に、インドネシアへ進出したB社(東京都、ニットウエア製造業、従業員200名)の事例を取り上げる。B社は、労働力の確保難という問題を解決するため、90年代初頭にインドネシアへ進出、合弁企業を設立した。同国を選定した理由は、(1)日系の原料・紡績企業がすでに同地へ進出していたこと、(2)人口が多く、市場としても期待できることが主な理由として挙げられる。日本国内とインドネシアでは同じ製品を生産しており、国内での生産比率を75%、インドネシアでの同比率を25%にしている。将来的には、インドネシアの生産比率を50%にまで引き上げる予定である。素材は現地の日系企業より調達し、製品は100%日本へ輸出している。以前は、現地にも販売していたが、インドネシアにおける政情不安や通貨危機の影響で、現在は販売を行っていない。
最後に、進出当初から100%現地で生産を行い、日本の拠点では受注先のアパレルメーカーに卸すのみという縫製企業の事例をみてみよう。90年代初めに中国へ進出したC社(愛知県、婦人・子供服卸業、従業員3名)は、現地の企業と50%ずつ出資し合い、合弁企業を設立した。C社は、素材・副資材を日本、韓国、台湾、インドネシアから調達し、生産を100%中国で行い、製品のすべてを日本へ持ち帰っている。C社の経営者は、高い人件費や若年労働力不足という問題が恒常化しているため、日本国内で縫製業が生き残るのは非常に難しく、付加価値の高い製品や、DCブランド以外の縫製は国内で生き残れないとみている。
このように、中小繊維企業の海外進出は「国際分業体制の推進」をもたらしているが、その一方で、企業の海外進出に伴う逆輸入の影響から、苦境に追い込まれている国内の産地も少なくない。次に、日本への持ち帰り需要を含む繊維輸入の拡大が、国内産地へどのような影響を与えているかを探ってみたい。
III.繊維輸入の拡大と消費不振に苦しむ国内の産地
1.産地が抱える問題点
中小企業庁の『全国の産地 平成9年度産地概況調査結果』(注9)(表2)によれば、国内の繊維産地(織物、ニット、染色整理)および衣類・その他の繊維製品産地(以下、衣服産地)が抱える問題としては、(1)内需の不振、(2)競合輸入品の増加、(3)受注単価の低下が挙げられる。競合輸入の増加に関しては、繊維産地の5割弱、衣服産地の8割強が問題であると指摘しており、具体的な競合先としては(複数回答)、ほとんどの産地が中国と回答、韓国、インドネシア、欧州が後に続いた。また、繊維産地では台湾、衣服産地ではベトナムと競合していると認識する産地が多かった。さらに、繊維産地の5割、衣服産地の8割が、出荷額減少の背景に、競合輸入品の増加があると考えていることが明らかとなった。
加えて、海外に生産拠点を持つ企業の割合は、産地によって、全産地企業に占める進出企業の比率は異なるものの、繊維産地の30%、衣服産地の88%が、海外に拠点を持つ企業があると回答した。企業の海外進出による産地への影響は、繊維産業では生産面で40%の産地が、雇用面では24%の産地が「減少した」と考えている。一方、衣服産地では、生産面でも雇用面でも影響を受けた産地が多く、6~7割の産地が生産・雇用が「減少した」と認識している。
次に、織物産地(泉州,尾州)およびアパレル産地(愛知、大阪)でのヒアリング調査(98年11月)を基に、産地が置かれている状況を探ってみよう。
泉州織物構造改善工業組合によれば、綿の白生地織物で有名な泉州産地は、輸入の急増、内需減退などを理由に生産が減少し、組合員数(機屋)が、ピーク時である73年度の1,150から、現在ではおよそ300に減少しているという。白生地産地は、繊維産業の中で最も輸入品の影響を受けているといわれており、定番品、量産品は輸入品にとって代わられている。泉州産地では従来、原料買い、製品売りに伴う見込み生産が多かったが、近年、消費需要の要請に対応した受注生産へと変遷してきたこともあり、賃加工(注10)業者が増加してきた。そのため同産地内では、生地の差別化競争に加え、価格競争をも余儀なくされるといった問題を抱えている。さらに、組合商品開発センターを中心として、国の施策による助成をバックに、商品開発に積極的に取り組んできたが、繊維産業構造改善臨時措置法(繊産法)(注11)が99年6月に廃止され、産業全体の底上げを目的とした繊維政策が一般政策へと統合されることも、同産地に不安を与えている。
続いて、毛織産地として名高い尾州(尾西、津島、尾北、名古屋、岐阜の5つの産地組合で構成)に焦点を当ててみよう。尾州はイタリアと並ぶ毛織物の大産地であり、ここでは、親機(注12)が中心となり、下請けを使いながら生産を行っているのが特徴である。同産地も輸入の影響を受けてはいるものの、他の織物産地ほどは影響を受けていない。その理由としては、尾州で生産している製品は多様かつ高級品であるため、現段階ではアジア諸国が容易にこのような製品を生産できないことが一因である。尾西毛織工業協同組合では今後、生き残りの一策として、わが国の毛織物は海外製品との棲み分けを行うべきであると考えている。
さらに、縫製・アパレル産地(以下、アパレル産地)に目を向けてみよう。アパレル産地も輸入の増加により苦境が続いており、日本のアパレル輸出と同輸入の比率は1対67であるという(97年。日本輸出縫製品工業組合の資料)。世界一のアパレル輸入国である米国さえも、アパレル輸入の17%相当を輸出しており、同輸出と同輸入の比率は1対6程度である(95年)。このことから、わが国アパレル産業の貿易構造がいかに輸入一辺倒であるか、わかるであろう。
なお産地とは関係ないが、繊維産業全体の大きな問題点として、旧態依然とした生産・流通構造が指摘できる。例えば、衣料品は、1年以上も前から売れ筋商品を見込んで生産し、シーズンが来ると売り込むという、実需に基づかない「見込み生産」が主であるが、売れなければ当然返品され、在庫となる。また、たとえ売れたとしても、売れた製品を期近・期中(シーズン間近、シーズン中)に増産するというような対応ができず、販売機会を逃すという状況がしばしばみられている。この背景には、現在どの商品が売れているのかという情報が、糸商、染色企業、織・編物企業、縫製企業などに伝達されていないことがある。今後は、製造、アパレル卸、小売業がいかに情報を共有し、不良在庫を増加させない体制作りができるかが課題となる。
2.産地活性化に向けた産地企業の取り組み
先述のように、アジア諸国からの輸入急増や国内不況、繊維産業が抱える構造的な問題により、国内の繊維・衣服産地企業の生き残りは非常に難しくなっている。産地活性化に向け、産地企業は具体的にどのような取り組みを行っているのだろうか。その一例として、国内のみに生産拠点を置きながら、産地の共倒れを防ぐために企業間ネットワークを構築した、泉州産地企業の事例を取り上げる。
95年、泉州織物構造改善工業組合と大阪南部綿織物工業組合の若手後継者達が、SSS(スリーエスグループ)というネットワークを発足した。発足当初は、産地内メーカー同士、競合相手という意識が強かったものの、徐々に情報交換や、仕事の回し合い(受注の横請け)を行うようになり、各々の企業が得意分野に特化するようになった。また、98年には、テキスタイル見本市であるJC(ジャパン・クリエーション)に向けて、共同での新製品企画を始めている。現段階では、自分達の製品を自分達で開拓した販路に販売するという形態には至っていないものの、単に注文されたものを織るという「賃織り」(注13)から、最終製品の寿命、現在の売れ筋製品などを念頭に置きながら受注し、製品作りをするようになったという。産地メーカーが紡績、問屋、商社への生機(注14)納入のみを行う従来の取引形態を脱却し、企画・販売機能を身につけた「提案型」メーカーへ飛躍しようとする泉州企業の取り組みは、注目に値するであろう。
次に、尾州産地での取り組みをみてみよう。尾州産地の岩仲毛織は、LPU(Linkage Production Unit:実需対応型補完連携)を形成、同社を中心に、織布業者、ニット業者、アパレルなど素材から製品までのネットワークを構築している(『化繊月報』97年5月号)。LPUは、89年に改正された繊維工業構造改善臨時措置法によって導入された概念で、現行法である繊維産業構造改善臨時措置法でも使用されている。製品の高級化、多品種・小ロット生産、短サイクル化の動きに柔軟かつ積極的に対応することが必要との認識の下で、製品の企画機能の向上に加え、製造、流通の効率化を図り、工程間の分断を解消することが目的である。こうしたLPUの取り組みは、他の産地でも行われている。
IV.中小繊維企業の国際化へ向けた展望と生き残りへの課題
以上、繊維企業の海外進出動向や問題点、輸入急増による国内産地への影響、さらに不況打開へ向けた産地企業の取り組みをみてきた。今後、繊維企業による海外進出はどうなるであろうか。また、この厳しい事業環境のなか、企業の生き残りへ向けた課題とは何であろうか。海外進出を果たした企業と、国内のみに生産拠点を置く企業とに分けて、考察してみたい。
1.中小繊維企業の国際化へ向けた展望
中小繊維企業の新規海外進出は、以前のような急増はみられないものの、中長期的には続くと予想される。なぜなら、国内における労働者の高齢化や人件費の高騰、若手労働者不足という問題の解決は難しく、特に、労働集約的な縫製業が国内で生き残りを図ることは難しいとされているためである。
しかし、短期的には、日本への持ち帰りを目的とした新規海外進出は減少に向かうと予想される。その理由としては、(1)日本国内の消費が低迷していること、(2)すでに国内市場が供給過剰であることの2点が指摘できる。特に、これから人件費などのコスト削減のみを目的とした中国進出は減少するであろう。というのは、日系繊維企業の7割程度が上海や長江下流の沿岸部に進出しているといわれているが、(1)上海地区の人件費が大幅に上昇していること、(2)中国における重要産業が自動車産業や電気・電子産業へシフトしていること、(3)地場企業の技術水準が上がり、定番品であれば現地企業でも同レベルの縫製が可能になっていること、などが理由として考えられる。
また、すでに進出した企業に関しては、現地での生産体制の見直しが一層進められることが予想される。例えば、賃金の高騰がみられる既存工場を検品工場などに使用し、新たに人件費の安い地域(奥地)へ移転するケースなどもあり得るであろう。しかし、その場合には、インフラの未整備や、素材調達における物流面の不都合など、新たな問題が生じる可能性もあることを考慮する必要がある。また、撤退という選択肢もあるが、特に合弁企業を設立した場合、現地パートナーや現地従業員との間で労務問題などが生じると予想されること、さらに、労働集約的な縫製業が国内で生き残りを図ることが難しくなっている状況を勘案すると、現段階での撤退は得策ではないと判断する企業が多いのではないだろうか。
2.海外進出企業の課題
海外進出を行っている企業の生き残りへ向けた課題は数多くあるが、まずは以下の3点を実施することが肝要と思われる。すなわち、(1)適地・適品生産体制の充実、(2)リードタイムの縮小、(3)品質と生産性の向上である。
第一に、わが国と海外での分業を行っている企業は引き続き、適地・適品生産体制を充実させるべきであろう。わが国と海外の間では基本的に、ロットの大きい製品、納期に比較的余裕のある製品、低価格品を海外で生産し、多品種・小ロット・短納期が求められる製品や、高級品は日本国内で生産するという分業が行われていることは、先に指摘した通りである。進出企業は、今後も自社の実情に合わせ、最適な生産基地を模索しながら、納期や生産数量、製品のグレード、販売先などを考慮し、効率的な分業を行っていくことが課題である。
第二に、製品が企画されてから実際に製品化されるまで(流通側からいえば、注文して納入に至るまで)のリードタイムの縮小である。海外縫製工場の生産が本格化しているなか、海外でもリードタイムの縮小が求められるようになってきている。従来の、素材を日本から持ち込むという委託加工は、運搬面で時間的なロスが生じるため、素材の現地調達が必須要件である。そのためには、現地において、縫製とテキスタイル分野での連携が必要であろう。
第三に、品質と生産性の向上である。IIで触れた通り、進出企業の中には操業当初、日本向け製品の品質確保ができず、苦労したところも多い。従来、海外での生産では、比較的品質の低い製品が作られていたが、リードタイムの短縮と同じように、海外でも日本と同品質の製品作りが求められるようになっているため、日本から機械を持ち込む、あるいは、従業員を日本へ呼び寄せて研修を実施している企業も少なくない。また、品質管理の徹底により、縫製不良、染色不良などをなくし、生産性の向上を図ることも喫緊の課題である。不良品の発生は、生産コストの上昇につながることから、設備の革新化や人材育成などを図り、まずは品質対策を行うことが不可欠であるといえよう。
3.国内にのみ生産拠点を置く企業の課題
一方、日本国内にのみ生産拠点を置く企業の生き残りへ向けた課題は何であろうか。
第一に、海外製品と差別化した製品への取り組みである。例えば、わが国織物企業は、イタリア企業によるデザインの感性の高さには太刀打ちできないといわれている。そのため、国内テキスタイル企業は、天然繊維と合成繊維を組み合わせた素材の複合化など、織布段階での技術面の差別化を行っていく必要がある。競争力の強化に当たり、設備の革新化にのみ依存すると、大手メーカーによる紡織一貫との競合が予想されるため、企業の商品開発力や提案力が重要となっている。
第二に、下請け体質からの脱却である。従来、機屋やニッター(編み上げ業)、縫製企業は、アパレルメーカーや問屋の注文を製品化するのみであったため、同一産地内で工賃の引き下げ競争が起こることもしばしばであった。泉州でみられた取り組みのように、企業間ネットワークを構築して仕事の分配を行い、情報を補完し合うことで、自ら仕事を選別できる体制へと転換していくことが肝要である。また、異業種間との連携を行うことで、企画力、販売力、生産技術など、自社の経営資源を補強していくことも、下請け体質を脱する一手段である。そのほか、海外進出した企業同様、多品種・小ロット生産、短納期化にいかに対応できるか、また、国内だけでなく海外へ販路を拡大できるのかということも、生き残りへ向けた重要な鍵となろう。
最後に、繊維産業全体として、生産・流通構造の改善が必要であることは、先述の通りである。企業は、見込み生産ではなく、現在の売れ筋商品に関して期近・期中対応ができるような体制を作るべきである。縫製企業や織・編物企業、染色工場、糸商が、販売状況や発注情報などの情報をコンピュータで一括受信できれば、生産を行う上で非常に効率的である。中小繊維企業の中でもこうした動きがみられており、情報ネットワークを生かした生産体制の確立が急がれる。
このように、わが国繊維産業は厳しさが続くものと予想される。そのなかで、海外進出企業および国内にのみ拠点を置く企業が、生き残りへ向けどう対応していくか、企業の真価が問われているといえよう。
注
- わが国繊維企業の中小企業比率(従業員300人未満を中小企業とする)は高い。従業員規模別にみると、繊維企業の94.7%が中小企業に該当する。内訳をみると、繊維工業の94.4%、衣服・その他の繊維製品製造業の97.5%、化学繊維製造業の20.9%が中小企業である。
- 素材から最終製品までの生産および流通などに要する時間を短縮すること。
- 糸や生地を日本から持ち込み、編み立てもしくは縫製を行い、日本へ持ち帰る生産形態。
- 工場の一部のラインを借り切る生産形態。出資はせずに、生産設備を持ち込む形態。
- 生産機械を提供し、その代金を縫製か加工賃で回収する形態。
- 日本側が企画を行い、それを現地で生産してもらう形態。
- 97年9~10月には、岐阜の縫製・アパレル企業、愛媛(今治)のタオル企業、98年11月には、大阪および愛知のアパレル企業、東京のニッター(編み上げ業)を訪問。
- (注7)参照。
- 調査対象は、年間の生産額が約5億円以上の541産地で、うち繊維産地は126産地、衣服産地は34産地と全体の3割を占めている。質問によって、集計可能な繊維・衣服産地の回答数が異なる点に留意(表2参照)。
- 商社ないし大企業に従属して、そこから仕事を委託され、その加工賃をもらう生産形態。
- 「繊維工業構造改善臨時措置法」は、94年に「繊維産業構造改善臨時措置法」へと名称改正され、従来「工業」中心に行われてきた構造改善対策は、流通業界にも対象が拡大された。
- 産地の中核的な存在。下請け関係を有する工場間に行われる賃織で、受託者からみて委託者をいう。
- 委託先から契約に基づいて無償または有償で原糸の支給を受け、製織のうえ納品して、加工賃を受ける生産形態。
- 加工されていない、織ったままの織物のこと。
主要参考文献
- アジア経済研究所編(1980)『発展途上国の繊維産業』 1980年
- 石原亨一編(1998)『中国経済と外資』アジア経済研究所 1998年
- 岩島嗣吉・山本庸幸(1996)『コンシューマー・レスポンス革命』ダイヤモンド社 1996年
- 北村かよこ編(1995)『東アジアの工業化と日本産業の新国際化戦力』アジア経済研究所 1995年
- 小浜裕久(1998)「繊維工業の発展と衰退」(日本評論社『経済セミナー』 1998年7月号 所収)
- (財)商工総合研究所編(1990)『中小企業の海外進出』中央経済社 1990年
- 島田克美・藤井光男・小林英夫編著(1997)『現代アジアの産業発展と国際分業』ミネルヴァ書 1997年
- 通商産業省生活産業局編(1995)『新繊維ビジョン』ぎょうせい 1995年
- 通商産業省生活産業局編(1994)『世界繊維産業事情』(財)通商産業調査会 1994年
- 中小企業庁編『中小企業白書』各年版
- 日本化学繊維協会(1998)『繊維ハンドブック1999』 1998年
- 日本興業銀行産業調査部編(1997)『日本産業読本』東洋経済新報社 1997年
- 平井東幸(1997)『繊維世界』教育社 1997年
- 丸川知雄(1998)「日本繊維産業の中国展開」(アジア経済研究所『アジ研ワールド・トレンド No.34』1998年5月号 所収)
- 吉岡政幸(1986)『繊維』日本経済新聞社 1986年

