RIM 環太平洋ビジネス情報 1998年10月No.43
戦略的提携を進める完成車メーカーのアジア展開
1998年10月01日 さくら総合研究所 遠山淳子
はじめに
最近、世界の主要完成車メーカーの提携戦略に変化が起きている。グローバル競争での生き残りを目指し、世界の完成車メーカーが戦略的提携を加速しており、その動きは、アジアにも及んできた。アジア事業をグローバル戦略の柱の一つとして掲げ、戦略的提携によりアジアでの事業基盤の確保を図る完成車メーカーが増えている。
本稿では、最近の完成車メーカーの戦略的提携の動きについて、アジアを中心に整理するとともに、アジアの自動車産業の発展の方向性について考察する。なお、以下では、戦略的提携を合併、買収、資本提携、業務提携を含む概念としてとらえている。
I.加速する完成車メーカーの戦略的提携
1.98年に入って相次いだ大型提携
世界の完成車メーカーの間で、戦略的提携が活発化している。1998年に入ってから明らかにされた大型提携をみると、まず、98年5月にダイムラー・ベンツとクライスラーとの合併合意が発表された。続いて、その直後に、ダイムラーと日産自動車(以下、日産)との間で、日産ディーゼル工業の買収を含む提携交渉が行われていることが明らかになった。また、同じく5月には、欧州でフォルクス・ワーゲン(以下、VW)がBMWとの競争の末、ロールス・ロイスを買収することが決まったほか、日本ではトヨダ自動車がダイハツ工業と日野自動車工業への出資比率を引き上げ、子会社化する方針を発表した。さらに、9月に入ってからは、ゼネラル・モーターズ(以下、GM)がスズキへの出資比率を引き上げ、包括的に提携することで合意した(表1)。
表1 完成車メーカーによる最近の提携事例(1998年5月以降)
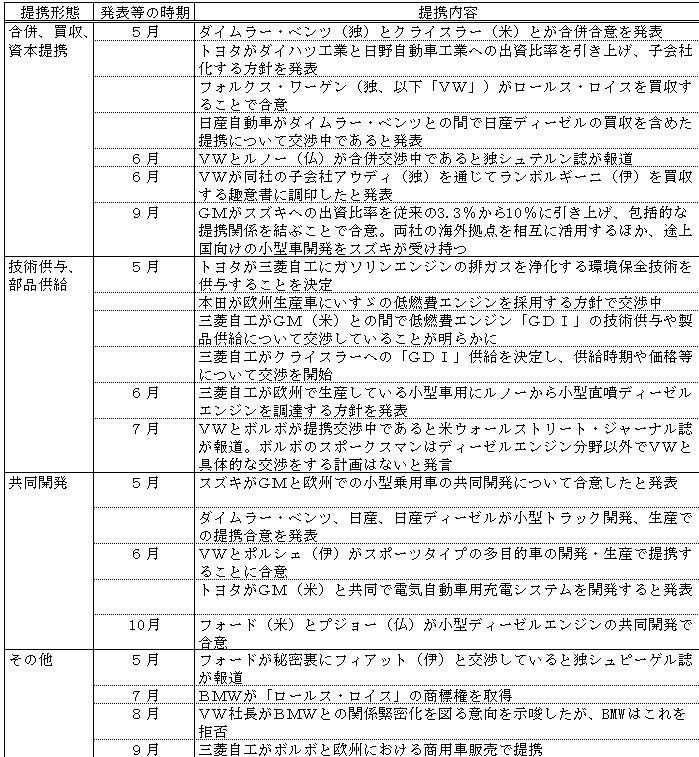
(資料)各種資料よりさくら総合研究所作成
2.経営環境の変化がグローバル競争を加速
このように大型提携が次々と発表・締結されてきた背景には、90年代に入ってから世界の完成車メーカーを取り巻く環境が急変し、それに伴って完成車メーカーの間の競争が、従来の先進国を中心とする地域ごとの競争からグローバル規模での競争へと変わってきたことがある。90年代に入ってからの自動車産業を取り巻く環境の変化は、次のように整理できる(図1)。
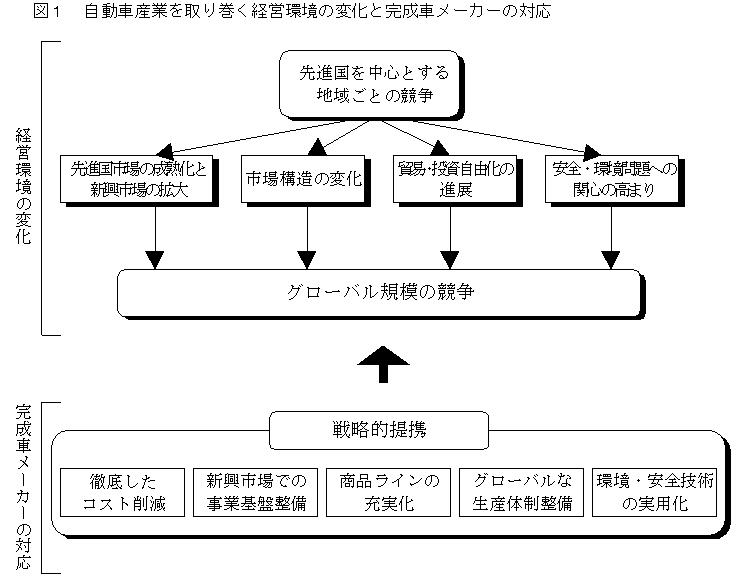
(資料)各種資料よりさくら総合研究所作成
第一は、世界の自動車市場の重心が、先進国からアジアや中南米などの新興地域へと徐々に移ってきたことである。グローバル規模での事業展開を考えた時に、新興地域は欠くことのできない地域となってきた。世界の自動車市場をみると、日米欧の先進国市場は、80年代までは順調に拡大していたが、90年代には成熟段階に入り、市場拡大のペースが鈍化し始めた。これに代わって、90年代に入ってから急速に自動車市場が拡大してきたのが新興地域である。
表2で、世界各地域の自動車販売台数の推移(80~96年)をみると、日本、北米、西欧では年以降、自動車販売台数が微増もしくは減少となっている。90~96年の年平均増減率も、日本が-1.6%、北米が1.6%、西欧が-0.3%と、いずれも低い水準となっている。これに対し、アジアと中南米では90年代に入ってから、ほぼ一貫して販売台数が大幅に増加しており、90~96年の年平均増減率も、アジア、中南米ともに10.2%の高水準となっている。なお、東欧では、旧ソ連の自動車市場回復が遅れたことなどから、94年までは販売台数が減少傾向にあったが、95年以降、自動車市場は急速に回復している。
97年7月に発生したアジア通貨危機の影響により、アセアンを中心に自動車販売台数が大幅に減少しているものの、新興市場の成長性に対する期待は依然として高い。米系の調査会社であるJ. D. Power-LMCの予測によると、95~2005年の各地域の自動車市場の平均増加率は、北米が0.9%、日本が-0.3%、西欧が1.7%と、いずれも世界平均の2.0%を下回っている(表3)。これに対し、アジアは5.3%、南米は2.2%、東欧は8.4%となっており、いずれも2.0%を上回っている。特に、アジアについては、2005年には日本を抜いて、879万台の巨大市場になると予測されている。(注1)
第二は、消費者のニーズが多様化し、市場構造が変化してきたことである。例えば米国では、商用車のカテゴリーに分類されるものの、実際には乗用車として利用されることが多い。ミニバンやSUV(スポーツ・ユーティリティ・ビークル。レジャー用多目的車)など、新たなセグメントの市場が拡大している。また、アセアンでは、多目的に利用される安価な商用車が市場の牽引役となっていたところに、日本の完成車メーカーがアジアカーを投入し、小型乗用車市場の拡大に取り組んでいる。さらに、先進国でも欧州を中心に、燃費効率の良い小型車を再評価する気運が高まってきている。このように、世界規模で小型車の重要性が飛躍的に増してきている。
第三は、貿易・投資自由化の進展である。これまでは、途上国を中心に保護政策により競争が制限され、国産車や特定の海外完成車メーカーが優遇されるケースなどがあった。しかし、世界貿易機構(WTO)などの枠組みの中で貿易、投資の自由化が進むにつれ、真に競争力のある完成車メーカーでなければ世界市場で生き残ることができなくなってきた。
第四は、環境・安全など、莫大な研究開発費を要する問題への対応である。現在、先進国を中心に、自動車の安全性や環境への影響について関心が高まっており、アジアを含む途上国でも早晩、安全性や環境の問題は重視されてこよう。より厳しい安全・環境基準に対応できる自動車をいち早く実用化し、市場に投入することが市場でのシェア獲得につながるとみられているため、世界の完成車メーカーは環境・安全対応技術の開発・研究に注力している。しかし、まだグローバル・スタンダードとなる技術は確立されていない。
このような背景から、完成車メーカーには、グローバル規模での事業展開と、グローバルな視野に立った戦略の構築が、これまで以上に求められるようになってきた。完成車メーカーは、どの事業を単独で行い、どの事業で他社と提携すればグローバル規模で競争力を維持・強化できるのか、そのための戦略を模索している。
その答えの一つが、最近、世界の主要完成車メーカーの間で活発化している戦略的提携である。従来、市場特性が地域ごとに異なることや、先進国が市場の中心であったことから、完成車メーカー間の提携関係は、一定の地域やセグメントなどにおける競争力強化を目的とした限定的な関係であった。これに対し、最近の戦略的提携は、グローバルな事業展開をにらんで、資本、生産、開発、販売など様々な分野での提携を複数の完成車メーカーと同時に結ぶ多角的・多層的な関係である。単独で事業を拡大する場合と比較して、戦略的提携には、投資負担やリスクが軽減できることの他に、多様化する消費者のニーズに、より迅速に対応できるといった利点がある。戦略的提携により、完成車メーカーは、徹底したコスト削減、新興市場での事業基盤整備、商品ラインの充実化、グローバルな生産体制の整備、環境・安全技術の実用化を図り、グローバル規模での競争力向上を目指している。
3.完成車メーカーの位置づけ
グローバル競争に勝ち残るのは、世界市場の多様なニーズに対応できるフルラインを備えた、限られた数の完成車メーカーであろうとの考え方が浸透しつつある。このため、完成車メーカーの位置づけは、フルライン戦略の中核となるメーカーと、中核メーカーとの提携を強める周辺メーカーの2通りに分かれてきている。
中核メーカーとなるのは、世界の完成車メーカーの中でも、特に資本力が大きく、グローバル規模で事業展開し、いくつかの地域でマーケットリーダーとなっている、フルラインを備えた量産メーカーである。具体的には、GM、フォード、トヨタ、VW、および98年11月に合併により誕生するダイムラー・クライスラーなどがこれに当たる(図2)。
一方、周辺メーカーとなるのは、資本力や事業規模では中核メーカーより小さいものの、ブランド力、商品力、技術力、生産拠点、販売網、市場シェアなど、特定の分野で強みを持つメーカーである。周辺メーカーと中核メーカーとの間には、戦略的提携により、相互補完関係が成り立っている。周辺メーカーにとっては、中核メーカーのフルライン戦略の一翼を担うことが、グローバル競争で生き残るための方策の一つとなる。具体的には、高い技術力を武器に、GMへのディーゼルエンジン供給役を獲得したいすゞ自動車や、小型車開発力と新興市場での高いシェアが評価され、GMの新興市場向け小型戦略車の開発を全面的に委託されたスズキなどがこれに当たる。そのほか、高級乗用車メーカーとしての高いブランド力が強みとなってVWに買収されたロールス・ロイスも、周辺メーカーと位置づけられよう。
大規模量産メーカーが中心となって戦略的提携を加速するなか、今後は、周辺メーカーとして生き残る道を選択する完成車メーカーが増えるとともに、戦略的提携のネットワークがさらに拡大するものと予想される。
II.アジアにおける戦略的提携
1.アジア重視の背景
完成車メーカーによる戦略的提携の動きは、アジアの自動車産業にも及んできた。アジア事業をグローバル戦略の柱の一つとして掲げ、アジアでの事業拡大を積極化する完成車メーカーが増えてきている。完成車メーカーがアジアを重視する理由としては、前述したように、アジアが長期的には高成長市場であるとみられていることの他に、次のような点が挙げられる。
第一は、通貨危機後、アジアでの投資コストが低下してきたことに加え、外資規制の緩和が進んできたことである。これまでアジア進出の足掛かりをつかめなかった海外完成車メーカーにとって、今が進出の好機となっている。
第二は、燃費効率が良いことから世界的にも重要性が高まっている小型車が、現状、アジア市場の主力となっていることである。このため、アジアで小型車事業の拡大を図るとともに、アジアを小型車の輸出基地とする戦略を進める完成車メーカーが増えている。
第三は、アジアには、単独で開発・生産能力を持つ有力な地場メーカーが存在しないことである。アジア進出に出遅れた海外メーカーであっても、高い技術力やマーケティング・ノウハウなどを武器に、戦略的提携を行うチャンスがあるといえる
2.活発化する戦略的提携
アジアの自動車産業の現状をみると、国や地域によって完成車メーカーの勢力図が大きく異なっている。例えばアセアンでは、日本の完成車メーカーが生産・販売ともに8割近いシェアを占めてきた。これに対し、韓国では、外資規制が厳しいことから、国内完成車メーカーが市場をほぼ独占している。また、中国やインドでは、政府の強力な支援を得た一部の海外完成車メーカー(中国ではVW、インドではスズキ)が圧倒的なシェアを占めている。このため、完成車メーカーのアジアをめぐる戦略的提携の動きも、国・地域によって異なった様相を呈している。アセアン、韓国、中国の市場をめぐる完成車メーカーの最近の動きは、以下の通りである。
(1) アセアン-日本メーカーと提携が目玉に
アセアンでは、特に、日本の完成車メーカーとの戦略的提携によって事業拡大を図ろうとする欧米完成車メーカーの動きが注目される。
フォードは、通貨危機発生以前から、出資関係にあるマツダとの合弁により、タイで13.5万台規模のピックアップトラック生産計画を進めてきた。80年代に一度撤退して以来、初めてアセアンに本格的に進出するフォードにとって、マツダがアセアンで持っている事業のノウハウやサプライヤーのネットワークなどを活用できることは、大きな利点である。通貨危機後の域内需要の低迷を受けて、生産計画の変更・縮小を余儀なくされたものの、フォードは98年7月には量産開始に漕ぎつけた。
また、フォードは、フィリピンでも乗用車、商用車、ピックアップトラックの生産を計画しており、すでにフィリピン政府から各種の優遇措置を取りつけている。マツダは、現地企業との委託生産契約が99年まで残っている上に、現地の経済情勢の先行きが不透明なことから、この計画への参加を現時点では見送ることとした。しかし、生産集約によるコスト削減には、マツダとしても関心があると思われ、フォードが99年から2000年にかけて稼動を予定している新工場への参加を、引き続き検討していく考えを示している。(注2)
ダイムラーとの戦略的提携交渉が進められている日産ディーゼルは、フィリピンで組み立てた大型観光バスが予想を上回る受注を獲得したことに加え、タイではアセアン地域をターゲットに開発したアジアトラック「パワーT」を販売するなど、アセアンでのプレゼンスを着実に向上させている。アジアにおけるトラック事業の拡大を目指すダイムラーにとって、このような日産ディーゼルの実績は、戦略的提携を進めていく上で大きな魅力となろう。
このように、アセアンにおいて欧米完成車メーカーと日本の完成車メーカーとの間に戦略的提携の事例がみられるようになった背景には、日本の完成車メーカーが、すでにアセアンに強固な事業基盤を持っていること、安全・環境対応技術で世界のトップクラスにあることの他に、日本の完成車メーカー側の事情もあるものと思われる。通貨危機の影響によるアセアンでの販売急減や為替差損の発生に加え、日本国内での販売低迷などもあり、日本の完成車メーカーとしても、アセアンでの戦略的提携により、業績回復を図りたいとの計算もあろう。
なお、欧米完成車メーカーと日本の完成車メーカーの戦略的提携ではないが、アジアでは数少ない国産車メーカーであるマレーシアのプロトンも、戦略的提携に乗り出しているので、ここで触れておきたい。プロトンは、出資者であり、かつ技術提供者でもある三菱自動車工業から低燃費エンジン「GDI」を調達することを決定している。環境に対する意識が世界的に高まるなか、プロトンの主要な輸出先である欧州では、排ガス規制など、自動車による環境への影響を低減するための規制が強化されつつある。また、アジアでも早晩、環境問題への関心が高まってこよう。プロトンは三菱自工からGDIエンジンの供給を受けることにより、自社での開発コストを大幅に節約するとともに、短期間で環境基準に対応する自動車生産が可能となる。
(2) 韓国-提携の先行きは不透明
韓国では従来、外資規制により国内の自動車市場が保護されていたことから、国内完成車メーカーによる独占が続いてきた。このため、海外完成車メーカーは、韓国完成車メーカーと提携することにより、韓国自動車市場への参入の道を模索してきた。特に、日本の完成車メーカーとの間では、これまで出資や技術供与、部品供給といった形で数多くの提携が進められてきた。また、最近では、GMが大宇自動車との間で生産・販売・金融面での提携について交渉を進めるなど、米国完成車メーカーも韓国完成車メーカーへの関心を高めている。
しかし、過剰投資によって生産能力が大幅に拡大したところで経済危機に見舞われたため、韓国完成車メーカーの経営は急速に悪化し、業界再編と生き残りをかけた新たな提携が模索されている。経済危機からの脱却を図る韓国完成車メーカー自らが、海外完成車メーカーとの提携強化へと動き出しつつある。しかし、韓国完成車メーカーを取り巻く情勢が極めて厳しいことから、海外完成車メーカーとの提携は予断を許さない状況にある。
韓国第4番目の乗用車メーカーとして、98年3月に生産を開始したサムスン自動車では、日産の技術供与により第1モデルの開発が行われた。その後、第2モデルの開発についても日産からの技術供与を受けるものとみられていたが、日産側は第2モデルの開発については、サムスンによる自社開発の可能性を強調している。(注3)
他方、経営が破綻し、売却が決まった起亜自動車については、8月に行われた第1回入札に、当初は現代、大宇、サムスン、フォード、GMの5社が参加する意向を示していたが、GMは最終的に応札を取りやめた。その後、9月に行われた第2回入札では、さらにフォードが、起亜自動車の抱える債務が予想以上に多いとの見方がでてきたことから応札を取りやめたと発表した。その結果、韓国完成車メーカー3社での入札となったものの、いずれも負債帳消しを付帯条件として要求したため、入札事務局により失格と判断された。10月12日に締め切られた第3回入札には、現代、大宇、サムスン、フォードの4社が参加しており、10月19日に落札者が発表される予定となっている。(注4)
また、GMとの間で戦略的提携関係の構築を進めている大宇についても、経営改善を目指す大宇がGMによる出資を希望していたのに対し、GM側は出資する意向がないことを示唆している。(注5)さらに、GMは、アジア拠点として買収を検討していた起亜の負債が予想以上に巨額であることから、アジア事業拡大のための提携先を、起亜からスズキへ変えたとみる向きもある。(注6)
韓国完成車メーカーは、このように海外完成車メーカーとの提携が順調に進まないことに加え、インドネシアやベトナムなど海外でも事業計画の見直しを余儀なくされている。これまでアセアンの小型車市場において、日本の完成車メーカーの潜在的ライバルとして食い込みを図ってきた韓国完成車メーカーの地位は、ここにきてやや後退したとみることができよう。
(3) 中国-日米欧メーカーがひしめく激戦区
アセアンや韓国と異なり、中国では、日本の完成車メーカーに先立って欧州完成車メーカーが進出し、事業基盤を築いてきた。なかでも、VWが6割近い市場シェアを占めており、圧倒的な地位を確保している。また、外資規制が厳しいことから、海外完成車メーカーの中国進出は、これまで容易には進まない状況にあった。しかし近年になって、中国政府は、米国や日本の完成車メーカーを誘致することで競争的な環境を作り出し、自動車産業の発展を促進しようとの姿勢をみせ始めており、GMや本田技研工業(以下、ホンダ)による大規模プロジェクトなどが発表されている。
なかでも注目されるのは、通貨危機以前からGMが上海汽車との間で進めている乗用車の生産計画である。GMは99年初めから、中・上級車を年間10万台ペースで生産し、うち30%を輸出する計画であり、このプロジェクトは、タイでの小型車生産プロジェクトとともに、GMのアジア・太平洋地域戦略の要として位置づけられている。上海ではさらに、汎アジア自動車技術センターを設立し、自動車部品のエンジニアリング拠点にすると同時に、専門技術のエンジニアリング・センターとして活用する予定である。
また、広州では、ホンダが東風汽車との間でエンジンを、また広州汽車との間で乗用者を組み立て・販売する計画を進めている。これは、広州プジョー(プジョーと広州汽車の合弁企業)からプジョーが撤退することを受けたもので、ホンダは99年10月から年産3万台規模で生産を開始し、将来は年産5万台に引き上げる計画である。
このように中国では、政府の認可を取得した現地資本との大型合弁プロジェクトが目を引く。しかし一方で、すでに中国に進出している完成車メーカーとの戦略的提携を通じ、中国への進出を図ろうとする動きがあることも見逃せない。
ライバルであるVWに比べて中国市場で出遅れたダイムラー・ベンツが、クライスラーや日産ディーゼルにアプローチした動機の一つは、中国での事業拡大と、それを足掛かりにしたアジア事業の拡大であるとみられている。(注7)クライスラーは、87年から北京汽車との合弁により「ジープ・チェロキー」を生産しており、着実に事業基盤を固めている。また、日産ディーゼルも東風汽車との合弁により、今年からトラックの生産を開始しており、アジアでのトラック事業拡大を目指すダイムラーにとっての魅力は大きい。
スズキとの戦略的提携により、小型車分野の強化を図るGMは、重慶にあるスズキの合弁工場で小型車生産に参加する可能性を示している。(注8)
さらに、天津ではダイハツが天津汽車に技術供与し、乗用車を生産しているが、中国での乗用車組み立てを目指すトヨタが、ダイハツへの出資比率引き上げにより発言力を増した後、ダイハツの中国事業にどのようにかかわっていくかも注目されよう。
3.アジアにおける完成車メーカーの勢力図
以上のような戦略的提携関係を踏まえると、アジアにおいても完成車メーカーの勢力図が明確になりつつある。これらの関係を図示すると、図3のようになる。
事業規模、生産能力、開発能力などからみて、今後、アジアにおける競争でメインプレーヤーとなってくるのは、次の7社であると予想される。すなわち、現在アジアで大規模に事業展開をしているトヨタ、三菱自工、ホンダ、フォード、VWと、合併後のダイムラー・クライスラー、上海・タイ事業立ち上げ後のGMである。このうち、三菱自工、ホンダ、VWの3社は、アジアでは日欧米韓の完成車メーカーとの間に戦略的提携関係を持っておらず、独立色が強いといえよう。
他方、メインプレーヤーとの戦略的提携により生き残りを図ろうとする完成車メーカーは、日本の7社(ダイハツ、日野自工、マツダ、日産、日産ディーゼル、いすゞ、スズキ)、韓国の3社(起亜、大宇、現代)、およびマレーシアのプロトンである。ただし、起亜とフォードとの関係は、今後の起亜の処理次第で大きく変わる可能性がある。なお、富士重工については、日産との間で資本提携、部品供給・調達関係などがあるものの、経営再建の立場から構築された関係であり、戦略的色合いが薄いことから、ここでは戦略的提携関係の対象には含めていない。
このほか、アジアでの戦略的提携関係に組み込まれていない企業として、BMW、ボルボ、ルノー、プジョー、フィアットなどの欧州完成車メーカーと、韓国のサムスンがある。これらの完成車メーカーは、いずれもアジアでの事業拡大を計画しており、今後、アジアでの戦略的提携関係に加わってくる可能性が十分にあろう。
4.アジアの自動車産業発展の方向性
アジアにおいても、戦略的提携は、事業拡大のための重要な戦略の一つとなってきた。しかし、世界からみれば、アジアの自動車産業の技術水準はまだ低く、アジアで生産される自動車の中でグローバル競争に耐えられるものは、小型車やトラックなどに限られている。完成車メーカーのグローバル戦略をみても、アジアを小型車やトラックの組み立て・輸出基地として位置づけ、そのための戦略的提携を模索しているケースが多い。
しかし、長期的な視野に立った場合、組み立て・輸出拠点としてだけでは、自動車産業の発展には限界がある。現在、アジアでの事業展開している完成車メーカーの多くは、設計・開発部門を先進国に設置している。完成車メーカーが多数アジアに進出することによって競争原理が働き、アジアの自動車産業の技術水準が向上したとしても、設計・開発部門がアジアで発達しない限り、アジアの自動車産業の先進国の水準に追いつくことは困難であろう。
グローバル規模で進む業界再編の流れの中で、アジアの自動車産業が生き残っていくためには、小型車、トラックの組み立て・輸出拠点としての比較優位を生かすことも一つの方法であろう。しかし、アジアの自動車産業の底上げという点からすれば、将来的には、アジアの自動車産業が組み立て・輸出拠点以上の役割を担うことが望まれる。アジア自動車産業の発展は、戦略的提携関係の中核となる完成車メーカーが、今後、グローバル戦略の中でアジアをどのように位置づけるかにかかっている。
おわりに
欧米完成車メーカーがアジアを注視しつつ戦略的提携を活発化してきている中で、日本の完成車メーカーも、これまでにない大きな戦略転換を迫られている。日本の完成車メーカーとの提携を望んでいる欧米完成車メーカーは少なくないとみられており、日本の完成車メーカーにとっても、国内や海外の完成車メーカーとの戦略的提携は、もはや生き残りのために欠かせないものとなっている。
すでに戦略的提携関係に組み込まれている完成車メーカーであっても、その地位は決して安定的ではない。激化する競争の中では、戦略的提携の当事者や内容が柔軟に変わる可能性がある。メリットがなくなれば、即座に戦略的提携が解消されることもあり得る。したがって、中核メーカーはもちろん、周辺メーカーも常に世界を視野に入れつつ、相互補完に値する自社の強みに磨きをかけていなければ生き残ることはできない。
日本の完成車メーカーの中には、高度な技術や、アセアンを中心とするアジアでの大きなシェアといった強みを持つ企業も多い。それらを武器に、海外完成車メーカーとの戦略的提携を有利に進めていくことも可能であろう。
今後、日本の完成車メーカーを巻き込んで、世界の自動車業界再編が加速すると予想されるなか、日本の完成車メーカーのグローバル戦略の真価が問われることになりそうだ。
注
- アセアンの自動車市場の最近の動向については、本誌p.22掲載の森美奈子「新たな動きをみせる日系自動車部品メーカーのアセアン戦略」参照。
- 98年2月23日付け「日本経済新聞」。
- 98年1月16日付け「日刊自動車新聞」。
- 98年10月13日付け「The Korea Herald」(ロイター・ビジネス・ブリーフィング)。
- 98年9月18日付け「日経産業新聞」。
- 98年9月17日付け「毎日新聞」。
- 藤本隆宏(1998)、『世界週報』(1998)。
- 98年9月17日付け「朝日新聞」。
主要参考文献
- 藤本隆宏、キム・B・クラーク(1993)『製品開発力』ダイヤモンド社 1993年
- 藤本隆宏、武石彰(1994)『自動車産業21世紀へのシナリオ』生産性出版 1994年
- 藤本隆宏「超大型合併で探る『世界で10社生き残り』説の真贋」(『週刊エコノミスト』98年6月16日号 所収)
- 国領二郎(1995)『オープン・ネットワーク経営』日本経済新聞社 1995年
- 日本興業銀行「メガコンペティション時代入りした自動車産業」(『興銀調査』1997年No.5、280号 所収)
- 「自力の投資なしで総合自動車メーカーに-ダイムラー」(『世界週報』98年6月9日号 所収)
- 「D-BenzがChryslerとの合併でめざす世界フルラインメーカーとしての生き残り」( FOURIN 『自動車調査月報』 1998年6月号
所収)

