Sohatsu Eyes
公共サービス提供の改革 -2/5:全5回 -
2003年06月24日 古澤 靖久
PPP担当マネージャーの古澤です。
前回は、公共サービスの提供の担い手として、市民から見た際に「最もValue for Money(バリュー・フォー・マネー;以下では「VFM」と標記します。)を達成できる代理人は誰か?」という問いが大事だ、ということをお話ししました。
では、ここでいうVFMとはなんでしょうか?簡単に言えば「費用対効果」のことです。すなわち、同じ税金という費用を投入して得られる効果を最大限にする、あるいは同じ効果を得る費用を最小限にする、という考え方です。しかし、費用対効果の比較といっても、ただ観念的に言っているだけでは、上記の図表に示すようになかなか容易ではありません(代替案1と2の比較はわかりやすいですが、代替案1と3や4はどうやって比べれば?)。
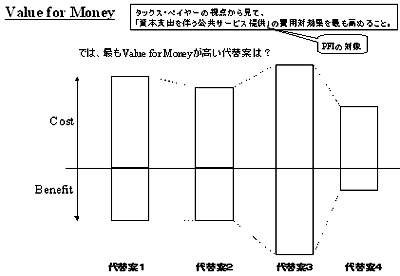
この比較問題を解決するための初期のPFIの発想は、非常にプラグマテックです。すなわち、仕様条件と契約条件を詳細に規定する等によって効果側を一定に担保することとして、費用最小化を競って貰う費用最小化問題に定式化するというものでした(最近のPPPの考え方では、ここまで単純化していないようですが、それは今後お話しすることにします)。
初期のPFIにおける考え方を、より体系的に整理しますと、最大のVFMを実現するためには、少なくとも以下の条件が最低限必要になります。
1. 公共サービス調達に伴うリスクとその分担主体を明確化する「明確な公共と民間の役割分担・リスク分担」という考え方
2. 公共は計画責任を負い、調達しようとする公共サービスのアウトプット(「what」だけ、「How」は民間)を特定し、民間が負った経営責任を果たしているかどうかを、その特定されたアウトプット指標 をモニタリングすることでみる「アウトプットの特定」(アウトプット・スペシフィケーション)という考え方
3. Value for Moneyを担保するための業績に見合った動機付けという考え方(民間の収益追求行 動を優良な公共サービスの提供に結びつけるしくみづくり)
4. Value for Moneyを担保するための「競争性の確保」
5. 設計、建設、運営などのプロジェクトのライフサイクルでの一括的な管理による効率化
これらの1.~5.もそれぞれは理念(ものの考え方)ですが、これらの考え方を具体の実務に落としていくところにPFIの真骨頂があります。すなわち、1.についてはリスク分担を契約書で規定すること、2.は仕様書を性能発注の考え方で作り込み、それと整合的なモニタリングを設計し契約書に盛り込むこと、3.は契約書における支払いメカニズムをモニタリングとリンクする形で規定すること、4.は事業者選定プロセスを競争性が高いように設計すること、といった具合です。
単なるお題目で終わらずに実務の体系として整備する、VFMの達成のための大事なポイントです。次回は、これらの実務のそれぞれについて、より具体的にお話しすることとしましょう。
※eyesは執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。

