コラム「研究員のココロ」
次世代の住宅は「プリウス」を目指す
2004年09月06日 山野泰宏
1.住宅市場の縮小傾向
昨今の厳しい経済情勢の中、住宅市場を取り巻く環境も例外でない。新設住宅着工戸数を見てみると、低金利や住宅ローン減税制度等の効果や、都心における工場跡地等のマンション適地が供給されたこともあり、ここ数年はほぼ横ばいの状況である(図1)。しかし、少子高齢化傾向、2006年がピークと言われる総人口の減少(図2)等の影響から、今後の見通しは厳しく、市場の縮小傾向は避けられないものとなっている。そういった状況の中、最近の住宅をめぐる動きの中から「情報化」「環境共生」の2点に注目し、今後の住宅の方向性について考えてみた。
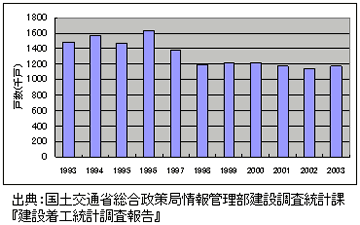
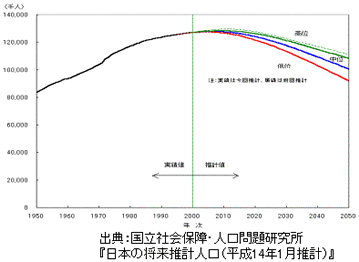
2.情報化住宅
コンピューターによって住宅や人々の生活を管理しようという研究が、公的機関や住宅・家電メーカー等を中心とする民間企業によって進められている。このような住宅では、指紋や顔による個人認証を利用したセキュリティシステム、人の体温や人数を認識し自動運転する空調システム、時々の場面や状況に応じた自動照明、などの仕組みが用意されている。
いわゆる情報化住宅といわれるもので、これらは人々に便利で快適な生活を提供する一方、環境への負荷増大、プライバシー侵害の懸念、管理されることへの抵抗感、人間の体力・思考力の低下、人工的閉鎖空間での不健康感など、様々な問題点が指摘されている。
3.環境共生住宅
一方で、地球環境になるべく負荷をかけない、クリーンでリサイクル可能なエネルギーを使った住宅の研究・開発も盛んに行われている。最近行われる住宅地開発は、程度の差こそあれ、ほとんどが何らかの形で環境への配慮を謳っている。このような街に建ち並ぶいわゆる環境共生住宅は、太陽光・風力発電、自然換気や雨水利用、生ごみコンポスト等の装置を取り入れ、環境への負荷低減を指向した住宅だ。
環境共生住宅には、消費エネルギーの削減、排出廃棄物の削減、持続可能な街づくり、健康的・自然な暮らし、何となくいいことをしたような気になること、そのほか多くのメリットがある。一方で環境に配慮した生活は、最近でこそかっこいいという価値観も認められるようになってきたが、以前は、手間がかかる、見た目が良くない、貧乏じみている等のイメージがあったのも事実だ。
4.今後の住宅の方向性
このほか、高齢化に対応したバリアフリー住宅・介護住宅、長寿命・高耐久住宅、などの動きもみられる住宅であるが、今後どういう方向に向かっていくのだろうか。その一つの解は、例えて言えば、プリウスのような形だろう。ご存知のように、プリウスとは、昨年秋に発売されたトヨタの2代目ハイブリッドカーのことであるが、この車はガソリンエンジンと蓄電池・モーターを組み合わせ、コンピューター制御することにより、従来方式のガソリンエンジン車から走行性能を落とすことなく、燃料消費量を半分以下に削減することに成功したエコ・カーである。
これからは住宅もこのプリウスのような姿になっていくのが一つの流れと考えられるだろう。すなわち、住宅に組み込まれたコンピューターが住宅や設備機器を制御し、住む人の快適性を損ねることなく、環境への負荷低減を実現するということである。もちろんこれが実現すれば、高齢者にも優しい住宅となるのはいうまでもない。地球にも優しく、そこに住む人々にも優しい生活が実現できるということである。
今はまだ、情報化も環境共生もそれぞれが別々の動きをしていたり、実験段階の域を出ない状態であるが、今後はこれらが統合され、全体として制御されていく方向に向かっていくだろう。技術の進歩と環境に対する人々の意識変化がうまくバランスしてきた、そういう環境が整ったこれからが上記したような各種の課題を克服するチャンスである。
技術の進歩が必ずしも人間の幸せにつながらないというのは世の常だが、「住宅のプリウス化」=「情報化と環境共生のハイブリッド」、という見方をしてみると、技術の進歩が人間を幸せにするような気がして、明るい気分になってきます。人工的なイメージのあった未来の生活が、潤いのある、親しみやすいものに変わってきたと思いませんか?
※コラムは執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。

