コラム「研究員のココロ」
地域自治組織
~合併論議の次にくるもの~
2004年08月16日 入山泰郎
1.地域自治組織とは何か
地方自治などの現場では今、「地域自治組織」「近隣政府」などと呼ばれるものが、静かな注目を集めている。
地域自治組織とは、地方制度調査会の答申によると「基礎自治体(市町村)内の一定の区域を単位とし、住民自治の強化や行政と住民との協働の推進などを目的とする組織」と定義されている。換言すれば、市町村より小さな(狭い)地域において、地域のことを地域自らが決め、それを実行するためにつくられる組織である。
「地域のこと」、つまり地域自らが決定し実行する事柄が何であるかは、地域により異なる。例えば、地域内の道路や水路の清掃、高齢者のケア、公共交通の確保、あるいはいわゆる「まちおこし」活動や日用品の販売など、多岐にわたる。
これらは今までは基本的には行政(特に市町村)が考え、責任を持って提供する、という傾向が強かった。それを行政に頼らず、地域自らで責任を持とうという考えが、全国各地で現れ始めたのである。
2.地域自治組織への関心が高まる背景
こうした「地域自治組織」への関心が高まっている背景には、これまで行政が半ば独占的に提供してきた公共サービスを、NPOや企業、地域コミュニティなど、多様な主体が提供すべきであるという考えが出てきたことがある。また、行政(特に市町村)の財政運営が厳しくなり、行政にすべてを依存することが事実上困難になりつつあるという点もある。
そして、市町村合併の動きがこうした傾向に拍車をかけている。いわゆる「平成の大合併」が各地で進みつつあるが、合併を選択した地域では、市町村の区域の拡大によって、地域に対する細やかな配慮を市町村が行うことは難しいという課題が出てきている。そのため、例えば、三重県の伊賀地区市町村合併協議会(2004年11月に合併予定)では小学校区(旧村)毎に「住民自治協議会」を設置することなどを検討している。
また、合併せずに「自立」を選択した地域においても、財政難を合併以外の手段で解決するために、行政が担っていたことでも地域自身が担うことによって行政のスリム化を図る必要性から、地域自治組織の検討に至るケースがみられる。例えば長野県小布施町の「自立に向けた将来ビジョン」では、地域の単位として3~5の自治会が集まった「コミュニティ地区」組織の充実や、町の財政支援のコミュニティ地区への一本化等が提言されている。
こうした動きは今春、国会に提出された「合併特例法」と「地域自治法」の改正案において、「合併特例区」と「地域自治区」という二つの制度が盛り込まれたことで、今後さらに広がっていくと考えられる。
3.既存地縁団体等との関係
地域自治組織を目指す事例は、既存の住民自治組織や地縁団体(自治会など)との関係で捉えると、大きく3種類に分けられる。
第一に、既存組織と併設される形で新たに地域自治組織が設置される「併設型」である。既存組織はこれまでのしがらみ等もあって、簡単にその役割を終わらせることはできない。かといって、新たに期待したい役割を既存の組織に押しつけるのは無理がある。そうしたことから、既存組織はそのまま生かしながら、新たな組織をつくるものである。例えば、熊本県宮原町の「まちづくり情報銀行」の各支店などがこれにあたる。
第二に、既存組織を包摂する形で新たに地域自治組織が設置される「包摂型」である。既に地域には自治会等の自治組織だけではなく、婦人会、老人クラブ、学校のPTA、それに各種のまちづくり団体など、多くの組織が存在する場合が多い。そうした組織の連絡会議的なもの、あるいはそれが発展してそれらを包摂した一つの団体が設置される場合である。例えば、広島県神石町の永野地区における「ながの村」はそうした事例の一つである。
第三に、既存の地縁団体より広い単位で、新たに自治組織あるいは連絡会議的なものを設置する「階層型」である。これまで行政が行っていたものを地域に還元するとしても、既存の地縁団体では規模が小さすぎて、それを担うのは困難である場合が多い。そのために、もう少し規模の大きな組織として新たな組織が設立されるのである。例えば、兵庫県宝塚市の「まちづくり協議会」(小学校区単位)や「ブロック別まちづくり連絡会議(地域創造会議)」(人口3~4万人単位)がそれに近い。宝塚市では、既存の「自治会」(200~300世帯)とあわせ、地域自治の組織が3段階で設置されている。
なお、こうした類型は相互に排他的なものではなく、例えば包摂型の地域自治組織を設置した上で、階層的に広域の地域自治組織を設置するといったことも考えられる。
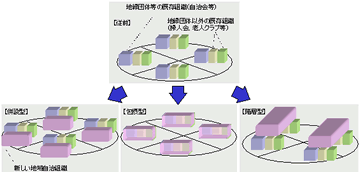
4.検討が必要な課題
最後に、今後、地域自治組織を検討していくにあたってのポイントをまとめておこう。
第一に、地域自治組織が何を行う組織にするか。上述したように地域自治組織が行う事柄は、様々なものが考えられる。地域の事情に応じて、地域自治組織の役割、市町村との役割分担を考慮しなければならない。
第二に、地域自治組織と行政の関係をどうするか。これは行政側に地域担当職員をいかに配置するかや、行政の支所との関係が鍵となりそうである。前者については岩手県藤沢町の取り組み、後者については、区役所に「まちづくり推進部」、学校区毎に「市民福祉センター」を設置している北九州市の事例などが参考になる。
第三に、上記の地域自治組織と行政の関係にも関連するが、地域自治組織の財源をどうするか。小布施町の事例でも言及したように、行政から地縁団体等への補助金等をどのように整理するかも含めて、検討する必要があるだろう。広島県安芸高田市に設置されている「地域振興会」では、行政からの助成に加えて、住民の会費や香典返しの一部などを財源に充てている。こうした事例も参考になる。
第四に、既存の地縁団体等との関係をどのようにするか。上述したように、既存団体とは別途、地域自治組織を設置するケースも、既存団体を吸収する形で地域自治組織を設置するケースもあり得る。
第五に、地域自治組織内の政策決定をどのように行うか。上述の「合併特例区」や「地域自治区」では「協議会」や「長」の設置について、それぞれ法律で定められているが、そうした制度に則るのか、独自の決定方式をとるのか、検討しなければならない。
以上で紹介した事例でも分かるように、地域自治組織やそれに類する試みは、政令指定都市から過疎地域の町村まで、市町村の規模を問わずに模索されていると言っても過言ではない。地域や市町村の実状に応じた地域自治組織の検討が、求められているのである。
参考文献:
地方制度調査会(第27次)「今後の地方自治制度のあり方に関する答申」2003年
国土交通省国土計画局監修、多様な主体による地域づくり戦略研究会『地域からの日本再生シナリオ(試論)~市民自治を基礎に置く戦略的地域経営の確立に向けて~』2004年
※コラムは執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。

