コラム「研究員のココロ」
雇用延長にどう対応するか
2004年07月20日 林 浩二
公的年金の支給開始年齢の引上げに呼応して、定年引上げまたは継続雇用制度の導入義務化等を内容とする高齢者雇用安定法の改正が先の通常国会で行われた。改正法案によれば、企業は段階的に、(1)65歳までの定年の引上げ、(2)65歳までの継続雇用制度の導入、(3)定年の廃止、のいずれかの措置を講ずる必要がある。本格的な少子高齢化社会に突入し、数年後には団塊の世代が60歳に到達し始めるなか、この問題への対応の巧拙は企業の競争力をも左右しかねない。
今回の改正の大きな特徴は、65歳までの雇用延長策について、上記(1)~(3)の複数オプションが提示されている点である。すなわち、必ずしも定年の引上げが求められるわけではなく、継続雇用制度の導入でもよい。1994年に60歳定年が義務付けられたときには、たとえば「55歳定年、60歳まで再雇用」では違法であり、定年を設けるのであれば「60歳(以上)定年」とする以外選択の余地はなかった。そこで、今回、企業にとっては、自社の従業員構成や経営環境を踏まえて戦略的にオプションを選択し、自社に適合度の高い雇用延長制度を設計することが重要になる。その検討に際して鍵となるのは、「高齢人材の活用意欲」と「人事賃金制度」である。
まず、「高齢人材の活用意欲」であるが、60歳以降も引き続き正社員として従来どおりの仕事で従来どおりの活躍を期待するのであれば、『(1)定年引上げ』を選択すべきである。すなわち、高齢人材の活用に積極的な場合である。一方、技能の陳腐化等の理由により高齢者の活躍余地が限られている場合など、高齢人材の活用に消極的か、少なくとも積極的にはなれない場合には、『(2)継続雇用制度の導入』が基本的選択肢となろう。『(3)定年の廃止』は、小規模企業など個別の退職管理が可能な場合を除き、現実的な選択肢としてはなかなか浮上してこない思われるが、加齢と成果との相関が無視できるような職務で、企業としても高齢人材の活用に積極的な場合には検討の余地もある。
次に、「人事賃金制度」であるが、自社の人事賃金制度が成果主義的であれば、そもそも勤続年数の増加は人件費負担の増加にダイレクトには跳ね返らない仕組となっているはずである。年齢や勤続年数が長くても成果が上がらなければ昇進・昇格はなく、したがって賃金も上がらない。こうした制度の下では、『(1)定年の引上げ』や、極端な場合には『(3)定年の廃止』を行っても、少なくとも人件費コストという面では、深刻な問題は生じないはずである。一方、人事賃金制度が年功的色彩を色濃く残している場合には、勤続年数の増加は直ちに人件費の増大につながる可能性が高く、雇用延長への対応して、定年は60歳としたまま新たな労働条件を設定して定年後再雇用する『(2)継続雇用制度の導入』の選択が基本となると思われる。
以上を整理すると、下図のようになる。ただし、ここで注意しなければならないのは、下図の縦軸及び横軸は不変の条件ではないということである。縦軸(高齢者の活用意欲)についていえば、「人生80年時代」を迎え、高齢化は今後ますます進むことが確実である。こうした中、高齢者活用を推進することはむしろ企業の社会的責任と考える経営者も多いだろう。また、高齢者の活用余地がないというのは単に思い込みに過ぎず、技術・技能の継承や豊富な経験を活かした顧客関係構築など、工夫すれば直接的・間接的に企業利益に大きく貢献してもらえる仕事がいくらでも存在するかもしれない。このように高齢人材の活用意欲というのは、企業の考え方次第で変わってくる。
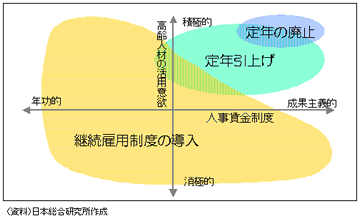
ただし、いくら高齢人材の活用意欲が高まっても、横軸(人事賃金制度)の問題は残る。経営者としては、年功賃金のままでは、定年の引上げや廃止は人件費負担の面からみて導入しがたいだろう。このような場合、定年の引上げと人事賃金制度改革をセットで進めるしかない。要は、年齢ではなく能力や成果に基づく処遇を行うことができるか否かが鍵となる。
いずれにせよ、「高齢化待ったなし」の今、今回の高齢者雇用安定法の改正を期に、自社の高齢人材マネジメントのあり方を構想し、自社に適合的な形で制度を構築していくことが重要である。その際、短期的なコスト・ベネフィットを考えることのみならず、中長期をも見据えた制度設計が求められるのである。
※コラムは執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。

