コラム「研究員のココロ」
行政評価と行政コスト
2003年11月11日 井上 研司
1.行政評価とコスト情報
行政評価が実施される上で、コスト情報の重要性は、思った以上に高い。もちろん満足度などパフォーマンス(業績)の測定も重要であるし、それらを指標化することも大切だが、財源が不足する自治体にとっては、いかに財源を効率的に利用するかが大きな課題となっている。総務省自治行政局が実施している調査によると平成14年度における行政評価の導入済み・試行中・検討中の自治体数は、次のようになっている。
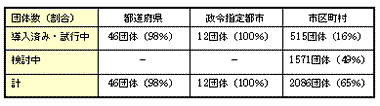
出典:総務省 平成14年度地方公共団体における行政評価についての研究会報告
市区町村でも6割以上の自治体が行政評価に関心を示しているが、多くは「検討中」の段階である。検討中の自治体の割合は、平成12年度から平成14年度まで3年間4割台後半で推移している。導入あるいは試行中の団体数は、合わせて19.5%、515団体である。
行政評価とバランスシートや行政コスト計算書の関係は、これら財務諸表の導入の初期の段階から議論されてきた。しかし、現状では、行政コスト計算書など財務諸表は、財務諸表としてだけ存在し、行政評価の際にこれらがリンクして検討されることは少ないようである。行政コスト計算書について総務省の研究会から報告書が出されたのが平成13年3月。作成はしたもののどのように使ってよいのかわからないという自治体も多いはずである。一方で、バランスシートは多くの自治体が作成したものの利用価値が見出せなかったことから行政コスト計算書の作成には至っていないという自治体もあるのではないか。
一方、行政評価は複雑で、指標のひとつとしてのコストの取り扱いもその複雑さの中にあいまいなまま埋没しがちである。
行政評価の各種指標の中でより客観的で、各事業間で比較可能な数値情報がコスト情報である。行政評価の事例を見ていると、たいした効果がないように思える事業でも、低コストで、この費用でこれだけのサービスができるなら、重要性が低いからと廃止することもないように思う事業がある一方、重要性が高く、当然コストもかかっているのだが、思った以上の高コスト体質に唖然とさせられる例もある。
各事業のコストは、いくつかの費用からなっているが、費用をどこまで集計するかで、評価が大きくかわってくる。事業費は当然として、人件費などその他にかかっている費用をどう処理すればよいであろうか。行政コスト計算書でのコストの分類を手がかりに、行政評価上のコストの取り扱いについて見てみたい。行政コスト計算書の性質別経費は、次のように分類される。
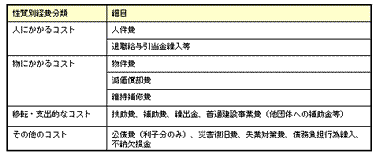
2.人にかかるコスト
行政コスト計算書を見ると、普通会計を対象に教育費、土木費、農林水産費、商工費などの項目に分けた上で、それを上記の性質別分類で整理している例が多い。行政評価というのは、上記の商工費などをさらに細分化した単位で評価しているものと考えられる。人にかかるコストから見ていきたい。
(1)人件費、退職給与引当金繰入等
行政評価では、細部にこだわらずとりあえず人件費を事業費に計上することからはじめるとよい。これだけでも多くのことがわかる。事業費は少ない事業でも、労力のかかる事業の場合、普通に考えると人件費がたくさんかかっているはずである。人件費の集計は、効率性を把握するまず第一歩だ。公務員人事制度が取りざたされているが、とりあえず一旦事業ごとに集計し、検討することが、人事制度を改革する場合でも第一歩なのではないか。
退職給与については、行政コスト計算書とは異なり、必ずしも最初から議論すべき項目ではないであろう。人件費の計上にコンセンサスが得られた段階で、退職金も含めたコストを計算してみるとよいのではないか。
(2)間接人件費
行政評価上のコストと行政コスト計算書の違いで大きいのは、各コストについて直接費と間接費に区分する必要がある点である。事務事業の評価のレベルで考えよう。
このレベルでの間接費とはたとえば、管理職や間接部門の「人にかかるコスト」である。各事業への管理職のコストは、各担当者の投入した労働時間などの割合で按分すればとりあえずはよいが、多くの管理職を抱えているとそれだけで評価が下がることになる。総務や財政部門のコストも、民間企業的には当然配分される。しかし、配分の基準の決定は、困難な場合もあり事務事業のレベルなどでは配分しないで、上位の施策評価のレベルで配分するなどの方が評価が妥当な場合も考えられる。
3.物にかかるコスト
(1)間接物件費
物にかかるコストでも課題となるのは、間接費であろう。
たとえば庁舎の電気代等光熱費も間接費である。これらは通常施設ごとに集計されるが、施設管理上、これらを考慮して施設ごとのコスト分析に利用すると施設の運営がどのような費用構造になっているかがわかって事業の特性が見えやすい。行政評価上、施設単位での評価があってもよい。
(2)減価償却費、投資的経費
行政評価上投資的経費の取り扱いは、その目的によって取り扱いは様々であろう。ここでは過去の支出である「減価償却費」のことを中心に考えてみよう。会計とは、過去の原価を将来に配分するという特質をもつが、この手続きのことを減価償却という。事業評価上は、建設事業費そのものを評価の対象とすることが必要な場合もあるし、減価償却の発想が必ず必要というわけではない。この点が行政コスト計算書とは大きく異なる点である。
行政コスト計算書に計上されないこれら投資的経費はどこに行くかというとバランスシートに計上されている。そして、将来のコストとして、行政コスト計算書に計上される。行政評価上も、投資プロジェクトを評価するのではなく、投資プロジェクトが完成し運用が始まってからコストを評価すると考えるなら、投資的経費は一旦バランスシートに計上すべき数値として、一旦棚上げし、その後運用期間にわたって行政評価上コストとして認識すればよい。この考え方は、行政コスト計算書の構造とも整合的で理解しやすいであろう。
その他のコストとして扱われる公債費も、実際、公債等によって資金が賄われている場合に、行政評価上、該当する投資に見合った負債に関する費用と資金が、年々のこの投資に対する費用(支出)と考えることも可能である。
3.発生主義と現金主義
ここまで、実際に行政評価等を通じて感じたことなどを行政コスト計算書との関連で考えてみた。コストという視点で問題を整理する場合基本になるのが、発生主義と現金主義の違いである。
6月に、財務省から「公会計に関する基本的考え方」という報告書が出ている。行政評価や、インフラの管理を目的とした様々な取り組みをする上で再度、発生主義という会計の原則に立ち戻ってみることが大切だとつくづく考えさせられる内容であった。国と地方自治体の会計は違うということを念頭に於いて、再度、原点に立ち返って整理されるとよいと思う。このなかでは、発生主義予算という少し進んだテーマも含めて公会計の意義について整理している。
報告書 http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/top.htm
参考資料 http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/top.htm
参考資料も興味深い内容を含みます。

