コラム「研究員のココロ」
自治体合併におけるIT統合マネジメント
2002年06月24日 柿崎平
平成の大合併'が進んでいる。現在、668の市町村が合併協議会を設置。研究会を含めると、全国の市町村の約70%にあたる2,226の市町村が合併を検討中である(平成14年4月1日現在)。言うまでもなく、国の合併特例法の期限となる2005年3月を目指した動きである。
ますます深刻化する財政状況、予想される地方交付税交付金の減少等々を勘案すれば、国主導の色彩が強いとはいえ、各市町村にとって合併が有力な改革手段の一つであることは間違いない。大きなメリットは確かにある。しかし、そのメリットを実際に手にできるかどうかは、どのようなビジョンや構想をもって、どのようなプロセスで合併し、そして合併後の新自治体を経営していくかにつきる。
ここでは、一例として、'政治的な決着'といわれるもので決められる傾向が強い、「合併に向けた情報システム統合の進め方」を挙げたい。
もはや、ITは自治体の事務手続きと表裏一体のものとなっていることは周知の事実である。そうであれば、合併後のITをどのようにするかという問題は、合併後の事務運営、組織運営、さらには経営システムをどのように設計するか、という問題に等しいという点も多くの人が理解するところだ。それほど重要な位置付けにあるはずのITなのだが、実際の合併協議のなかでは、残念ながら、十分な検討がなされているとはいえない。以下に、いくつかの側面から、その課題を指摘する。
1.検討スケジュール
これまでの事例の分析結果では、検討期間の不足が大きな課題となっているケースが多い。合併を経験した自治体の担当者の間では、「検討期間として2年間はほしかった」という声が多い。近年の事例では、任意協議会の設置から数えれば、平均で約2.5年の検討期間がある。
しかし、その時点では、合併そのものが流動的であるため(合併期日も決定されていない)、ある種の牽制や警戒心が相互に働き、実のある調整ができないのが実態である。合併期日が決定され、合併に向けて正式に動き出すのが合併期日のおよそ1年前というのが従来の平均的パターンであり、システム統合の作業も実質的にはそこからスタートする形になっている。その結果、現状の情報システムの十分な評価や、合併後のあるべきシステム構成・運用形態等を構想する時間はきわめて制限され、その場しのぎの統合作業となりがちである。
◎対応の方向性
任意協議会の時点で、「システム統合の方針及びスケジュール案(合併前、合併時、合併後)を打ち出すことで、必要な作業工程をトップレベルも含めて共有する。そのためには、合併市町村のトップレベルでの信頼関係が前提となる。
法定協議会の設置そのものを、できるだけ前倒しすることで正式な調整に入れる環境を作る。
統合スケジュールをおよそ1年間と考え、その中で確実に出来る統合範囲、合併時点での統合が不可欠なシステム範囲を予め明確化し合意しておく。
2.検討体制
システム統合の検討をどのような体制で進めるかという点も極めて重要である。通常は、合併協議会全体の中で、システム統合は図1のような位置付けを占めることになる。ここでのポイントは、実務に通じた事務部会(係長レベル)や分科会(課長レベル)での検討内容が適切に、専門部会や幹事会にあげられ、重要な意思決定がタイミングよく下されることである。
一般に、「情報システムの問題は専門家に任せておけばよい」といった間違った考えを上層部が持っているケースが多く、必ずしも明確な方針の決定が無いままに、実務レベルだけで細かな検討が進められる傾向がある。
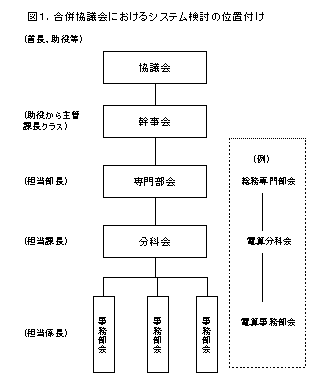
◎対応の方向性
上層部が適切な意思決定を下すためには、情報システムに通じた幹部(CIO=首席情報官など)の存在が必要になる。しかし、こうした人材は、性急に育成できるものではなく、それまでの各自治体におけるITマネジメントのあり方が問われることになる。合併時の対応策というよりは、「通常のITマネジメント体制の強化」をしていかねばならないということである。
CIO等が存在しない場合でも、システム統合の重大性や困難性を上層部に分かりやすく説明し、上層部には、危機管理(リスクマネジメント)の一項目であることを認識してもらうことが肝要である。これを出来るだけ早い段階で行うことで、その後の作業を円滑化することができる。
また、システム統合プロジェクトそのものの体制構築においては次の諸点に留意することが大切である(図2体制案を参照)。
プロジェクト全体の責任者、意思決定方法を明確化しておくこと。すなわち、「だれが、どの時点で、何を決めなければならないのか」を事前に十分に洗い出し、その決め方を決定しておくこと。(この作業は現実にはかなり難しい作業となる)
プロジェクトマネジメントを専門に行うチームを設けること。電算課等のシステム関係職員のみならず、政策/業務面を統括する企画課等の職員を入れること。さらには、中立的な立場から助言を投じる外部専門機関コンサルタント等を上手く活用すること。
ユーザー部門(事業担当課)の協力を得るため、システム統合連絡会委員(仮称)には、各事業門の責任者クラスを任命するとともに、個別システムの統合検討チームには、各事業担当課職員も組み入れること。
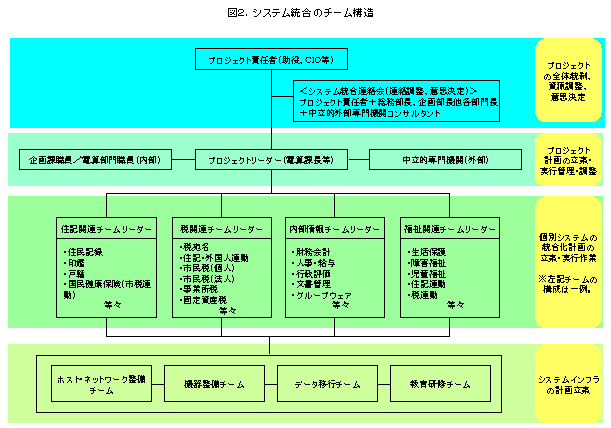
3.ベンダーマネジメント
システム統合を成功させるための重要な関係者の1つがベンダーである。自治体によっては、情報システムの開発はもとより、その運用までを大部分ベンダーに依頼している場合もある。合併する自治体の既存ベンダーが1社である場合は問題ないが、複数ベンダーが存在する場合は、必要な協力体制を早い段階で得ることが重要である。そのためには、以下の点に留意する必要がある。
ベンダーをパートナーとして捉え、情報共有を図ること。
既存のシステムを公正に評価した上で、統合化の方針を描き、ベンダーへの協力要請事項を明確化すること(既存システムの評価には、第三者専門機関の活用が望ましい場合がある)
4.システム統合化費用の負担方法
合併のシステム統合に際して必要となる費用の手当て、および負担方法(配分方法)を予め合意しておく必要がある。方法はさまざまであるが、以下のような方式が考えられる(事例より)。
住民数の比率に応じて負担。
全費用の一定割合を均等割りした後、残部分を住民数比率に応じて負担。

