| 2005年05月24日 |
| 量的緩和の「修正」をどうみるか |
|
日銀は金融調節方針において「目標残高の下振れ」を容認。 当面の市場金利への影響は限られる見込み。 |
| 日銀は、20日開催した金融政策決定会合において、「30~35兆円程度」としている当座預金残高目標の据え置きを決
定。ただし、金融調節方針のディレクティブにおいて「資金供給に対する金融機関の応札状況などから資金需要が極めて弱いと判断される場合には、上記目標を
下回ることがありうるものとする」として、「目標下振れ容認」の「なお書き」を追加した。なお、同会合において提起された「目標残高を27~32兆円に引
き下げる」との提案は「2:7」の反対多数で否決された。 今回の「なお書き」追加は、金融システム不安の後退で金融機関の予備的な資金需要が後退するなか、日銀の資金供給オペへの応札が予定額に満たない「札割れ」が頻発し、残高目標の維持が困難化していることに対応した措置。 「残高目標引き下げ」も方法論としてはあり得たが、昨年1月に現行レンジへの「目標引き上げ」を決めた際に「金融緩和の強化」と説明してきた経緯があり、 従来と逆方向への動きが「金融引き締めへの転換」と受け取られることを警戒したとみられる。今回の措置は、「所要準備額を大幅に上回る潤沢な資金供給」と いう量的緩和の枠組みのなかで、実質的な「量の目標水準」を変えることなく、その達成方法に幅を持たせたに過ぎず、基本的にわが国の「超」金融緩和状態に 変化は生じない。 予想される市場への影響については、日銀が資金供給の困難化を克服すべく増やしてきた「比較的長期間の資金供給オペ」 を実施する誘因が低下する分、ターム物金利のイールドカーブにおいて長めのゾーンのフラット化圧力が後退し、その部分で金利上昇ないし低下抑制に作用する 可能性はある。ただし、長期金利を含め、期間が長めの金利はそれ以上に景況感や量的緩和の持続期間に関する市場の期待に左右される部分が大きく、今後の動 きは実体経済の展開次第と言える。 この点に関し、17日発表されたわが国1~3月期実質GDPは、前期比年率+5.3%と事前予想を大幅に上回 る伸びを示したが、①個人消費の好調には昨年後半の天候不順や自然災害で押し下げられた反動が含まれる、②輸出は全体の半分弱を占めるアジア向けの停滞を 主因に13四半期ぶりの減少、③在庫投資の増加にも「意図せざる在庫増」が含まれている模様である等、額面通りには受け取れない内容であった。先行きも従 来の「一進一退」「強弱混在」といった景気状況からの早急な脱却は見込み難く(詳細は、「マーケット・ウォッチ No.3 2005~06年度改定見通し」をご参照)、長期金利もそうした冴えない景気展開を映じて1%台前半を中心とした推移が続くと予想される。 |
|
(図表1-1) 日銀の金融調節方針(5月20日決定)
|
(図表1-2) 福井日銀総裁会見(5月20日)
|
|
(図表1-3)日銀による手形買いオペの実績(2004年1月以降) 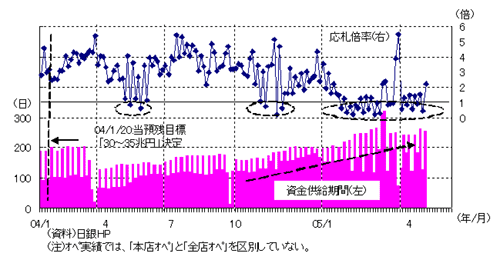 |
|
当面の当預残は「均して33兆円」が基本線。ただし、今回の措置が、 結果的に「目標レンジ引き下げへの地均し」となる可能性も否定できず。 |
| もっとも、「目標下振れ容認」自体は事前の観測報道等で予期された内容とは言え、その際にセットで想定された「月中平均で目標レンジ内の残高を維持」等の「縛り」が設けられなかった点には、やや意外感がある。穿った見方をすれば、これは「目標残高下振れ」のトラックレコードが徐々に積み上がるなかで、それを既成事実として将来の「事後追認的な目標レンジ引き下げ」に動く道筋を開いた、と解釈することも可能。 この点に関し、福井日銀総裁は会合後の会見で、「目標の下限を割るといっても、無制限にではなく、極力短期的に元に戻す」、「通常は30~35兆円程度。一時的に下限を下回ることを除けば、33兆円を中心とした調節を結果としてできる」と、上記のような憶測にクギを刺す発言をしている。しかし、その通りであったとしても、そうした内容をディレクティブに明記しなかったことが、疑心暗鬼を残す恐れがある。 そもそも、量的緩和解除の具体的プロセスについて日銀と市場の間に明確なコンセンサスがなく、今回の「微修正」も事前に各方面の十分な理解が得られたとは言い難い状況であったことは、市場の金融政策に関する期待形成が不安定化するリスクを残したままであると言える。今後「目標下限割れ」が頻発したり、予想外に景気が力強さ増すような局面があれば、福井総裁の意に反して「早期解除観測」が浮上し、市場で波乱が生じる可能性も完全には排除できない。 |
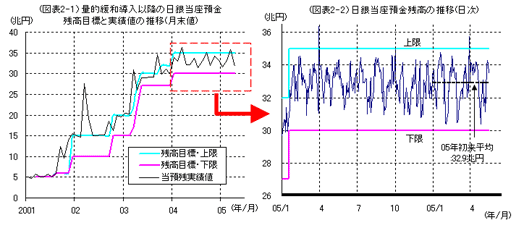 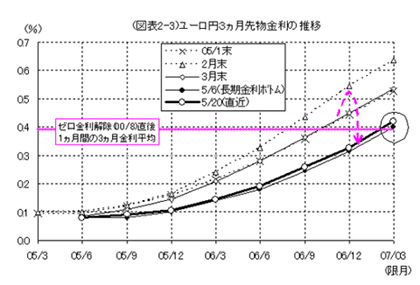 |

