コラム「研究員のココロ」
コンピテンシーによる行政改革の実現を
2003年03月24日 山中 俊之
現在人事マネジメントの分野で活用が進むコンピテンシーとは、業績が高いとされる職員の行動パターンを分類・類型化して記述したものである。
従来の能力が潜在的な保有能力に焦点が当たっていたのに対して、コンピテンシーにおいては実際の行動や成果につながる発揮された能力に焦点があたっていることが特色である。現在コンピテンシーは、多くの日本企業の人事制度において活用されており、その実効性が証明されている。
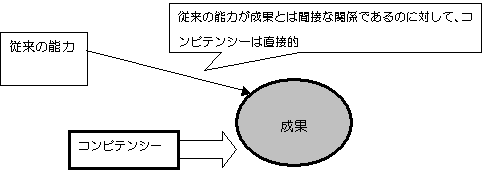
筆者は、このコンピテンシーは業績を数値化しにくい行政において大変に活用度が高いと考えている。事実、最近になって多くの行政機関からコンピテンシー型人事モデル構築に関する相談が寄せられている。
具体的な活用方法として以下のものが考えられる。
(1)人材像の明確化
現在議論されている多くの公務員の人材像は、
①その職種や職位、部門を考慮しないものであり、抽象的である。
②潜在的能力に焦点が当てられており、発揮能力や行動に対する配慮が小さい。
③行政が本来目指すべき成果とのリンクが弱い。
といった欠点を抱えていた。
コンピテンシーは、上記の欠点を補うものであり、公務員制度改革の出発点といえる公務員の人材像を具体的に行政の成果とリンクさせた形で明確化することに資するものと考えられる。
(2)能力等級制度への活用
上記の人材像におけるコンピテンシーは、今後整備される能力等級制度への活用が可能である。能力等級制度においては、各能力等級における能力要件が必須である。この要件については、従来型の潜在能力ではなく、発揮能力(行動特性)を基に記述することが行政における成果の向上の観点から望ましい。
その場合、一つの等級において単一の能力要件であれば、複雑化した行政の現状に対応できない。複数のカテゴリーの能力要件を定立することが重要である。
(3)コンピテンシーを活用した評価制度
定量的な目標を掲げることが困難な場合が多い行政においては、コンピテンシーを評価項目として活用することが効果的である。
具体的には、前述した能力等級における各等級の要件定義をもとに、職種及び部門を考慮して、コンピテンシーの評価項目(定義及びレベル)を作成する。
この際、考慮すべき点は以下の点である。
第一に、部門別(局や部の段階)に分けることは必要であるが、課レベルにまでわけることは、コンピテンシーが細かくなりすぎて運用に困難をきたすので避けるべきである。課レベルの場合、具体的な知識やスキルの問題として、コンピテンシーとは別途の要件とした方が運用としては容易である。
第二に、具体的なコンピテンシーの選択にあたっては、各部署(課の段階)の選択の余地を残すことである。これは、NPMにおける人事権限委譲の考えと通じる。目標管理の目標設定を基本的には各部署にまで委譲するのと同様コンピテンシーについても委譲することが望ましい。
(4)コンピテンシーを活用した適材適所の実現
人材配置においてもコンピテンシーを活用することで、現在よりも容易に人材配置を実現できる。
具体的には、各職員のコンピテンシー評価結果、職員の希望、蓄積された経験・知識を基に人材シート(キャリアディベロップメントシートと呼んでもよい)を作成する。この人材シートと各部署において必要とされる人材の人数(行政評価から導き出される)をマッチングさせる。
(5)コンピテンシーを用いた能力開発
コンピテンシーを基にした能力開発プログラムの策定も重要である。
上記のコンピテンシー評価結果と本人の希望を実現するために必要とされるコンピテンシーのギャップを埋めるための能力開発プログラムを策定して、OJTを中心に能力開発に努めることが重要である。
(6)コンピテンシーを活用した外部人材の登用
今後の行政は、内部の純粋培養の職員だけでは、複雑化高度化した国民のニーズにこたえることができない。民間人などの外部者を登用することが不可欠である。
その場合、コンピテンシーを活用して、必要とされる人材のスペックを明確化して、登用することにより、より的確な任在が確保できる。

