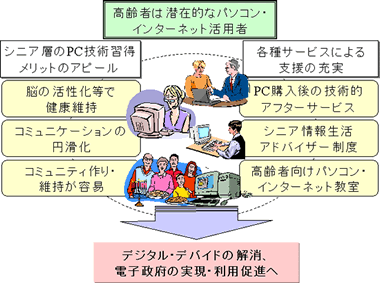コラム「研究員のココロ」
パソコン初心者のシニアユーザーの獲得には、使い方や活用方法の支援がポイント!
~デジタル・デバイド解消へ向けた取組み~
2001年10月22日 矢ヶ崎 紀子
パソコンやインターネット利用のターゲットとしてシニア層が注目されて久しいが、メーカーやプロバイダーの思惑通りには利用が進まないのが現状である。そんな中で、最近、シニア層にパソコンの使い方や活用方法を教えるサービスが定着しつつある。
イータイピング株式会社(名古屋市名東区)では、50歳以上のパソコン初心者を対象とした雑誌「暮らしとパソコン」を出版するソフトバンクパブリッシング株式会社(東京都港区)と提携して、パソコン初心者向け「キーボード練習」の無料サービスを開始した。「暮らしとパソコン」のウェブサイトを訪れると、基本練習・初級練習・実践練習の3つのレベルで、自分のペースにあわせてキーボード入力の練習ができるようになっている。使いやすい画面構成で、「あせらず、ゆっくり、正確に」等のメッセージがある。試しに、基本練習にトライしてみたが、なかなか難しい。「実は基本というのはとても難しいですよ。」とのコメントに、思わず頷く。
アメリカではネット人口の2割が50歳以上のシニアであると言われている。米DELL Computerがスポンサーとなって実施した調査(Bruskin Goldring Researchが実施)によると、55歳以上のパソコン・ユーザーには、「インターネット・アクセスのためにパソコンを利用している人が多いが、優れた技術サービスが受けられるならば、もっと進んだ利用方法に挑戦してみたい」、あるいは、「アフターサービスが受けられるなら、新しくパソコンを購入してもよい」と考えている人が多くなっている。つまり、コンピュータやインターネットに詳しい誰かがきちんと面倒をみてくれるなら、パソコンを新規購入したり、もっと進んだ機種等を購入したりしてもいいと考えているシニア層が多いのである。
ひるがえって、わが国では、まだシニア層のパソコンやインターネット利用は発展途上の状態である。株式会社日本総合研究所が実施した「ネット革命時代のアクティブシニア向けサービスのあり方」の調査結果によると、1999年12月時点では、首都圏在住で50歳以上の男女のパソコン利用率は8.6%、同インターネット利用率は2.9%であった。利用率は未だに低いものの、パソコン、インターネットとも、未利用者の半数以上は高い利用意向をもっている。また、パソコンやインターネットの未利用者が利用しない主な理由は、使い方が難しいことである。
わが国のシニアは、今後パソコンやインターネットの利用者となる可能性が高い層であるといえよう。では、シニアの「使い方が難しい」という声をどのようにクリアしていくのか。
シニアがパソコン技術を習得するための支援は、行政によっても既に着手されている。経済産業省が提唱するメロウ・ソサエティ(円熟社会)構想の推進団体であるメロウ・ソサエティ・フォーラムでは、シニア情報生活アドバイザー制度を実施している。また、身近な郵便局では「高齢者等パソコン教室」を開催しており、受講者が終了後に「パソコン教室友の会」等の自主サークルを結成して仲間づくりをしている。さらに、長寿社会文化協会等の高齢者を対象としたNPOでも、ワープロ・パソコン・インターネットをゆっくりと学びあう教室を開催している。
学生や社会人は、日々の勉強や業務上の必要性や自分の興味から、パソコンをどのように活用するかについてのイメージをもっている。一方、退職後のシニア層には、このような明確な動機がない場合が多い。しかし、シニア層がパソコンやインターネットを活用する意義は大きいのである。まず、指先を使うキーボード操作によって脳の活性化が図られるといった健康維持上の理由があげられる。また、ゲーム世代である孫とのコミュニケーションも広がる。電子メールやデジタル映像のやりとりは、離れて暮らす子ども夫婦や孫とのコミュニケーションを円滑化する。そして、パソコン教室や、電子メールの交換によって、仲間づくりも可能となる。つまり、パソコンやインターネットの利用は、シニア層が家族・親族や共通の目的をもったコミュニティとの絆を維持するうえで、大きな役割を果たすことが期待されるのである。
このようなインフォーマルなレベルでの効果とともに、昨今の電子政府・電子自治体化の流れのなかで、シニア層が取り残されないようにすることにも効果が期待できる。シニア層は、保健・福祉施策の主要な利用者であり役所での書類手続きが他の世代よりも多く必要となるが、パソコンやインターネットの利用が他の世代よりも低いため、デジタル・ディバイドが生じやすい層である。特に、福祉関連手当等の申請主義の施策に関しては、申請方法において不利益を被る層がないように、権利擁護の観点からも対策が講じられる必要がある。
潜在的に大きな需要が見こまれるシニア層には、パソコンやインターネットを活用することによって可能となる多様なコミュニケーションや健康増進、そして、情報化社会のなかで弱者とならないようにすることなどのメリットをアピールし、使いこなせるようになるためのサービスを企業、行政、NPO等の各方面から充実することが、利用促進のポイントである。