Sohatsu Eyes
公共サービス提供の改革(第6回)
2005年10月18日 古澤 靖久
| 公共サービス提供の改革(第6回) (2005/10/18) 古澤 靖久 |
 PPP担当マネージャーの古澤です。第1回に公共サービスの担い手が必ずしも官ではない時代が来たこと、そして市民から見た「最もValue for Moneyを達成できる代理人は誰か?」という問いに直面する、ということが肝心であることをご紹介しました。そして、第2回から第5回までで、そのVFM(バリュー・フォー・マネー)の達成メカニズムについて見てきました。 PPP担当マネージャーの古澤です。第1回に公共サービスの担い手が必ずしも官ではない時代が来たこと、そして市民から見た「最もValue for Moneyを達成できる代理人は誰か?」という問いに直面する、ということが肝心であることをご紹介しました。そして、第2回から第5回までで、そのVFM(バリュー・フォー・マネー)の達成メカニズムについて見てきました。今回からは、PFIの基礎知識についてお話ししていくこととしましょう。まずは、PFI事業の主要な関係当事者についてです。一般的なPFI事業の議論において、主要な関係当事者として行政サービスの購入者である行政とその提供者である(民間)事業者の2者の関係として議論されがちです。しかし、初期投資が大きい資産形成型のPFI事業においては、その資金調達の大部分(例えば70%から80%)が借入金でなされることから、この資金を提供する融資機関が、当該事業に融資するかどうかという事は非常に大きな鍵を握ります。従って、この意味で融資機関も行政、事業者に並ぶ主要な関係当事者なのです。 PFI事業を成立させるためには、これら主要な関係当事者がどのような価値判断(事業評価)をするのかをそれぞれの立場について把握することが必要となります。特に、行政の立場から考えると、行政以外の関係当事者がビジネスとしてPFI事業に参画する際に、どのような価値判断(事業評価)をするのかを把握されることが重要です。なぜなら、事業を推進する事業者と融資をおこなう融資機関がそれぞれの事業評価基準において、当該PFI案件に魅力を感じないとその案件は成立し得ないからです。 PFI事業における行政の判断基準がバリュー・フォー・マネー(VfM)であることは、前回までにお話ししたとおりです。このバリュー・フォー・マネーについては、理想的にはタックスペイヤーの視点からのバリュー・フォー・マネーだけ議論すればいいことになりますが、実際には、行政内部にもさまざまな関係当事者(ステークホルダー)が存在し、補助金や地方交付税交付金等を考慮する議論となると、国、県、市町村等のそれぞれにとっての異なるバリュー・フォー・マネーを考える必要があります。このような点については特に行政内部での調整により、採用するバリュー・フォー・マネーの考え方を整理しておく必要があります。 一方、事業者は自己の利益(リターン)の最大化を、融資機関はリスクのもれない分担がなされていることを主要な関心事としています。次回以降でより具体的に事業者と融資機関の判断基準について見ていくこととします。 図表:相反する3者の利害が一致してPFI事業は成立する 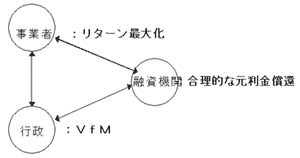 |

