 PPP担当マネージャーの古澤です。第6回は2005年10月掲載でしたから、忘れた頃にやってくる連載になってしまいました。現在、PPP推進室のホームページの構成を改めて、今まで創発eyesに掲載した内容(なんと初回は2003年5月です)も再掲し、第6回で宣言した基礎知識シリーズをもう少し短い間隔でアップしていく予定です。 PPP担当マネージャーの古澤です。第6回は2005年10月掲載でしたから、忘れた頃にやってくる連載になってしまいました。現在、PPP推進室のホームページの構成を改めて、今まで創発eyesに掲載した内容(なんと初回は2003年5月です)も再掲し、第6回で宣言した基礎知識シリーズをもう少し短い間隔でアップしていく予定です。
ということで、今回は英国における公共サービス提供の改革の動きについてご紹介いたしましょう。いまわが国において公共サービス効率化法も施行されPPP(Public Private Partnerships)の動きが本格化する機運がありますが、英国ではPPPより上流のPublic Sector Reformの取り組みとしての「パブリックサービス提供の仕方をデザインする」という考え方が議論されているようです。2003年のKelly Report(OGC Report to the Chancellor of the Exchequer : Increasing Competition and Improving Long-Term Capacity Planning in the Government Market Place)を受けて、現在は英国内閣府首相戦略オフィスからディスカッション・ペーパー(”The UK Government’s Approach to Public Service Reform”, 2006.6)がリリースされています。この議論の成果はGEMS(Guide to Effective Market Shaping)というツールキットに結実する予定のようです。
このディスカッション・ペーパーによれば、(1)中央政府からのプレッシャー(トップダウンのパフォーマンス・マネジメント)、(2)市場メカニズムの導入、(3)選択と発言(choice and voice)による市民からのプレッシャー、(4)中央及び地方政府の公務員の能力強化の4つの要素の組み合わせにより公共サービス改革に取り組んでいく、とのことです(図表をご覧下さい。英語のままの方が細かいニュアンスが伝わると考えて訳していません。ご了解下さい)。
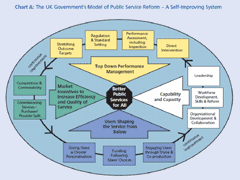
クリックすると大きい画像がご覧いただけます |
これらの組み合わせは、分野ごとに異なると理解されており、それぞれの分野に適切なデザインをしていくとの考え方です。主要なターゲットとして教育と医療とが挙げられています。このような統合的なアプローチが指向される背景には、誤解を恐れずにいえば「契約概念をいれたNPM(New Public Management)から様々な担い手が適切に担っていくGovernance設計の時代へ」という思潮の変化があるように思われます。すなわち、NPMの導入の中で、公共サービスの担い手は、従来の公共だけでなく民間企業やボランタリーセクターといった多様な主体が担い手となりえるのだ、ということが徐々に常識となってきています。このように多様な主体により担われることが当たり前になると、今度は「これら多様な主体間の統合をどのように行っていくか」、或いは「さまざまな担い手が同じ土俵で競えるよう(Level Playing field)適切なGovernanceをどう設計するか」がポイントとなる、というわけです。
たまたまですが、関西の政令指定都市で財政局のスタッフとして自治体経営のさまざまな課題に対する検討を市スタッフと協働して検討する機会(アドバイザー業務)に恵まれています。英国の上記のような「ものの考え方」を、必ずしも自分が十分に消化できているとはいえません。しかし、だからこそなのかもしれませんが、このような「ものの考え方」が、このようなアドバイザー業務を行う際に非常に示唆に富んでいると感じています。PFIや長期責任委託といったアウトソーシングと同様に、わが国においては地方自治体においてすばやい動きが出てくる可能性を感じており、この動きに少しでも貢献ができればと考えているところです。 |