| 2004年09月01日 |
| 定率減税縮小が個人消費に与える影響 |
| 【要旨】 |
| (1)定率減税が半減される場合を想定し、年収階級別に可処分所得減少に伴う消費支出減少額を試算すると、年間の個人消費を0.45%(1.3兆円)押し下げると試算される。 (2)この試算値の大きさ、および以下の4点を勘案すると、定率減税の廃止・縮小は時期尚早と判断される。縮小するとしても、個人消費へのマイナス影響をなるべく顕在化させないように、その規模を大幅に抑えるべき。 |
| [1] | 所得環境の改善の遅れ、すでに決まっている各種負担増を勘案すると、0.45%という減少幅は決して小さくないこと。 |
| [2] | 2005年度からの減税縮小は、景気減速のタイミングと重なり、景気後退をもたらしかねないこと。 |
| [3] | 過去2年間の景気回復により、税収額はこれまで想定していたよりも上振れしていること。 |
| [4] | 年金制度の将来展望が拓けず、不安感が払拭されないなか、その財源として減税を廃止するというのは、国民の理解を得にくいこと。 |
| 定率減税の廃止・縮小が政策上の大きなテーマに |
| 年末の2005年度税制改正に向けて、定率減税の廃止・縮小問題が大きなテーマに。定率減税は、もともと1999年に恒久的減税として導入されたものだが、昨年度の与党税制改革大綱で、基礎年金の国庫負担割合の引き上げ(3分の1→2分の1)の財源に充てる目的で、2005~2006年度にかけての「縮減・廃止」が盛り込まれたという経緯がある。 家計を巡る環境をみると、マクロの景気は着実な回復が続いているが、所得環境はようやく底打ちした段階であり、まだ景気回復を実感できていない状況。こうした点を勘案し、政府も、2005年度に定率減税を一気に廃止するのではなく、減税規模を半減する方向で検討している模様。 ここで、世帯の年収別に減税規模をみると、税額控除という性質から、税負担の少ない低所得層での恩恵は小さく、比較的高い所得層での減税額が大きい。相対的に生計に余裕のある世帯に対する負担が大きくなることから、「低所得者層へのマイナス影響は小さい」という説明が成り立ち、政策的にも廃止・縮小への抵抗は少ないとみられる。 そこで、以下では、「夫婦+子供2人世帯」をモデルとして、定率減税が半減された場合の個人消費に与える影響を試算したうえで、定率減税のあるべき方向性について検討してみた(*)。 (*) なお、単身世帯では、配偶者・扶養など各種控除の対象外で、年収に対する税負担額が大きいため、定率減税の廃止・縮小によるマイナス影響も扶養家族のいる世帯に比べ大きくなる。もっとも、単身世帯の大半は低所得層に集中していることから、マクロ全体でみた場合の影響は小さいと判断される。そのため、以下では単身世帯も「夫婦+子供2人世帯」に含めて試算を行っている。 |
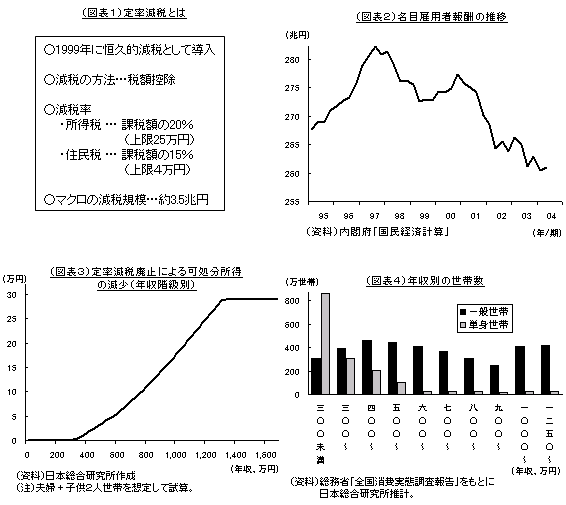 |
| 定率減税の半減により、個人消費は1.3兆円減少 |
| 以下では、家計調査をベースに一般世帯を年収基準で分類し、定率減税の半減による可処分所得(税引後の手取額)減少額と消費減少額を試算した。 (1) 可処分所得減少額 年収300万円未満では全く影響がないが、年収1,300万円超の世帯では14.5万円の可処分所得減少と、年収が高くなるほど減収額が大きくなる。年収700万円台の平均的なサラリーマン世帯では約5万円の可処分所得減少に。 (2) 限界消費性向と消費減少額 可処分所得が増減した場合、どれだけ消費支出を増減させるか(限界消費性向)を調べると、年収600万~1,000万円世帯では1に近い数値に。すなわち、可処分所得が減少した場合、その分を全て節約してしまうという消費行動をとっている。限界消費性向が年収600万~1,000万円世帯をピークとする山型になるのは、年収600万円未満の世帯ではもともと消費性向が高いうえ、義務的支出の割合も高いため、可処分所得減少に合わせて消費支出を削減しにくいこと、年収1,000万円を超える世帯では可処分所得増減が消費支出の制約条件になりにくいことが背景。 減税縮小による可処分所得減少額に、この限界消費性向をかけて消費支出減少額を試算すると、図表7のように年収900万~1,000万円世帯を中心とした山型になる。 (3) マクロ全体での影響 消費減少額に世帯数をかけて、マクロの消費減少額を試算すると、年収800万~1,250万円世帯に個人消費減少のピーク。世帯数は比較的少ないものの、可処分所得減少額の大きさ、限界消費性向の高さが、消費減少が大きくなる主因。全ての年収層を合計すると、定率減税の半減によって、個人消費は1兆2722億円減少すると試算。これは、2003年度の個人消費の0.45%に相当。 |
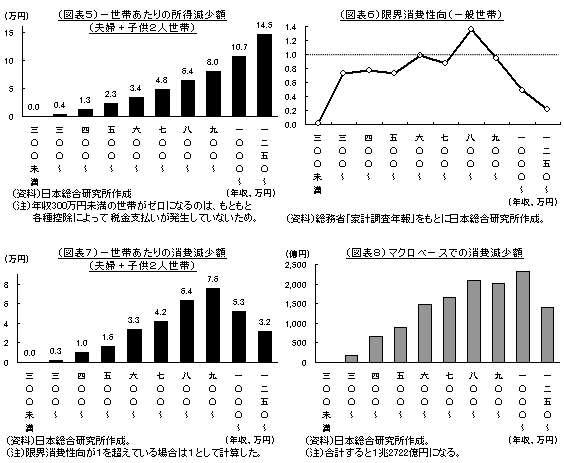 |
| 定率減税の廃止・縮小は時期尚早 |
| 以下の4点を勘案すれば、2005年度税制改正での定率減税の廃止・縮小は時期尚早。仮に縮小に踏み込むとしても、2009年度までかけて段階的に廃止するなど(年間の個人消費減少は6,000億円)、家計が収入減を意識しない程度にまで縮小規模を抑えるべき。 (1) 負担の大きさ [1]名目雇用者所得の伸びが極めて緩やかにとどまる公算が大きいこと、[2]すでに決まっている年金負担増、配偶者特別控除の廃止などの影響が2004年10~12月期から顕在化すること、を勘案すると、減税半減に伴う0.45%という個人消費減少のインパクトは決して小さくない。 (2) 縮小のタイミング 2005年度は、海外経済の減速、国内設備投資のピーク越え、電気機械産業での調整局面入りなどを背景に、成長率が低下するという見方がコンセンサス。こうした状況下、2005年度というタイミングでの廃止・縮小は、景気を後退局面に導く要因になりかねない。 (3) 財政再建との整合性 名目成長率の持ち直しを主因に、2003年度の税収額は当初予算対比3.6%上振れたのに続き、2004年度の税収額も5%程度上振れる可能性が高い。すなわち、2004年度、2005年度ともに、税収額はこれまでの想定よりも約2兆円ベースアップしているとみられるため、新たな財源を求めなくても、この自然増収分で賄うことができるという考え方も可能。景気減速のタイミングを勘案すると、拙速な減税廃止・縮小は景気後退をもたらし、財政再建にもマイナスに働く恐れ。 (4) 廃止目的の妥当性 定率減税廃止の目的は基礎年金財源であるが、年金制度の長期的展望の提示を先送りし、将来の年金制度に対する不安感が払拭されないなか、当座しのぎのために最も手をつけやすい部分を利用して取り繕うといった印象が拭い切れず、国民の理解を得ることが難しい。 |
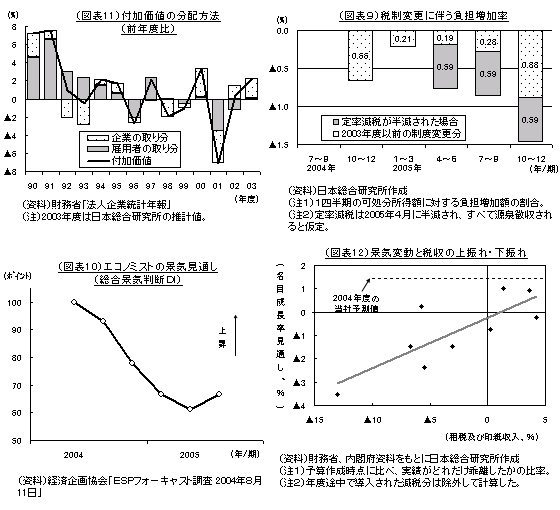 |

