| 2004年08月20日 |
| 電子デバイス調整局面入りのリスク |
| 電子部品・デバイスの在庫が増加に転じる |
| 電子部品・デバイスの在庫が増え始めたことから、シリコン・サイクルの調整局面入りの懸念が台頭してきた。実際、出荷の増勢鈍化と同時に、在庫が増加し始めた結果、在庫循環図では調整局面入りと判断できる状況になっている。意図的に在庫を積み増しているとの見方もあるが、生産計画からの下方修正が続いていること、在庫率も上昇していることから判断すると、「意図せざる在庫増」の可能性が高く、今後、在庫圧縮に伴う生産調整は避けられないと判断される。 2000年以降を振り返ってみると、今回と類似の局面を2回経験している。 (1) 2000年秋口~ ITバブルの崩壊といわれた大規模な調整。世界的に電気機械全般の需要が急減するなか、投資姿勢が積極化していたこともあって生産能力の抑制が間に合わず、この結果、深刻な在庫調整・資本ストック調整が1年にわたって持続。 (2) 2002年半ば~ 在庫の積み上がりがみられたものの、その後、需要が大きく減少することはなく、生産調整は比較的スムーズに進み、在庫は短期間で元の水準に戻った。この間、生産能力は増加に転じることもなく、減少傾向を続けた。 足元の状況は、[1]需要(出荷)が大きく減少していないという点では、2002~2003年のような軽い調整の可能性を示唆している半面、[2]生産能力の拡大が急ペースであるという点では、2000~2001年のような大きな調整の可能性を示唆している。そこで以下では、今後の需要および生産能力の動向を展望したうえで、電子部品・デバイスの生産調整がどの程度の規模で起こるかを検討する。 |
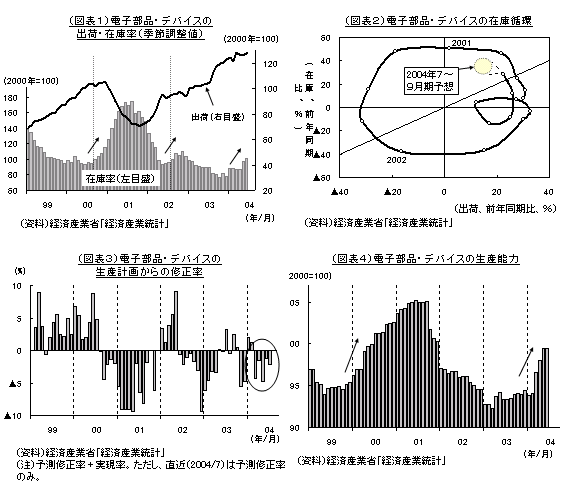 |
| 在庫増加の主因は一部のデジタル家電需要の減少 |
| まず、足元の需要減速の背景を確認しておくと、電子部品・デバイスの出荷寄与度が低下しているのは通信機械、民生用電子機械向けの二つ。 (1) 通信機械 これまで下支えしてきた携帯電話端末が減少に転じたことが主因。携帯電話の出荷は約3年周期の波が形成されており、足元で下向きのサイクルに転じている。2005年半ばくらいまではマイナスの局面が続き、需要の回復が見込みにくい状況。 (2) 民生用電子機械 高い水準を維持しているものの、これまで牽引役となってきたビデオカメラ・デジタルカメラが減少に転じたため、足元は弱含みに。これら2製品は、[1]これまでの急速な普及拡大に伴って、国内需要が一巡しつつあること、[2]海外需要も弱含んでいること、が需要減少の背景。 このように、足元の電子部品・デバイス需要の弱含みは、携帯電話と一部のデジタル家電の需要減少が主因であり、2001年のように電気機械全般が大きく減少した状況とは異なっている。実際、電子部品・デバイス需要の半分を占める輸出向けは高い伸びを維持しているため、電子部品・デバイス全体では減少に転じることもなく、緩やかながらも増勢が続いている。 |
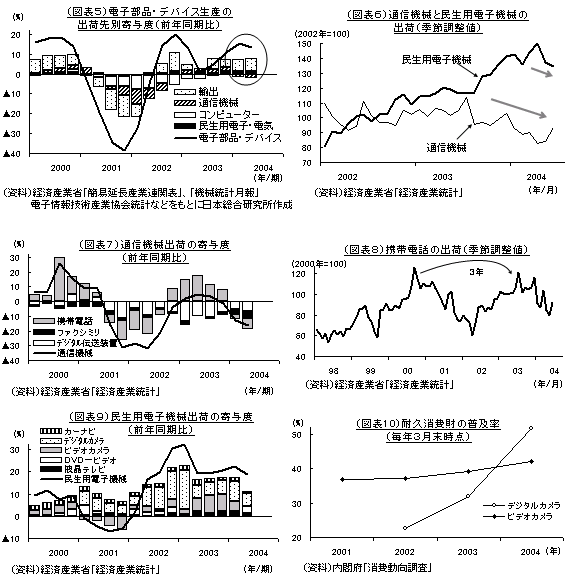 |
| 国内需要は個人向けを中心に回復基調が持続する見通し |
| 次に、今後の需要動向について展望すると、国内需要については、携帯電話やビデオカメラの低迷が足を引っ張るものの、以下の2点を勘案すれば、電子部品・デバイス需要が大きく減少する可能性は小さく、基本的に回復基調が持続すると判断。 (1) 家庭向けでは、デジタル家電需要が中長期的に着実に拡大するとみられる。足元では、DVDレコーダーの牽引力が高まっているほか、今後は、緩やかなペースで薄型テレビの需要が拡大していくと予想される。薄型テレビは、現時点では価格が高いことがネックになって購入層が高齢世帯に偏っているが、今後価格が低下するにしたがい、徐々に若い年齢層にまで市場が拡がる見通し。 (2) 企業向けでは、情報化関連投資に積極姿勢が強まっている。過去2年間、企業の情報化投資は低迷を続けてきたが、2004年度の計画では、非常に高い伸びが見込まれている。投資目的をみても、生産・流通・販売システム効率化を目的とする内容が多くなっている。 さらに注目されるのは、ここ数年、電子部品・デバイスの生産拡大の牽引役が、設備投資から個人消費にシフトしている点。最近のデジタル家電の需要急増を考慮すると、この傾向は足元でさらに強まっている可能性が高い。こうした動きは、以下の2点から電子部品・デバイス市場の安定的な拡大に寄与すると予想される。 (1) 設備投資への依存度が低下することにより、設備投資循環に連動して形成される振幅の大きいサイクルが抑えられる。 (2) 消費者向け電気製品は、企業による新製品開発努力が最も実を結んできた分野であり、次々と新しい市場が創出されてきた。今後も、新製品の投入が消費意欲を喚起する動きが続き、電子部品・デバイス市場の拡大に寄与する見通し。 |
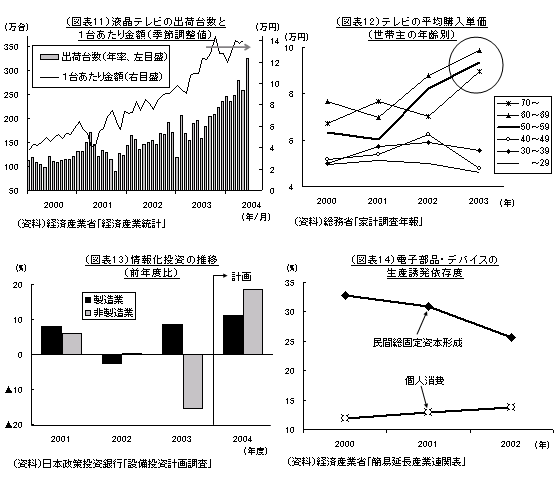 |
| 海外需要は減速に向かうも、底堅く推移する公算 |
| 一方、海外需要についても、今後、回復ペースが鈍化する可能性が高いものの、電子部品・デバイス需要が大きく崩れることはなく、底堅く推移する見通し。 まず、台湾・韓国の電気機械生産をみると、増勢は鈍化しているものの回復傾向が続いている。この2カ国は電気機械の世界的な生産拠点と位置付けられ、過去の調整局面入りの際にも、他国に先駆けて生産が減少する傾向がみられた。台湾・韓国の生産が堅調を維持していること、韓国の在庫率が歴史的な低水準にあることを勘案すれば、当面は電気機械の調整局面入りのリスクは小さいと判断される。さらに、生産の先行指標として考えられる台湾の輸出信用状(L/C)受取額も、足元でピークアウト感がみられるものの高い水準を維持しており、世界的な電気機械関連需要が根強いことが窺える。 台湾・韓国における電気機械生産拡大の背景としては、先進諸国でのIT需要が底堅く推移していることが最大の理由。米国の設備投資の内訳をみると、能力増強投資などは回復感に乏しい状況から抜け出せていないが、コンピューター投資は増勢が続いている。また、高成長が続く中国での携帯電話・コンピューター需要の拡大も、米国に次ぐ第二の牽引役として期待可能。 こうした「海外での電気機械需要→アジア諸国での生産→日本のデバイス輸出」というルート以外にも、日本からのデジタル家電輸出の増加が電子部品・デバイス需要を拡大させるというルートも引き続き働く見通し。とりわけ最近では、欧米向けの薄型テレビの輸出が急増。 もっとも、米国のコンピューター投資は過去2年間拡大局面が続いており、循環的にも増勢が鈍化に向かう可能性。実際、2004年4~6月期には、コンピューター・ストックの伸びが高まるなか、コンピューター投資の増勢が鈍化するなど、調整局面入りの兆しが現れている。ただし、調整に転じる場合でも、ストック水準が低いため、大規模な調整に陥る公算は小さい。 |
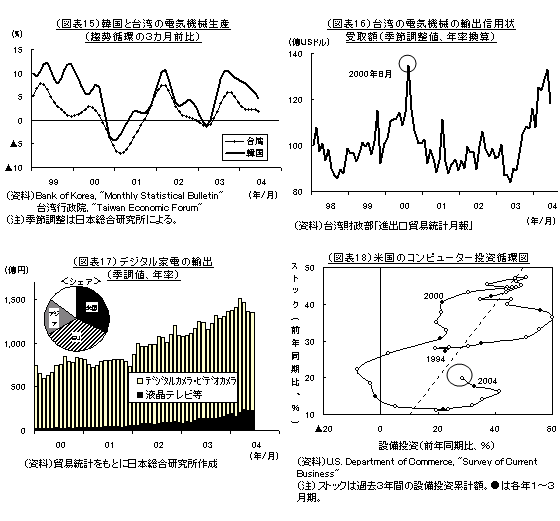 |
| 需要堅調な下、過剰投資が回避されれば大きな調整は起きにくい |
| 一方、生産能力の拡大は国内だけでなく海外でも起きており、このままのペースで能力増強投資が続けば、大規模な資本ストック調整につながる恐れも。もっとも、以下の2点をみれば、生産能力水準が過度に拡大していくリスクは小さいと判断。 (1) 国内での電子部品・デバイスの生産能力は、[1]半導体製造装置受注が2004年入り後、高水準ながら伸びが止まっていること、[2]過剰生産設備を廃棄する動きが続くとみられることから、当面は拡大が続くものの、その後、一定水準で歯止めがかかるとみられること。 (2) 海外から日本企業への半導体製造装置発注もピークを越えていることから、韓国や台湾での生産能力増強も、加速的に拡大し続けるとは考えにくいこと。 最終的な需給関係を反映する価格をみても、生産能力が拡大を始めた2004年入り後も下落幅が拡大する兆しは現れていない。この点からも、現在の生産能力の拡大は、需要拡大ペースを大きく逸脱した水準ではないと判断される。半導体製造装置受注が現在の緩やかなペースでの増加にとどまる限り、供給過剰によって電子部品・デバイスの需給が大きく崩れる懸念は小さい。 以上を総合すると、2004年度後半は、在庫調整、供給能力の拡大を背景に、電子部品・デバイス生産は調整局面入りする可能性が高い。もっとも、内外需要の底堅さ、抑制気味の供給能力拡大を背景に、調整は軽微・短期間に終わり、2005年後半ごろから、再び電子部品・デバイス生産は回復基調に復帰する見通し。電子部品・デバイス部門の設備投資は、若干のラグをもって2005年に調整局面を迎えるものの、大幅減少は回避され、2006年には再び増勢に向かう見通し。 |
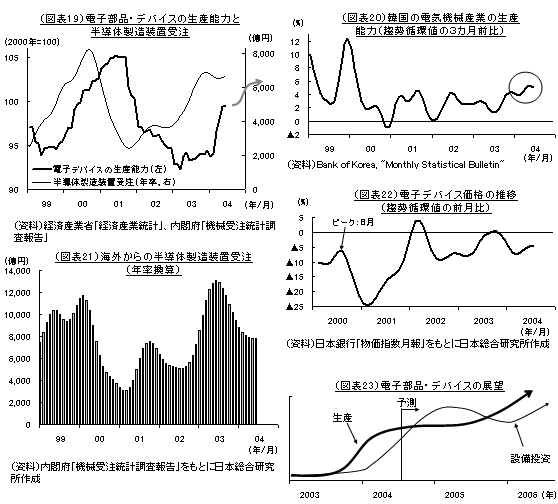 |

