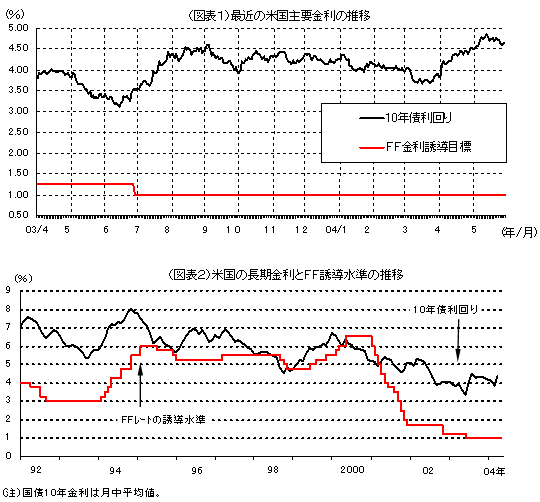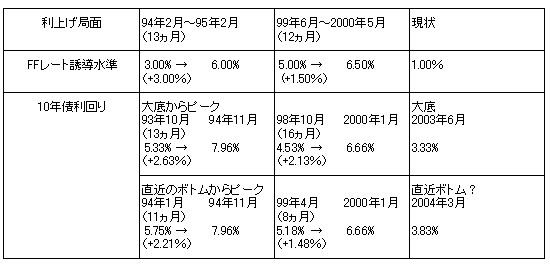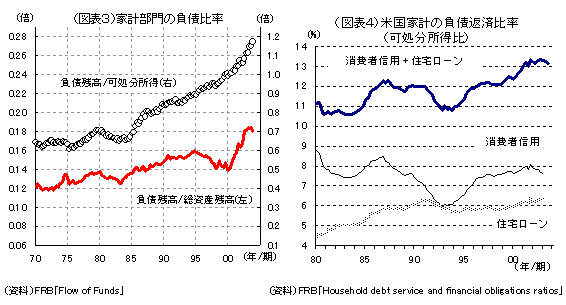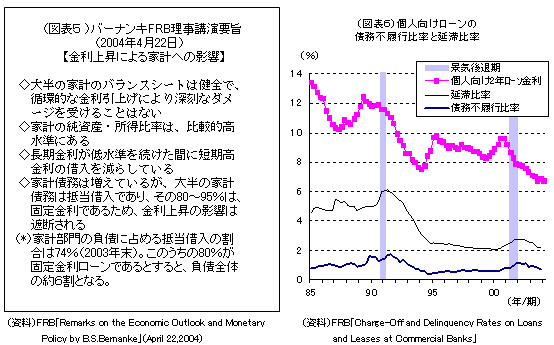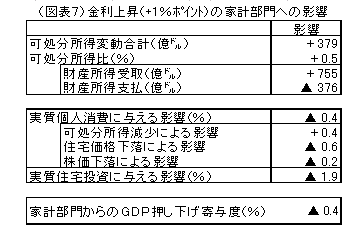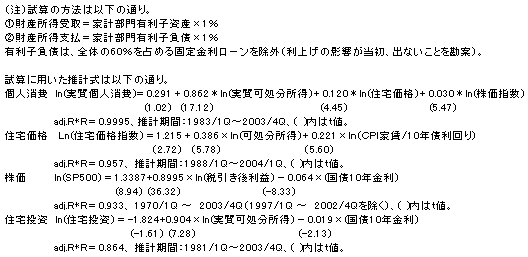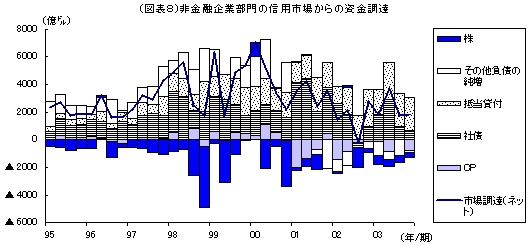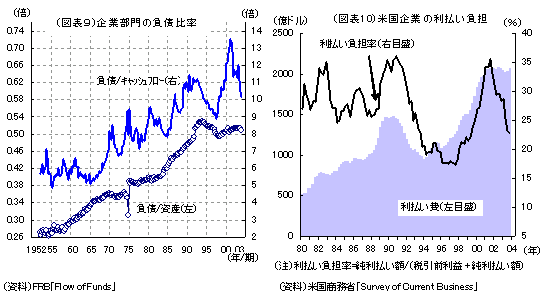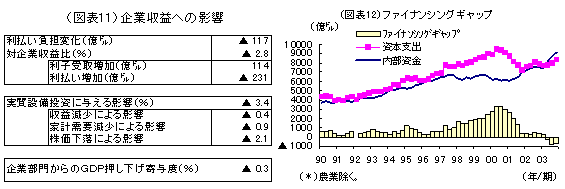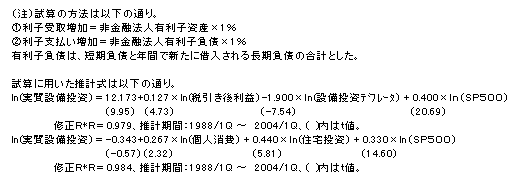| ・ |
米国では、雇用情勢の大幅な改善やFedの利上げスタンスの明確化を受け、長期金利が3月中旬のボトム3.68%から5月中旬には4.86%へと約1.2%ポイントも急上昇。足許の長期債市場は、既にFF金利誘導水準の1%引き上げを織り込んでいる可能性。 |
| ・ |
家計部門の財務状況を概観すると、負債比率(対可処分所得比、対総資産比)、返済負担比率は過去最高の水準にあるが、[1]固定金利負債の割合の高さ、[2]足許の景気拡大傾向を勘案すると、負債水準の高さ自体が金利上昇局面で直ちに家計部門の下押し圧力に直結するわけではない。 |
| ・ |
金利上昇が可処分所得に与える影響を試算すると、資産が負債を上回る家計部門では、 1%の金利上昇が、名目可処分所得を0.4%増加させる。しかし、金利上昇が株価・住宅 価格などの資産価格を下落させ、これが消費等へ影響するという間接的影響を勘案すると、実質個人消費は、▲0.4%減少。住宅投資減少(▲1.9%)を含む家計部門全体では、 実質GDPを▲0.4%下押しする結果に。 |
| ・ |
一方、企業部門では、1%の金利上昇により、[1]直接的な利払い負担の増加を通じて 企業収益が ▲2.8%下押しされること、[2]資産価格の下落、個人消費の減速などに伴う 間接的な影響が出ること、の二つの経路から設備投資が▲3.4%減少し、実質GDPを ▲0.3%押し下げると試算される。 |
| ・ |
家計部門・企業部門への影響を総合すると、金利1%の上昇で実質GDPが向こう1年間で▲0.7%下押しされるとの結果。循環的な回復局面にある米国経済にとって、深刻な景気後退に陥る程のインパクトでないものの、2004年後半の景気拡大ペースが、年前半の4%台から加速せず、 3%台にスローダウンする要因となろう。 |
| ・ |
さらに、リスク要因として、金利の上昇を契機とした株価・住宅価格などの資産価格の下落が予想以上に進む結果、家計のバランスシートが悪化し、実体経済を一段と下押しするルートについては警戒的にみていく必要。 |