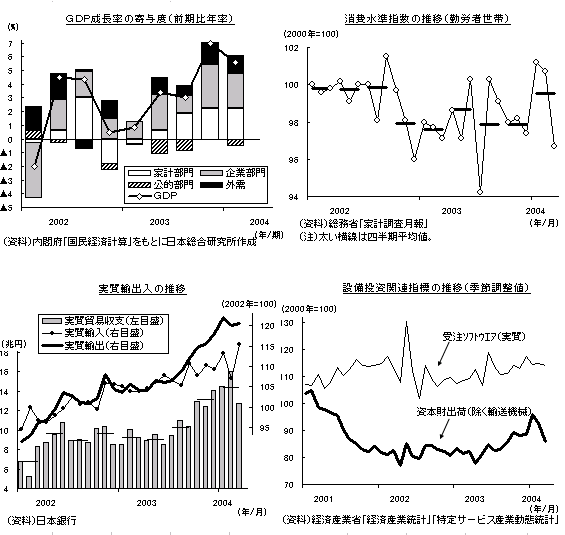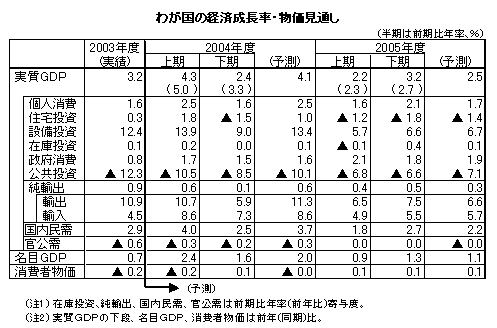|
| 2004年05月20日 |
|
| 2004~2005年度改訂見通し |
|
| 1~3月期の評価-高成長からの反動減もなく、堅調維持 |
2004年1~3月期の実質GDPは前期比+1.4%(年率+5.6%)と、8四半期連続のプラス成長。10~12月期の高成長からの反動が懸念されたものの、[1]消費マインドの持ち直しを背景に個人消費が底堅く推移したこと、[2]世界的に景気回復傾向が強まるなか、輸出の増勢が持続したこと、[3]製造業を中心に設備投資が回復傾向を続けたこと、などが景気押し上げ要因として寄与。
(1) 家計部門:個人消費は、雇用・所得環境の悪化に歯止めがかかり、消費マインドの改善が明確化するなか、[1]乗用車などで比較的価格の高い製品への需要が拡大し始めたこと、[2]サービス支出が持ち直したこと、などを背景に増勢が持続。懸念されていたBSE・鳥インフルエンザや天候不順などの影響はほとんど顕在化しなかった模様。また、住宅投資も、貸家や首都圏でのマンション着工が持ち直したことから、小幅ながらも増加に転じた。
(2) 輸出:世界的に景気回復傾向が強まるなか、前期比年率二桁ペースの高い伸びが持続。とりわけ、アジア向けは、電子デバイス・音響機器部品などの生産財に加えて、化学製品・一般機械といった内需向け輸出も大幅に増加。米国向けも特殊産業機械(設備投資向け)、デジタル家電に牽引されて増加に転じた。
(3) 設備投資:急増した10~12月期の後にもかかわらず、前期比+2.4%(年率+10.1%)と堅調に拡大。生産・稼働率の回復を受けて、製造業を中心に設備投資意欲が強まったほか、低迷を続けてきたソフトウエア投資にも回復の兆し。
|
| (1) |
特殊法人改革では、独立行政法人への組織変更が大半で改革の効果は限定的。道路公団改革では、新規の道路建設への歯止めがかからず。
|
| (2) |
三位一体では補助金削減が先行し、国から地方への権限や財源の移譲が遅延。特区では、教育・医療分野への株式会社参入に厳格な条件が付与され、実質的に競争阻害。 |
| (3) |
年金改革では、引き続き給付水準の削減と負担の増大という従来路線が踏襲。国民の安心を確保するには依然至らず。 |
| 展望-2004~2005年度にかけ回復傾向が持続する見通し |
| 当面を展望すると、以下の3点を背景に、景気回復傾向が持続する見通し。原油など素材価格の上昇は、最終財価格への転嫁が困難な状況下、企業収益の押し下げ要因として働く公算が大きいものの、売上増による増益効果が見込まれることから、交易条件悪化に伴うマイナス影響は吸収可能。 |
| (1) |
欧米・アジア経済の回復が続くことから、輸出による景気下支え効果が持続。とりわ
け、中国向け輸出は、「世界の工場」としての地位確立とともに、内需拡大の効果も高
まっていることから、素材・部品・資本財と幅広く増加する見通し。
|
| (2) |
設備投資は、コンピューターなど資本財価格の下落により、実質ベースの設備投資が大
きく押し上げられる構図が持続。加えて、輸出の増勢持続、国内民需の持ち直しを背景 に、製造業を中心に名目ベースでも増勢が強まっていく見通し。 |
| (3) |
個人消費は、雇用・所得環境の悪化に歯止めがかかったことに加え、消費性向の高い高
齢者層による下支えも期待できることから、底堅く推移する見通し。携帯電話・デジタ ル家電など、企業の新製品開発努力が消費意欲を喚起する効果も、当面は持続する見通
し。 |
なお、前回の予測値(3月11日公表)と比べると、2004年度は実質で1.6%ポイント、名目で1.7%ポイントの上方修正となった。
2005年度を展望すると、今回の景気回復の牽引役の一つであるデジタル関連設備投資の一巡につれ、年末ごろにはピークアウト感が出てくる見通し。ただし、[1]中国経済の成長持続により海外需要の回復は続くこと、[2]国内でも企業リストラの進展などを背景に景気回復の裾野が広がっていること、を勘案すれば、基本的には緩やかなペースでの回復傾向が持続する見通し。 |
全文はこちら(PDF:38.6KB)