| 2004年04月28日 |
| 「人件費の変動費化」が変える消費パターン ~所得・雇用環境からみた消費拡大の可能性~ |
| 【要 旨】 |
| 1. | わが国の失業率はバブル崩壊後、上昇トレンドをたどってきたが、2003年後半以降は 緩やかに水準を下げる方向。 この背景には労働分配率が低下しはじめたことがあるが、その理由は以下の二点。 |
| (1) | 生産・物流プロセスの効率化に加え、輸出増を主因に売上が回復するに伴い付加価 値額が増え始めたこと。 |
| (2) | 非正社員比率の引き上げ、成果主義賃金導入により人件費の削減が進展したこと。 |
| 2. | 今後を展望しても、景気回復の持続が予想されるなか、労働分配率の低下に伴って 雇用情勢も改善基調を続ける見通し。ただし、以下の理由から、失業率が4%前半以下に低下していくのは困難な状況。 |
| (1) | 企業の求める人材像が高度化・専門化するなか、いわゆるミスマッチ失業率は4%強。 |
| (2) | 激化する国際競争を勝ち抜くための生産性引き上げ要請の強まり、様々な不確実性 が残存するもとでのリスク回避志向の強まりの結果、企業の雇用増加スタンスに慎重さが残る。 |
| (3) | 新規サービス産業が雇用を大きく吸収していく可能性も当面小さい。 |
| 3. | 労働分配率の引き下げに向けて、企業が人件費を抑制するために講じてきた(1)非正
規雇用シェアの引き上げ、(2)成果主義賃金の導入という手法は、人件費の「変動費化」 を進める要因に。 すなわち、解雇規制の緩い非正規雇用の増加は、景気変動に伴う雇用量の調整スピードを速めることに。また、成果主義賃金の導入により、企業は基本給を削減する一方、 賞与で報いる方向。 |
| 4. | 今年の賞与は相応の伸びが予想されるなか、個人消費を押し上げる効果が期待される。もっとも、その効果は、大手企業の賞与増額がイメージさせるほど強いものにならない
公算。 さらに、同じ所得増加にしても、賞与などの「一時所得」の場合は基本給など「安定所 得」の場合にくらべて消費押し上げ効果は「局地的」かつ「一時的」になる傾向。 |
| 5. | 以上のようにみてくれば、今夏のボーナス増を受けてデジタル家電が売れ、デフレー
ターの大幅低下も重なって、夏場の実質個人消費は好調な数字となる可能性。ただし、それは一時所得の増加に伴う局地的な消費増の結果であり、何らかの外的ショックの発
生で一転して下振れする可能性を秘めている。それだけに、量的緩和の解除や個人向 け増税にあたっては慎重な姿勢が求められる。 消費の安定的かつ全般的な回復を実現するには、やはり所得・雇用環境が安定的・持 続的に改善していくことが不可欠。そのためには、雇用・所得が景気の遅行指標であることを勘案すれば、まずもって景気回復を持続させることが大前提。その意味で、知識資本 の蓄積支援、規制改革・競争政策等を通じて、一段の産業活性化を推進することが必要。 |
| 失業率の上昇トレンドに歯止め |
| 1.”次の焦点”となる家計部門の動向 わが国の景気は2003年秋以降、企業部門を中心に回復傾向が明確化。80年代の景気回復時と比較 すると、設備投資等企業部門の回復ペースは劣らない一方、個人消費等個人部門には出遅れ感(図表1)。この背景には、所得雇用環境の改善の遅れが存在。 もっとも、ここにきて雇用者数が前年比プラスとなり、夏のボーナスの増加が予想されるなど、所得雇用環境は徐々に改善の方向。デジタル家電の売れ行き好調など、個人消費にもきて明るさが みられる。 以下では、今後、景気が本格回復に移行していくかどうかを判断する上で最大のポイントとなる、 雇用・所得環境の改善テンポ、および個人消費の先行きについて展望。 |
| 2.失業率のトレンド変化 (1)90年代入り以降の上昇トレンド わが国の失業率は90年代入り以降、十数年にわたり上昇トレンドを辿る。これは、景気後退期に大きく上昇する一方、回復期にも高止まりを余儀なくされるというパターンを繰り返してきたため (図表2)。 この背景には、[1]大手・中堅企業が雇用過剰感が強いもとで採用抑制・人員削減スタンスを続ける一方、[2]開業率が低迷するなか、かつては雇用の受け皿であった中小企業が、むしろ雇用を吐き 出す側に回ってきたこと(図表2)。 以上の構図のもとで、経済全体の雇用量(就業者数)は、既存企業の雇用過剰感と関連の深い労働分配率とほぼパラレルに変動しつつも、トレンドが徐々に下方にシフト(図表3・4)。 (2)2003年後半以降は低下へ もっとも、2003年後半以降、失業率は緩やかながらも低下傾向を示す。半年以上に渡って失業率が低下傾向を続けるのは、90年代に入って以降では初めてのこと。この背景には、景気回復が定着 するなか、労働分配率が93年半ば以来の水準にまで低下しはじめたこと。 |
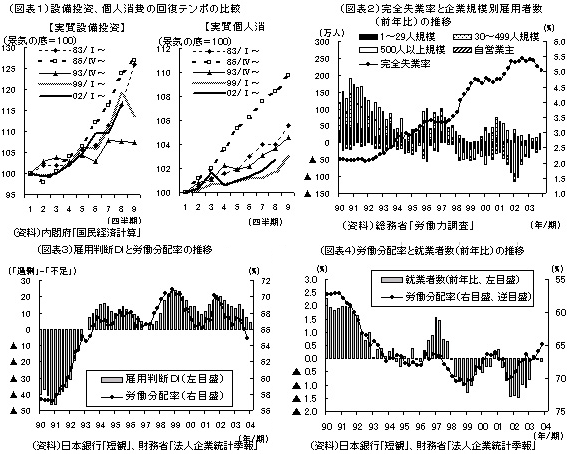 |
| 労働分配率低下の要因 |
| 3.労働分配率低下の要因 (1)労働分配率低下の要因 労働分配率が低下に向かい始めた理由は以下の二点。 イ)付加価値額の回復 2002年中を通じて生産・物流プロセスの再編を通じて変動費比率の引き下げが進展。 さらに、2003年に入って、アジア向けをはじめとする輸出の増加を主因に売上がプラス基調に転じ、付加価値額が回復(図表5)。 ロ)人件費の抑制 賃金の安いパートタイマー等非正社員の比率の引き上げ、成果主義賃金の導入により、分子である人件費が減少傾向に。 常用雇用ベースのパートタイマー比率は1995年から2003年までに8%ポイント上昇。パート比率の引き上げは96年以降、平均賃金毎年0.5~0.9%減らす要因に(図表6)。 一方、正社員の賃金についても、昇進人数の絞り込み、ポストと賃金の連動などを通じ、 賃金カーブをフラット化させる形で平均賃金水準を押し下げ(図表7・8)。 (2)業種別バラツキ もっとも、総じてみれば製造業に比べて非製造業の分配率低下が遅れ気味。これは、付加価値額の回復の遅れに原因(図表9)。 |
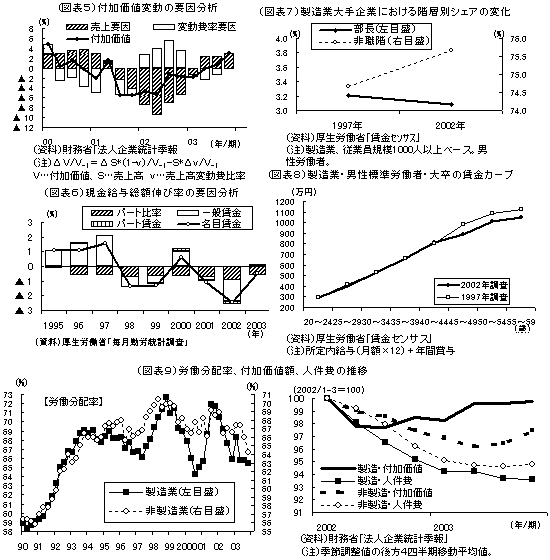 |
| 失業率低下を阻む3つの要因 |
| 4.失業率は低下に向かうも4%後半で高止まり 今後を展望しても、労働分配率が緩やかな低下トレンドを辿るなか、失業率も徐々に改善していく見通し。 ただし、以下の点を勘案すると、当面、就業者数の大幅増加は期待できず、失業率も4%台前半にまで低下していくのは困難と判断。 イ)「ミスマッチ」が雇用増加の足枷に…企業が即戦力を必要とするなか、人材スペックの専門化・高度化が一段と強まる結果として、企業が求める人材が見つからない。ミスマッチ失業率は4%強あると試算される(図表10)。 ロ)企業の収益体質強化スタンスの強まり…(1)激化する国際競争を勝ち抜くための生産性引き上げ要請の強まり、(2)様々な不確実性が残存するもとでのリスク回避志向の強まりの結果、企業の雇用増加スタンスは慎重さが残る。 すなわち、90年代入り後の景気回復局面における製造業の労働生産性の増加テンポを比較すると、今回の速いスピードが目立つ(図表11)。多能工化による生産性向上を目指した「セル生産方式」の導入の広がり等が背景にあると推察される。また、設備投資の対キャッシュフロー倍率が大きく1を下回る状況に示唆されるように、原材料・金利コストの上昇懸念、テロ発生など将来不安を背景に企業の事業スタンスに慎重姿勢残る。 ハ)新規雇用の創出力は当面限定的…一方、90年代アメリカにみられたような新規サービス産業が雇用を大きく吸収していく可能性も当面小さい。わが国でもサービス業での雇用が増えているが、90年代アメリカと比較してその吸収力は依然小さい(図表12)。とりわけ、事業所サービス分野での彼我の差は大きい。医療・介護・教育といった人的サービス分野でも立ち遅れ。 |
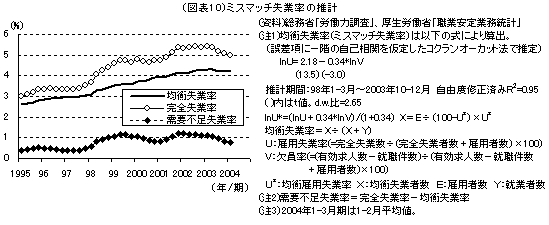 |
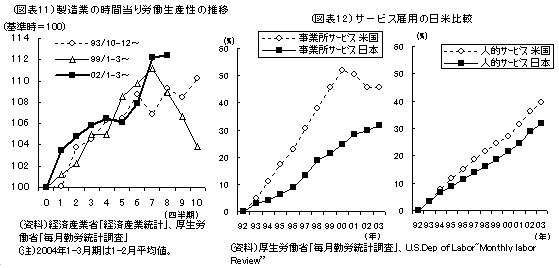 |
| 進展する人件費の「変動費化」 |
| 5.進展する人件費の「変動費化」 労働分配率の引き下げに向けて、企業が人件費を抑制するために講じてきた[1]非正規雇用シェア の引き上げ、[2]成果主義賃金の導入という手法は、人件費の「変動費化」を進める要因に。 (1)非正規雇用シフトによる人件費の「変動費化」 解雇規制の緩い非正規雇用の増加は、雇用量の景気変動に伴う調整スピードを速めることに。 厚生労働省の調べ(パートタイム労働者総合実態調査」)によれば、パート労働者を雇用理由として、「一時的な繁忙に対応するため」を27.3%の企業が、「仕事が減ったときに雇用調整が容易 だから」を16.4%の企業がそれぞれ挙げており、景気変動の調整弁として位置付けられていることが示唆される状況(図表13)。 また、雇用者数の増加を実質GDP(景気要因)、実質賃金(コスト要因)により説明する関数 を、80年代後半期、90年代前半期、90年代後半以降の時期に分けて推計。その結果によれば、[1]雇 用変動の景気感応度は90年代に入って大きく低下したものの、最近ではやや持ち直していること、[2]雇用調整のスピードが最近になるほど速くなっていることが確認される(図表14)。 (2)成果主義導入が進める人件費の「変動費化」 成果主義賃金の導入により、企業は基本給を削減する一方、賞与で報いる方向。とりわけ、2004 年春闘では、ベースアップの凍結のみならず、賃金カーブ自体のフラット化による事実上の基本給 部分の削減が進む一方、一時金は大幅に増加する形で妥結(図表15)。夏のボーナスは大手企業ベ ースで3~4%増加すると予想。 |
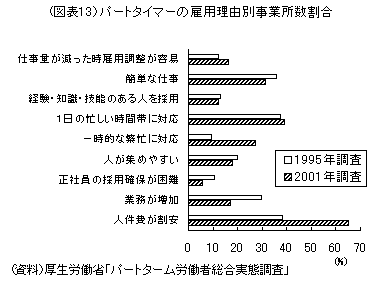 |
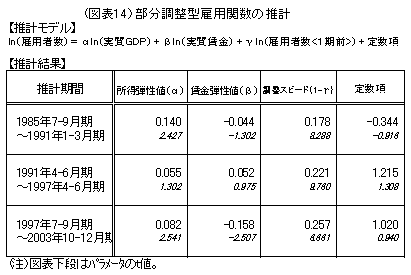 |
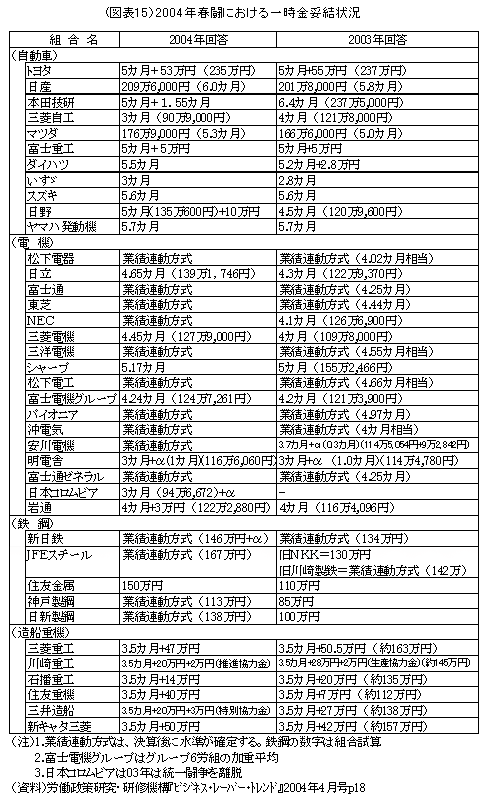 |
| 消費は回復するも局地的、振れも拡大 |
| 6.消費変動のパターン変化」 (1)賞与増加の消費押し上げ効果 今年の賞与は相応の伸びが予想されるなか、個人消費を押し上げる効果が期待される。 もっとも、その効果は、大手企業の賞与増額がイメージさせるほど強くはならない公算。 イ)大手企業ベースとマクロベースの乖離 春闘で報じられる大手企業の一時金伸び率は相当程度になる見込みながら、これは経済全体の一部を占めるに過ぎない。大企業・中小企業間の業況格差が残るもと、マクロでみた賞与の増加は小幅にとどまる公算(夏は1%台半ば程度)。実際、大手企業を対象とする「日本経団連ベース」の賞与と中小企業も含む「厚生労働省ベース」の賞与の伸び率格差が拡大傾向に(図表16)。 ロ)「一時所得」と「安定所得」の効果の違い さらに、同じ所得増加にしても、賞与などの「一時所得」の場合と基本給など「安定所得」 の場合で消費に対する影響は異なると考えられる。この点に関し、計量経済学の手法で分析を行うと、「安定所得」が1%増えれば消費は0.9%強増えるものの、「一時所得」の場合は向こう1年間で0.5%程度しか増えないとの試算結果(図表17)。 (2)人件費の「変動費化」が変える消費パターン 以上の分析を踏まえれば、人件費の「変動費化」のもとでの所得増加は個人消費の回復に寄与 するものの、局地的なものにとどまり、かつ大きな振れを生む可能性。 イ)局地的盛り上がり…一時所得の増加はヒット商品や新規サービスに対する需要の集中を生む傾向があると推察。また、過去の賞与支払時期の消費パターンをみると、高額品が多い耐久消費財のシェアが大きくなる傾向(図表18)。これらを踏まえると、新製品が投入され関心が集中しているデジタル家電分野が大きく盛り上がる可能性。その一方で、基本給が減少する分日常品に対する支出が抑制される公算。 ロ)振れの拡大…安定的な所得増加期待に裏付けられたものではない「一時所得」の増加が消費を支えるだけに、何らかの外的ショックによって消費が一転して大きく下振れるリスクを示唆。 |
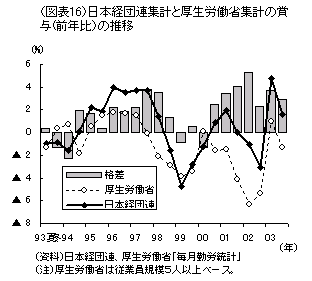 |
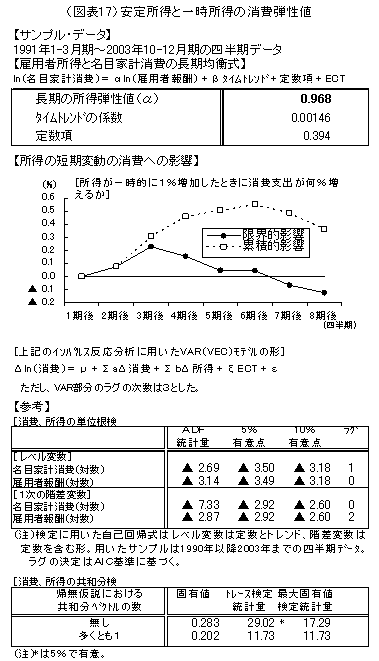 |
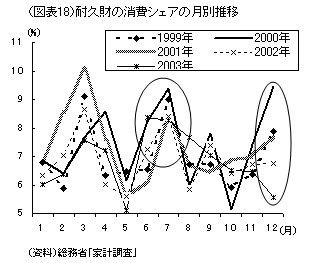 |
| 消費の安定的拡大に向けて |
| 7.消費の安定的拡大の条件 (1)消費の安定的拡大軌道復帰へのシナリオ 消費の安定的かつ全般的な回復を実現するには、所得・雇用環境が安定的・持続的に改善していくことが必要。そのためには、雇用・所得が景気の遅行指標であることを勘案すれば、まずもって景気回復を持続させることが大前提。 具体的には、現在の景気回復を牽引している輸出部門・部品製造部門が、アジア経済との連携を一段と深めるとともに一段の高付加価値化を推進していくことで、引き続き景気回復をリード していくことが期待。 一方、非製造業部門についても、景気回復の先導役の生産性向上を支援する新しいサービスを提供することで、輸出・部品製造部門の成長を取り込むとともにユーザー企業の一段の成長に貢献していく必要。 こうした結果として、製造業部門のみならず全業種で賃金が増えはじめ、やがては個人消費の力強い拡大が実現していくことが展望可能に。 (2)求められる産業・雇用政策 以上のようなシナリオ実現のためには、企業・個人が不断の自己革新に取り組むことが大前提であるが、政府としても以下の点でサポートする必要。 イ)FTAの積極的推進 各種構造要因により所得雇用環境の改善が遅れることが予想されるなか、今しばらくは「外需頼み」の状況からは逃れられず。ただし、それはかつての欧米市場向けではなく、アジア諸国との共存共栄関係のもとで実現可能なもの。その前提として、農業改革とのセットのもとでアジア各国とのFTAを着実に締結していくことが重要。 ロ)知識資本の蓄積支援 アジア諸国との共存共栄関係を構築するためには、FTAによる自由貿易のインフラを整えるとともに、日本が比較優位分野を一段と強化していく必要。わが国の比較優位は製造分野における知識資本にあり、この蓄積を一段と促すためのインフラ作り―知的財産の保護、研究基盤の強化、技能工養成システムの整備等が重要な政策課題。 ハ)規制改革・競争政策 製造業が一段の生産性向上を要請される中、安定的な雇用拡大のためにはサービス産業の活性化が不可欠。そのためには、医療・介護・教育分野での規制改革・競争政策の強化により、サービスの多様化・高度化を通じて雇用を創出していく必要。同時に、わが国で遅れている事業所サービスの成長のために、人材関連ビジネスの一段の自由化などが求められる。 ニ)起業支援策 エンジェル税制の拡充、日本版LLC(有限責任会社)制度の早期導入など、雇用の受け皿となる新規ビジネスの起業をサポートする環境整備が必要。 ホ)積極的労働市場政策 雇用のミスマッチを緩和するためには、新しい産業が要請する技能・知識を効率的に身に付けることのできる産学官連携の職業教育システムの創設が不可欠。とりわけ、530万人雇用創出プログラムに示されたような既知の有望産業については、体系的な技能習得の仕組み作りが必要。 その上で、民間職業紹介機能の強化、公共職業紹介の自治体への権限委譲を通じた効率的なジ ョブ・マッチングの仕組みを整えるべき。 (3)マクロ経済政策に対するインプリケーション 人件費の変動費化がもたらす消費の振れの拡大の可能性を踏まえれば、マクロ経済政策の変更にあたっては慎重な姿勢が求められる。 すなわち、今夏のボーナス増を受けてデジタル家電が売れ、デフレーターの大幅低下も重なって(*)、今年夏場の実質個人消費は予想以上に好調な数字となる可能性。ただし、それは一時所得の増加に伴う局地的な消費増の結果であり、外的ショックの発生で一転して下振れする可能性を秘めている。それだけに、大幅な財政赤字を勘案すればマクロ政策正常化への模索の時期に入っているのは確かながら、量的緩和の解除や個人向け増税を実施するまでには慎重で周到な準備が求められる。 (*)デジタル家電の一部(デジタルカメラ、ビデオカメラ等)は、質的向上分がデフレーターの低下として処理されるため、デジタル家電に消費が集中すればするほどデフレータは大きく下落することになる。 |

