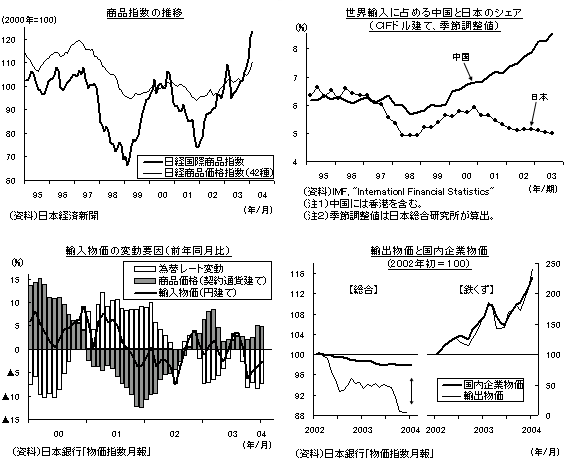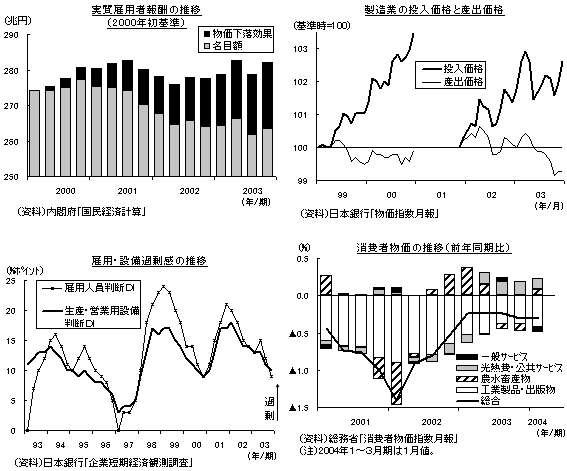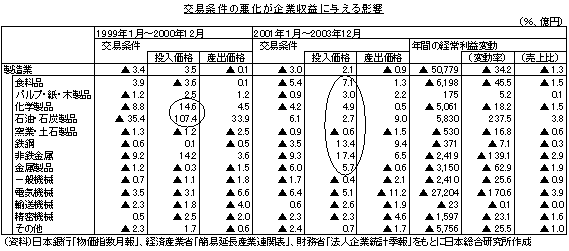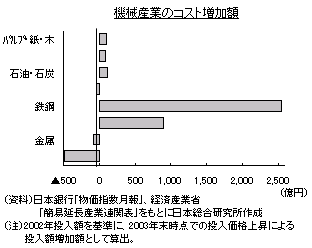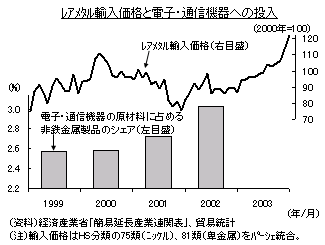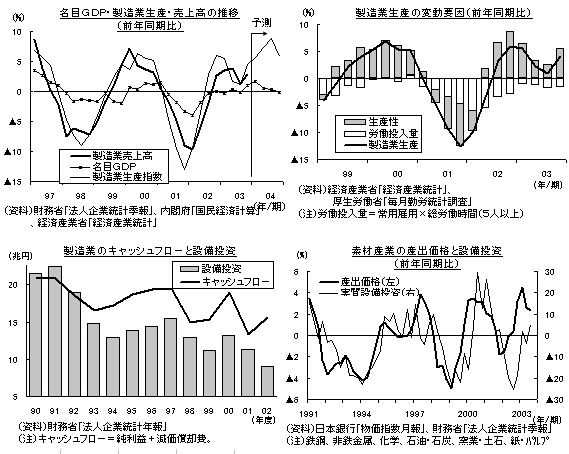| 要 旨 |
国際商品価格の上昇は、現在のところ円高により相殺されているため直接のマイナス影響は小。もっとも、中国からの素材引き合いの増加を背景に、国内商品価格にも上昇圧力がかかっている。今後を展望すると、中国経済の高成長持続、円高の一巡などから、素材価格の上昇圧力が国内でも強まっていく見込み。
素材価格の上昇は、最終製品価格に転嫁された場合は家計の負担増に、転嫁されなかった場合は企業の負担増になる。足元の動きをみると、投入価格が上昇しているのに対し、需給ギャップが残るなかで産出価格は弱含み傾向から脱せず。当面、需給ギャップは大きく残るとみられることから、素材価格の上昇は企業部門の収益圧迫要因として作用する可能性大。
素材価格の上昇は、製造業の経常利益を5兆円程度押し下げると試算。1999~2000年の投入価格上昇が石油価格に偏っていたのに対し、足元では幅広い素材で価格が上昇しているため、多くの製造業で収益押し下げ要因になる見込み。とりわけ、影響が大きいとみられるのは鉄鋼価格の上昇。また、「産業のビタミン剤」であるレアメタル価格の急上昇にも注意が必要。
もっとも、企業活動全体に与える影響は、(1)景気回復に伴う売上増により十分に相殺可能であること、(2)生産性引き上げによる収益体質強化により、マイナス影響の吸収余力が高まっていること、などから、景気失速の引き金になるリスクは小。設備投資に与えるマイナス影響も、(1)キャッシュフローが潤沢にあること、(2)素材メーカーによる設備投資積極化が期待できること、から軽微にとどまる公算。 |
| 素材価格が国内外で大きく上昇 |
2003年半ばから、国際商品価格の上昇に拍車。この背景には、一部投機的な動きも加わっているものの、基本的には、世界的に景気回復傾向が強まっていることが背景。とりわけ、過去数年にわたる急速な工業化の結果、中国での素材需要が急増していることによる影響が大。世界の輸入額に占める中国のシェアをみると、90年代まで6%前後で安定して推移してきたのに対し、2000年以降急上昇しており、足元では9%近い水準に。
わが国の輸入物価をみると、現在のところ、昨秋から進展した円高が国際商品価格の上昇を完全に相殺しているため、全体でみると下落傾向が続いており、海外での素材価格上昇によるマイナス影響は顕在化していない。もっとも、今後を展望すれば、(1)欧米・アジア諸国での景気回復が持続すると予想されるなか、「世界の工場」としての地位を確立した中国の高成長も続き、国際的な商品需給の逼迫が一段と進む可能性があること、(2)円高の一巡により輸入物価押し下げ効果が低減する可能性があること、などを勘案すれば、輸入物価には上昇圧力がかかりやすい状況が持続する見込み。
加えて、国内の商品価格をみても、国際商品価格の上昇につられるかたちで、鉄スクラップなど一部の商品では上昇傾向に転じている。上昇ペースは国際商品価格に比べ緩やかにとどまっているものの、すでに前回のピーク(2000年)時を大きく上回る水準に。これは、中国からの素材引き合いが増加し、国内需給がタイトになってきたことが主因。 |
| 素材価格の上昇は最終価格に転嫁されず、収益圧迫要因に |
| 素材価格上昇が実体経済に与えるマイナス影響は、価格転嫁の状況によって以下のような違い。 |
| (1) |
最終製品価格に転嫁された場合は消費者物価の上昇圧力になり、名目所得の改善が遅れるなか で、実質購買力の低下をもたらして個人消費の下押し要因に |
| (2) |
最終価格に転嫁されない場合は、コスト増として素材メーカー・加工組立メーカーいずれかの 企業収益押し下げ要因に |
そこで、足元の製造業部門の投入価格・産出価格をみると、投入価格は素材価格の上昇を反映して増勢となっているのに対し、産出価格は弱含み傾向が持続。これは、1999~2000年にかけての投入価格上昇時にもみられた傾向。
基本的に最終製品価格は需要と供給のバランスに左右されるため、需給ギャップが根強く残るもとでは、企業が投入価格の上昇分を最終製品価格に転嫁しにくい。日銀短観の雇用過剰感・設備過剰感をみれば、依然として大きな需給ギャップが存在していることが示されており、過剰感が完全に解消するには少なくとも2~3年はかかる状況。したがって、当面、素材価格の上昇は消費者物価などの最終製品価格の上昇にはつながりにくく、大部分は企業収益押し下げ要因として働く公算が大きい。また、仮に最終製品価格の下落幅がゼロ近くにまで縮小したとしても、消費者物価は、足下での公共料金・医療費・食料品価格の一時的な上昇が一巡することが予想されるため、下落傾向は変わらず。 |
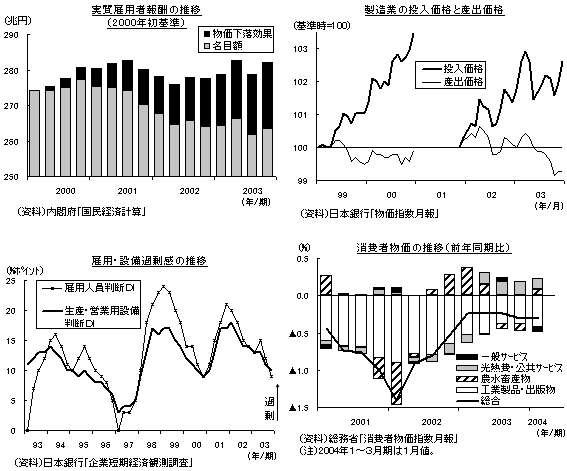 |
| 投入価格の上昇が製造業の経常利益を3割押し下げる可能性 |
そこで、企業収益へのマイナス影響をみると、投入価格の上昇によって製造業の経常利益は5兆円程度押し下げられると試算(足元の経常利益の3割強に相当)。投入価格の上昇は前回(1999~2000年)よりも小幅にとどまっているものの、前回の投入価格上昇は石油価格急騰が主因で、マイナス影響も一部企業に限られていたのに対し、今回は幅広い投入財で価格上昇が起きている結果、多くの業種で収益押し下げ要因となっている点が大きな違い。
詳細にみると、板紙・段ボール、鉄スクラップ、非鉄金属鉱物、生ゴムなどの価格が大きく上昇しており、これらを使って生産された中間製品価格の上昇が、他の製造業の投入価格上昇として波及するという構図になっている。例えば、鉄スクラップ・鉄鉱石の価格上昇の影響をみると、鉄鋼業では比較的産出価格への転嫁が進んでいるため収益悪化は小幅にとどまっているものの、鉄鋼製品を原材料として使用する機械産業(一般機械・輸送機械・電気機械・精密機械)では投入価格の上昇要因として働いている。
現在までのところは、鉄鋼価格の上昇が最大のコスト増加要因になっているが、今後、注意しておく必要があるとみられるのは、ニッケル・クロム・コバルトなどのレアメタル(希少金属)。レアメタルの大半は輸入に依存しており、輸入価格をみても、円高が進展したにもかかわらず、2003年入り後から急上昇している。レアメタルは、様々な製品で利用されており、とりわけ日本企業が得意とする半導体・電子部品・レンズなどの製品を高付加価値化するうえで不可欠な材料。足元の景気を牽引しているデジタル家電では多量の半導体・電子部品が投入され、レアメタル使用量も増加傾向にあるだけに、今後、レアメタルの価格上昇に拍車がかかった場合、デジタル家電・電子デバイス業界へのマイナス影響が強まる恐れも。 |
| 素材価格上昇が直ちに景気失速要因になるリスクは小 |
| このように、収益下押し圧力は避けられないとしても、以下のように、一方で収益拡大要因が強まっていることに加え、収益鈍化が企業活動に与える制約も限定的とみられることから、素材価格の上昇が直ちに景気失速の引き金になるリスクは小。 |
| (1) |
5兆円という経常利益減少額は、売上高が3%程度増加すれば相殺可能と試算されること。実 際、売上高は足元ですでに3%増レベルにまで回復しており、さらに今後の景気回復局面のな かで増勢が強まると予想されることから、素材価格上昇による減益効果よりも、売上増による 増益効果の方が上回るとみられること。 |
| (2) |
製造業部門では、生産性を引き上げる動きが定着して、収益体質の改善が進んでいるため、マ イナス影響の吸収余力が高まっていること。 |
| 収益押し下げが設備投資に与えるマイナス影響も、以下の2点から軽微にとどまると判断。 |
| (1) |
キャッシュフローが設備投資を大幅に上回る状態が続いていること、金融機関の貸出態度がや や積極化していることを背景に、多少収益が悪化しても資金面での問題は発生しないこと。 |
| (2) |
そもそも素材価格の上昇は、世界的な景気回復の強まりを受けた需要増加を背景としており、 設備投資に対してはむしろ追い風の状況にあること。過去の傾向をみると、市況が改善して価 格が上昇に転じると、半年程度のラグをおいて設備投資が持ち直す傾向がみられる。 |
| 以上のように、素材価格の上昇は、向こう1年間程度に限れば、需給ギャップが残るなか価格転嫁が進まず収益圧迫要因となるものの、景気腰折れは回避されると判断。もっとも、中期的にも素材価格の上昇が予想されるなか、輸出急減などの外的環境の悪化により、収益圧迫圧力を売上増で相殺しきれなくなるリスクには要注意。また、逆に、海外景気が予想以上に強まる場合には価格転嫁が行いやすくなる可能性もあり、2~3年先以降の影響については注意深く見守っていく必要。 |
全文はこちら(PDF:51.2KB)