| 2004年02月19日 |
| デジタル家電の景気牽引力 |
| 要 旨 |
| 今回の景気回復局面では、デジタル家電関連分野が急速に台頭しており、今後の景気回復の牽引役としても期待が強まっている。 デジタル家電需要の拡大が個人消費を押し上げる力は、(1)全体に占めるデジタル家電のシェアが小さいこと、(2)最も需要拡大が期待される薄型テレビの市場拡大ペースが緩やかにとどまるとみられることから、当面は限定的と判断できる。 しかしながら、デジタル家電需要の拡大は、以下の3ルートを通じて、中長期的にみて、わが国経済の持続的成長に大きく寄与していく見込み。 |
| 1) | (1)需要拡大が内需中心で外需依存度は低下していること、(2)テレビの貿易収支黒字化 でみられるように高付加価値製品での輸出競争力が強まっていること、に象徴されるよ うに、外部環境の変化に左右されにくい方向でわが国経済の足腰が強化されつつあるこ と |
| 2) | 部品集約度の高さから電子デバイス需要の急拡大が見込まれるうえ、デジタル家電用の電子デバイスは日本企業が優位性を持っていることから、電子デバイス分野への大き な生産誘発効果が見込まれること |
| 3) | 電子デバイス需要の拡大が、半導体関連の設備投資を押し上げること 通信機械・コンピューター需要の低迷により電気機械全体での回復はみられないものの、以上3点を勘案すれば、デジタル家電主導の景気回復は息の長い持続性が期待可能。 |
| 電気機械産業の牽引役がデジタル家電にシフト |
| 2002年以降、電気機械の生産が回復局面に転じており、鉱工業生産全体の回復を大きく牽引。こうした電気機械主導の生産増加は、IT景気と呼ばれた前回の景気回復局面(1999~2000年)と同様の姿。 もっとも、電気機械生産の回復状況を仔細にみると、前回とは大きな違いが存在。すなわち、前回は、世界的なIT投資意欲の強まりを背景に、通信機械・コンピューター需要が力強く拡大し、それに伴い電子部品・デバイス生産も急増。一方、今回の回復局面では、通信機械・コンピューターはむしろ電気機械生産を押し下げる方向に働いており、代わりに回復が目立っているのはデジタルカメラ・液晶テレビなどのデジタル家電を中心とする民生用電子機械。 さらに、民生用電子機械の回復に引っ張られる形で、電子部品・デバイスも前回の回復局面以上に大きく増加。稼働率をみても、大半の業種で前回回復局面のピークに達しているなか、電気機械のなかでピークに達しているのは電子部品・デバイスのみ。情報通信機械では、民生用電子機械の急回復よりも通信機器・コンピューターの落ち込みの影響が大きく、稼働率は低水準。 このように、足元の電気機械生産の回復は民生用電子機械、とりわけデジタル家電だけに牽引されていている状況で、電気機械全体の「回復の強さ」は前回と同レベルながら、「回復の広がり」が見られず。こうした広がりの欠如は日銀短観の業況判断DIにも現れており、2000年には電気機械の景況感が大きく改善したのに対し、今回はようやく水面上に転じた段階。 今後の我が国経済を展望すれば、製造業部門の回復に依存する構造が続くと予想されるなか、デジタル家電の回復力の強さ・持続性に大きく左右されることに。 |
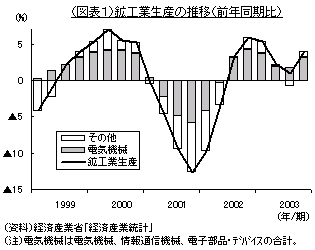 |
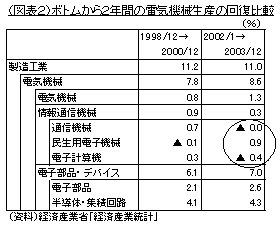 |
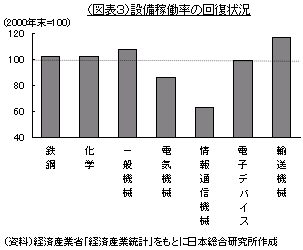 |
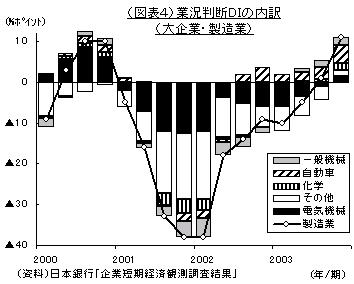 |
| 個人消費を押し上げる効果は限定的 |
| デジタル家電需要の急拡大により、一定の個人消費押し上げ効果が期待可能。もっとも、以下の点を勘案すれば、デジタル家電消費が景気全体を持ち上げる効果は、当面、限定的と判断。 |
| (1) | 個人消費全体のなかで、デジタル家電が占めるシェアは小。白物家電なども含めた民生用電 気機械全体でみてもシェアは2%強にすぎないことから、仮に市場規模が急拡大したとしても全体を押し上げる力は限られる。また、所得環境の大幅改善が期待薄ななか、デジタル家電需 要の拡大は既存製品の消費削減を伴う可能性があること。 |
| (2) | 今後、最も需要拡大が期待される薄型テレビについても、以下の3点から市場拡大ペースは緩やかにとどまる見込み。 [1]完全な新製品ではなく、既存製品に対する更新需要が主とみられることから、爆発的な需要拡大は見込まれないこと。 加えて、少子化などを背景に、テレビ市場全体の規模が緩やかな縮小傾向に転じる可能性があること。 [2]現状では価格が高いこと。高度成長期のカラーテレビ需要は、相対価格(月収で測った小売価格)の下落とともに普及率が高まっていった。さらに、この時期の相対価格下落は、テレビ価格の下落以上に、月収増の効果の方が大きかった。今後、所得の伸びが緩やかにとどまると予想されるなか、相対価格の下落も緩やかにとどまるとみられることから、普及率の上昇ペースは緩やかになる可能性。 [3]薄型テレビ購入のインセンティブとして期待される地上波デジタル放送の視聴エリアが狭いこと。 |
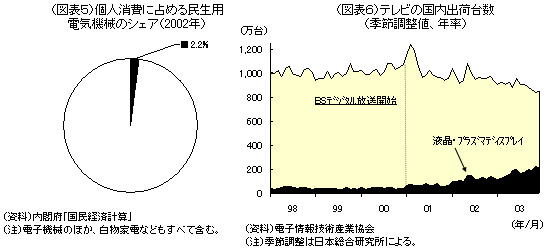 |
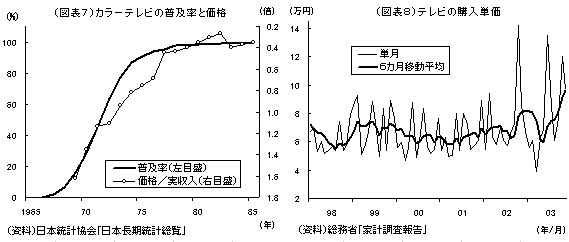 |
| 外需依存度の低下が景気の足腰を強化 |
| デジタル家電需要の拡大は、こうした直接的押し上げ効果よりもむしろ、(1)外的ショックへの耐性確保、(2)電子デバイス分野への波及、(3)設備投資の底上げ、という間接的効果の方が大。その意味で、中長期的にみて、わが国経済の持続的成長を支える役割を果たすことが期待可能。 |
| 1) | 外的ショックへの耐性確保 |
| デジタル家電出荷を内需と外需とに分けると、圧倒的に大きいのは内需であり、当面はこうした傾向が続く見通し。足元の出荷をみると、デジタルカメラやカーナビなどに加えて、薄型テレビ・DVDレコーダーといった新製品市場が急速に拡大し始めている状況。薄型テレビ・DVDレコーダーなどは、まさにこれから市場が立ち上がっていく段階であり、これは、前回のIT景気が、牽引役となったコンピューター・携帯電話がすでに一定の市場規模を確保していて、需要拡大余地が大きくなかったことと対照的。 一方、デジタル家電は貿易面でも安定した強さを発揮。例えば、テレビの輸出入はこれまで大幅な入超が続いていたが、2002年以降の輸出急増を主因に、足元では出超に転化。これは、欧米・アジア市場での需要拡大によって、薄型テレビの輸出が増加していることが主因。注目すべきは、輸出額増加の要因で、数量増加要因よりも価格(単価)上昇要因の方が大きく寄与している点。日本企業が得意とする高付加価値分野での市場創出により、低価格品に対抗しうる輸出競争力を回復できるという好例。 このように、(1)国内市場を中心とした需要拡大が外需依存度を低下させること、(2)日本が強みを持つ製品で輸出競争力が回復しつつあること、の2点は、外的ショックへの耐久度を高め、景気の足腰が強化されていることを意味する。したがって、2001年のように、欧米諸国でのIT投資の大幅減少を引き金に、わが国の電気機械生産が急減するようなリスクは小。 |
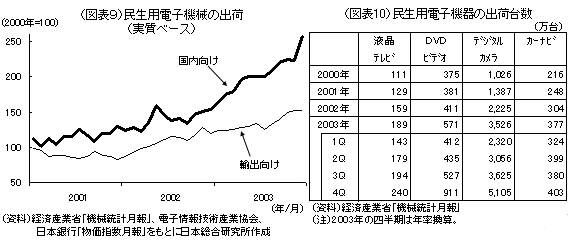 |
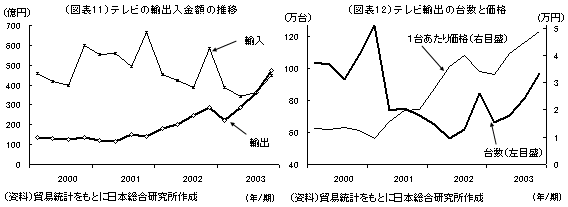 |
| 日本企業が強みを持つ電子デバイス生産が急増 |
| 2) | 電子デバイス分野への波及 |
| デジタル家電は部品集約度が高いだけに、電子デバイス分野への大きな生産波及効果が期待可能。実際、2003年の電子デバイス生産の内訳をみると、DRAM・マイクロコンピュータなどの低迷が続くなか、ディスプレイドライバ、フラッシュメモリ、CCD(電荷結合素子)、液晶素子などデジタル家電向け製品の生産が急拡大。 こうした電子デバイス製品は、CPUやDRAMとは異なり、現在でも日本企業が「強さ」を維持している分野。すなわち、デジタル家電の中核部品であるシステムLSIやCCDといったデバイスは、日本企業が市場をほぼ独占している状況。これら半導体は技術集約度が高く、単なるコスト削減で対抗できるような性質のものではないことから、これらの分野における日本企業の優位性は今後数年は崩れない見通し。したがって、今後のデジタル家電市場の拡大とともに、電子デバイスの生産規模は着実に拡大していくことが期待可能。 ここで、足元での電子デバイス生産をみると、液晶テレビ・DVDレコーダー市場の立ち上がりにより2003年後半から出荷が急拡大。前回の回復局面では出荷増に合わせて在庫を積み上げる余力があったのに対して、今回は、出荷が増加しているにもかかわらず在庫は低水準にとどまり、結果的に在庫率が大きく低下している。一方、稼働率も、すでに前回の回復局面のピーク水準にまで回復している(1ページ図表3)。すなわち、電子デバイスは、業界全体でみても、需要の拡大に対して生産が追いついておらず、需給が相当逼迫している可能性が大。 |
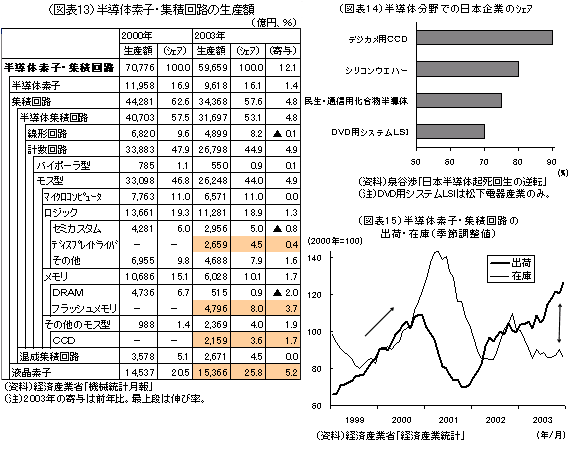 |
| 期待される電子デバイス関連の設備投資拡大 |
| 3) | 設備投資の底上げ |
| 電子デバイス需要の急拡大により、半導体関連の設備投資も今後回復傾向が一段と明確化していく見通し。すでに、足元で、半導体製造装置の受注が急増を始めており、設備投資を大きく押し上げている。また、半導体製造装置についても日本企業が優位に立っている分野であり、製造装置メーカーの設備投資を誘発する効果も見込める。今後も、デジタル家電が普及していくなかで、半導体関連の設備投資が景気を下支えする効果が高まっていくことが期待可能。 | |
| 4) | 息の長い景気押し上げ効果に期待 |
| 以上を総合すると、今回の生産回復局面では、通信機械・コンピューターの回復の遅れといったマイナス面が残り、電気機械全体の回復はみられないものの、デジタル家電主導の回復は、(1)内需を中心に、中長期的な市場拡大が見込まれること、(2)部品集約度の高さ、技術面での優位から、電子デバイスへの生産誘発が大きいこと、(3)個人消費・輸出だけでなく設備投資も大きく押し上げること、の3点を背景に、息の長い持続性が期待可能。 もっとも、デジタル家電に対する期待が過度に盛り上がるリスクには注意が必要。とりわけ、薄型テレビの需要拡大ペースは緩やかにとどまることも考えられるため、最終製品・半導体メーカーが数年後までの需要を見越して供給能力を一気に拡大させた場合、在庫調整・資本ストック調整が起きる恐れも。製品サイクルの短さ、部品集約度の高さは、需要拡大効果を高める一方で、シリコンサイクルの振幅を大きくするという諸刃の剣になりうる。その意味で、個別企業としては、業務エリアの明確化、新製品開発に一段と注力するとともに、不断のコストダウンに取り組んでいくことが必要。 |
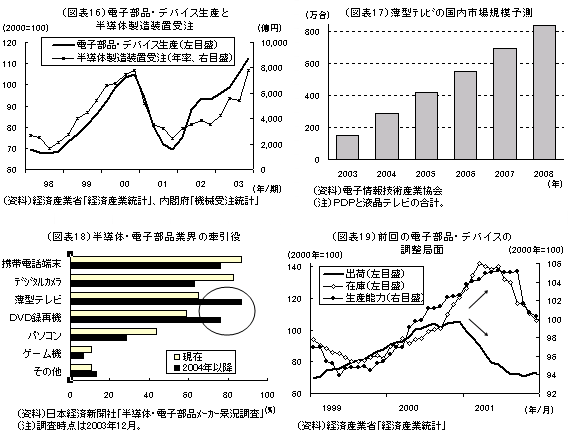 |

