| 2004年02月12日 |
| 引退世帯が支える消費と家計負担増加のインパクト |
| 【目 次】 |
| 【1】 個人消費の現状 (1) 減少を続ける勤労者世帯の消費 (2) 引退世帯の消費は選択的な支出が牽引する中で堅調維持 (3) 引退世帯の消費堅調の背景 [1]収入の安定性 [2]物価下落による金融資産の実質購買力の増加 (4) 引退世帯消費のインパクト (5) 消費性向上昇が持つ二面性 ―― 持続性への懸念 【2】 2004年度以降の家計負担増加 (1) 負担増加は2004年度5000億円、2005年度1兆円 (2) 負担増加の影響は限定的 [1]家計部門が政府部門から受け取る「ネット」の給付額の増加 [2]物価下落による金融資産の実質購買力の増加の持続 [3]雇用・所得環境の下げ止まり傾向 【3】 家計負担増加が家計に与える影響 【4】 個人消費の持続的な成長のために |
| 要約 |
| 1. | 2004年度、2005年度には、年金保険料の引き上げなど家計負担の増加につながる制度変更が相次いで予定されており、景気への悪影響を懸念する声がある。そこで以下では、個人消費の現状を整理した上で、今後の家計負担増加の影響を検討した。 |
| 2. | 個人消費の現状を世帯タイプ別にみると、勤労者世帯では、可処分所得の減少に並行する形で過去5年間に支出額が約1割減少した。一方、引退世帯では、[1]相対的な収入の安定性の高さ、[2]物価下落による金融資産の実質購買力の増加、を背景として、消費性向が上昇し、消費は堅調に推移している。 |
| 3. | こうした引退世帯の消費堅調は、世帯数の増加ともあいまって、わが国の個人消費全体を支える形となっている。もっとも、マクロの消費性向の上昇を招くため、中長期的には貯蓄不足による金利上昇を惹起し、日本経済にマイナスに作用するリスクがある。 |
| 4. | 配偶者特別控除の廃止や、雇用保険料引き上げに加え、2004年度政府予算案と税制改正案に基づく制度変更により、今後、年金保険料の引き上げ等、家計負担が増える予定である。家計の負担増加は、2004年度5000億円、2005年度1兆円超に上る。 |
| 5. | 上記の制度変更が家計に与える下押し圧力は無視できないものの、以下の事情を勘案すると、2004年度は消費の底割れは回避される見通し。 [1]家計の給付から負担を差し引いた「ネット」の給付額増加の状態が続くこと。[2]物価下落による金融資産の実質購買力の向上が引き続き消費下支え要因となること。 [3]雇用・所得環境の下げ止まり傾向に伴い、勤労者世帯の消費抑制が緩和されること。 もっとも、2005年度には、現在検討課題となっている一段の家計負担増につながる施策が実施される可能性があり、景気後退を招くリスクが高まることに留意が必要。 |
| 6. | 個人消費の持続的な成長のためには、[1]持続可能な社会保障制度の構築を着実に進め、制度への信頼を取り戻していくとともに、[2]経済再生を通じ、勤労者世帯の家計所得増加を実現することが必要。とりわけ、家計所得を増加させることは、マクロの貯蓄率低下に一定の歯止めをかけつつ消費を拡大するために不可欠。 |
| 昨年末に発表された2004年度政府予算案と税制改正案で、保険料の引き上げ、老年者控除の廃止など家計負担の増加につながる制度変更が相次いで発表された。2003年度税制改正で決定されていた配偶者特別控除の廃止や、雇用保険法改正による雇用保険料の引き上げに加えての負担増加となる。こうした制度変更の結果、消費の低迷が一層深まり景気へ悪影響が及ぶことを懸念する声があがっている。 そこで以下では、個人消費の現状を整理した上で、今後の家計負担増加の影響を検討した。 |
【1】個人消費の現状
|
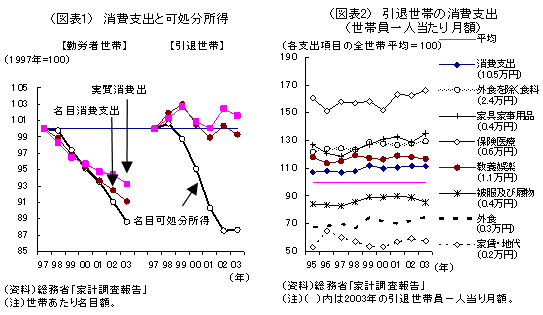 |
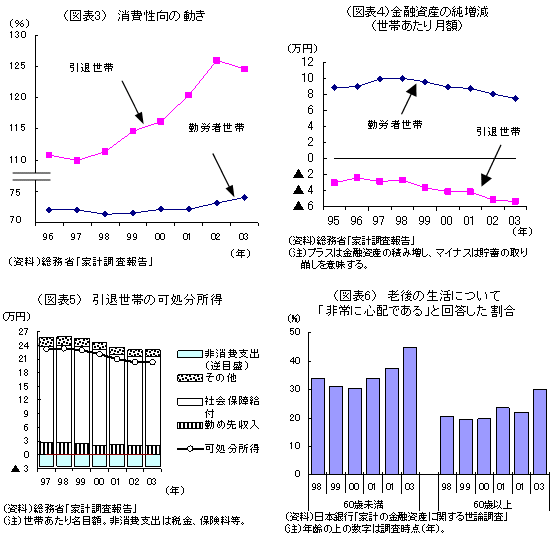 |
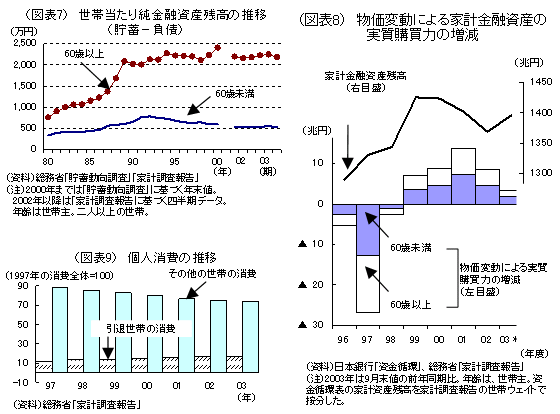 |
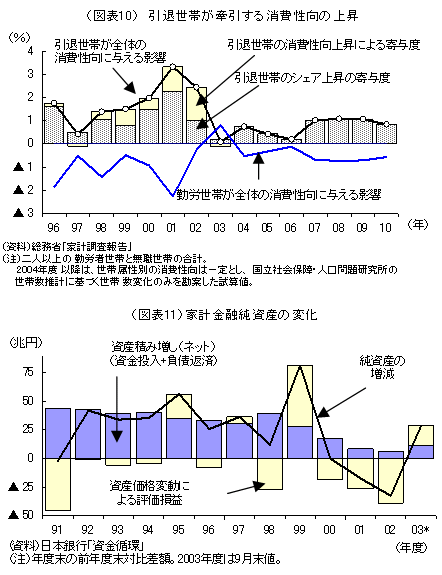 |
| (1)本稿では、データの制約から全世帯の7割強を占める世帯員二人以上の世帯についてみた。このうち引退世帯は世帯主が60歳以上で無職の世帯とした。自発的に「引退」した世帯に加え、就労意欲はあるが、職が見つからない「失業」世帯を含む。なお、勤労者世帯、引退世帯のほかに、[1]法人経営者、自由業者等からなる事業主等世帯(2003年の世帯シェア18.5%)と[2]世帯主60歳未満の無職世帯(同1.7%)があるが、世帯シェアが小さいこと、サンプル数が小さく統計の振れが大きいこと、[1]については収入のデータが公表されていないことから、本レポートでは勤労者世帯と引退世帯をとりあげた。 |
| (2)勤労者世帯でも、世帯主50歳台、60歳台の世帯では消費性向が上昇傾向にあるものの、20歳台、40歳台が低下し、勤労者世帯全体では微増にとどまっている。 |
| (3)総務省の「全国消費実態調査」によれば、実物資産も、金融資産同様、高齢者世帯が多く保有している。しかし中古住宅市場の整備やリバース・モーゲージの普及が遅れるなか、家計が実物資産価値を流動化し、消費につなげることは事実上困難であるため、本稿では、金融資産のみをとりあげた。 |
| (4)世帯主60歳未満世帯の金融資産残高の伸び悩みは、持ち家率が上昇し、金融資産が実物資産(持家)に置き換わった影響を一部含むものの、基本的には、貯蓄余力低下のあらわれであると判断される。 |
| (5)二人以上世帯の数。単身の引退世帯も2003年には360万世帯(単身世帯全体の26.4%)に上る。 |
【2】2004年度以降の家計負担増加
|
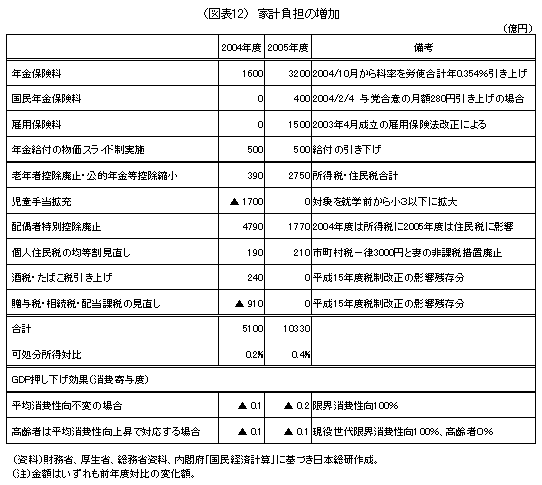 |
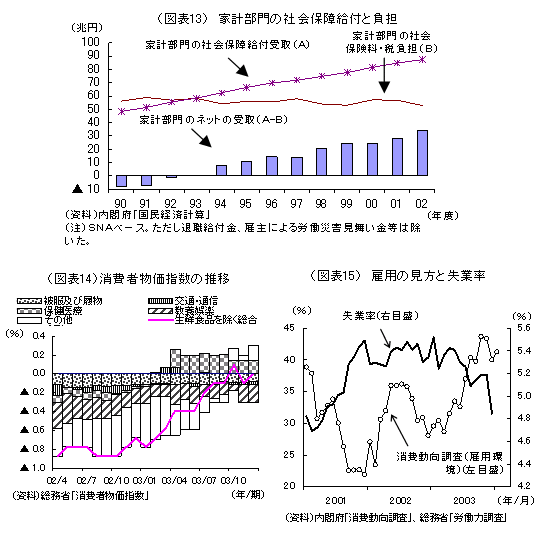 |
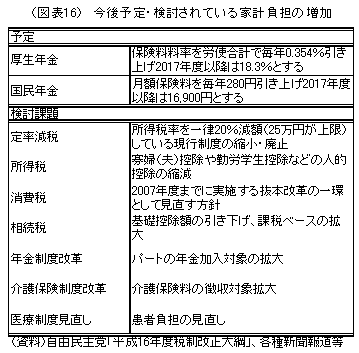 |

