
日本総研では2023年後期から「子ども社会体験科 しくみ~な®」(以下、しくみ~な)の開発を始めました。開発にあたり、着想のヒントとなったフィンランドの教育カリキュラムYrityskylä(Me & MyCity) の創始者であるTomi Alakoski氏の多大な協力を得ました。Alakoski氏は元教員で、仕事をするなかで学校での学習と社会とのつながりの必要性を感じ、Yrityskyläの開発に着手されたそうです。Alakoski氏がゼロから創り上げたYrityskyläはその後大きく成長し、現在、フィンランドの6年生と9年生の91%がYrityskyläに参加しています(※)。
今回はしくみ~なのアドバイザーも務めていただいているAlakoski氏に、子どもたちの教育における体験の重要さや、教育と社会のつながりに対する考え、企業の関与の重要性をお伺いしました。
※出所:nytウェブサイト(NYT - Yrityskylä)
 、2025年5月7日確認。なお、6年生と9年生ではカリキュラムの内容が異なる。
、2025年5月7日確認。なお、6年生と9年生ではカリキュラムの内容が異なる。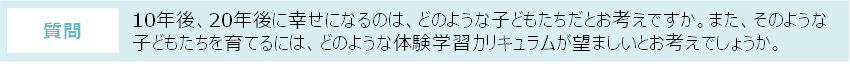
(Alakoski)価値観の基盤が人を幸せにすると私は信じています。ウェルビーイングを達成するには、自分の思考力と実践力を駆使すること、また、それは他者への優しさに根ざしていることが大切です。幸せな人は、健康、良好な人間関係、安全、基本的な生計手段を持っていると私は考えています。幸福の基盤は、今後10年、20年で大きく変わることはないと思います。
私たちはJohn Dewey氏の理論を踏襲しています。実践による学習を中核に据え、教育を総合的に行うためのDeweyの指針「学校を生活そのものと結び付ければ、すべての科目は必然的に相互に影響し合うようになる」を実践しています。彼の理論は、学習は現実世界の経験に根ざし、積極的な関与を伴うときに最も効果的であるという考えに基づいています。
そこには二つのキーワードがあります。一つは「実体験」です。教育は、情報の背景となる現実世界の経験に基づいている必要があります。彼の教育哲学は実用主義であり、現実を経験するべきだとしています。もう一つは、「子ども中心(Child-centered)」です。教育システムは子どものニーズと興味に焦点を当てるべきです。
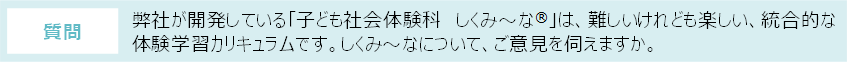
(Alakoski)子どもが学習プロセスに積極的に参加できると、学習はより意欲的で意義深いものになると思います。Yrityskyläなど、これまでの私自身の経験もこの考えを裏付けています。この学習アプローチは、従来の教室環境での学習が難しいと感じている子どもの助けになることがよくあります。例えば、教室で良い学習成果を上げるのに苦労している子が、Yrityskyläでは最も積極的で意欲的だったと頻繁に報告されています。ただし、これは自然に起こるものではありません。このタイプのアプローチには、教員側だけでなく、学習環境とカリキュラムの策定においても、相当な準備と努力が必要です。
私は先日、富士市でのしくみ~なの社会体験学習環境を視察しました。私がYrityskyläを開発しているときに感じた、問題解決や協働といった「学びの音」、つまり子どもたちの会話や活動から生じる様々な音が聞こえてきました。生徒たちが意欲的で、様々な役割を積極的にこなす様子を目にしました。子どもたちは、タブレットのなかにはいった金流アプリというものを使っていました。銀行システムを通じ、民間経済と公共経済でお金がどのように循環するかを具体的に学んでいました。また、富士市の体験の全体の共通のキーワードになっていた「防災」は、何かが起こった時にどう行動するかを学ぶ上で若者にとって重要な課題であり、子どもたちが学ぶ良い機会だと思いました。
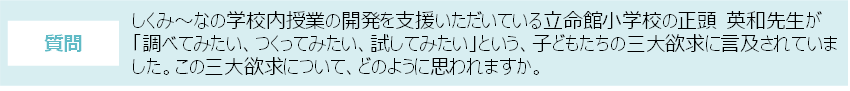
(Alakoski)素晴らしいアイデアだと思います。子どもは本来好奇心旺盛で、いろいろなことに挑戦したいという欲求を持っています。子どもの好奇心をサポートし、実験を奨励するのは大人の役割です。4Hフィンランド(注)の哲学は、「実践することで最もよく学べる」という考えに基づいています。この考えと正頭先生の考えには多くの共通点があると思います。
我々は何か行動をして、そこから何かを学ばなければなりません。先生と一緒に学校を出て学びに行きましょう。
(注)約45,000人のメンバーを擁する、フィンランドの青少年組織(非営利団体)。子供、若者、家族、そして活動を支援する意向のある大人で構成される。メンバーの平均年齢は13歳。(出所:4Hフィンランドウェブサイト(フィンランドの4H - Suomen 4H-liitto)
 、2025年5月8日閲覧)
、2025年5月8日閲覧)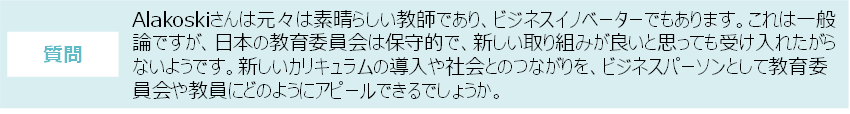
(Alakoski)本質的な問題は、「なぜ私たちは子どもたちを教育するのか」ということです。
私は、カリキュラムや教育は、世界や社会におけるスキルや知識のニーズがどのように進化しているかと密接に結びついているべきだと考えています。新しいイノベーションが絶えず生まれ、仕事の性質は変化しています。私たちは30年前と同じ仕事をしているわけではありません。将来、人工知能は多くの仕事を変革し、生産性は向上するでしょう。学校は子どもたちに基礎的なスキルを教えるべきですが、周囲の社会と連携しながら、新しく、より良い、そしてより意欲的な学習方法を模索することも同様に重要です。そのため、学校が周囲の社会とオープンな対話を行い、子どもや若者が社会で活躍するための十分な準備が整うようにする教育システムを構築することは有益です。学校教員の姿勢も、時代に合わせて変わるべきだと思います。
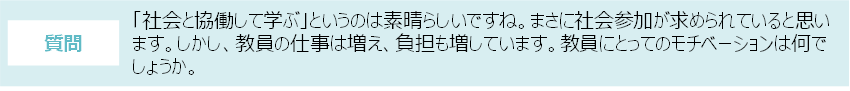
(Alakoski)すべての教員にとって最も重要なことは、子どもたちが可能な限り効果的に学習できるようにすることだと私は信じています。子どもたちのやる気が出れば、教員のやる気も高まります。少なくとも私の場合、生徒が熱心でもっと学びたいと熱望しているとき、仕事へのモチベーションが大きく高まりました。
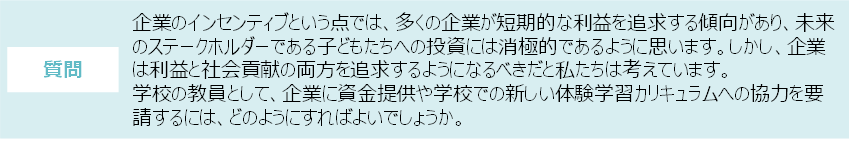
(Alakoski)ビジネスと産業は、学校と同じくらい重要な社会の構成要素です。学校の役割は、子どもや若者に人生で成功するためのスキルを提供することです。学校卒業後、人生の中心となるのは仕事の世界です。ビジネスと産業の成功は学校教育の質にかかっており、将来の労働力に必要なスキルの習得もサポートする必要があります。賢明な企業は、学校のこの役割をサポートし、将来の従業員に好印象を与えることで、優秀な人材の獲得にも成功すると理解しているはずです。
フィンランドの教育は、この20年間で劇的に変化してきました。企業も公立学校での教育について考えなければなりません。最近では、評判の高い企業は利益も高いようです。社会体験学習の環境は学校では提供しにくいのですが、子どもや若者の家庭に大きな影響を与える重要なものです。(教育への)関与の量が評判の鍵です。子ども向けのプログラムの量と、プログラムに参加する子どもたちの数が重要なのです。社会活動への関与が少ないと、評判はわずかしか上がりません。量を追求するには、分かりやすいコンセプトとプログラムが重要です。
(編集後記)
Alakoski氏には2024年11月に日本にお越しいただき、日本総研しくみ~な ふじの中学二年生の社会体験活動の見学、日本総研YouTubeでの立命館教育プロデューサー正頭先生との対談、そして、弊社主催の「子ども社会体験共創交流会」でのプレゼンテーションを行いました。今回のインタビューは、その訪日時に実施したものです。プレゼンテーションではフィンランドのアントレプレナーシップ教育やYrityskyläの開発に至った経緯について講演をしてくださいました。彼は物静かな紳士ですが、インタビュー中にある「実体験」「子ども中心(Child-centered)」をキーワードに、子どもたちの社会体験の重要性を強く信じ、熱い想いと実行力を持ってYrityskyläを立ち上げた方です。
彼は、仕事・生活の活動に伴うお金の流れを一つの体験カリキュラムで包括的に学ぶことにこだわりを持っていて、日本総研がしくみ~なの社会体験活動を開発する際に、「銀行システムは活動のコアだから絶対必要だ」と何度も何度もお話されていました。世の中には、子どもの職業体験、市民としての体験、金融経済教育が、それぞれ個別にたくさん普及してきているように見えます。しかし、それらが連携した社会のしくみを学ぶ体験はあまりありません。実社会ではそれらは意識することなく連携しているのに、です。日本総研は、富士市のしくみ~な ふじから、お金の流れも体験できるアプリを導入して、仕事や生活の活動の都度、お金をポチポチして動かす体験を始めました。今回、彼にその様子を見学していただき、良い感想を得られたことで、わが国の出前・座学型の金融経済教育を刷新して体験型へと高度化する励みにもなるのではないかと思います。
※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。

