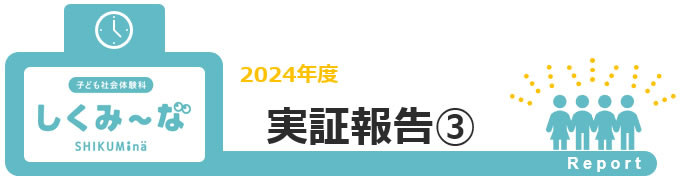
このシリーズでは、日本総研が開発した、学童期の子ども向けのカリキュラム「子ども社会体験科 しくみ~な®(以降、しくみ~な)」の、2024年度の実証の様子を紹介してきた。最終回となる今回は、渋谷区や富士市での実証の振り返りを行い、成果や課題、今後の展望を記す。
(1)実証の振り返り:教育的側面
2024年度、渋谷区では延べ260名、富士市では延べ160名の児童・生徒が、しくみ~なに参加した。しくみ~なの教育的意義を、こうした児童・生徒の声や学校関係者の声から振り返ってみたい。
(ア)児童・生徒からのフィードバック
初回の実証地となった渋谷区では、児童に事後アンケートを行った。まず、「しくみ~なはどうでしたか」(選択肢:とても楽しかった、どちらかと言えば楽しかった、どちらかと言えば楽しくなかった、楽しくなかった)という設問では、学年やクラスによって細かな差はあったものの、全体として8~9割が「とても楽しかった」と回答した。また、難易度についての質問(選択肢:とても難しかった、どちらかと言えば難しかった、どちらかと言えば簡単だった、簡単だった)には、学年やクラス、社会体験活動の実施回数によってばらつきが出たものの、全体として「とても難しかった」、「どちらかと言えば難しかった」の合計が過半を占めることがほとんどであった。
また、自由記述で「しくみ~なの活動や準備において学んだこと」という質問をしたところ、子どもたち自身の言葉でさまざまな気づきや学びについてのコメントが集まった。以下に一部を抜粋して、子どもたちの記載内容を紹介する(一部、明らかな誤植と思われる箇所は日本総研にて修正)。
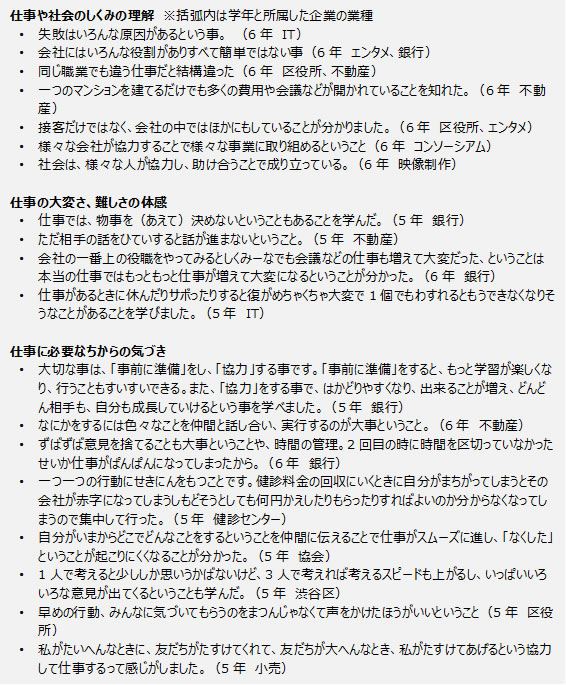
アンケート結果からは、児童がそれぞれのタスクに正面から向き合い、難しさを感じながらも、達成感や充実感を感じていたことが把握できた。
富士市の実証では、しくみ~なの教育的効果を測定するため、信州大学 学術研究院 教育学系・教授の伏木先生にアドバイスをいただき、しくみ~なの学びを行う前と後で児童にアンケートを行うこととした。「思考力・判断力・表現力」と「学びに向かう力、人間性等」のカテゴリーに分け、子どもたちの回答が学びの前後でどのように変化するかを分析した。例えば、「わたしは、社会を構成する一員として、積極的に他者と協力したい」に「あてはまる」と回答した人は、事前事後を比べると、6年生でプラス12.5pt、中学2年生でプラス22.7ptになるなど、社会と自分のつながり、自分と他者のつながりを学び、社会に対して前向きな姿勢で関わろうとする児童・生徒が増加したことが把握できた。
(イ)教員・教育委員会からのフィードバック
現場の先生方、そして教育委員会の皆様には、現場の声を率直に届けていただいたり、児童の学びを深めるために調べ学習の時間を独自に設けてくださったりと、カリキュラム全般を通じて多大なサポートをいただいた。特に、しくみ~なのカリキュラムを単独で考えるのではなく、年間の学習計画の中での位置づけを決めて取り組んでいただくことで、前後の学びとの連続性を生かすことができ児童の学びの最大化につながることなどは現場の先生方との会話から教わったことであり、日本総研の視野が大きく広がるきっかけとなった。
先生方からは、「子どもたちが日常よりも主体的に動いている。反省を生かして2日目に臨んでいる子どももいる。成長度が高いと感じる」、「子どもたちがこんなに活発にできるんだなという印象だった。普段、あまり人と一緒に活動できない子供が、今日は良く他の子どもとコミュニケーションを取りながらやっていた」などのコメントをいただいた。また、しくみ~なが「カリキュラム・オーバーロードという昨今の教育現場の課題への解決策の一つになるのではないか」とのお声もいただいた。
(2)実証の振り返り:事業的側面
もう一つの側面として、「みんなで支える」というしくみ~なの特徴を実現することができたか、という事業としての振り返りも行ってみたい。まず、運営面については、一定程度は実現することができた。カリキュラム開発においては教員や教育委員会の皆様に議論に参加いただいたほか、子どもたちが取り組むタスクの設計に企業/機関の皆様にご協力いただいた。また、カリキュラムの運営においても一部企業/機関の皆様に企画や社会体験当日の見守り等のご協力をいただいた。しくみ~なをきっかけとして、実証を行った学校からの職場体験を受け入れることになった、自治体との関係強化につながったといった声も企業の皆様からいただいている。子どもたちが居住する地域にある企業/機関を知り、地元に対する理解や愛着を深めるきっかけになれば嬉しい。
富士市においては、事前調整や準備、運営は地元の一般社団法人まちの遊民社に担っていただき、日本総研はノウハウの提供のみを行った。関与いただく皆様にしくみ~なのビジョンを伝え、適切に理解いただく方法の導入や、ノウハウ提供に際してのコミュニケーション効率化などの課題は継続検討が必要である。しかし、このカリキュラムを今後展開していくうえで、地元の組織に運営を担っていただくための課題が具体的に見えたことは今年度の大きな成果の一つである。
次に、運営資金面については、引き続き検討が必要である。しくみ~なを開発するにあたって着想を得たYrityskylä(ユリティスキュラ)の場合、国/自治体、民間企業、財団などがバランスよく資金を拠出しているが、日本総研の取り組みの場合、まだそこには至っていない。まずは本カリキュラムの認知度を上げるとともに、民間企業/機関も入って皆で公教育を支えていくことに賛同いただける方を増やすことが必要であり、そのためには、そうした活動が企業の社会的価値に結びつくものであるという仮説を検証し、説得力を持って民間企業の皆様を巻き込んでいけるようにすることが重要課題である。
(3)課題と今後の展望
2024年度は、しくみ~なを開発し、実証をしながら繰り返し改善するプロセスに取り組んできた。児童・生徒や学校関係者、自治体、企業、メディア関係者などさまざまな立場の方からフィードバックをいただいたことで、回を重ねるたびにコンテンツが充実し、運営が改善されてきた。しかし、まだ、入り口に立ったばかりである。地域に所縁のあるさまざまなプレーヤーが協力し、運営面でも資金面でも持続可能な、質の高い教育を提供できるよう、取り組んでいく所存である。
このシリーズでは、2024年度に実施した子ども社会体験科しくみ~な®の実証の様子を紹介してきた。開発を始めてから短期間で、ここまで実証を進めることができたのは、ひとえに、協力いただいた児童・生徒、先生方や教育委員会、自治体、協賛・協力企業、有識者の皆様のお陰である。始めたばかりで何者ともわからないカリキュラムを受け入れ、前向きに楽しみ、フィードバックをくださった皆様に心から感謝し、さらに良いものにしていくべく準備を進めている。今後も引き続き、しくみ~なに注目していただけるとありがたい。
以上
※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。
関連リンク
子ども社会体験科 しくみ~な®
・2024年度実証報告①
・2024年度実証報告②
・2024年度実証報告③

