「シンクタンクの目」 研究開発戦略、不確実性に動的対応
出典:日本工業新聞 1月23日号
1980年代日本経済は空前の繁栄を謳歌した。この頃「研究所ブーム」が沸き起こり、こぞって研究所が設立された。しかしながら、昨今その存在意義が問われることが多く、さらに日本の経済事情も向い風となり、全体的に縮小傾向にある。このような傾向の主な原因として「研究開発の効率性」が問題視されている。研究開発の効率性を意識した具体的な対応が必要である。研究開発を取り巻く様々な不確実性に対して、いかに柔軟にかつ動的に対応するか、ということが今後の研究開発戦略を考える上で重要なポイントとなる。
ポイント
研究開発における不確実性を、スタート時点で静的に捉えるのではなく、時間軸に沿って動的に捉えることが重要である。
デスバレーの深さとシナリオツリーとを関連付けることにより、デスバレーの深さを具体的かつ動的に認識することが可能となる。
研究開発を動的に捉えることにより、組織内での的確な意思決定次第で、埋もれた技術を発掘することが可能となる。
かつて海外に架電した際にこちらが話しかけてから応答が返ってくるまでに非常に時間がかかっていた時期があった。今日では、国内に架電するのも海外に架電するのも、時間的な差異を感じることはほとんどない。通信媒体が電気から光に移行したことが大きな理由であろう。近年では、米デルをはじめ米ハイテク企業各社はコスト削減のため、顧客対応電話サービス拠点をインドに移している場合が多い。クレーム対応の電話のやりとりで電話回線に遅延があるようでは話しにならない。
IP電話への移行が盛んであるように、近年ではデータ通信のトラフィックが大きな割合を占める。一本の光ファイバーで最大約十Gbps(注1)のデータ伝送が可能であるが、さらなるトラフィックの増大に対応するためにWDM(注2)という技術が使われている。一本の光ファイバーに160波分の光を束ねた場合、約1.6Tbps(注3)のデータ伝送が可能という計算となる。
「Gbps」:1秒あたり1ギガビットのデータが流れる速度。1ギガビット=10億ビット。
「WDM」:Wavelength Division Multiplexingの略。1本の光ファイバーで、波長が異なる複数の光信号を伝送する技術のこと。
「Tbps」:1秒あたり1テラビットのデータが流れる速度。1テラビット=1兆ビット。
実際に1.6Tbpsというデータ通信を常時運用している通信事業者が存在するかどうかは不明である。しかしながら、大陸間の長距離海洋通信や、最近では加入者側からのイーサーネット信号を束ね、通信事業者側への橋渡しをする場面など、近年の光ネットワークプラットフォームとしてWDM技術は欠かすことができない。
この現在の情報通信において欠かすことのできないWDMに関する技術はどのような過程で誕生したのであろうか。簡単にその歴史を振り返る。1980年代中頃から当時のNTTではPLC(注4)技術の開発が進められていた。PLC技術は、光の多重や分離、光ルーティングなどを光の波長単位で実現可能とする、光通信においてはコアとなりうるキーデバイス技術である。しかしながら、WDMのキーデバイスとしてPLC技術を応用したAWG(注5)というデバイスが実用化されたのは1990年代中頃である。PLCという新技術が、約10年の歳月を経て、AWGとして日の目を見るに至ったことになる。
「PLC」:Planar Lightwave Circuitsの略。シリコンや石英基板上に、光の通る光回路を形成し、その回路パターンにより、光信号の分離や多重など各種機能を実現する。
「AWG」:Arrayed Waveguide Grating の略。WDMシステムにおいては、複数波長の光を1本の光ファイバーで伝送させるため、複数波長を1本に多重分離する機能が必要となる。AWGはその機能を、PLC技術を用いて実現する一つの方式。
ここで注目すべき点は「技術が最初に誕生してから製品化に至るまでの間、その技術に対する認識はどのように変化したのか?」ということである。PLC技術が最初に誕生した時にはWDMや光ルーティングといった言葉すら無かった。このような時期に、PLCという新技術に対してどのような将来像を描き、その後10年以上にわたり研究開発を継続することができたのであろうか。近年よく聞かれる「デスバレー」(注6)という現象は、WDMの場合、まさにこの10年という期間に潜んでおり、これをうまく乗り越えることができた一例といえる。
「デスバレー」:北米において、製造業が圧倒的な優位性を失い産業競争力低下が深刻化した80年代の状況をデスバレーと表現する。研究開発から実用化の中間段階において事業化が可能か否かの見極めが困難となり、投資が不足してしまうことによって研究開発成果が死んでしまう状態をさす。
ベースとなる新技術(PLC技術)の誕生後もその技術に対する研究開発投資が継続され、非常に長い年月を経てから真の意味(AWGの実用化)が見出されるに至った。なぜそのような長い期間、研究開発を継続することができたのかは推測の域を超えない。研究開発に対しては当時追風的であった日本の景気を考慮すると、現在の日本の決して芳しいとはいえない経済環境下において、同様のケースで研究開発が継続される判断が下されるかどうかは疑問である。
WDMの例から学び取れる重要な点は、新技術が誕生した時点で「新技術の将来的な真の意味を考察し、研究開発投資に対して適切な継続可否の判断がなされるシステム」をその組織や企業が持ち合わせているか、ということである。WDMの事例の場合、そのような系統だったシステムの中で継続の判断が成されたのかどうかは不明である。しかしながら、このようなシステムが無いために埋もれてしまっている技術の数は計り知れない。
新技術の将来的な真の意味を見出せるか否かによって、以降の製品開発に至らしめる研究開発投資の継続可否が判断される。従って、新技術が誕生した時に、その時点での企業や組織の経済環境だけといった狭い視野で新技術の将来性を判断すると、将来的な価値が過小評価されてしまい、以降の研究開発投資が継続されない。これは、新技術が「デスブランチ」(注7)を乗り越えられず、そのまま埋もれてしまうことを意味する。そのような状況をできるだけ回避するためにも、技術的な動向や競合他社の動向は当然のことながら、その他の社会、経済、政治、環境などの動向も総合的に考慮した上で将来的なシナリオを動的に捉え、その真の意味を判断していく必要がある。
「デスブランチ」:組織での意思決定次第では、それがたとえ将来にポジティブな潜在性をもったものであっても、死に至る(製品化されない)ことでビジネスの機会を失う可能性のある分岐点のこと(新保、2003)。「【図表】埋もれた技術に対する将来的な意味付け」参照のこと。
ある一つの新技術が一定期間を経た後にその意味が見出され、具体的な製品化につながり日の目を見るに至るまでには、様々な不確実要因の積み重ねが存在するはずである。
【図表】 ある特定の結果事象に至るシナリオツリーのイメージ
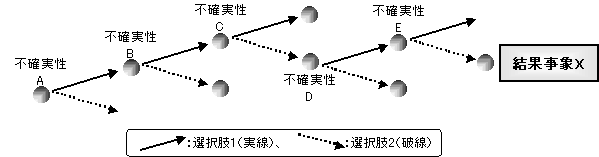
例えば上図表の例では、結果事象Xに至るまでにAからEまで5つの不確実性の積み重ねが存在することを示す。つまり、結果事象Xは、不確実性Aで選択肢1が選択され、不確実性B、C、Dを経て、最終的に不確実性Eで選択肢2が選択された結果、実現される。
結果事象Xを「AWGはWDM技術のキーデバイスとして不可欠なものとなる」と仮定すると、各不確実性としては技術的な問題点はいうまでもなく、その他にも「ブロードバンドアクセスの普及」、「通信業界の再編」、「専用線の衰退」、「光ファイバーインフラの整備状況」などが考えられる。それらの積み重ねにより最終的に「AWGはWDM技術のキーデバイスとして不可欠なものとなる」という結果に到達したと考えられる。
このようなシナリオツリー的なアプローチでの認識を適応すると、新しい技術の意味はある特定の時点で確定している訳ではなく、時間の経過とともに変化しているという捉え方ができる。例えば前述の図表を例にとると、不確実性AからEまでが同時に発生する訳ではなく、各不確実性は時間軸上に沿ってある程度順番に発生すると考えられる。ある時点で結果事象Xに到達する確率が30%であったとしても、次の不確定事象の選択如何によってその確率が変動する。つまり、時間軸に沿って各分岐点を選択していく過程で、その意味が時間とともに変化しているという見方ができる。つまり、シナリオツリー的なアプローチにより、時間軸上での動的な変化への柔軟な対応が期待できる。
このシナリオツリーの分岐点数、つまり不確定事象の数、そしてその積み重ねとして得られる結果事象の数が、このデスバレーの「深さ」に対応するという考え方ができる。例えば、ある研究開発対象に不確実性要素が全くなく、「顧客ニーズに合致した製品化が確実である」という結果事象が100%の確率で発生するのであれば、デスバレーは全く無いことになる(投資に対する障壁がない)。これとは逆に、不確定要素が多ければ多いほどデスバレーは深くなることを示す(投資判断が難しくなる)。
【図表】 デスバレーとシナリオツリーの関係
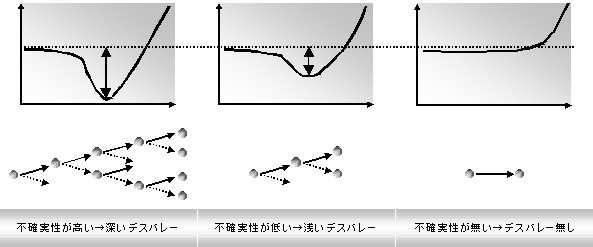
このように、単にシナリオツリーだけを用いて将来的なシナリオを考察するのではなく、デスバレーの深さとシナリオツリーとを関連付けることにより、デスバレーの深さを具体的かつ動的に認識することが可能となる。
近年、休眠状態にある知的財産や、製品化には無関係な技術に関する論文、その他具体的な結果として公開されるまでにも至らない数々の研究開発成果などに対する価値評価が注目されている。このようないわゆる「埋もれた技術」に対して、これまで述べてきたような動的な捉え方の適応が組織的に可能になると、思いがけない「掘り出し物」を発見することができるかもしれない。
下図表は、「埋もれた技術」に対して将来的な意味付けがなされる様子をグラフ化したものである。ある時間「t1」においては、技術P(破線)も技術Q(一点破線)もともに「埋もれた技術」であり、この時点では技術Pの方が重要度が高いと仮定する。しかしながら、将来的なシナリオを考慮した場合、技術Qの方が製品化の可能性が高いという場合もある。このように、ある技術に関する真の意味(重要度)を動的に捉えることができるようなシステムを構築することが重要となる。
【図表】 埋もれた技術に対する将来的な意味付け
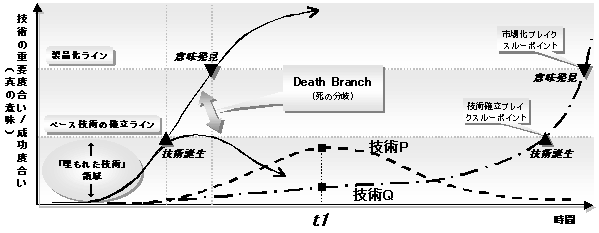
前もって新技術の意味を見出すということは、シナリオツリーが描け、各不確実性においてどのような選択がなされるかということが分かっていることが前提条件となる。これは非常に難しい。不確実性を考慮する際にはその技術そのものに関連する事項だけでなく、周囲のビジネス環境など様々な要素を考慮する必要がある。それら全ての不確実性を洗い出し、さらにどのような選択肢が選ばれるかを前もって予測することがいかに難しいかは想像できよう。しかしながら、不確定事象Xという選択肢がどのような確率で発生するかを前もってある程度認識できているかどうかということは、研究開発に対する投資継続の可否判断という重要な経営判断に大きな影響を及ぼすことは間違いない。
- メディア掲載・書籍

