「告発サイト」勢い続く米国 企業側の対応にも変化
出典:朝日新聞社 「論座」 2000年1月号
インターネット先進地・米国では、ネット告発のうねりは日本に2年ほど先行している。
「ネット・コンシューマリズム」とも言うべきこの動きに対し、企業側の対応も工夫が進んだ。われわれは何を学べるのか。
米国でのネット上の事件は、インターネット以前の段階から、「企業対プロバイダー」あるいは「個人対プロバイダー」の形で現れていた。プロバイダーサービスの中で、企業や個人に対する誹謗・中傷内容がネット上に掲載され、その責任の所在がプロバイダーにあるのかどうかを巡った事件が主なものであった。
例えば、最初のネット上の大きな名誉毀損事件として、1991年の「カビー対コンピュサーブ社事件」があげられる。データベースサービスを提供するカビー社が、コンピュサーブの会議室上で自社が中傷されたとして、コンピュサーブ社を訴えたものだ。これは、コンピュサーブ社は事前にその内容を知る事ができなかった(単なる情報の「ディストリビューター」にあたる)と判断され無罪になった。
●ネット・コンシューマリズムの実態
ところが、インターネットが本格的にtoy(玩具)からbusiness(ビジネス)へと転換し始めた1996年前後を境として、ネット上で消費者が一般企業に対し自身の主張をアピールするものが急増した。ネット・コンシューマリズムの台頭である。その後、現在に至るまで、様々なケースが起きているが、消費者と企業側の対決の度合いに応じて、次のような整理が可能と思われる。即ち、①苦情、②告発/侮辱、③紛争(商標侵害等)、④収束(和解/サイト閉鎖等)の四段階だ。
①苦情
企業に対する消費者からの苦情がネット上のウェブに掲載される例は、後を立たない。数々の企業が消費者の不満を突きつけられている。九九年時点で現存しているものとして一例を挙げれば、旅行会社の対応が悪かったとかコンピューターソフトの使い勝手がよくないといった苦情をのせたページを開き、同様のケースを募る、といったものがある。
②告発/侮辱
苦情の多くが、散発的で言いっ放しに近いものであるのに対し、ある企業を系統的に批判したり、具体的な補償を求めたりする「告発」のサイトも、米国では早い時点から出現した。しかも日本でも名の通っているような大企業が、数多く対象になっている。日本では東芝事件で脚光を浴びたような、音声や映像といった手段もすでにかなり用いられているようだ。
【マクドナルド社】
環境保護団体のロンドン・グリーンピースは、1996年、ハンバーガーチェーンのマクドナルド社に対する苦情、告発サイト「マック・スポット」を開設した。両者は数年前から、グリーンピース側の告発を発端に裁判で争っており、グリーンピース側は裁判過程で明らかになった情報をもとにサイトをつくった。このサイトの12週間でのヒット数は172万5,000回、4万1,000人以上とされ、USAトゥデイ等の主要紙やテレビ局もこぞって取り上げた。現在も係争中だが、裁判の結果のいかんに関わらず、同社は「ネット・コンシューマリズム」への対応を誤り、ブランドイメージを大きく傷付けたといえる。
【ゼネラル・モーターズ(GM)社】
GM社製サターンSC2クーペに乗っていた妻が欠陥部品のために事故を起こしてけがを負ったと主張している消費者の告発サイトが最近開設された。告発者の主張によると、GM社は2人の技術者を送って車を分解し、証拠を隠滅してしまったとのこと。その後同社に苦情を寄せても対応がなされないために、告発サイトを立ち上げたようだ。
【ペプシ・コーラ社】
ペプシコーラの未開封のビンが爆発した事によって片目を失明したとする少女の告発サイト。少女の写真を載せている。告発者によると、事件は3年前に起き、裁判で係争されているが、同社側が様々な手立てを講じて裁判を遅延させようとしため、告発サイト作成に踏み切ったという。サイトは現存している。
GM社とペプシ社への告発内容の真偽は不明だが、今のところ両社は静観しているようだ。
米国の事例の特徴として、企業を侮辱するような名前を使ったサイトを立ち上げる事例が目立つ。具体的には企業ドメイン名(ウェブ上のサイト名)に下品な単語を加え、企業イメージ全体のダウンを図るものだ。
【ベル・アトランティック社】
同社は当初、bellatlanticsucks(くそったれベルアトランティック).comというというドメイン名を自ら登録し、告発サイトのドメインとして用いられるのを防いでいたが、そのドメイン契約を更新しなかった。その結果、その名前が取得されてしまい、1996年に苦情サイトとして開設された。不当な料金の請求、サービススタッフの対応が悪い等の様々な問題に関して、多くの人がクレームを寄せている。
【チェース・マンハッタン銀行】
ある顧客が、自分のクレジットカード利用明細書に、身に覚えのない650ドルの記載があったという苦情を掲載するために、chasebanksucks.comというサイトを1998年に開設した。その後、同行への様々なクレームが集まる場になった。銀行側は、サイト名が侮辱的であること、またサイト内の苦情が虚偽であるとして、サイトオーナーを訴える準備があると警告。同銀行はchasesucks.com等のドメイン名は、告発サイトに使われないように自ら取得していたが、悪意のあるドメイン名をすべて購入することは不可能であったようだ。
③紛争(商標侵害等)
告発/侮辱のような消費者側からの積極的な攻撃に対し、企業側が「応戦」し、争いになる事例も増えている。「言論の自由」もあり、ウェブ上での苦情自体は手の打ちようがないが、商標を侵害するドメイン名については訴えるという姿勢だ。
【バリートータルフィットネス社】
同社は全米に店舗を展開しているヘルスクラブ。カルフォルニア在住の顧客が、他のチェーン店も利用できるように会員グレードを上げる手続きを行ったが、クラブ側がチェーン店を利用させなかったとして、BallySucksサイトを1997年に開設した。苦情自体は受け入れられたが、その頃には他顧客からの苦情がサイトにあふれていた。同社は顧客の苦情に対処する努力を行うとともに、開設者を商標侵害で訴えたが、裁判では退けられた。
④収束(和解/サイト閉鎖等)
告発サイトに対し、企業側が金銭的補償や製品回収の姿勢を示すことで、収束に至ったケースも出ている。まさに「ネットコンシューマリズム」の力が発揮されたかたちだ。部分的に企業側の主張が通ったケースもあるが、その場合でも苦情サイトそのものは継続しているものもある。
【ダンキンドーナッツ社】
同社は「お好みに合わせてコーヒーをお楽しみください」という広告を打ち、4種類のミルクを選べることを示していたが、スキムミルクの要望にはこたえなかった。これを不満に感じたある消費者が同社への苦情を自分のホームページ上に掲載したところ、類似クレームが多数集まったため、独立したクレーム・サイトを1997年に立ち上げた。ダンキン側は商標侵害を理由に、告訴も辞さない旨を告げてサイトの閉鎖を申し入れたが、拒否される。その後、同社側が問題のサイトを買い取る事で和解。条件は非公開だが、同社に対する意見を寄せられる場所が同社サイトに設けられた事から、告発者側は当初の目的を達したと考えて和解したようだ。
【フォード・モーターズ社】
1996年に開設された「Association of Flaming Ford Owners」というサイト上には、欠陥車が炎上している写真や、過去のフォード車に対する訴訟の記述が多数掲載されている。こうした指摘を深刻に受け止めた同社は、エンジン点火装置に問題があることを認め、870万台の普通車やトラックの不良製品回収を発表。サイトは現在も継続している。
【Kマート社】
元従業員が、同社でひどい体験を受けたとウェブ上に掲載したところ、告発サイト対策をしているコンサルタント会社がCNNオンラインでのインタビューで同サイトについて触れたため、注目が集まった。企業側は当該サイトを閉鎖するように告発者の所属する学校に勧告。学校側は商標侵害の恐れが有ると判断し、作成者はKの文字をXに変えて、サイトを持続させた。
●閉鎖説得を請け負うサービスも
このように企業活動に多大な影響を及ぼすようになった「ネット・コンシューマリズム」の台頭に対して、米国企業はどのような手立てを講じているのであろうか。企業へのコンサルタント活動が発達した米国では、この分野に対応したビジネスも、すでに盛んに行われている。
例えば、ウェブサイトを監視し、苦情サイトへの対処方法をコンサルティングしているものとしては、ミドルバーグ・アンド・アソシエイツ (M&A) 社がある。ウェブ、メーリング・リスト、チャット等の様々なネット上の領域を、検索し、誹謗、中傷、苦情が発見された場合、それを掲載した個人を特定し、その人とコンタクトを取る。相手の主張を理解しそれに適切に応じ、告発サイトを閉鎖してもらうように説得する、という。
告発サイトへの対処では、「スピード」と「最初のコンタクト時における対応の仕方」がとりわけ重要という基本方針を掲げる。コンピューターメーカーのEPS社などを顧客として持ち、同社に対する苦情サイトを閉鎖させた実績を持つ、としている。
類似のサービスとして、1995年に開始され現在世界中に800以上の顧客を持つという eワークス社の「eウォッチ」サービスがある。ここの場合は、告発サイトに対する反論を掲載するためのミニサイトの立ち上げサービスも提供しているのが特徴だ。
1995年にニュース番組で、あるクッキー会社がO・J・シンプソン裁判の陪審員にクッキーを送ったという事件が報道された。実はこれは事実ではなかったのだが、数分の内にネット上のニュースグループへ情報が流れ、ネット上で同社への不買運動が巻き起こった。米国では有名になった事件だ。eワークス社によると、このクッキー会社はeウォッチサービスを依頼し、ネット上で何が言われているかをモニターした。ネット上で不買の声が増えるとともに売り上げが数パーセント落ち込んでいる事をつかんだ同社は、eワークス社の指示で、ニュースグループに噂を否定するコメントを投稿。こうした対応で、一週間後にネット上の噂は消え売上も回復した、とされる。
このほかにも、カーディーラーに対する「顧客サービスに電話がつながらない」といったニュース・グループへの投稿を早期に感知して手を打った結果、最初の告発者が苦情を流すのをやめただけでなく、ディーラーの対応の姿勢を投稿してくれたといった実績もある、という。
●日本では2年遅れで「再現」
最近話題のeコマース(インターネット上の電子商取引)などを含め、米国でのインターネットの動きは、一定のタイムラグをもって日本に広がる傾向にある。ネット・コンシューマリズムも同様だ。東芝事件ほど注目を浴びる事例は少ないが、米国からほぼ2年遅れの1998年から1999年にかけて、日本でも以下のように「告発」の動きが活発になってきている。
【住宅メーカーA社の雨漏り問題】
A社から新しくマイホームを購入したところ雨漏りを起こしたとする告発サイトが1998年7月に開設された。壁の染みなどの写真も掲載。同社担当者が電話でホームページ上の実名を取り消し依頼。その後、告発者を来訪してサイトの閉鎖を依頼したが、現存している。
【自動車ディーラーB社の修理不具合問題】
B社に修理を頼んだところ、勝手にフェンダーとバンパーが交換されて、事故車同然になったとネット上で訴えた事件。B社との約束としてホームページは現在閉鎖されている。
【ファーストフードC社のかえる入り牛丼問題】
C社のある店舗で牛丼弁当を買った際に、かえるの上半身が混入していたとする告発サイトで1999年7月に開設。告発者は「謝罪を求めるつもりも無く誹謗中傷する訳ではなく、どうこうする、してもらうつもりはまったくありません。(中略)ただし嘘偽りはまったくございません。すべて実際に起きたことです」と書いていた。
【サッシメーカーD社の欠陥住宅問題】
D社の独自工法で欠陥住宅が生まれているとの告発を行っているサイト。各種文書、映像、家の写真も掲載。D社側は自社ホームページ上でこの事件に関して反論した。現在裁判になっている。
こうして見てくると、日本でも米国同様、サイトの閉鎖に至る事例も出てきている。しかし、企業側が組織的な対応を図り、訴訟にまで持ち込まれるようなケースはまだ少ないように思える。インターネットの普及度の違いのほかに、どういう条件の差があるのだろうか。
米国と比べ日本の事情は、消費者と企業の側の双方で異なる。まず、消費者意識の違いがある。PL法に見られるような、消費者は保護されるべきだとする理念が、日本では米国ほど確立されていない。日頃はっきりと言葉で表現(批判)することに慣れていない、あるいはそれをよしとしない空気が日本にはある。従って、米国と比べ、日本の消費者の不満が執拗かつ強力なクレームとして表出している度合いは、まだ少ないと言えよう。
一方、企業側には消費者対策を訴訟にまで持ち込むことが多くない実態がある。法的手段を講ずることが少ないのは、何もネットの世界に限らない。また、この種の問題への経験不足から、対策手段をとるための基本的ノウハウも欠けている。この点では、企業サイドには「先行」する米国企業の対処の方法から学ぶべき点も多いと思われる。しかし、その前提として、ネット特有のプロセスをしっかりと認識することも重要だ。
●クレームは加速度的に増加
ネット・コンシューマーリズムを背景とした消費者からの企業への告発は、当該企業から見れば厄介なものである。もちろん、企業の商品・サービスの性能・機能、価格等の商品・サービスに直接帰属する内容に落ち度があれば、企業はそれらに対する消費者からのクレームを正当に甘受すべきだ。しかしながら、継続して消費者対応を誤って事を大きくしてしまい、企業のブランドないしイメージを大きく損なってしまうのであれば、ネット時代にあって賢い企業とは言えない。ネットの世界は単に現実世界の向こうの鏡像(虚像)ではない。これまで見てきた生々しい事例の通り、ネット上で次第に激しさを増した消費者の声は、確実に現実社会に戻ってくるからだ。
ネットの世界を通過することでクレームの影響度が逓増するプロセスは下図のようなものと考えられる。リアルな世界が「一時的なやり取り、通話の秘守性(一対一)、影響度小(マスコミに取り上げられる前)」というものであれば、ネットの世界は「一定期間掲載、非管理かつ公然性を有するメディア(1対多、多対多)、影響度大(大きく速い)」なる特徴を持ち合わせている。このネットの特徴が、クレームを当事者の予想以上に押し上げるのだ。
ネットワーク時代のビジネスでは、規模が大きければ大きいほど、相乗効果によっていっそう収益性が増す「収穫逓増の法則」が強く働くことに特徴がある。逆説的だが、企業にとってマイナスの影響力についても、同じような「逓増の法則」が成り立つといえるだろう。
こうしたプロセスの本質を考えると、米国に発したネット・コンシューマリズムのうねりは、収斂の方向に必ずしもあるようには思えない。攻撃者は一層効果的な手立てを用いて自身の不満を表現するであろうし、あるいは悪意のある嫌がらせ・恫喝の類も一緒になってネットの中で増幅し、より強大になって現実の世界に戻って来るということを繰り返していく可能性は大きい。
日本の警視庁は、「サイバーパトロール」と称して、ネット上での違法情報を24時間監視する体制を敷きはじめた。民間でも、ネット上の企業リスク情報の収集を代行するサービスが現れている。事態が深刻化している米国では、先に見たように、法的な手段行使の検討も含めた告発サイトへの対処法のコンサルティングをする企業が定着している。
企業にとって、これらの解決の手立ては、図の「③ネットでの告発」に関するものだ。問題情報をいち早く発見し、ネット上で告発されている企業に通報する。その目的は、「④ネットでの関心・合意形成」「⑤マスコミ報道」に至るプロセスをできるだけ早く断ち切ることが目的にある。
クレームの逓増を食い止めるためには、こうした手段の利用に加え、「苦情をいたずらに刺激しない」ということも挙げられる。特にクレームがまったく不当な場合などは、同じ土俵にのらないほうがよいだろう。むやみに反応すれば、ネット上では反応がいっそう拡大されて戻ってくるのだから。
しかし、企業にとって最も重要なのが、「消費者のクレームに耳を傾けること」であるのは、米国の例からもはっきりしている。クレームに真摯に耳を傾け、自社の商品・サービスに着実に反映させていく仕組みが不可欠だ。ネット・コンシューマリズムを恐れるだけでなく、自社に関心をもった得がたい顧客の声だという見方に転換できるかどうかが問われているのではないだろうか。
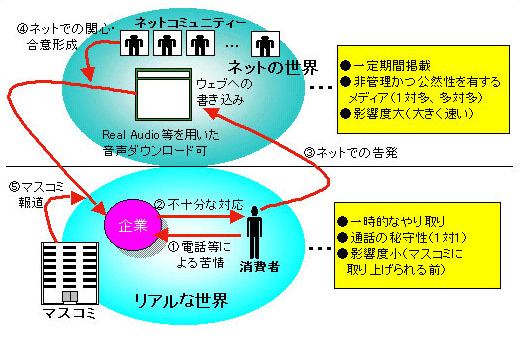
(出所)日本総合研究所 ネット事業戦略クラスター

