プロフェッショナルの洞察
社会の変容と企業リスクマネジメント 01 防災からリスクマネジメントへ
2007年02月01日 鈴木敏正
 日本は、1995年に「リスクマネジメント元年」とも言うべき大きな転機を迎えた。そのきっかけのひとつは、同年初頭に起きた阪神淡路大震災である。
日本は、1995年に「リスクマネジメント元年」とも言うべき大きな転機を迎えた。そのきっかけのひとつは、同年初頭に起きた阪神淡路大震災である。それまで災害に対しては「防災」という考え方が主流で、これは想定する災害により重大な被害が発生しないよう予め対策を施しておこうというもので、その主体を国や地方自治体など、いわゆる公的機関が担うというものであった。また、そのような災害に対する対策の考え方から、対策を担う公的機関(民に対して官という概念)が安全と言えば皆が安全だと信じる、あるいは安全と信じたいという、いわゆる「安全神話」が意識的にも無意識的にも社会の底流に流れていた。これは、科学的・技術的な意味でも絶対安全を担保するものではなく、いわば条件付の「安全と考えられる、あるいは現状では安全と考えてもいいであろう」というものであって、社会全般がそう信じ込むことによって成立していた(括弧付きの)「安全」であったと言える。想定以上の災害、その結果としての被害が起きた場合の想定は社会の不安を煽るだけで所詮益の無いこと、安全に関する少々の疑義が有っても、それが不確実な事象なのであれば、それを楽観的に考え、社会としては「安全」と考えて行動していこう、という暗黙のルールがあったというのが、この社会の「安全神話」の実体であったと考えられる。
しかし、そのような中、阪神淡路大震災において、まさに想定以上のことが起きてしまい、「安全であると信じていたこと」の意味が問われることとなった。絶対に壊れないと言われていた高速道路やビルが壊れたことで、今まで安全と考えてきたものに疑問を抱き、その結果「絶対安全」が担保出来ないのであれば、結局は許容できる被害レベルを自らが設定し、それに基づく条件付の「安全な社会」で生活していることを認識するしかないと覚悟することとなった。このことはまた、災害社会における「自己責任」の自覚をもたらすことにもなった。
 さて、自然災害はたとえそれが大地震であっても、国全体を壊滅させるという状況は考えにくい。つまり、その被害は被災地限定の局所的なものである。従って企業がある地域でのみ活動し、他のライバル企業との競争もその地域限定とすると、災害時、一時的ではあっても、企業間競争は停止する。また、被害そのものについてもある程度の諦めがついたとも想像できる。なぜなら競争相手も同じように被害を受けているのだからとの慰めもあったからである。しかし、多くの企業が国レベル、あるいは国際競争の中にある状況では、災害が起きても企業間競争は停止せず、また被害を受けた地域の中でも、それぞれの企業の行うリスク対策により受ける被害は企業間で大きな差が生じ、結果として災害をきっかけに重大な企業体力格差が生じることを知った。
さて、自然災害はたとえそれが大地震であっても、国全体を壊滅させるという状況は考えにくい。つまり、その被害は被災地限定の局所的なものである。従って企業がある地域でのみ活動し、他のライバル企業との競争もその地域限定とすると、災害時、一時的ではあっても、企業間競争は停止する。また、被害そのものについてもある程度の諦めがついたとも想像できる。なぜなら競争相手も同じように被害を受けているのだからとの慰めもあったからである。しかし、多くの企業が国レベル、あるいは国際競争の中にある状況では、災害が起きても企業間競争は停止せず、また被害を受けた地域の中でも、それぞれの企業の行うリスク対策により受ける被害は企業間で大きな差が生じ、結果として災害をきっかけに重大な企業体力格差が生じることを知った。企業も個人同様、万一何か重大な事態が起きた時、自分で被害をどこまで許容できるかの範囲を決め、それに基づいて企業活動を準備しなければならないという、言わば企業リスクマネジメントの「個別化」の時代になったということである。
このように阪神淡路大震災は「自らのリスクを考える」と言う意味で、個人、企業双方にそれまでと比べようもない大きな影響を与えた出来事であった。
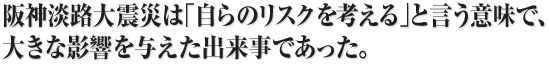
 1990年代後半、リスクマネジメントという考えを確立させたもうひとつの出来事がバブル崩壊後に起こった金融ビックバンである。それまで金融業界は護送船団方式とも言うべき、業界横並び意識の強いところで、土地バブル崩壊の痛手も、その程度の差はあれ、各金融機関共同じように深刻であった。しかしバブル崩壊後、その回復過程で規制緩和が進み、世の中の趨勢であった「健全な競争社会」の構築という流れの中で、金融機関にも業界横並び意識の脱却に加え、さらに生き残りを賭けて競争する時代がやってきた。その結果、利用者自らが金融機関の安定性、リスクへの対応性、さらに提供されるサービスの内容や質によって個別金融機関を選別するという時代となった。一方、顧客の保護を掲げる監督機関も、金融ビッグバンに向けて金融機関の安定性の確保の観点から、「リスク管理」の徹底を課し、リスクマネジメント導入が当たり前の時代へとなっていった。
1990年代後半、リスクマネジメントという考えを確立させたもうひとつの出来事がバブル崩壊後に起こった金融ビックバンである。それまで金融業界は護送船団方式とも言うべき、業界横並び意識の強いところで、土地バブル崩壊の痛手も、その程度の差はあれ、各金融機関共同じように深刻であった。しかしバブル崩壊後、その回復過程で規制緩和が進み、世の中の趨勢であった「健全な競争社会」の構築という流れの中で、金融機関にも業界横並び意識の脱却に加え、さらに生き残りを賭けて競争する時代がやってきた。その結果、利用者自らが金融機関の安定性、リスクへの対応性、さらに提供されるサービスの内容や質によって個別金融機関を選別するという時代となった。一方、顧客の保護を掲げる監督機関も、金融ビッグバンに向けて金融機関の安定性の確保の観点から、「リスク管理」の徹底を課し、リスクマネジメント導入が当たり前の時代へとなっていった。これは、個別の企業毎に、自らの持つリスクを認識し、それらの適切な管理を行いながら、不断に成長するためのビジネス戦略を立てる必要が出てきたということを意味する。つまり、それぞれの企業活動に伴うリスク管理を企業が自らの責任で行うことを社会が求めたということである。
未だに存在する談合問題は、このような社会のリスクに対する考え方の変化を理解していないことから派生したものである。社会はすでに10年以上前に、個別企業がコンプライアンスをはじめ、様々な企業リスクを適切に管理することを前提に、健全な企業間競争を行いながら、その結果、個別の企業が自らの力をつけることを求めており、それができない企業は、競争の社会から退出することも仕方が無いと決断していたのである。
このように震災や金融ビックバンを経験しながら、1990年代において、わが国ではリスクマネジメントの概念が一般に認識され、定着に向かっていった。次回は、企業リスクマネジメントの方法論、実践の課題等について考えていきたい。
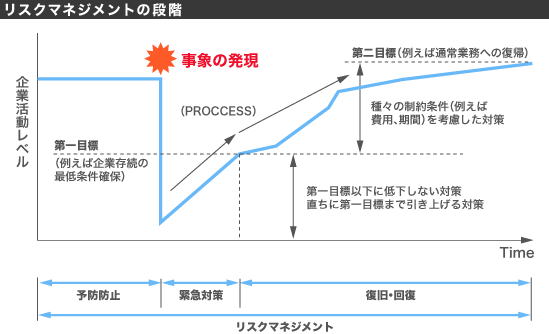
関連リンク
- 01 防災からリスクマネジメントへ
02 企業リスクマネジメントの現代的課題
03 リスクマネジメントのための組織作りと人材育成

