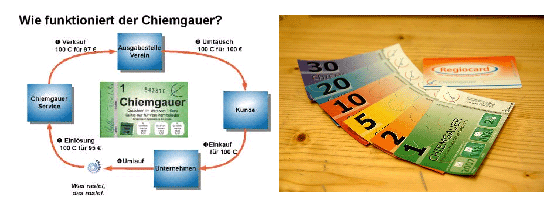(3)ゲゼル型地域通貨(減価型マネー)などによる地域経済の浮揚試案
|
■【経済】地域通貨の事例 | |||||
| ≪担当者のメモ≫岡本俊哉〔2009年2月26日(木)〕 | |||||
|
● |
世界的には、「LETS」と「REGIO」が比較的流通している。 | ||||
|
|
◇ |
LETS:Local Exchange Trading Systemの略。1980年代にカナダ西部・バンクーバー近郊のCommox Valleyでマイケル・リントンによって開始される。中央銀行が発行する法定通貨は全国くまなく流通するため、炭鉱の閉山などによって地場産業が無くなると地域内での物やサービスをするにもその道具である法定通貨が不足するという事態が発生するが、LETSは地域内で生産できる物やサービスに関しては地域独自の交換手段を用いることによって自給自足を高めようという試み。現在カナダの他、英国や豪州・NZや欧州各国などに広がる。なお、フランスではSEL(Système d’Echange Local)、ドイツではTauschring、オーストリアではTauschkreisと呼ばれる。(出所)主に「Wikipedia」を基に編集。 | |||
|
|
◇ |
REGIO:ドイツ各地で運営されている「地方通貨」 (Regiogeld) の総称である。シルビオ・ゲゼルの減価する貨幣の概念を取り入れている。2006年現在、14の事例がドイツ各地で動いている他、40以上の準備中の事例がある。「地域通貨」がローカルレベル(数百人から数千人の居住地区対象:日本で言えば中小の町村や、都市圏内の一地区)を対象としていたため、事業者などの参加が難しかった。そのため、地域経済圏と呼べる範囲を「地方」 (region) と定義し、この範囲内で使用できる取引手段として「Regio(地方通貨)」を構想した。具体的には数万人~数百万人の範囲、日本で言えば複数の市町村の広域圏から県、あるいは道州制における「州」がここでの「地方」に相当すると言える。(主に「Wikipedia」を基に編集) | |||
|
● |
キームガウアー(Chiemgauer:「REGIO」の1つで、ドイツ・バイエルン州のプリーン・アム・キームゼーを中心とした一帯で流通)の仕組み | ||||
|
|
◇ |
キームガウアー事務局がC100を97ユーロで地域のNPOに販売。 | |||
|
|
◇ |
地域のNPOはC100を100ユーロで会員に販売し、利益の3ユーロを自分の活動に使用。 | |||
|
|
◇ |
会員はC100を100ユーロのかわりに地元商店で使い、3ユーロを応援するNPOに間接的に寄付。 | |||
|
|
◇ |
地元商店はC100を他の地場企業への支払に使うか95ユーロに換金、残りの2ユーロは事務局の運営経費として使用。 | |||
|
|
◇ |
3か月ごとに2%減価。 | |||
|
|
★ |
減価する貨幣はドイツの企業家・経済学者シルビオ・ゲゼル(1862年-1930年)が提案。代表作は『自然的経済秩序』(1916年) | |||
|
|
|
|
- |
自然的経済秩序とは、人間の「性質(Nature)」に沿った経済秩序という意味。 | |
|
|
◇ |
2008年末現在、2,000名近くの個人会員と500件以上の企業会員が参加し、30万キームガウアーが流通し、キームガウアーでの売上合計は年間400万キームガウアー程度。 | |||
|
【図表】 キームガウアーの流通方法とデザイン | |||||
| (出所)キームガウアーWebsite | |||||
|
● |
≪参考≫交換クラブ | ||||
|
|
◇ |
アルゼンチンで1995年に生まれる。元々は日本のフリーマーケットのような形で行われていたが、現金収入に乏しい人たちの生活向上の手段として急速に発達、一時期は600万(総人口の6分の1)が利用した。2001~2002年の経済危機の際には貧困者の生活維持に役立ったが、インフレや地域通貨の管理ミスにより縮小し、現在では数十万人程度の利用に留まっている。 | |||
|
● |
日本の地域通貨は、ボランティア活動、地域活性化の一環として実施されているものが多く、マネー経済の補完、地域経済の補強と言った意味は薄い。 | ||||
|
|
◇ |
「ピーナッツ(千葉県千葉市西千葉駅周辺)」や「ふれあい切符(さわやか福祉財団)」が有名である。 | |||
|
|
★ |
ピーナッツ:用途は不問で、交換した当人同士により通帳に記帳。サービス等を提供する側の人は「受取(+)」、受ける側は「支払(-)」を記入し、お互いの通帳を交換して「相手のお名前」欄にサイン、持ち主に戻したら、最後に「アミーゴ!」と言いながら握手をする決まり。換金性はない。 | |||
|
|
★ |
ふれあい切符:助けが必要な人はチケットを購入し(1時間相当で約600円)、必要なときに使用。ボランティアもこのチケットを貯めておき、必要なときに使うことができる。換金も可能。 | |||
|
● |
元JRI研究員の嵯峨生馬(さがいくま)氏は、「アースデイマネー・アソシエーション」の代表理事として、「アースデイマネー」の管理・運営を実施している。 | ||||
|
|
◇ |
アースデイマネー:渋谷を中心とした地域通過であり、ボランティア活動への参加による受け取り、または渋谷駅周辺に設置された「ガチャガチャ」で購入できる。渋谷周辺を中心として、100店舗強で利用可能(ただし、1回で100rまでなどの制限がある)である。加盟店は、イメージアップ、パブリシティなどを目的として、アースデイマネーを受け入れており、換金性はない。 | |||
|
|
★ |
「アースデイマネー・アソシエーション」の2005年度(2005年4月23日~2006年4月22日)の支出は7,487,225円、収入は7,833,415円となっている。 | |||
|
【図表】 「アースデイマネー」のホームページの様子 | |||||
| (出所)アースデイマネー・アソシエーションWebsite | |||||
| ≪課題≫地域通過をいかに普及促進させるか | |||||
|
● |
日本の地域通貨は、ボランティア、地域経済、Non-Monetary-Economyなどの概念形成には一定の効果はあるが、現在のマネー経済(利子支払いのための経済成長)を補完・補強していくにはインパクト不足。 | ||||
|
● |
従来の地域を中心として生活していた日本(中産階級が中心)であれば普及の土壌はあったと思われる。 | ||||
|
|
◇ |
不動産バブルや新自由主義の台頭により、勝ち組負け組や都市と地方を選別するような潮流が定着したことも普及しない要因(心理的に、集権されたマネーのみを信頼してしまう)となっているのではないか。 | |||