コラム「研究員のココロ」
TOC/SCMによる経営革新(その2)
2002年08月19日 松崎 健一
Business Architecture Design
パッケージ導入型のアプローチでは、目指すべき目標に向けた業務改革・組織改革を実行していなかったり、既存の業務ルール・プロセスや組織構成のまま SCMを導入しているために、現状の業務機能やシステム機能に引っ張られた、部分最適なソリューションが導き出されるという問題が起こりがちである。サプライチェーン全体として、TOCで導かれた全体最適なソリューションの方向性を実現するためのビジネスモデルを明確化し、目標と整合性の取れた最適な業務機能を設計する必要がある。
Business Architecture Designとは、企業として利益を上げ続けるために整合性の取れた業務機能を設計するフレームワークであり、「構想策定」、「基本設計」、「詳細設計」を経て、実行・定着化されるものである。また、TOCで導かれたブレークスルーがBusiness Architecture Designのインプットとなり、Business Architecture Designのアウトプットである、一貫した設計思想に基づく整合性の取れた業務機能設計が、システム設計のインプットとなる。これにより、目標策定から、業務機能設計、システム設計・開発までが、全体として整合性が取れることになる。
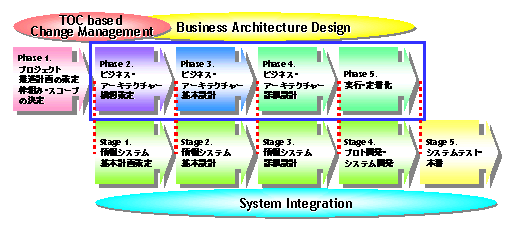
最初の「ビジネス・アーキテクチャー構想策定」では、目標策定フェーズで導かれたブレークスルーに基づき、SCM戦略を策定する。例えば、サプライチェーンのメンバー構成、企業間のサプライチェーン計画連携、デカップリングポイントの上流化を目指した延期化などの戦略策定である。
ここでは、企業間のサプライチェーン計画連携の一例として、CPFR(Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment)を取り上げてみる。CPFRは、小売業と製造業が協業(Collaborative)による商品計画(Planning)、需要計画(Forecasting)、在庫補充(Replenishment)を行なうプロセスである。
従来、小売業者は製造業者の供給能力が分からず、実際の見込よりも多めに発注、一方、製造業者も小売業者からの急オーダーに備え、実際の見込みよりも多めに在庫を持ち、その結果、小売業者と製造業者の双方で在庫過多になるという問題が発生していた。こうした計画の不透明性による在庫多あるいは欠品を解決するための施策がCPFRである。
CPFRでは、小売業者側の店舗売上実績、販促計画、販売計画等の経営情報、製造業者側の出荷実績、販促計画、生産計画をリアルタイムに共有する。共有した情報をもとに需給計画を行ない、全体を最適化する。サプライチェーン上の企業間において、従来の問題に対して、その問題を打破すべく策定した目標を、全メンバーが共有できている好例である。CPFRにおいては、例外事項処理も含めて、その手順がプロセス化されていることも特筆すべき点である。
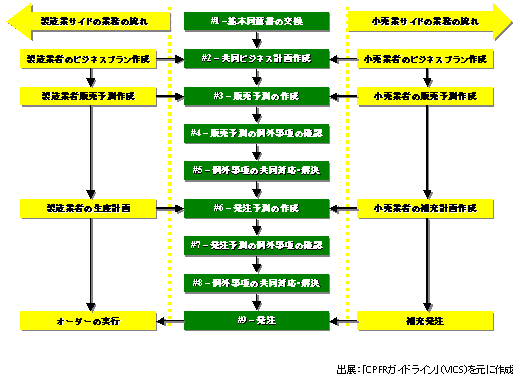
次に、「ビジネス・アーキテクチャー基本設計」では、SCM戦略にフィットした具体的なモデリングを行う。サプライチェーンネットワーク設計、デカップリングポイント設計、計画系や実行系業務のオペレーション概要設計などを実施する。また、効果検証も重要なタスクとなる。
最後に、「ビジネス・アーキテクチャー基本設計」に基づいて、「ビジネス・アーキテクチャー詳細設計」を行う。サプライチェーンの機能設計、オペレーションの詳細設計を行い、企業間・企業内の業務ルール・プロセスを定義し、業務の整合性とフレキシビリティを確保する。
System Integration
SCM戦略に基づき設計されたビジネス・アーキテクチャーを支えるSCMシステムの構築においては、需要計画、需給連鎖計画、生産・日程計画などの SCMシステムを構成するツール群の最適な組合せ(ベストオブブリード)の設計が必要である。また、単にパッケージの選定・導入を行うだけでなく、新たに設計された業務プロセスとパッケージとの適合性分析や、ギャップに対するソリューションの設計など、ビジネス・アーキテクチャーの設計とシステムインテグレーションとをシームレスに連携させることが必要である。
SCMシステム導入フェーズにおいても、目指すべき目標に沿ってコアコンピタンスが何かを明確にしておくことが前提となる。コアコンピタンスを支える業務プロセスについては、システムの追加開発(アドオン、補完的周辺パッケージシステム採用、等)も辞さず、コアコンピタンス以外の部分については、パッケージに極力適合させることで標準化・ルール化を促すという方針が肝要である。例えば、ある企業において、生産・日程計画におけるスケジューリングのモデルとロジックに、その企業の競争力の源泉があるのであれば、パッケージに無理に適合させるのではなく、精緻なモデルとロジックを構築するために、システムを追加開発すべきである。
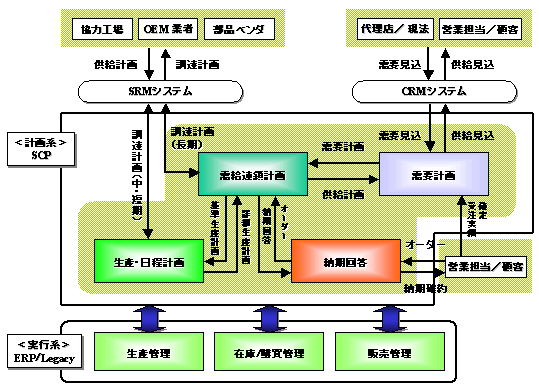
また、SCMシステムはSCPとERPの両輪から構成されており、どちらか一方のみでは、求められる機能を実現できない。SCPはサプライ側とデマンド側の需要と供給をうまくマッチさせるための計画ツールであるのに対して、ERPはこの計画を実行する実行ツールであると言える。計画をうまく立てても、実行段階で確実な仕組みがなければ、当然効果は出ない。
計画系であるSCPが最適な計画を作るためには、実行系システムからの適切なインプットが欠かせない。ERPにおいて在庫データや生産ライン能力データ、標準生産リードタイムといった基礎データが統合され、リアルタイムで更新されて、SCPにスムーズに流れ込む仕組みがなければ、良い計画は作れないのである。業務要件にマッチした計画系と実行系の機能分担の設計、計画系と実行系のインターフェイス・タイミングの最適化、などがポイントとなる。なお、実行系の業務においても、スピードと柔軟性を保証する改革が必須であることは論を待たない。
おわりに
日本企業がサプライチェーン改革を通じて真の経営革新を実現するには、多くの困難が待ち受けている。しかし、企業内の組織間あるいはサプライチェーン上の企業間において、どのような問題が存在し、その問題を打破してどのような目標を目指すべきなのかを、全メンバーが共有することをスタートポイントとすることにより、短期間で劇的な効果を上げうる可能性は大きい。
また、策定された目標と整合性が取れたビジネス・アーキテクチャーを設計し、そのビジネス・アーキテクチャーを支えるSCMシステムの構築において、システム導入自体を目標としないことに注意すれば、日本企業の持つ潜在的な競争力を顕在化させることが可能となる。
TOC/SCMによる経営革新(その1)へ
【ご案内】
●真のTOCによるマネジメント革新方法論
●TOC導入支援コンサルティング&トレーニングプログラムの紹介

