コラム「研究員のココロ」
TOC/SCMによる経営革新(その1)
2002年08月12日 松崎 健一
日本におけるサプライチェーン・マネジメントの現状
日本企業のサプライチェーン・マネジメント(以下、SCM)が暗礁に乗り上げている。ブームに乗り遅れるなとばかりにSCMシステムを導入し、形は整えてみたものの、思うような成果を上げられない企業が続出している。SCMの成功を阻む要因は、業種や業態、あるいは業務固有の事情など企業によって様々である。
ただし、いずれのケースでも、サプライチェーン改革を妨げている原因に共通している点がある。企業内の組織間あるいはサプライチェーン上の企業間において、どのような問題が存在するのか、そして、その問題を打破してどのような変革を目指すべきなのかを、全メンバーが共有できていない点である。今こそ SCMの持つ困難さ、課題を改めて直視し、戦略を見直し、真の経営革新を実現すべき時期に来ている。
本来、SCMシステムを導入するに当たっては、目指すべき変革の方向性の策定がスタートポイントとなる。次に、その変革の方向性と整合性を取りつつ、企業間・企業内の業務ルール・プロセスを見直す業務改革・組織改革を着実に実行し浸透させることが必須である。最後に、その業務プロセスをシステム面から支援するツールとしてSCP(Supply Chain Planning)とERP(Enterprise Resource Planning)から成るSCMシステムを導入すべきである。
にもかかわらず、多くの日本企業においては、目指すべき変革に向けた業務改革・組織改革を実行することなく、既存の業務ルール・プロセスや組織構成のまま、SCMシステムを導入している。場合によっては、目指すべき変革の方向性を全く策定することなく、「SCMシステムを導入すること」自体が目標となってしまっている企業すら散見される。
また、SCMシステムを導入するフェーズにおいては、目指すべき変革の方向性に沿った業務プロセスを実現することが、その目的となる。その目的に向けたシステム開発方針を明確化することが肝要である。しかしながら、多くのSCMシステム導入プロジェクトにておいては、パッケージの選定・導入に専念しているのが実態である。その結果、業務プロセスとパッケージとのギャップに対して、無分別に追加開発し、開発費用と開発期間を浪費してしまっているのである。
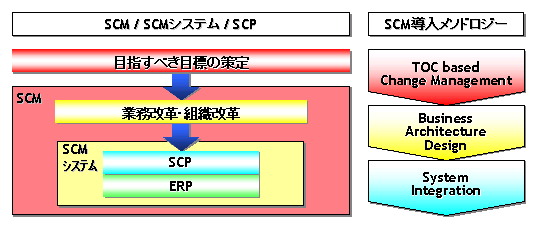
今回、このような日本におけるSCMの現状を鑑み、真の経営革新を実現するためのSCM導入メソドロジーについて考察する。具体的には、次の3点である。企業が目指すべき変革の方向性をどのように策定すべきか。その変革の方向性と整合性が取れたビジネス・アーキテクチャー(事業構造・業務基盤)をどのように設計すべきか。そして、設計されたビジネス・アーキテクチャーを支えるSCMシステムの構築においてどのような点に留意すべきか。
日本企業がサプライチェーン改革を通じて真の経営革新を実現するには、多くの困難が待ち受けている。しかし、企業内の組織間あるいはサプライチェーン上の企業間において、どのような問題が存在し、その問題を打破して目指すべき変革の方向性を、全メンバーが共有することをスタートポイントとすることにより、短期間で劇的な効果を上げうる可能性は大きい。
また、策定された変革の方向性と整合性が取れたビジネス・アーキテクチャーを設計し、そのビジネス・アーキテクチャーを支えるSCMシステムの構築において、システム導入自体を目標としないことに注意すれば、日本企業の持つ潜在的な競争力を顕在化させることが可能となる。
本連載の第1回(今回)では、「TOC based Change Management」と題して、企業が目指すべき変革の方向性をどのように策定すべきかについて、第2回(次回)にて、「Business Architecture Design」と題して、その変革の方向性と整合性が取れたビジネス・アーキテクチャー(事業構造・業務基盤)をどのように設計すべきかについて、および、「System Integration」と題して、設計されたビジネス・アーキテクチャーを支えるSCMシステムの構築においてどのような点に留意すべきかについて述べる。
TOC based Change Management
企業の究極の目標は「顧客と従業員の満足度を高めつつ、現在から将来にわたって利益を上げ続けること」と定義することができる。ただし、この目標を分かっていながらも、何故か上手く行かないといったことに直面し続けている企業は多いのではなかろうか。ここでは、まず、サプライチェーン改革に取組みながらも、暗礁に乗り上げ、さらなる前進を阻んでいる要因は何なのかを見てみよう。
はじめに、病人を例にとって考えてみる。病人は、しばしば複数の症状を示し、それらの症状から「ひどい風邪を引いてしまったようだ」と結論を出し、個々の症状それぞれ別々に対処しようとする。発熱には風邪薬、咳には咳止めシロップ、寒気には厚着する、といった具合である。しかし、症状が改善しないということがよく起こる。
同じように、企業においても、販売量の減少には販売改革、生産効率の低下には生産改革、物流費の増加には物流改革、といったように、個々の問題それぞれ別々に対処しようとしていないだろうか。その結果、どのような事態が発生するかは想像に難くないだろう。
例えば、販売部門が販売計画を策定し生産部門に提示するが、販売部門はその販売計画に対する引取責任(=在庫責任)を持たないという業務ルールが設定され、そのため、生産部門は提示された販売計画を参考にせずに、生産部門で新たに需要を予測し、その需要予測に基づいて生産するといった業務ルール・プロセスが設計されているということがしばしば見受けられる。
また、物流部門が倉庫の保管費用や倉庫からの輸配送費用の観点のみから倉庫の拠点配置を設計し、サプライチェーン全体としての費用や在庫量といった観点などが考慮されず、そのため、工場に以前より多くの在庫を保管したり、工場からの直送が増加しトータルの輸配送費用が以前より増えるといった事態が発生するという問題が起こりがちである。
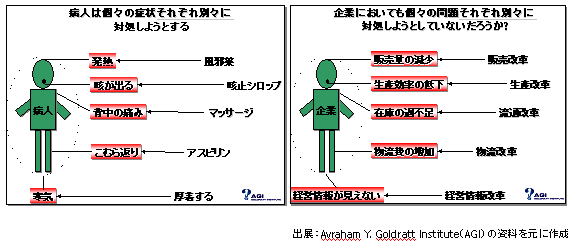
このような例からも分かる通り、サプライチェーン改革を妨げているのは、企業内の組織間において、どのような問題が存在し、その問題を打破してどのような目標を目指すべきなのかを、全メンバーが共有できていないことである。では、企業が抱える問題をどのように認識し、その問題をどのように打破し、企業が目指すべき目標はどのように策定すべきなのだろうか。今までの経験から、多くの企業においては、無意識に設定している方針(Policy)、評価指標(Measurement)によって、従業員の行動(Behavior)が誘導されている。このことが問題現象や望ましくない結果を招いているのが現状である。これらの構造を理解した上で改革に取り組めば、確実に実効性が上がる。
例えば、販売部門が「少しでも多く販売する」という方針のもと「販売量」という評価指標のみにより測定され、「在庫量」という評価指標では測定されておらず、一方、生産部門は「適正な量だけを生産する」という方針のもと「在庫量削減と販売機会損失低減」という評価指標により測定されているとしよう。その結果、販売部門は多めの量を見込んだ販売計画を策定し、生産部門は販売部門に提示された販売計画を信用しないという行動が誘導される。本来は「在庫削減」という共通目標を目指して、販売部門と生産部門が協力して行動すべきところが、全く逆の行動を取ることになる。
また、同様に、物流部門が「物流の費用を最小化する」という方針のもと「倉庫の保管費用や倉庫からの輸配送費用」という評価指標のみにより測定され、「在庫量」という評価指標では測定されていないとしよう。その結果、ここでも物流部門と生産部門の非協力的な行動が誘導されることになる。
これらの例が示すように、全社が目指す方向性と部門の目指す方向性の整合性が取れていない場合、その部門にいるメンバーの行動は、部分最適(ローカル・オプティマ)に陥ってしまい、そのことが目標達成を阻む本質的な問題にさえなる可能性を秘めているのである。企業内の組織間あるいはサプライチェーン上の企業間において、どのような問題が存在し、その問題を打破してどのような目標を目指すべきなのかを、全メンバーが共有できていないことが、サプライチェーン改革を妨げているのである。
逆に言うと、どのような問題が存在し、その問題を打破してどのような目標を目指すべきなのかを、全メンバーが共有することが、サプライチェーン改革の成功の必要条件となる。企業の究極の目標が「顧客と従業員の満足度を高めつつ、現在から将来にわたって利益を上げ続けること」であるとすると、ほとんどの企業においては、無意識に設定している方針がその目標の達成を阻む本質的な問題になっている。
メンバーの行動を部分最適に陥らせている方針を明らかにし、全体最適(グローバル・オプティマ)に導く方針に転換する必要がある。その方針に合致した評価指標を設定することにより、全社が目指す方向性と部門の目指す方向性の整合性が取れた行動を誘導することが可能となる。その結果、全体最適を目指したサプライチェーン改革の成功を実現するのである。今回は、企業内の組織間を中心に考察したが、サプライチェーン上の企業間においても同様のことを論じることができる。
企業が抱える問題を認識し、その問題を打破し、企業が目指すべき目標を策定する有効な手法として、日本でも近年注目され始めているのが、 TOC(Theory Of Constraints:制約条件の理論)である。TOCは、企業やサプライチェーンを一つの「システム」として捉え、そこに存在するさまざまな制約条件(方針制約、行動制約、管理・評価制約、能力制約、市場制約など)に着目し、ブレークスルーを実現する。そのブレークスルーにより、企業やサプライチェーンの目標(現在から将来にわたって利益を上げ続けること)を達成する経営改善手法である。
TOCでは、始めに組織・システムを全体的組織として捉え、制約の特定やブレークスルー策、方向性を策定・共有化することを重視する。この一連のステップを実施可能なプログラムとして提供するのがBOC(Breaking Organizational Constraints:企業が抱える制約条件の打破)である。サプライチェーン改革に取り組むに当たって、企業内の組織間あるいはサプライチェーン上の企業間において、どのような問題が存在し、その問題を打破してどのような目標を目指すべきなのかを、全メンバーが共有できていない企業やサプライチェーンには、このBOCが非常に有効な手法の一つとなるであろう。
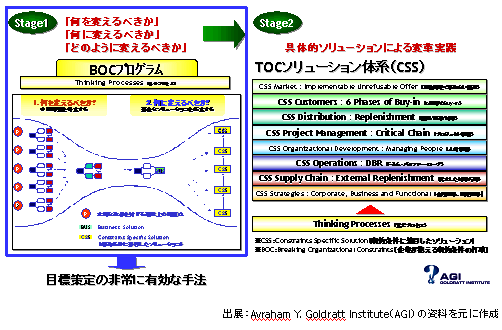
【ご案内】
●真のTOCによるマネジメント革新方法論
●TOC導入支援コンサルティング&トレーニングプログラムの紹介

