コラム「研究員のココロ」
地方自治体における事業継続計画(BCP)への取組みはPPPの視点で
2007年11月26日 山野泰宏
1.BCPとは
BCP(Business Continuity Plan 、事業継続計画)とは、テロや災害、事故などが発生した場合、主要な業務を継続させ、また早期に復旧させることを目的に、様々な観点から対策を講じるものです。我が国では2001年の米国同時多発テロの際、欧米企業を中心としたBCPに基づく対応が注目されました。
これまで我が国では、主に地震等の自然災害に備えた防災計画が策定されてきましたが、BCPは、生命の安全を確保した上で、事業の継続性を如何に確保するかというところに視点を置くものです。最近では、新潟県中越沖地震などの際、地震の直接被害に加え、生産の停滞により、取引先企業を含むサプライチェーン全体への影響の大きさ、その対応の重要性が改めて認識されました。
建物の例で言うと、これまではまず建物自体が壊れないような構造にするとともに、免震・制震装置などにより如何に被害を抑えるかに主眼を置いてきましたが、BCPは、建物の一定の被害は免れられないことを前提に、その中で使える資源を活用し、如何にソフト面で必要機能を確保するか、ということを計画として策定しておくものと言えます。
図 BCPの考え方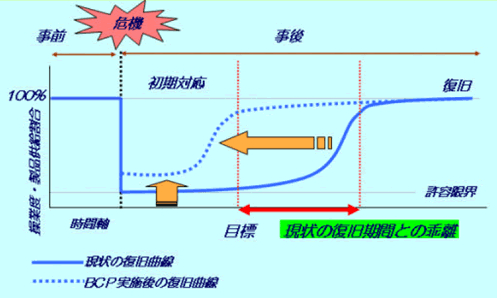
出典)民間と市場の力を活かした防災戦略の基本提言(2004年10月、内閣府)
2.企業、政府の取り組み
日本企業におけるBCPへの取組みについては、今年9月に公表された日本政策投資銀行の調査によると、BCPを策定している企業は8.0%にとどまり、改善の余地が依然大きいことが指摘されています(注)。一方で、海外企業ではBCPの策定を取引先企業に求めることも多くなってきており、また欧米を中心に、BCPについてISOの規格化を進める動きがみられることからも、今後我が国においても、より多くの企業への導入が進むと思われます。別の観点として、環境対策やCSRなどとともに、数値では計り難い定性的な企業評価として、より注目が高まることが想定されます。
政府においても、内閣府が2005年8月に策定した「事業継続ガイドライン」を始め、経済産業省が2005年に「事業継続計画策定ガイドライン」を、中小企業庁が2006年2月に「中小企業BCP策定運用指針」を策定するなど、企業への導入、普及への取組みを行っています。
また、公共分野においても取組みが進められています。内閣府では、今年7月に「中央省庁業務継続ガイドライン」を策定し、まずは政府としての業務継続計画を整える姿勢を示しています。今後は地方自治体においても、住民サービスを始めとする自治体業務の継続計画策定が求められることになると考えられます。
3.取組みの視点
企業におけるBCPへの取組みは、被害そのものによる収益の大幅な低下、製品供給の停滞による顧客の流出、マーケットシェアの低下、更には結果としての企業価値の低下など、想定される数多くのダメージを防ぐことを目的に行われます。
これに対して行政では、災害対策活動の円滑な実施、平常時の行政サービスの早期回復、災害復旧過程における情報信頼性の担保、民間企業BCPの支援(自治体機能の回復が前提となっている場合が多い)などが求められることに留意し、取組みを進める必要があります。
地方自治体では、本庁機能のほか、上下水道や病院などの都市インフラ施設において、業務継続はより直接的に求められます。特に医療施設においては、災害拠点としての救命救急活動が効果的に行われるためのトリアージの導入など、BCP的な考え方により、自治体全体としての複合した取組みを体系化して整理する、従来の防災計画に留まらない対策が求められます。
4.取組みの進め方
BCPへの取組みとして、通常以下のような考え方で進められます。
- 著しいダメージを与えかねない重大被害を想定する。
- 災害後に活用できる資源に制限があることを前提に、継続すべき重要業務を絞り込む。
- 重要業務ごとに、事業継続が困難となりうる事象を想定する。
- 復旧の制約となりかねないボトルネックを想定し、重点的対応を考える。
- 重要業務の目標復旧時間を設定し、準備をしておく。
- 緊急時の意思決定、管理などのマネジメントとして意識する。
取組みにあたっては、一度に完成形を求めるのではなく、防災計画が業務継続の考え方に合致しているか見直すなど、既存の計画をベースに、着手しやすいところから、まず始めることが大切ではないでしょうか。
災害などの業務阻害要因はいつ、どの規模で発生するか、予想できません。来るか来ないか分からないものが相手であるため、慌てて対応する必要はない一方で、長期に渡る粘り強い取り組みが求められます。そのため、まずは既存の計画を見直すことにより、課題を抽出・認識し、必要かつ可能なところから修正を加えていくため、文書化・定期的チェック・ブラッシュアップといった継続した取組みを進めるための仕組みづくり、人々の意識向上が重要になります。
5.地方自治体のBCPへの取組みにあたって
地方自治体が住民及び企業住民を対象として、その安全確保と生活、事業継続を支援するBCPは、リスク管理の重要性が大きくなっている現代社会において、今後必要不可欠な社会インフラになると考えられます。地方自治体のBCPへの取組みにあたっては、地域経営という観点から、住民の安全や財産を守るとともに、地域の企業がBCPを策定し、有事の際の計画実施を支援するのに十分な体制・計画を自治体が整えるという、官民協働(PPP)の視点が重要です。
また、人口減少社会に入り、地方自治体間の競争が激しさを増している我が国の現状において、自治体のBCP導入は、大きな差別化要因となる可能性を秘めています。企業誘致を例にとれば、これまで自然災害の発生リスクの高さから劣勢を強いられていた自治体においては、「災害が発生することがリスク」なのではなく、災害は発生し得るものという前提で「対策を講じていないことがリスク」として、発想の転換による積極的な取組みが可能となります。このように、政策実現の幅を広げ、また政策転換を優位に進める手段として、BCPは多くの場面での活用が期待されます。
以上
- 参考文献:
- 事業継続計画(BCP)を巡る動向と今後の展開(2006年3月、日本政策投資銀行)
事業継続ガイドライン(2005年8月、内閣府)
中央省庁業務継続ガイドライン(2007年6月、内閣府)

