Business & Economic Review 2007年01月号
【OPINION】
外国人の高度人材活用を-成長戦略の推進力強化に向けて
2006年12月25日 藤井英彦
- はじめに
高度人材の獲得に向けた国際競争が激化している。とりわけ、近年、留学生獲得をめぐる各国間の競争が厳しい。世界最大の留学生受入れ国であるアメリカでは、2006年11月の日韓中訪問を皮切りに連邦教育省のスペリングス長官が対外ミッションの団長となり、今後、有力大学十数校の学長とともにアジアやラテンアメリカ、さらに中東や中欧など世界各地を直接歴訪して、学生のみならず、学校や政府関係者に対してアメリカ留学のメリットをアピールする予定である。
わが国でも、これまで海外の高度人材獲得に向け、様々な施策が推進されてきた。例えば、まず、2006年4月から第三期に入った科学技術基本計画をみると、1996年にスタートした第一期から外国人研究者の登用や受入れの促進が、研究開発力の強化を実現する重要な取り組み課題の一つとして明確に位置付けられている。一方、2002年度にスタートした21世紀COEプログラムでは、わが国の大学が世界最高水準の研究教育拠点に飛躍するという目標を実現するために、具体的方策として、優秀な若手研究者の活用や一流の海外諸大学との共同研究に加え、世界のトップレベルの研究者の招聘が打ち出された。さらに、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」、いわゆる2006年骨太の方針では、外国人留学生制度の充実と優れた外国人研究者や技術者等の受入れ拡大が労働生産性を引き上げ、成長路線を実現する方策の一つとして明記されている。
さらに先行きを展望しても、海外の高度人材の重要性は一段と増大し、その成否がわが国経済の力強い成長力を維持できるか否かを左右する重要な鍵の一つとなる公算が大きい。すでに2005年から総人口が減少に転じ、今後、若年層を中心に人口減少に拍車がかかるなか、わが国が着実な経済成長軌道を持続的に歩むためには、まずイノベーションを原動力に労働生産性を上昇させる以外に有力な方策が見当たらない。そうした情勢下、研究開発競争が先進国と途上国とを問わず国際規模で一段と厳しさを増しており、異なる人種や民族から構成されたチームを組成したり、分野を超えた研究プロジェクトを立ち上げるなど、研究開発競争を勝ち抜くために様々な取り組みが各国で推し進められているなか、日本人を中心としたクローズドな推進体制だけで、わが国が国際競争力を幅広い分野で中期的に維持することは容易でないからである。
こうした観点から、本稿では、まず留学生を中心に外国人活用に向けた現状を概観したうえで、わが国が直面する主な問題を抽出し、最後にわが国がイノベーションを原動力とする成長戦略を推進するうえで最優先で克服すべき政策課題を整理してみた。 - 増加する留学生
(イ)高度人材を中心に外国人の活用に向けた動きを世界全体として俯瞰的にみると、研究者やエンジニアなど、第一線の人材を呼び込むよりも、むしろその予備軍である留学生に照準を合わせた取り組みが近年一段と強まっている(図表1)。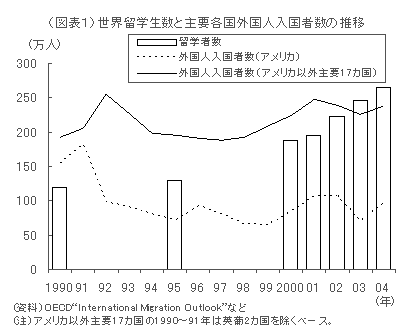
まず外国人の活用を示す指標として、OECD加盟各国のなかで、データが取れる18カ国を対象に外国人入国者数の推移をみた。無論、外国人入国者のなかには、高度人材としての入国以外に、一般的な労働力としての入国、あるいは妻子や親戚を呼び寄せる家族統合のための入国など、様々な形態がある。しかし、少なくとも先進各国の場合、近年、外国人の入国はIT技術者など高度人材に対しては積極的であるのに対して、それ以外の分野では、原則禁止としながら、国内で必要とされるマンパワーが不足・逼迫している職種は例外措置を認めるなど厳格なスタンスが採られており、入国者数は限定的である。一方、家族統合のための入国についてみても、国によって多寡はあるものの、総じて入国審査は厳しく、家族統合の目的であっても入国者数の増加には各国とも積極的ではない。
(ロ)そうしたなか、外国人入国者数をみると、91~92年にピークを迎えた後、いったん93~94年に減ったものの、再び2000~2001年に増加するという推移をたどっている。外国人入国者数が際立って多いアメリカとそれ以外に分けてみると、まず、アメリカの外国人入国者数は、80年代を通じて60万人前後で推移していたが、89年の東西冷戦終結に伴って大きく増加して91年には183万人へ80年代の3倍の水準に達した。しかし、92年以降、減少して98~99年には60万人強と80年代の水準に戻った後、2000年から再び増加し、2004年には95万人となっている。
一方、アメリカを除くドイツやフランスなどOECD加盟17カ国についてみると、92年のピークは90年10月の東西ドイツ統合に伴うドイツへの移民増加が主因であるのに対して、90年代末以降、イギリスやフランス、ベルギーやスウェーデンなど、大半の国々で増加しており、多くの国々で外国人入国者数が増加した。もっとも、2002年以降、アメリカを含め各国への外国人入国者数は一進一退で推移しており、増勢は止まっている。
それに対して、留学者数は90年代後半以降、一貫して増勢が持続し、外国人入国者数を凌駕するまで増加数が増えてきた。例えば、世界全体の留学生数は95年の130万人規模から2000年に188万人、2004年には265万人へ増加し、2004年の水準は95年に比べて135万人増加した。それに対して、95年と2004年の外国人入国者数は、アメリカが72万人から95万人へ13万人増加、アメリカ以外のOECD17カ国が195万人から235万人へ43万人増加であり、合計しても66万人にとどまる。
(ハ)無論、留学生は世界全体を対象にしているのに対して、外国人入国者数はOECD18カ国であり、両者のベースは異なっているため、単純な比較はできない。しかし、世界の留学生全体に占めるOECD各国の受入れシェアは9割弱に上っており、近年の留学生数増加の大半はOECD各国の受入れによるものである。ちなみに、世界の留学生総数に占めるOECD各国の受入れ数をみると、2000年は188万人のうち160万人を占めて85.5%、2004年でも265万人のうち226万人で85.2%に上る。
これらを総合してみると、まず、近年の外国人入国者数の増加は留学生の飛躍的増加が主因といえよう。しかし、留学生と対照的に、一般的な労働力の調達や家族統合の目的による従来型の移民数は各国政府の厳しいスタンスのもと、むしろ先細り傾向が強まっている。一方、技術者やエンジニアなど、第一線の高度人材を外国から調達しようとする取り組みは、国内外の激しい調達競争と人材プールの少なさから、一部では成功しているケースもみられるものの、外国人入国者数の増加に寄与するほど大きなインパクトを持つには至っていない。 - 留学生増加の要因とわが国の問題
(イ)主要各国では、近年、留学生受入れ政策が強化されてきた。背景を改めて整理すると、そこには様々な事情が作用している。主なポイントを指摘すれば、次の通りである。
第1に、第一線の高度人材を海外から調達する困難さに比べて、その予備軍である留学生の受入れが相対的に容易なことである。
受入れサイドからみれば、特定の能力やスキルを身に付けた人材を事業計画や業務要請に従って着実に採用する必要があるなか、留学生と異なり、海外から高度人材を調達する場合、能力やスキルのチェックを行うことは容易でないうえ、採用時期が不定期となりやすく、計画的な人材獲得が難しい。一方、個々人のサイドからみると、技能やすでに職を得て業務に従事している人々が居住地を移し所属先を変えるコストは留学生を上回る。
(ロ)第2に人口動態の変化がある。すなわち、中国や東欧諸国など途上国が飛躍的な経済発展を遂げ、先進各国が持続的な経済成長を実現するためにイノベーションを原動力とする新産業や新事業の創出が不可欠となった結果、従来以上に多くの有能な人材が必要とされているものの、先進各国では総じて出生率が低下し、高齢化が進行する一方、若年人口が伸び悩む傾向が強まっているため、国内だけで必要な高度人材を調達し確保することが難しくなっている。
もっとも、先進各国のなかで、アメリカは唯一例外的存在である。これまで着実に人口が増加してきたし、今後も中期的に人口増加が続くとみられている。しかし、それはヒスパニック系を中心とする移民の増加と彼らの出生率の高さが主因であり、この要因を除くと、他の先進各国と大きな違いはない。
(ハ)第3に、高等教育システムの整備の問題がある。とりわけ、途上国サイドでは、依然としてハイペースでの人口増加が続いている国が多く、加えて、近年の経済成長によって所得が増加した国では高等教育へのニーズが国民各層に拡大している。
しかし、一般に充実した教育システムを、とりわけ高等教育課程において短期間で構築することは難しい。このため、そうした国々を中心に高等教育ニーズが国内にとどまらず、国外へ向かう動きが強まっている。ちなみに、送り出し国のサイドから2004年の留学生数をみると、最大が38万人の中国であり、第2位が13万人のインドである。
(ニ)こうしたなか、わが国でも、中曽根政権下の83年に掲げられた「留学生受入れ10万人計画」を嚆矢に、留学生の増加が重点政策と位置付けられ、爾来、積極的に推進されてきた。しかし、わが国の留学生受入れには問題点が少なくない。現状に即して主な問題を整理すると、受入れの規模や分野、留学生の質の3点が指摘される。
a.受入れ規模
まず、わが国でも受入れ留学生数は年を追って増加してきたものの、他の先進各国と比べてみると、受入れ規模が依然大きく見劣りすることである。例えば、高等教育 学生総数に占める留学生数のシェアを先進主要各国と比べてみると、2004年時点で、最大はイギリスの16.2%、次いでドイツ11.2%、フランス11.0%、カナダ10.6%と続いており、OECD加盟各国平均でも7.3%と1割弱に達しているなか、わが国は2.9%に過ぎない。
さらに、90年代後半以降、各国が留学生の受入れを積極的に推進し始めるなか、わが国の留学生受入れ数の増加幅は主要各国に比べて際立って少ない(図表2)。ちなみに、2000年から2004年まで4年間の増加数をみると、最大はフランスの10.1万人、次いでオーストラリア9.4万人、イギリス7.7万人、ドイツ7.3万人であるのに対して、わが国は5.8万人にとどまる。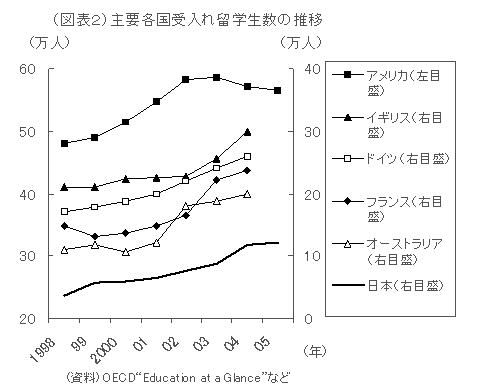
なお、アメリカは9.11事件以来、留学生に対してもビザの発給が厳格化された結果、増勢が鈍化しており、2000年から2004年の増加数は5.8万人であるうえ、2003年の58.6万人をピークに、2004年から2年連続して前年比減少して2005年には56.5万人となった。このところ、連邦政府や大学関係者をはじめ、アメリカで留学生増加に向けた取り組みを改めて強化する必要があるという認識が拡がってきた背景には、他の先進各国との留学生獲得競争が激化するなか、現状を放置すれば、教育産業の低迷を招来するのみならず、イノベーションを原動力としてこれまで切り開いてきた力強いアメリカの経済成長軌道が持続できなくなるという深刻な危機意識がある。
b.受入れ分野
わが国が抱える第2の問題は、受入れ留学生が専攻する分野が社会科学に偏り、とりわけ人文科学分野を専攻する層が厚いのに対して、サイエンスなど自然科学分野を専攻する層が極めて薄いことである(図表3)。他の先進各国と人文科学とサイエンスの二つの分野について留学生の分布シェアを比べてみると、2004年時点で、まず人文科学では、シェアの小さな国から順にオーストラリアが8%、カナダ10%、アメリカ11%、イギリス14%、ドイツ24%となっており、それらに対して、わが国は26%を占める。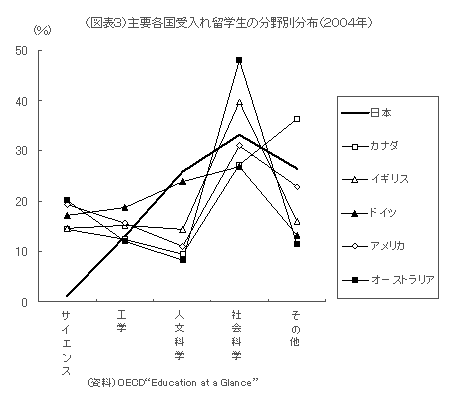
一方、サイエンス分野についてシェアの大きい国から順にみると、オーストラリアが20%、アメリカ19%、ドイツ17%、イギリス15%、カナダ14%に対して、わが国は1%に過ぎない。他の先進各国では留学生の専攻分野が幅広い分野に満遍なく拡がり、イノベーションの中核となるサイエンス分野を専攻する留学生も相当数に上るのに比べて、わが国の現状は歪みが大きく、こうした姿が大きく変わらない限り、留学生を今後のわが国成長戦略の推進力を強化する牽引役の一つにするという展開は期待薄であろう。
こうした歪みは留学生の在学段階別分布からも看取される。世界最大の留学生受入れ国であるアメリカと比べてみると次の通りである(図表4)。まずアメリカでは、従来、大学と大学院の受入れ留学生数はほぼ拮抗してきたなか、2001年には大学院の留学生受入れ数が大学を上回り、さらに9.11事件によってビザの発給が厳しくなるなか、大学の留学生受入れ数が2002年から減少に転じたのに対して、大学院の留学生受入れ数は2003年まで増加した。これは、大学院レベルでの留学生の受入れを大学より選好する連邦政府や大学関係者など、アメリカの姿勢が鮮明に投影された結果といえよう。
それに対して、わが国をみると、近年の留学生の増加は大学および専門学校レベルが大半を占め、大学院の留学生受入れ数の増加は相対的に緩慢なものにとどまっている。例えば、受入れ留学生の在学段階別シェアを2004年度についてみると、最大は大学の52.7%、次いで大学院の25.2%、専門学校の20.3%、高等専門学校などの1.8%となっており、大学が飛び抜けて大きなウエートを占めている。一方、2000年度から2004年度まで4年間の増加数をみると、大学が3.2万人、専門学校が1.5万人であるのに対して、大学院は0.6万人に過ぎない。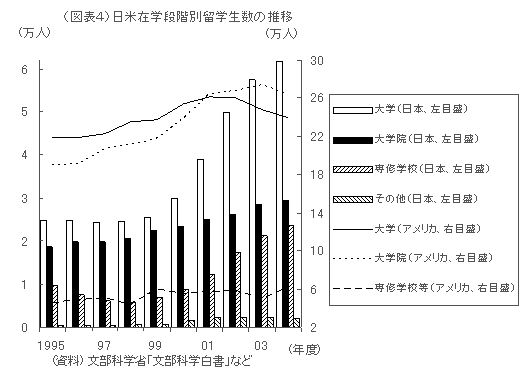
c.留学生の質
第3の問題は受入れ留学生の質である。もっとも、受入れ留学生の5割強が大学に在学し、2割が専門学校に在学している現状からすれば、まず大学や専門学校での状況をチェックすべきであることは言を俟たないものの、アンケート調査以外に拠るべき資料が見当たらないため、ここでは、大学院での学位取得動向をみることとする(図表5)。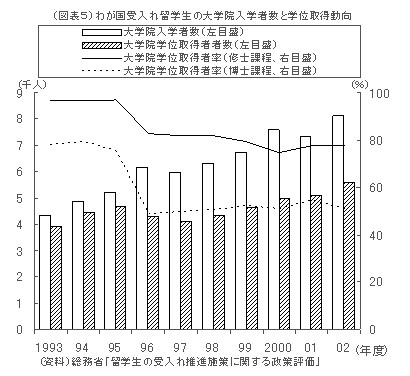
上記の通り、大学や専門学校に比べれば増勢は鈍いものの、大学院でも留学生数は近年ほぼ趨勢的に増加している。例えば、過去10年間の推移をみると、93年度の4,350人から2002年度には8,144人にほぼ倍増した。しかし、大学院で学位を取得した留学生数は緩やかな増加にとどまっている。同じく10年間の推移をみると、93年度の3,936人から2002年度には5,612人と93年度の1.4倍に過ぎず、入学者数とのギャップは93年度の414人から2002年度には2,532人に拡大している。
さらに、留学生の大学院での学位取得動向、すなわち入学者のうち学位を取得した者が占める学位取得者率を修士課程と博士課程それぞれについてみると、次の通りである。まず、修士課程では、90年代半ばには97%とほぼ全員が学位を取得していたものの、96年度以降、大きく切り下がった。近年では70%台半ばとなり、入学者の4分の3しか学位を取得できなくなっている。一方、博士課程の状況は一段と厳しく、90年代半ばには80%弱と入学者10人のうち8人は学位を取得していたが、修士課程と同様に96年度以降、大きく切り下がった。近年では、50%内外に低迷しており、入学者の半分は学位を取得できない状況に陥っている。
なお、近年の研究や科学技術の飛躍的発展の結果、大学院課程のレベルが大幅に上がり、学位の取得が難しくなったのであれば、留学生の学位取得率の低迷を質の低下に結び付ける見方は妥当性を欠く。そこで、日本人の大学院での学位取得率を対比してみると、2001年度時点で、修士課程は留学生の77.8%に対して95.5%、博士課程では留学生の65.5%に対して111.1%、大学院全体では留学生の69.6%に対して98.1%であり、留学生と日本人との間に無視できない学力格差があることが窺われる結果になっている。 - 今後の課題
(イ)研究開発プロセスのみならず、研究の成果を新産業や新事業の創出に繋げ、経済・産業の発展を実現するには、TLOをはじめとする産学協働やSBIRを中心とする政府の支援など、様々なスキームが欠かせない。しかし、一連のイノベーション・サイクルが円滑に機能し成果を上げるためには、そうした様々なスキームを支える多くの有能な高度人材が大前提である。
このため、このところの成長戦略では、有力な成長分野の明確化やイノベーションを支える様々なスキームの整備とともに、人材強化が重要な政策課題として位置付けられ、そのなかで、外国人の高度人材の積極的な受入れ強化が具体的な取り組みテーマとして打ち出されている。例えば、2006年3月に公表された第3期科学技術基本計画をみると、次の通り、様々なメニューが盛り込まれ、総合的な取り組み姿勢を強化していく方針が明記されている。すなわち、研究環境を整備するだけでなく、外国人研究者のための住宅の確保や子弟教育といった生活環境面での受入れ体制の充実を図る一方、出入国管理制度や査証発給制度を見直して研究職や技術職のビザ発給に必要な10年以上という職務経験の条件を緩和したり在留期間を3年から5年に延ばすことが取り組み課題として掲げられている。また、2006年6月の経済財政諮問会議に提出された経済成長戦略大綱をみると、国際競争力のある人材強化に向け、世界的研究教育拠点、いわゆる21世紀COEプログラムの強力な推進と並んで、留学生や外国の高度人材の受入れ強化が、今後、推進すべき重点課題として明確に位置付けられている。
さらに、外国人の高度人材を国内で多数活用していくためには、このように制度的枠組みを整備するだけでなく、職場や地域社会が外国人を抵抗なく受容し、新たなコミュニティーがスムースに形成されていく風土造りや意識改革も望まれよう。これは、まず第1にわが国では今日でも依然として外国人労働力が果たす役割が諸外国に比べて際立って小さく、外国人を受け入れる社会基盤が必ずしも整備されていないからである。ちなみに、労働力人口に占める外国人労働力のシェアを主要各国と対比してみると、2003年時点でわが国の0.3%に対して、イギリスは5.1%、フランス5.2%、ドイツ9.0%、さらにアメリカは14.8%に上る。
さらに、産業分野別にみると、各国では幅広い分野に外国人が労働力として活躍しているのと異なり、わが国では一部の分野に集中していることである。そこで、外国で出生した労働力の産業別分布を主要各国と比べてみると、2003~2004年平均で、まず各国では、鉱工業から商業、飲食業、サービス業など幅広い分野で外国人労働力が活用され、さらにイギリスでは健康や医療分野で外国人が活躍する一方、アメリカでは教育分野での活躍が目立つなど、高度人材分野に対する外国人の進出も相当進んでいる(図表6)。それに対して、わが国では、外国人労働力全体の6割が鉱工業で占められているうえ、次いでサービス業などが3割弱、卸売小売業が1割強であり、これら3業種で大半を占める。
加えて、とりわけ高度人材についてみると、各国に比べて、流動性が極めて低い(図表7)。大学を卒業した人数を分母とし、大卒者のなかで出入国した人数を分子として、高等教育を受けた人材の国際的な流動性を2000年時点で主要各国と対比してみると、OECD主要20カ国平均で入国者数が12%であるのに対して、出国者数は7%にとどまり、差し引き5%の高度人材がネットベースで入国しているなか、わが国は、入国者数は0.7%、出国者数が1.1%と諸外国と比べて際立って流動性が低いうえ、入国者数から出国者数を差し引いたネットの入国者数は▲0.4%と頭脳流出に陥っている。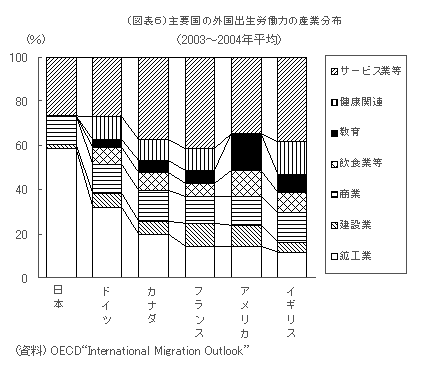
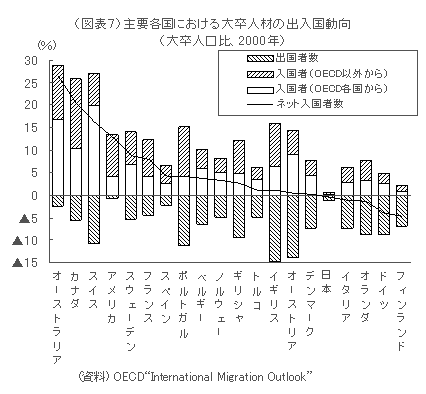
これらを踏まえてみれば、わが国の場合、全体として外国人労働力の活用度合いが相対的に比べて低いうえ、高度人材の活用分野をはじめとして、外国人がほとんど、あるいは全く活用されていない分野が諸外国に比べて相当数に上っている。その結果、多くの分野で外国人労働力を受け入れる経験やノウハウが不足し、十分な受け入れ態勢が整っていない公算が大きい。
(ロ)このようにみると、わが国が今後、外国人労働力を積極的に活用していくためには、様々な課題が山積しているといえよう。そうした課題のうち、とりわけ高度人材の受け入れを強力に進めていくためには、研究環境のみならず、住宅や子弟の教育環境の整備も見落とせないポイントの一つであろう。例えば、フランスのソフィア・アンティポリスが、大学に加え、2003年末時点で1,276社に及ぶフランス内外の企業が進出し、今日、情報通信分野を中心に医療・バイオ、エネルギーなど幅広い分野で世界有数のサイエンス・パークに成長した要因の一つとして、広大な敷地をベースにした優良な研究・居住環境、加えて南仏ニース郊外に位置し余暇を有意義に過ごせる点を指摘する向きは少なくない。
しかし、研究環境や居住環境が万全でなくても、外国人の高度人材の受け入れに成功しているケースは少なくないし、近年、わが国を上回って留学生の受け入れ増加に成功している各国、さらに各国の大学や研究機関がすべてそうした条件を満たしている訳でもない。むしろ、外国人の高度人材や留学生の受け入れ格差を生み出したわが国と主要各国との差異に着目し、わが国が抱える最重点課題を克服することが近道ではないか。こうした観点から、外国人の高度人材活用に向けて、今後、わが国が取り組むべきポイントを、まず多数の優秀な留学生を集め、次いで十分な高等教育を実施し、最後に高度人材として縦横に活躍してもらうというフェーズ順に整理すると、次の3点が指摘されよう。
a.留学勧奨システム
90年代後半以降、留学生受入れ数を大きく伸ばした国はフランス、イギリス、ドイツの西欧3カ国である(前出、図表2)。3カ国はいずれも、90年代後半から2000年代初頭に、留学生政策を大きく転換し、政府主導のもと、留学生数増加に向けて積極的な受け入れ対策をスタートさせた。
具体的にみると、ビザ取得の簡素化や英語による授業の拡大、あるいは留学中の就労規制の緩和や奨学金の拡充など、様々な施策が盛り込まれている。そのうち、わが国サイドからみてとりわけ重視すべきは留学希望者に直接、あるいは留学生送り出し国の高等学校や大学の関係者に対して、各国がそれぞれ仏英独留学のメリットをアピールする一方、自国の高等教育システムや奨学金、さらに宿舎や生活コストの概要など、留学に必要な諸制度や関連知識を分かりやすく公開したうえで、個別相談にも丁寧に応じるなど、踏み込んだサービスが多くの国々で強力に展開されていることである。
こうしたサービスは3カ国とも政府関係機関が実施しており、イギリスは1934年に設立されたブリティッシュ・カウンシルが、ドイツは50年に再スタートを切ったドイツ学術交流協会(DAAD)が、フランスは98年に発足したエデュ・フランスが行っている(図表8)。2003年3月の中央教育審議会資料によると、ブリティッシュ・カウンシルは110カ国229都市に事務所を置き7,300人のスタッフを擁しており、3カ国中最大の機関である。ドイツ学術交流協会はブリティッシュ・カウンシルに比べると海外事務所が13カ国13都市、スタッフ数は543名と小規模である。一方、近年、留学生の受け入れ数を最も大きく増加させたフランスではエデュ・フランスが150名規模のスタッフのもと海外事務所を35カ国80都市に展開している。翻ってわが国をみると、こうした役割は日本国際教育協会が担っている。創立は57年とフランスより早く、50年弱の歴史を持つものの、海外事務所はアジア4カ国の4都市にとどまるうえ、スタッフは73名に過ぎない。加えて、情報発信という面からみても、依然として外国の研究者や技術者にとってわが国の制度は使い勝手が悪い。例えば、2006年3月に公表された第3期科学技術基本計画をみると、外国人研究者の活躍を促進するために、わが国の大学や公的研究機関は、研究者の採用にあたり英語で告知したうえで英語での応募を認めるよう改めて提言されている。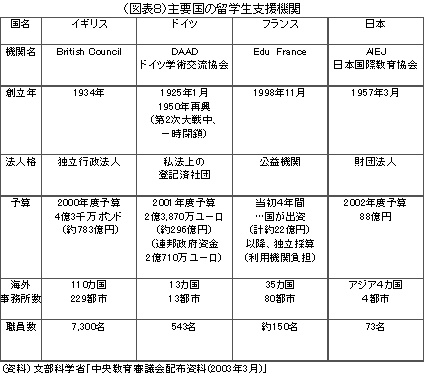
b.高等教育課程の水準引き上げ
ドイツでは、大学の国際競争力を向上させることがドイツ留学の魅力に繋がるという認識に立ち、英語による授業の拡大に加えて、ドイツ以外の国々で就職や研究活動を行ううえでも有効な国際的に価値を持つ学位の導入や拡充に注力し、そうした努力が奏功して、近年、留学生数の大幅な増加が実現されてきた。こうした視点からみると、留学先の大学や大学院で勉学にいそしみ、良い成績を修めることで、どれだけの能力やスキルを身に付けることが出来るか、さらにどれだけ国際的に評価される学位を取得して次のステップに生かせるのかが、留学生一人ひとりの立場に立ってみると、留学先を選択する重要な要素の一つになっているといえよう。それを逆にみれば、学位の取得や卒業には、どのような能力やスキルを身に付け、何が強みなのかが学内や国内のみならず、国際的にも評価される専門性の裏付けが要請されることになる。
こうしたニーズに応えていくためには、高等教育課程の履修について厳格なチェックが最低限必要になる。その場合、優秀かつ健康で意欲的なハイレベルの入学者が揃わない限り、全員が学位を取得し、卒業することは難しい。実際、先進各国についてみると、大学卒業者数は総じて入学者の6~7割にとどまる(図表9)。大学の大衆化が進んだアメリカでは、卒業できた者のシェアは54%と低く、半数弱が卒業に至らない。さらに、同年齢人口に占める大学入学者のシェアを重ね合わせてみると、同年齢人口に占める大学入学者のシェアが大きい国ほど、入学者に占める卒業者数の割合が小さいという相関関係が看取される。言い換えれば、高等教育の大衆化が進んだ国ほど、大学を卒業しない、あるいはできない者のシェアが高い。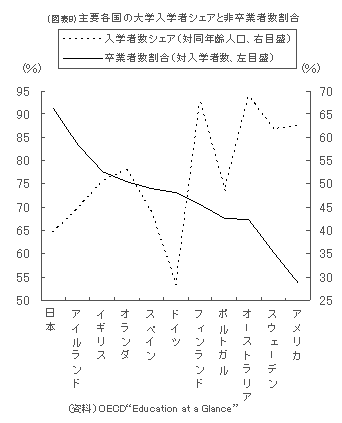
なお、ドイツについてはこうした相関関係が見出し難く、入学者に占める卒業者数の割合は73%とイギリスやオランダ並みであるのに、同年齢人口に占める大学入学者数は28%と先進各国のなかで最もシェアが小さい。もっとも、これはドイツ特有の問題、すなわち、専攻分野によって大学の受入れ限度を上回るため入学が制限されるヌメルス・クラウズス問題が大きく作用している模様である。すなわち、数年間にわたって入学を待機させられる間に、実務的な職業資格を取得する学生が少なくないなか、ドイツの就職事業は厳しく、大卒でも特段優遇されないため、魅力的な就職口があると、在学中でも就職しようとする動きが根強い結果である。このようにみると、ドイツの事象は他の各国で看取される傾向を否定するものではない。
翻ってわが国をみると、同年齢人口に占める大学入学者数は40%と、ドイツを除け ば、各国のなかで最も小さい規模であるものの、入学者に占める卒業者数の割合が91%と際立って高い。これは、わが国の場合、高等教育課程の履修に関するチェックが各国に比べて厳格さに欠ける可能性を示唆しよう。しかし、こうした事態が放置される限り、海外、とりわけ留学生からわが国高等教育への高い支持を獲得し、優秀な留学生を多数確保することは難しい。国際的に通用する学位の導入をはじめ、高等教育の国際競争力強化は焦眉の急である。
c.研究機会の拡大
アメリカでは、多数の留学生を受け入れているなか、近年、学部生よりも、即戦力として期待できる大学院生を重点的に受け入れようとする動きが強まっている。こうした姿勢は、上記、在学段階別留学生の推移でみた通り、2001年以降、大学院での受入れ留学生数が大学のそれを上回っていることに加え(前出図表4)、留学資金にも表れている。すなわち、アメリカに留学する学生の資金原資をみると、学部生の場合、本人あるいは家族が負担しているケースが8割と大半を占めるのに対して、大学院生の場合、本人あるいは家族が負担するケースは4割に半減し、代わって留学生を受け入れる大学が負担するケースが4割に上る。さらに、多数の留学生を受け入れて高度人材の予備軍を囲い込む一方、大学や研究機関が第一線の研究者や技術者を積極的に受け入れようとする動きも引き続き根強い。ちなみに、上記、高等教育を受けた人材の国際的な流動性をみると、アメリカは、入国者は13.7%に達する一方、出国者の規模は0.7%とわが国を下回り、先進各国のなかで最も小さい(前出図表7)。
このようにアメリカが諸外国から高度人材を吸引する力が強い要因を探れば、幅広い分野で最先端の研究が推進されていることや他民族国家であるため外国人にも門戸が広く開かれていること、さらに英語圏であることなど、様々なポイントを指摘することができる。そうしたなか、研究者や技術者一人ひとりの立場に立てば、有望なプロジェクトである限り、出自や年齢、実績に囚われることなく資金やスタッフをはじめ十分な研究リソースが付与され、可能性に挑戦するチャンスを手に入れられる点が最大の魅力であろう。
一方、大学や研究機関サイドに立ってみれば、そうした有望な研究者を多く抱えるほど、財政面で余裕が生まれるというメリットがある。すなわち、政府や民間企業から大学や研究機関に対して供与される研究資金の多くが競争的研究資金として有望なプロジェクトに付与されるなか、研究資金の一部は間接経費という位置付けのもと、当該研究プロジェクトのみならず、大学にも資金が流れるため、優秀な研究者を受け入れ、有望な研究プロジェクトが増えれば増えるほど、大学や研究機関は資金面で豊かになれる。この点に着目すれば、上述の通り、大学院に留学する学生の留学資金の4割を大学が供与したり、海外から第一線の研究者や技術者獲得にアメリカの大学や研究機関が極めて積極的であるのも理の当然といえよう。
翻ってみると、わが国でも、競争的研究資金の重要性に対する認識が深まるなか、近年、国の科学技術関係予算では年を追って競争的研究資金が積み増されてきた(図表10)。2000年度の総額2,968億円、科学技術関係予算に占めるシェア7.9%から、2006年度には総額4,701億円、シェア13.2%へ、さらに2007年度予算の概算要求ベースでは総額5,762億円となり、シェアも14.7%と2000年度からほぼ倍増の水準に達している。
しかし、アメリカの競争的研究資金は、総合科学技術会議が2003年4月に意見具申した資料によると、科学技術関係経費に占めるシェアはわが国の1割強に対して4割前後、金額は300億ドルで1ドル115円で円換算すると3.5兆円に上り、いずれもわが国を大幅に上回る)。加えて、諸外国を参考に競争的資金に占める間接経費のシェア3割を目標とされてきたものの、依然、1割前後にとどまっている模様である。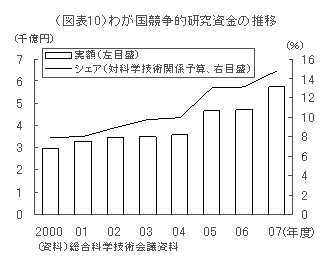
競争的研究資金制度が有効に機能するためには、無論、単に金額を上積みしたり、直接経費のなかに人件費コストを認めたり、間接経費を拡大させるだけでは十分でない。様々な分野にわたる多数のプロポーザルに対して的確な優先順位を付け、オリジナリティーに溢れた有望なプロジェクトに重点を置いて推進する一方、プロジェクトの進捗状況や成果、加えて科学技術の進歩や市場ニーズの変化を踏まえて、プロジェクトのスクラップ・アンド・ビルドを平行して進めるという戦略的な取り組みを積み重ねていく必要があり、多数の優秀な専門家集団の積極的参画が不可欠である。
(ハ)国際競争が一段と激化するなか、イノベーションを原動力とする経済発展を見据え、人材の獲得競争がますます激しさを増している。とりわけ、国内にみるべき天然資源もなく、人口減少社会に突入したわが国にとって、今後引き続き力強い経済成長を実現するために高度人材の確保は最大の問題の一つである。
しかし、わが国の場合、他の先進各国と大きく異なり、高度人材を海外から呼び込むどころか、このところ、逆に海外へ流出する傾向が強まる兆しすら窺われる。厳しい21世紀の国際競争を勝ち抜く成長戦略を成功させるために、高等教育から研究開発へ至るイノベーション・システムの抜本的見直しは喫緊の課題である。

