Business & Economic Review 2005年08月号
【CHINA TREND】
不動産バブルと中国的改革
2005年07月25日 調査部 主席研究員兼日綜(上海)投資諮詢有限公司 首席研究員 呉軍華
中国の不動産市場に大きな異変が生じている。つい最近まで、上海や杭州、南京、北北京といった主要都市を中心に不動産価格は2桁の上昇を続けていたが、今や、売れ残残残り物件が急増するとともに取引額・成約件数が急減しており、混迷の様相を呈していいる。ちなみに、香港系の大手不動産仲介業者である戴得梁行(Debe Tie Leung)の調査によると、上海における4月の中・高級物件の取引件数は3月より半減、取引額は約60%減少、価格も同2.4%低下したという。一方、杭州においても、市内の主要地域における4月の不動産取引件数は3月より40%減少したという。
不動産市場急変の契機は、中央政府が過熱する不動産市場に対する引き締め姿勢を強化したことに求めることができる。2005年3月16日、中国人民銀行(中央銀行)は不動産ローンの金利優遇措置を撤廃し、事実上の利上げに踏み切った。4月27日には、温家宝首相が不動産市場のマクロ的引き締めの強化を議題に国務院(内閣)常務会議を主催した。さらに5月11日、国家発展改革委員会や国土資源部、建設部、中国人民銀行など七つの関係官庁が共同で「住宅価格の安定に関する意見」と題する通達を出し、不動産の転売課税制度の導入や開発業者による土地保有期限の設定、未完成物件の転売禁止といった措置を導入する方針を発表した。これを受けて、同5月27日、建設部は不動産価格を安定化させるに当たっての具体的なタイムテーブルを提出した。こうしたなかで、上海をはじめとした不動産市場の先行きに対する懸念が高まり、一部には中国が不動産バブルの崩壊によって深刻な経済不況に陥った日本や香港の二の轍を踏むのではないかと危惧する声もあがっている。
中国の不動産バブルは果たして崩壊するのであろうか。2004年来、筆者は中国、とりわけ上海の不動産市場のバブル化について警鐘を鳴らしてきた。しかし最近、中国の直面している不動産市場の問題を、不動産市場とそれを取り巻く内外環境の関係から分析した結果、当面、ある程度の価格調整が進むことは避けて通れないものの、中国はかつての日本や香港のように、不動産バブルが崩壊し、それに起因して 経済が深刻な局面に陥る可能性は低いと考えるに至っている。むしろ、中国経済の今後を考えるに当たって、不動産市場の崩壊リスクよりも不動産バブルの生成過程において顕在化したこれまでの改革路線の限界に注目すべきだと主張したい。
不動産バブル崩壊の可能性は低い
不動産市場がすでにバブルの様相を呈しているとの認識を持っているにもかかわらず、なぜ、崩壊の可能性は低いと判断するのか。最大の理由は、現在の中国において、程度の差はあるものの、中央から地方までの各レベルの政府が事実上、不動産業の虜になっていることである。このため、政府はたとえ過熱する不動産市場の問題に対して正しい認識を持っていたとしても、その崩壊による経済・社会への打撃という即発的リスクを恐れ、問題の抜本的解決よりもこれ以上深刻化させないことを目標に政策運営を進めることによって、価格上昇の勢いを抑えつつ不動産市場のソフトランディングを図っていくものと予想される。その背景として、不動産業が中国の経済成長を支える最も大きな柱の一つになっていることを指摘することができる。
こうした現象は拡大する中国経済のなかでもとりわけ好調な上海並びにその周辺地域において顕著である。上海を例にとってみると、不動産市場が盛り上がり始めた1998年の時点において、GDPに占める不動産業の比率は5.2%であったが、2004年には8.4%まで上昇し、GDPの伸び率に対する不動産業の寄与率は大きく上昇した(図表1)。ちなみに、2004年のGDPの伸び率に対する不動産業の寄与率は直接的に13.2 %であったが、間接的には約25%にも達していたと推計されている。この結果、不動産業は今や情報通信関連産業に次いで上海経済を支える大きな柱にまで成長した。
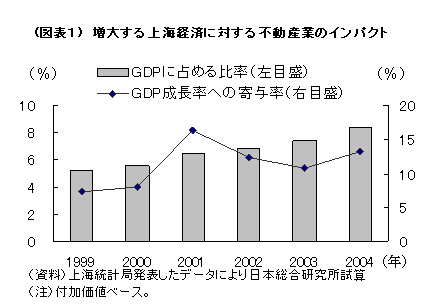
一方、過去25年に及んだ改革・開放によって、イデオロギーの形骸化が大きく進んだ結果、経済成長の達成とそれに伴う国民生活水準の向上が共産党にとっての執政のよりどころになってきた。こうしたなかで、党・政府にとって、不動産市場のバブル化はもちろん警戒すべきことではあるものの、その崩壊によって、経済成長の勢いが鈍化し、社会が大きな不安に陥ることはより危惧すべき最悪のシナリオである。したがって、不動産市場の動向次第で今後、さらなる引き締め策が導入されることがあっても、政府としての狙いはあくまでも過熱する不動産市場の沈静化であり、市場の歪みを是正するといったバブルを崩壊させかねない抜本的対策を打ち出す可能性は低い。実際、住宅ローン優遇金利の撤廃や転売課税制度の導入をはじめとする最近打ち出された一連の対策をみると、従来と比べて引き締めの姿勢が強化されたとはいえ、政府の目的は不動産市場の抱えている問題を抜本的に解決するというよりも、価格急騰の勢いを抑制することにあるのは明らかである。ちなみに、上海市政府は明確に「不動産価格の上昇率を前年対比で10 %以内に抑えること」を引き締めの目標として掲げて おり、不動産業の所管官庁である建設部も「引き締めの目的はあくまでも価格の安定化である」と再三強調している。
現時点において、こうした戦略が結果的に功を奏し、不動産市場のソフトランディングという目的を達成するか、それともバブルをより大きく膨らませて、最終的に中国経済の崩壊に繋がっていくか、についての結論を出すことはなお時期尚早である。しかし、少なくともこうした政策が限界に達するまでは、不動産価格の急落に起因するバブル崩壊の可能性は低いとみていいであろう。
不動産バブル発生の背景(1)-不動産開発業者
不動産バブルそのものの崩壊リスクが当面低いと判断されるなかで、上海をはじめとする中国の不動産市場の問題と中国経済の関係を考えるに当たって、筆者の関心は、もっぱら今回の不動産バブルの生成過程において顕在化した中国的改革路線の限界に集中している。なぜなら、不動産業は現在の中国において、一つの産業部門であると同時に、経済的利益を獲得するために各利益グループの闘争が最も激しく展開されている場の一つであり、社会的富がいかに歪んだ形で再配分されているかを観察するに当たって最も適切な場であるからである。換言すれば、いかなる産業部門よりも、不動産業ほど中国の政治・社会の実態を反映し、それを分析するに当たって参考になる産業部門はない。以下、具体的にみてみよう。
80年代後半の日本や97年前後の香港を例に挙げるまでもなく、不動産バブルはどの国においても発生しうる問題である。しかし、今回の中国の不動産バブルの生成過程を振り返ってみると、「中国的」ともいえる特色が大きな役割を果たしてきたことが明らかとなる。なお、ここでいう「中国的特色」とは、不動産の開発業者・仲介業者や投機筋といった利益グループと政府、とりわけ地方政府が実質的に一種の利益共同体を形成し、不動産に対する需給関係の形成や政策の意思決定、世論などに対する影響力を駆使しつつ不動産価格を意図的に急騰させてきたことを指す。すなわち、今回の不動産バブルの生成には、市場の暴走に加え、政府という「見える手」が極めて大きな役割を果たしてきたわけである。
このような利益共同体は一体、どのように不動産バブルを膨らませてきたのであろうか。不動産開発業者を中心とする利益グループについてみてみると、その手法は世論・価格操作と政策誘導の二つに集約することができる。
まず、前者からみてみよう。市況を盛り上げるための利益グループの世論操作は実に様々な形態で行われてきた。たとえば、資金力にものを言わせ、マスコミや研究者にマーケットの需要増大や価格上昇を煽る情報・レポートを流させることが間接的手法として多く利用されてきた。こうした間接的手法に加え、大手不動産開発業者の経営トップがしばしば新聞やテレビなどのマスメディアに登場し、世論に直接的な影響を与えようともしてきた。その代表的な例として、4月23日に海南省博鰲で起きた事例を取り上げてみてみよう。
その時点では、中央政府を含めて不動産市場のバブル化に対するコンセンサスはすでにかなりのレベルにおいて形成されていた。それにもかかわらず、4月23日、「ボアオアジアフォーラム(Boao Forum for Asia)」というアジア主要国の官民代表が集まるフォーラムにおいて、SOHOチャイナ、華遠集団、万通集団、首創置業有限公司といった中国を代表する大手不動産開発会社の経営トップが口を揃えて不動産 価格のさらなる急騰を予言したうえ、不動産市場のバブル化に警鐘を鳴らしたエコノミストを「政府が発表したデータしか情報を持っていなかったために、不動産市場の実態を理解できておらず、分析の結論はでたらめだ」と激しく非難した。これは香港を含む中国社会において大きな反響を呼んだ。しかし、実際には、著名な大学教授を含むエコノミストの多くが実質的に利益グループの影響下にあるか、あるいはその一員になっており、マーケットの実態を正しく分析して政策提言する「良心的」エコノミストはごくわずかだといわれる。このわずかな「良心的」声をも許さず封じ込めようとする不動産開発会社の経営トップの行動をみると、利益グループは世論操作に向けてある種「恣意的な」状態に入っていると言っても過言ではない。ちなみに、不動産市場の実態を表していないとされている国家統計局の不動産関連指標は、実際には開発業者の申告をベースに集計したものである。
世論をここまで公然と操作しようとしている利益グループはもちろん、不動産価格そのものに対する操作にも躊躇していない。たとえば、仲介業者と結託して物件が完売したように見せかけたり、虚偽の名前で開発物件を大量ないしはそのほとんどを押さえることによって、人為的に供給不足の状況を作り出したりするなど、その手法は枚挙にいとまがない。世論操作や価格操作の他、政策の意思決定に対する不動産開発業者を中心とする利益グループの影響力も無視できない。不動産市場の過熱問題が内外でクローズアップされたのは2004年であったが、実は2003年6月5日、中国人民銀行は「不動産関連貸出業務の管理強化に関する通達」を出し、住宅ローン、とりわけ高級住宅の購入資金としての融資を抑制するように商業銀行に対して指導していた。2004年に入ってから、過熱する不動産市場の沈静化は中央政府のマクロ経済運営の主要なテーマとして打ち出された。それにもかかわらず、不動産価格はむしろそれ以降急騰の一途を辿った。なぜ、政策と実態経済の間にこのような乖離が生じたのであろうか。それは、マクロ経済政策が結果的に不動産価格をできるだけ引き上げようとする開発業者を中心とする利益グループの望む方向で運営されてきたためである。たとえば、本来ならば、不動産市場の過熱を押さえるためには、供給を拡大しなければならない。しかし、実際の政策はむしろ土地供給の停止や不動産開発融資の規制を中心に展開されてきた。この結果、住宅市場の需給バランスが崩れ、価格は大きく上昇した。こうしたマクロ引き締め政策が実際にどれだけ不動産開発業者に利益をもたらしてきたかについて確かな数字を得ることは不可能であるが、一部の不動産開発会社の経営者の発言を通して、その一端をうかがい知ることができる。たとえば、大手不動産開発会社である万科集団は、2004年度の営業利益のうち、60%以上が「市場からのお土産だ」と説明した。こうした説明に対して、万科集団と肩を並べるもう一つの代表的不動産開発会社であるSOHO チャイナの潘石屹総裁は「市場からのお土産だということは実はマクロ引き締め政策からのお土産だという意味である」との解釈を付け加えた。
不動産バブル発生の背景(2)-地方政府
不動産開発業者を中心とする利益グループだけでなく、政府、とりわけ地方政府も今回の不動産バブルに大きく加担してきた。具体的にみてみよう。
図表2は2000年7~9月期から2005年1~3月期にかけて、主要都市の不動産価格の上昇率を全国平均と比較したものである。これによると、上海および上海を中心とする長江デルタの主要都市(南京、杭州、寧波)の上昇ペースは、全国平均はもとより、同じく中国経済の成長を支えてきた珠江デルタ地域(広州、深鰾)や北京、天津をも上回っている。上海および長江デルタ地域が今回の不動産バブルを膨らませるうえでもっとも大きな役割を果たした地域であったことは明らかである。そこで、上海を例に、地方政府と不動産バブルの関係をみてみよう。
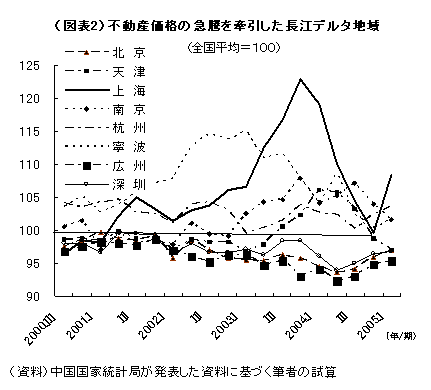
上海も含めて中国において、不動産市場が本当のマーケットとして成立したのは住宅制度改革が始まった98年以降のことである。この改革によって、公務員や国有企業の従業員などを対象とする住宅制度は、従来の実物配分、すなわち年功や地位に対応して住宅そのものを配分する制度から、住宅手当などの支給による貨幣配分へと大きく変化した。この改革とほぼ同時期に導入された内需拡大政策(詳細は次節)は不動産市場の活性化に大きなインパクトを与えた。これまでの上海の不動産市場の流れを振り返ってみると、図表3に示した通り、市況は2000年をボトムに上昇し、2002年以降、とりわけ2003年に入ってから急騰した。
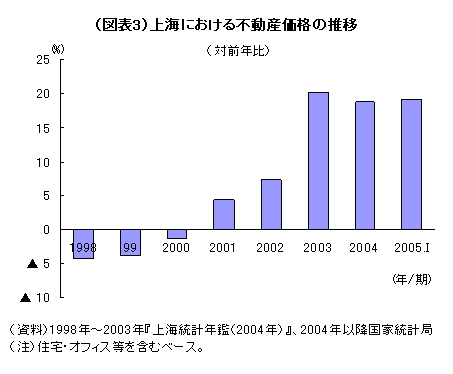
その間、上海市政府は不動産市場に対して、主として世論の形成、優遇政策の導入、需給の操作という三つの側面から影響力を行使してきた。
世論の形成からみてみよう。市況の動向を問わず、世論形成の観点からいえば、不動産市場に対する政府の支援姿勢は一貫性を保ってきた。98年には、低迷していた不動産市場を振興させるために、上海市政府は市民に向けて、「賃貸よりもマイホームを」と呼びかける一方、国内の他の地方や海外の投資家に対して、「ぜひ上海の不動産に投資を」「上海の不動産価格は必ず上昇する」といったキャンペーンを繰り広げた。2003年以降、価格が急騰に転じ、不動産市場のバブル化に対する内外の懸念が急速に高まったなかで、上海市のトップ並びにその影響下にある上海のマスメディアは、「上海は上海人だけの上海ではない。上海は中国の上海、世界の上海だ」、「香港や東京、ニューヨークと比較して上海の不動産価格は決して高くなく、これからも確実に上昇する」と喧伝し、市況の急騰に一層の拍車をかけた。
政策の面においても、上海市政府は不動産購入の奨励策を導入するなど市場の活況を煽ってきた。たとえば、98年6月1日より、住宅の購入者に対する所得税の還付政策が導入されたほか、同年10月26日以降、1戸当たりの面積が70平米以上など一定の基準をみたした住宅の購入者に上海の戸籍を付与する制度も実施された。このうち、前者の措置は、高額な所得税を支払っている上海在住の外国人を含む高所得者層に対し、高級住宅の購入意欲を高めるのに大きなインパクトを与えた一方、「富む人が一層富む」という結果を生み、所得の二極分化に拍車をかけた。
不動産市況に対する上海市政府の関与は、世論や政策といった間接的な手法にとどまらず、需給の操作や価格の設定といった直接的な手段にも表れた。このうち、需要拡大の典型的な最たる例として、都市近代化の促進という名の下で、旧市街地の再開発を必要以上に推し進めることによって、新設住宅に対する需要を大きく拡大させたことがあげられる。ちなみに、こうした都市再開発関連により生み出された需要は上海の住宅需要の約30 %に相当するといわれるが、50%ないし60%に達した地方もある。需要をこのように半ば人為的に拡大させる一方、政府は土地の供給をむしろ制限してきた。この結果、需要が供給を大きく上回るペースで拡大し、それに価格の先高感に伴う投機的需要も加わり、住宅市場は完全な売り手市場になった。
不動産市場に対する上海市政府の直接的関与は需給の操作だけにとどまらず、価格そのものにも及んだ。たとえば、2002年秋に、朱鎔基首相(当時)が不動産部門への過熱投資に対する懸念を表明し、不動産バブルに対する中央政府レベルでの警戒感が強まったのに伴い、不動産価格は一時期安定化する方向に動き出していた。こうしたなかで、上海市政府は2003年、周辺地域の一般住宅よりも高い価格設定で低所得者層を対象とする「安居房」の建設計画を打ち出した。この計画は結果的にその後、不動産市況がバブルに向けて一挙に急騰する契機となった。
このように、地域経済の振興という大義名分のもとで、地方政府は今回の不動産市場のバブル化に大きく加担してきたと言っても過言ではない。
ソフトランディングに向けての課題
ここまで、不動産開発業者を中心とする利益グループ、地方政府と不動産バブルの関係についてみてきた。もっとも、不動産開発業者や仲介業者が経済活動を行う主体として、利益の最大化を追求しようとするのは当然のことである。一方、不動産市況を盛り上げるに当たっての地方政府の行動にも地域経済の振興という大義名分がある。問題は、こうした利益グループや地方政府が経済の安定や社会的公平を犠牲にしてまで自らの利益を求めようとした場合においても、それを規制する法的・制度的な枠組みが存在しない、あるいは存在しても機能しないことである。不動産開発業者に代表される「資本」と地方政府の有する「権力」が実質的に結託することによって形成された利益共同体に対して、一般市民・消費者はもとより、中央政府でさえもしばしば無力の状態に陥っているわけである。こうした状況を改めない限り、中央政府はたとえ強硬な行政措置によって一時的に不動産市場の過熱問題を緩和することができたとしても、中長期的にはより深刻な問題を孕ませてしまうことになりかねない。
問題の所在が分かっているにもかかわらず、不動産市場のソフトランディングに向けた抜本的な改革はなぜできないのであろうか。最大の原因は市場経済化を進めるなかで、政治システムの改革を躊躇してきたこれまでの「政経分離」型改革路線の限界にある。
これまでの分析を踏まえて、こうした改革路線の限界を具体的に見ると、次の2点に集約することができる。すなわち、第1点は「政経分離」であるがゆえに、党・政府がいつまでも経済活動の主役としての立場から身を引くことができないことである。第2点は、市場経済化の進展に伴って、社会の多元化が大きく進んできたにもかかわらず、それに対応する政治システムの改革が立ち遅れたために、皮肉にも社会主義の中国において、資本や権力を持つ、またはそれにアクセスできる「強者」と、そうでない「弱者」に二極化した一種の「弱肉強食」の社会が形成されてしまったことである。
後者については、これまでの分析ですでに触れたので、ここでは前者を中心にみてみよう。前節では、上海を中心に地方政府がこれまでにどのように不動産市場のバブル化に加担してきたかをみてきた。実は、地方政府だけでなく、中央政府も今回の不動産バブルと大きなかかわりを持っている。
そもそも、今回の不動産景気は中央政府によって作られた政策景気であった。98年初、深刻な需要不足に起因して失速しかけていた経済を振興するために、当時の朱鎔基内閣は不動産業を国民経済の成長を支える最も重要な柱として位置付け、その拡大を促すために一連の政策を打ち出した。たとえば、中国人民銀行は98年4月に「不動産関連融資の拡大による不動産関連建設と消費の拡大を支援することに関する通達」を出し、国有商業銀行を中心とする金融機関に対して不動産関連融資の拡大を強力に促した。全国的な開発区ブームと華南地域の住宅バブルに起因した前回の不動産バブルを終息させるためのマクロ引き締め政策が「ソフトランディングという所定の目的を達した」との宣言が同内閣によって出されてから1年も経っていない時の政策変更であった。
もちろん、朱鎔基内閣は決してバブルを膨らませるために政策変更を行ったわけではない。しかし、土地と政府、とりわけ地方政府の利益関係が断ち切れない状態のもとで、不動産業を国民経済を支える柱として大きく打ち出した場合、結果的にマクロ経済レベルにおいて大きな代価を払うことになりかねないということは、過熱と引き締めを繰り返してきたそれまでの中国経済の軌跡を振り返ればある程度予想できたはずであった。それにもかかわらず、なぜ、このような政策変更が行われたのであろうか。それは、「政経分離型」改革路線のもと、共産党が執政の合法性を経済成長の維持とそれに伴う国民生活水準の向上に求めざるをえなくなったため、景気拡大ペースの維持は党・政府にとっての最大の政治的課題になっていたからだと考えられる。マクロ経済運営は時として、国民経済の持続的成長という中長期的目標と目の前の経済成長の維持という短期目標のどちらを優先すべきかというジレンマに直面する。そして、政権維持が中国共産党にとっての至上命題であるために、ほとんどの場合は後者が選ばれることになる。98年に、朱鎔基首相(当時)が自らの政治的威信をかけて93年から実施してきたマクロ引き締め政策によって不動産バブルに起因した前回の経済過熱をやっと沈静化させたところで、自らの手で再び不動産景気に火をつけてしまったのはまさしくこうしたジレンマに直面した結果であったといえよう。
「政経分離型」改革路線の限界は地方政府の行動にも大きなインパクトを与えている。経済成長の実現という中央政府レベルが受けた圧力は結局、必然的に地方政府に転化されて行くことになる。経済成長を実現するに当たっての実績が地方政府の担当者にとって最も重要なキャリアパスになっているなかで、GDP至上主義の横行はもはや必然的な流れとなった。こうした状況のもとで、国レベルにおいては非合理的であっても、または中長期的には地域経済や社会福祉にとって不利なことであっても、在任中の経済成長率を高めることさえできれば、不動産バブルであっても、それを最大限に利用しようとすることが地方政府の担当者にとって一種の合理性を持った選択肢になる。加えて、土地取引の過程において、地方政府あるいはその担当者は合法的にも非合法的にも巨額な経済的利益を享受することが可能である。ちなみに、2002年から2004年にかけての3年間で、地方政府が土地を譲渡することによって得た収入は9,100億元(1元約13円)にも達していたといわれる。これは、同期間の地方財政収入の3分の1にも匹敵するほどの金額であり、多くの地方政府にとって、土地による収入は財政収入と並ぶ最も重要な収入源になっている。政治的にも経済的にも地方政府にとって、不動産業がこれだけの効用を持っているために、不動産業の拡大に対する中央政府の規制さえ緩和されれば、不動産バブルの形成はある意味では当然の帰結だと言って過言ではない。
このように、中国における不動産バブルとそれに起因する経済過熱は景気循環に伴って現れる問題であると同時に、制度に根付く構造的な問題である。計画経済の時代はもとより、市場経済化に向けた経済改革が進められてから25年経った今も、中国経済が「一放就乱・一抓就死(緩和すれば経済過熱、引き締めれば経済失速)」というサイクルから脱することができないのは、まさしくいつまでもこうした制度的問題にメスを入れずに、小手先の改革で済ませてきたことによるものといえよう。「政経分離」による漸進的改革は、これまでに中国に経済成長という大きな成果をもたらしてきたが、今や持続的成長基盤を構築するに当たっての大きな足かせになっている。不動産市場の問題をはじめ、中国経済が新たな発展段階にソフトランディングしていくためには、もはや抜本的改革の断行を避けては通れない段階に差し掛かっているといえよう。

