第8回 「顧客の要求曲線を意識したイノベーション・マネジメント」
2004年6月2日 浅川秀之
(1)はじめに
「どこまでの機能を持った製品をどのタイミングでリリースすればよいのか」、製造業企業にとっては共通の悩みであろう。他社よりも優れた機能を備えた製品をリリースできるにこしたことはない。だからといっていたずらに開発期間を長引かせるわけにもいかない。顧客の要求をある程度満たした製品をタイミングよくリリースする必要がある。また、他社よりも優れた製品をリリースするといはいっても、どこまで機能アップすれば他社に対して十分な優位性を築くことができるのか。ただ闇雲に機能アップを追及すればよいというものでもない。開発部門や、製品企画部門などにおいては、自社の持つ技術力に鑑みつつ「機能」と「タイミング」の最適な落としどころについて常に悩んでいることと推察される。特に、開発投資決定部門などの上位意志決定部門においては、その判断が直接経営上の数字となって表れることから、さらにその悩みは大きいであろう。
「どこまでの機能を」という問題を解決するためには、自社の技術革新状況をユーザーの要求に照らし合わせて分析する必要がある。また「どのタイミングで」という問題を解決するためには、技術革新およびユーザー要求を時間軸に沿ってダイナミックに把握する必要がある。本稿においては、クリステンセンのイノベーション論(注)を基に、顧客の要求するレベルを意識したイノベーション・マネジメント方法について、その考え方のフレームワークを整理する。さらに過去および現在の事例について本フレームワークを用いて分析し、このフレームワークの有効性を検証する。このフレームワークを用いることにより「どこまでの機能を持った製品をどのタイミングでリリースすればよいのか」という問題に対して定性的かつ定量的な分析が可能となる。
(注) イノベーションのジレンマ』(2002年12月第6刷)、『イノベーションへの解』(2003年12月初版)において述べられている「破壊的イノベーション」を中心とした一連のイノベーションに関する理論体系をさす。
(2)要求曲線を意識したイノベーション・マネジメント:フレームワーク
クリステンセンの著書においては「破壊的イノベーション」をいかにマネージメントするか、ということが重要なメッセージの一つになっている。同書の中では、技術進歩の様相を「破壊的イノベーション」および「持続的イノベーション」という2つの定義を起点とし、利益を最大化させる資源配分メカニズムが時として優良企業を滅ぼすことがあるということについて検証を行っている(文献1、文献2)。
同書の中においては技術イノベーションの時間的発展は常に「直線」で表現されている(下図表参照)。本稿においては、「製品や技術、サービスなどは、一定の時間が経つと、その機能や性能は飽和状態に至り、さらなる機能向上、性能向上はこのような飽和状態を経てから実現される」という仮定のもと、イノベーションの様相を「直線」ではなく「ステップ」的曲線で表現する。これにより、特に近年の情報通信分野などに顕著にみられる複雑なイノベーション様相をより詳細に分析可能であることについて、具体的な事例などを交えて検証を試みる。
【図表】 破壊的イノベーションのモデル 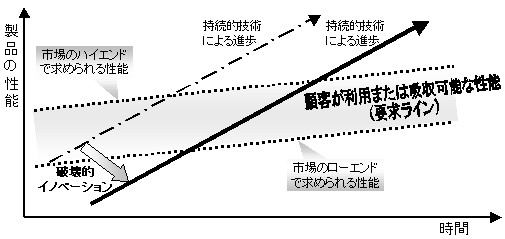
(出所) クレイトン・クリステンセン『イノベーションのジレンマ』(2002年12月第6刷、玉田俊平太監修、翔泳社)を基に日本総合研究所加筆
一般的に、製品や技術、サービスなどは、一定の時間が経つと、その機能や性能は飽和状態に至ると考えられる。例えば、近年のブロードバンド通信の代表的な技術であるADSLについてとりあげる。ADSLは当初数Mbpsクラスのサービス提供からスタートし、その後8Mbps、12Mbpsとステップ的に発展し、現在に至っては40Mbps超のサービス提供が実現している。この間の第二種通信事業者を中心とした通信キャリア間競争の激しさは、誰もが知るところであろう。同じアクセスレイヤーの通信技術である第三世代携帯電話や無線LANをはじめとする「無線アクセス技術」に関する競争についても、今後数年~10年程の間非常に激しい競争状況が展開されることが各方面で予想されており、その動向が注目されている。この「無線アクセス技術」に関する競争状況を例にとり、「ステップ型イノベーション曲線」を用いた分析方法について述べる。
「無線アクセス技術(主にデータ通信)」を分析する場合、技術的、性能的な指標は「帯域(通信スピード)」と「アクセシビリティ(つながりやすさ、通信安定度など)」の2点に集約することができる。これが下図表の縦軸に相当する。
【図表】 無線アクセス技術に関するイノベーション概観 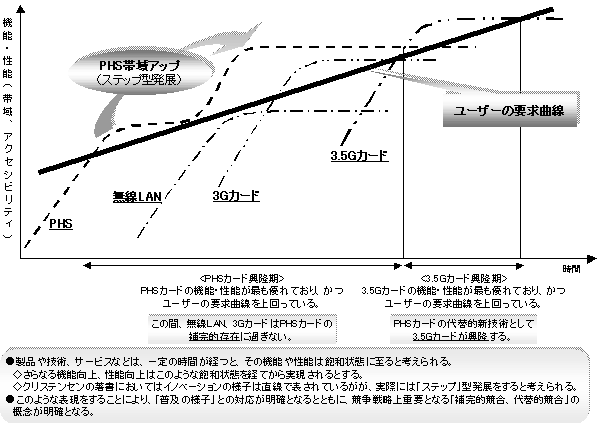
(出所) 日本総合研究所ICT経営戦略クラスター浅川[2004.05]作成
時間の経過に伴って、各技術要素は技術的、性能的向上を続けるが、あるフェーズにおいてはその向上が一時的に鈍り(もしくは一定となり)、新たな革新などによりさらに向上(ステップ型発展)を続けるという様相を示す。この一連のイノベーションプロセスにおいて、一部の他技術が補完的な技術として発現する場合や、当該技術が非常に優れているために、既存の技術が完全に取って代わられる、つまり代替的な技術が発現する場合などが想定される。また各新技術の発現により、それぞれの技術に属するユーザーの増減の様相(普及の様子)についても、ユーザーの要求曲線とイノベーション曲線との交差点を意識することにより、より詳細な分析が可能となる(下図表参照)。
【図表】 イノベーションと普及曲線の関係 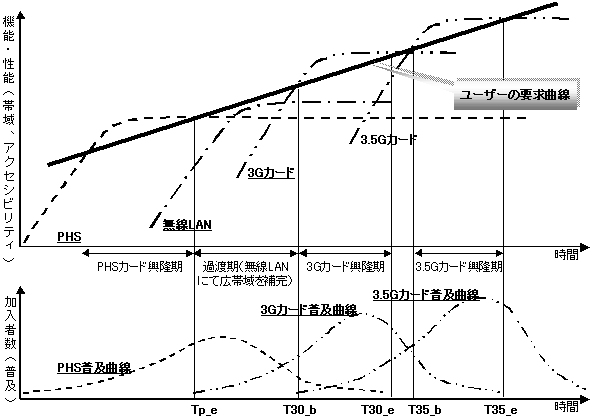
(注) ◆「Tp_e」:PHSカードの終焉時期、◆「T30_b」:3Gカードの始まり時期、◆「T30_e」:3Gカードの終焉時期、◆「T35_b」:3.5Gカードの始まり時期、◆「T35_e」:3.5Gカードの終焉時期
(出所) 日本総合研究所ICT経営戦略クラスター浅川[2004.05]作成
このように「ステップ型イノベーション曲線」を用いることにより、ユーザーの要求曲線を意識したより詳細なイノベーション・マネジメントが可能となる。具体的には、①「普及の様子」と技術発展との対応が明確となること、および②競争戦略上重要となる「補完的競合、代替的競合」の概念が明確となる、という2つのメリットが挙げられる。
(3)要求曲線を意識したイノベーション・マネジメント:ケーススタディ
ここまで述べてきたユーザーの要求曲線を意識したイノベーション・マネジメント手法を用いて、過去に発生した事例としてNECのコアネットワーク製品2種(Spectral Waveシリーズ)をとりあげ、対比分析を試みる。また、現在進行中の事例として近年話題になっている「ネット家電」についてその普及の難しさについても同様の分析を試みる。
1)過去の事例
●NECのコアネットワーク製品における成功と失敗:「Spectral Wave 160」と「Spectral Wave U-Node」
1980年台後半から1990年代中頃にかけて、日本のインフラ通信装置ベンダー各社はデジタル伝送装置の開発に力を入れてきた。この間、技術的な向上は著しく、また世界的にみても情報通信インフラへの設備投資が増大傾向にあったため、各社とも好調な業績を残すことができた。しかしながら、1990年代後半から現在に至るまでの間、日本ベンダー各社のインフラ情報通信装置の売上高縮小は非常に顕著である。このような厳しい状況の中、NECは開発コンセプトの対照的な「Spectral Wave 160」(以下SW160)と「Spectral Wave Universal-Node」(以下U-Node)という2つの光通信インフラ装置を相次いでリリースした。
【図表】 NEC Spectral Wave 160およびSpectral Wave U-Node対比表
| 対比事項 | Spectral Wave 160 | Spectral Wave Universal-Node |
|---|---|---|
| 概要(NEC製品紹介ホームページ、プレスリリースから抜粋) | ● 電話回線に換算すると約2,000万回線に相当する、最大1.6テラビット/秒(Tbps)の伝送容量を実現した160波DWDMシステム。 ● 1本の光ファイバー上で、2.4ギガビット/秒(Gbps)または、10Gbpsのインターフェースを任意に組み合わせることにより最大160波まで波長多重可能。 ● 2000年10月北米最大の通信キャリアAT&T向け160波WDMシステム包括受注契約を締結。 |
● 北米市場向け、国内市場向け、アジア/中南米/欧州等CEPT市場向け規格を統合し、各市場の様々な要求に対応するシステムで、グローバルに事業を展開する通信事業者に効率的、経済的な保守・運用を提供することが可能な、コアネットワーク光通信装置。 ● イーサパケットやIPパケットなどをSDHフレーム等に収容し、伝送帯域を無駄なく有効に使用して、インターネット等のIP信号を効率的に収容することが可能。 ● 最先端のデバイス技術で当社従来製品比で約2分の1の小型化と消費電力を実現し、バックボーンからメトロまでの幅広い分野での適用が可能です。 |
| 補足 | ● 2000年5月に製品化を発表。製品レベルで1.6テラビット/秒(Tbps)の伝送容量の実現は世界最高峰であり、世界的にみても注目度が非常に高かった。 | ● 2001年1月に製品化を発表。基本的には従来のSONET/SDH装置。すべての標準規格に準拠可能であり、さまざまなインターフェースや容量アップに柔軟に対応できるようなプラットフォームを採用。 |
| 特徴 | ● 技術的新規性、優位性が非常に高い ◇ NECの誇る最先端光通信技術を集約 |
● 技術的な新規性は少ない(基本的には従来技術) ● 各種ネットワークやインターフェースへの柔軟性を考慮 ◇ 未知なるインターフェースへの対応性を考慮 ● 小型集約化 |
(注) ◆「DWDM」:高密度波長分割多重方式の略。光ファイバーを使った通信技術の一つ。波長の違う複数の光信号を同時に利用することで、光ファイバーを多重利用する方式。
(出所) NECホームページ公開情報を基に日本総合研究所作成
今現在のこの2製品の状況はというと、SW160については製品ラインナップから既に姿を消しており(製品開発はストップしたと推測される)、容量的には縮小されているものの柔軟性をとりいれた新規のWDM装置がラインナップされている。一方のU-Nodeについては、現在も機能拡張を続けながら順調に国内外への出荷が続いている模様である。結果のみからの判断ではあるが、SW160に関してその開発戦略は「失敗」であり、U-Nodeに関しては「成功」であることは明らかであろう。
この2製品に関して、ユーザーの要求曲線を意識した「ステップ型イノベーション曲線」を用いて、その成功・失敗要因の分析を行う。下図表(左図)はSW160についてその技術的発展の状況を示したものである。
【図表】 SpectralWave160/DW40XXに関するイノベーション概観 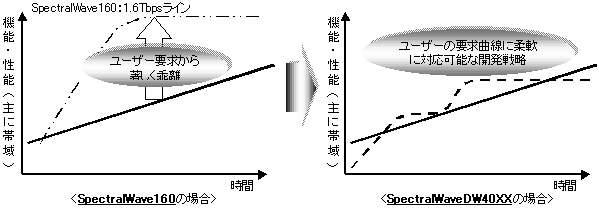
(出所) 日本総合研究所ICT経営戦略クラスター浅川[2004.05]作成
開発当初、1.6Tbps(テラビット/秒)の伝送容量は、技術的にみても世界最高峰であり、他社の追随を許さなかった(リリースされた翌年には、北米AT&Tと包括受注契約を取り交わすに至ったことからしても、その技術水準の高さがうかがわれる)。しかしながら、その後大規模な受注に関するプレスリリースはほとんどみられず、現時点では製品開発がストップするに至ったと推測される。北米のITインフラ投資が一巡したことも大きな原因の一つであろう。しかしながら、1.6Tbpsという伝送容量は、当時のユーザー(この場合日本国内外の大手通信キャリアなど)の要求ラインを大きく上回りすぎていたことが主原因の一つではないかと考えられる(注)。
(注) JRIの計算では、日本全国約5,000万世帯のADSLを賄う場合、バックボーンに必要な容量は「約60Tbps」と算出している。また、実際に日本の代表的なIXにおいてもその瞬間最大帯域は「35Gbps」程度(JPIX、2004年1月)である。このような状況の中で1.6Tbpsという巨大な装置が何台必要かということについては、少なくとも「飛ぶようには売れない」ということは容易に想像できよう。
このような状況を認識しているのかどうかは推測の域を出ないが、現在のNECのWDM製品は「SpectralWaveDW40XXシリーズ」という新規製品をリリースしており、「伝送容量やネットワーク形態に合わせた最適なモデルを選択することでコストを抑えたスモールスタートが可能」というコンセプトのもと、ユーザーの要求曲線に柔軟に対応可能な開発戦略をとっている。
一方U-Nodeに関して開発当初は、競合他社に比して非常にコンパクトな伝送装置であったことを特徴としていたのみで、それ以外の機能的な部分に関しては、特に他社に比して特別な優位性を持っていたわけではない。しかしながら、リリース直後はその時点で必要最低限の十分な機能を有しつつも、その後は10Gbps(ギガビット/秒)インターフェースや、Fast Ethernetインターフェース、Gigabit Ethernetインターフェースと新たなインターフェースや機能メニューをタイムリーかつ矢継ぎ早に追加している。現在に至っては10Gbit Ethernetインターフェースも新たに追加されており、同一のプラットフォームにもかかわらず、ユーザー要求に対して柔軟に拡張対応していることがうかがわれる(下図表参照のこと)。
【図表】 Spectral WaveU-Nodeに関するイノベーション概観 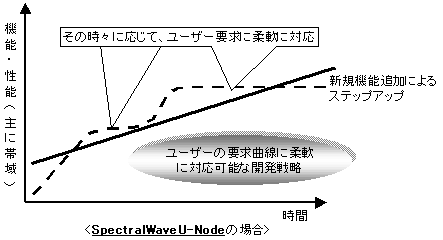
(出所) 日本総合研究所ICT経営戦略クラスター浅川[2004.05]作成
このように同一のプラットフォームをベースに柔軟な拡張性を持たせているという戦略は、新たに最初から装置開発を立ち上げる場合に比して、そのコスト的、時間的な効率性は計り知れない。現在に至っても好調に出荷を続けることができる要因はここにあると考えられる。「Universal」という名称を付していることからもうかがえるように、開発当初から将来の未知なる機能拡張に柔軟に対応可能なプラットフォームを作り込んでいたのであろう。
SW160は、その技術的な優位性は非常に高かったが、ユーザーの要求曲線を無視した開発戦略であったことがうかがわれる(現在は、新たな製品群により柔軟な対応を意識した開発戦略に変更している)。一方でU-Nodeに関しては開発当初からユーザーの要求曲線を意識した柔軟なプラットフォームを作り込んでおり、現在も柔軟な拡張を続けている。つまり「ユーザーの要求曲線を意識した柔軟な開発戦略」をとったか否かが両製品の明暗を分けたといえるであろう。
2)現在の事例
●「ネット家電」の普及の難しさ
「ネット家電」という言葉自体は盛んに耳にする。しかしながら、身の回りが「ネット家電」の普及している状況かというと決してそのような状況にはない。各家電メーカーは「ネット家電」の普及に向け、数多くのコンソーシアムを設立したり、多額の投資により「ネット家電モデルルーム」を建設したりと努力を惜しまない。しかしながら一般のユーザーの声を聞くと「洗濯機や冷蔵庫がインターネットにつながって何が便利なのか。使えればそれでよいではないか。」といった消極的な意見が多いようである。このようなメーカーと一般ユーザーの乖離状況についても、ここまで述べてきたユーザーの要求曲線を意識したイノベーション分析により説明が可能となる(下図表参照のこと)。
【図表】 ネット家電普及の難しさ 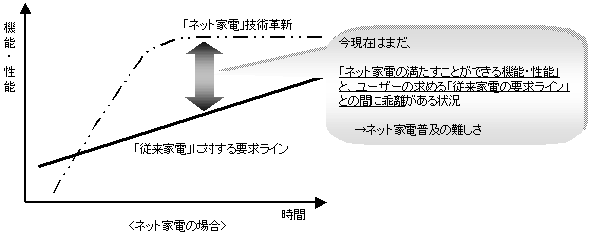
(出所) 日本総合研究所ICT経営戦略クラスター浅川[2004.05]作成
(4)要求曲線を意識したイノベーション・マネジメント:柔軟性
1)柔軟な意思決定
ア.不確実性への動的な対応
近年、休眠状態にある知的財産や、製品化には無関係な技術に関する論文、その他具体的な結果として公開されるまでにも至らない数々の研究開発成果などに対する価値評価が注目されている。このようないわゆる「埋もれた技術」に対する価値評価の手法は様々に論じられている。浅川・新保[2003:文献3,4]は、特定の技術に対して時間軸に沿った動的なとらえ方をすることの重要性について述べている。
下図表は、「埋もれた技術」に対して将来的な意味付けがなされる様子をグラフ化したものである(浅川・新保[2003:文献3,4])。ある特定の技術に関してその真の意味を発見すること、つまり同図表中において「製品化ライン」を超えるポイント(市場化ブレイクスルーポイント)をいかに見出すかということが重要となる。この浅川・新保の示すところの「製品化ライン」が、ここまで述べてきた「ユーザー要求曲線」そのものであるととらえることができる。従って、ユーザー要求曲線は時間とともに変化する(通常は高い要求へとシフトしていく)という前提から、「埋もれた技術」に対して将来的な真の意味を見出すためには、この「製品化ライン」も時とともに変化するという概念をとりいれることの重要性が導きだされる。これにより、より厳密な分析が可能となる。
【図表】 埋もれた技術に対する将来的な意味付け 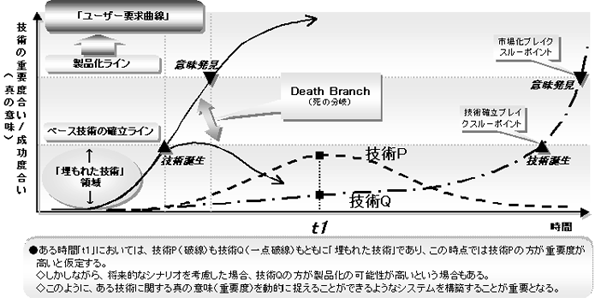
(出所) 日本総合研究所ICT経営戦略クラスター新保・浅川[2003.12]作成
イ. リアル・オプションへの応用(注)
(注) ここまで述べてきた「顧客の要求曲線を意識したイノベーション・マネジメント」手法に、リアル・オプションの考え方を適応することの有用性については、新保(日本総研主席研究員)から示唆を得た。以下に述べる事例を用いた計算およびそれに対する考察は、新保から得た示唆に基づくものである。
ある架空の通信機器ベンダーT社の事業価値について、リアル・オプション手法を適用する事例を紹介する。また、一連のリアル・オプション手法の中で、ここまで述べてきた「ユーザーの要求曲線を意識したイノベーション分析」について、その概念をどのように織り込むことができるかについても述べる。
●架空事例:通信機器デバイスメーカーT社の次世代「光スイッチングデバイス」開発
T社は、インフラ系光通信装置向けのデバイス開発企業である。これまでインフラ系光通信装置は電気処理による信号切替方式が主であったが、ブロードバンド化の急激な発展とともに、信号を光のまま処理を行う「光スイッチング」装置の需要増が見込まれている。そこで、T社は「光スイッチング」装置のキーデバイスである「光スイッチングデバイス」の開発着手を検討している。光スイッチングデバイス開発には多額の開発資金が必要で、製品化に必要な期間(3年と見積もられている)において、人件費を中心に120億円程度必要と見込まれている。この間固定費がかさみ黒字転換の見通しは立たない。一方でT社の光スイッチングデバイスが、大手通信ベンダー各社の装置に搭載された場合、T社の光通信向け事業の現在価値は以下のように見積もられている。
【図表】 T社の光通信向け事業の現在価値
| シナリオの分類 | T社の光通信向け事業の現在価値 | 発生確率 | シナリオ |
|---|---|---|---|
| 楽観シナリオ | 480億円 | 15% | ◇ユーザーのブロードバンドに対するニーズが急速に高まり、これに伴いインフラ帯域需要も著しく拡大。既存の電気処理による信号切替方式では帯域需要を全く満たすことができない。 |
| 堅実シナリオ | 240億円 | 65% | ◇ユーザーのブロードバンドに対するニーズの高まりに伴い、インフラの帯域需要もある程度は高まる。一部のインフラはこれまで通り電気処理による信号切替方式が採用され、都心部などでは光スイッチング装置が採用される。 |
| 悲観シナリオ | 130億円 | 20% | ◇ユーザーのブロードバンドに対するニーズは期待していた程高まらず、インフラの帯域に関しても、既存の電気処理による信号切替方式で、十分に需要がまかなえる状況である。 |
(出所) 日本総合研究所作成
リアル・オプション価値の算出に必要な各パラメータ値は以下のように求められる(定義する)。
【図表】 T社リアル・オプション価値算出に必要なパラメータ
| 原資産価値:S | 254億円 | ● 原資産価値は3つのシナリオの現在価値の期待値 ◇ 480x15%+240x65%+130x20%=72+156+26=254(億円) |
|---|---|---|
| 原資産価格変動性:σ | 81% | ● 類似ケースのヒストリカル・ボラティリティを用いる |
| 権利行使価格:X | 120億円 | ● 3年間の開発費用(人件費やマーケティング費用なども含む) |
| リスクフリーレート:r | 3% | ● 3%とする |
| 満期:t | 3年 | ● 製品化に必要な期間 |
(出所) 日本総合研究所作成
ここまでの前提から、T社の事業価値(t=3における)は174.9億円と算出される。仮に変動性が30%であった場合は134億円となる。他方で、DCF法を用いた場合その事業価値は「137.9億円」と計算される。
【図表】 T社リアル・オプション価値算出に必要なパラメータ
| リアル・オプション価値 | 174.9億円 | ◇ 変動性81%の場合 |
|---|---|---|
| 137.9億円 | ◇ 変動性30%の場合 | |
| DCF法価値 | 134億円 | ◇ 254-120=134(億円) |
(出所) 日本総合研究所作成
本事例は、開発の開始可否判断というスタートアップ時の事業価値評価を題材としている。当然のことながら、開発がスタートした後においても、今後のシナリオに影響をおよぼすような重要ファクターの発現が予想されるような場合には、その都度リアル・オプション計算分析を再構築し、柔軟な対応を計っていく必要がある。
例えば、本事例においては将来のユーザーの「ブロードバンドに対するニーズ」動向が大きく影響をおよぼす。このユーザーニーズは、ここまで述べてきた「ユーザーの要求曲線」によってその動向を明確化させることが可能であり、この分析の結果をリアル・オプション計算へ反映することが可能となる。具体的当初「480億円、15%」と見積もられていた「楽観シナリオ」についても、例えば「ユーザーの要求曲線を意識したイノベーション分析」により、ある時点での技術発展状況から推測するとユーザーの要求曲線を超えることが難しいと判断された場合には、その時点で事業価値を下げることにより、リアル・オプション価値を再計算することが可能となる。
このように、3つのシナリオに対して「ユーザーの要求曲線」を意識した分析を加味するということは、ユーザー要求と技術動向に鑑みた上でシナリオを再構築することを意味する。これはリアル・オプション計算上において、ボラティリティ(将来発生しうる事象の分布状況)そのものに「ユーザーの要求曲線」を意識した分析を適応することに他ならず、製品開発戦略上の柔軟な意思決定に重要な影響をおよぼす。
(5)まとめ
「ステップ型イノベーション曲線」を用いた分析により、ユーザーの要求曲線を意識したより詳細なイノベーション・マネジメントが可能となる。具体的には、「普及の様子」と技術発展との対応が明確となること、および競争戦略上重要となる「補完的競合、代替的競合」の概念が明確となる、という2つのメリットが挙げられる。この分析を、研究開発における不確実性に動的に対応することや、研究開発投資判断などに重要な示唆を与えるリアル・オプション法などへの適応することにより、より柔軟な研究開発戦略策定が可能となる。
● 参考文献など
[本文中にて直接引用している文献等]
◇ (文献1)クレイトン・クリステンセン『イノベーションのジレンマ』(2002年12月第6刷、玉田俊平太監修、翔泳社)
◇ (文献2)クレイトン・クリステンセン、マイケル・レイナー『イノベーションへの解』(2003年12月初版、玉田俊平太監修、翔泳社)
◇ (文献3)新保豊、NIKKEI BizPlus連載企画「"IT革命第2幕"を勝ち抜くために」、第38回「ITを駆使する研究開発戦略(上)――研究者の知を高める仕掛け(2003年12月26日)
◇ (文献4)浅川秀之、「研究開発戦略、不確実性に動的対応」『日本工業新聞』(2004年1月23日)
[全体を通して概念形成に有用な示唆を与えた文献等]
◇ マイケル・L・タッシュマン他『競争優位のイノベーション』(1997年11月、ダイヤモンド社)
◇ ジョン・P・コッター『企業変革力』(2002年4月、日経BP社)
◇ 榊原清則「日本企業の研究開発の効率性はなぜ低下したのか」『ESRIディスカッション・ペーパー・シリーズNo.47』、内閣府経済社会総合研究所(2003年6月)
◇ 技術革新型企業創生プロジェクトの第1回オープンセミナー(2003年11月11日、於東大先端研)における慶應大学 榊原清則教授の講演内容
◇ 村上路一「危機意識から生まれたイノベーション・マネジメント」『Works』(1999年12月)
◇ ジョン D.ウォルパート「埋もれた技術の市場化戦略」『Diamond Harvard Business Review』(2003年1月)
◇ 二瓶正 他「デスバレー現象と産業再生」『NEXTING Vol.4 No.3』三菱総合研究所(2002年3月)
◇ ゲイリー・ハメル、C.K.プラハラード『コア・コンピタンス経営―未来への競争戦略』(2001年1月、日経ビジネス人文庫)
◇ 西村吉雄『産学連携―「中央研究所の時代」を超えて』(2003年3月、日経BP社)
◇ 「Cover Story特集:研究開発、異域の才を得て未踏の地を狩る」『日経エレクトロニクス』(2004年1月5日)
◇ 保江邦夫『最新Excelで学ぶ金融市場予測の科学』(2003年10月、ブルーバックス)
◇ 刈屋武昭、山本大輔『入門リアル・オプション』(2002年12月第4刷、東洋経済)
◇ 小林啓孝『MBAビジネス金融工学 デリバティブとリアル・オプション』(2003年5月、中央経済社)

