第5回 「『絞る』マネージメントの重要性について」
2004年2月6日 浅川秀之
(1)はじめに
昔「高校生クイズ大会」なるものに参加したことがある。正式な大会名ははっきりと覚えていないが、高校の同級生3人で一組になり、地区予選大会に出場した。勝ち上がるにつれ強豪チームと対戦する頻度が高くなり、あと一歩で地区予選大会を突破するところまで運良く勝ち上がることができた。しかしながら、最終的な結果は地区予選敗退。最後に対戦したチームの中には、100チーム以上からなる地元高校の予選大会を勝ち抜いた後、この地区予選大会に出場しているというチームもあった。我々のように、気まぐれで出場しただけの一時的なチームがまともに相手をして勝てるわけがない。
100チームからなる予選を勝ち上がったチームと、何の予選プロセスも経ていないチームとの対戦では、その対戦結果は明白であろう。もちろん勝ち上がる前の母集団の「質」にも大きく依存するので、数が多ければ多い程良いという単純なものではない。製品開発の一連のプロセスにおいても「ある程度質が高くかつ数の多い集団から選出される」、つまりある程度質の高い「絞り」プロセスを経ているかが重要となる。さらには、その「絞り」プロセスが、研究開発段階から市場化へ至るまでの全体の流れを俯瞰し、無駄なく効率化されたマネジメントの中で実施されているかが重要となる。
製品開発プロセスのそれぞれのフェーズにおいて、このような「絞る」プロセスを効率よく実施することの重要性を示唆した事例を、開発プロセスの順に沿って紹介する。紹介する事例はそれぞれ独立した内容(全く異なる文献からの引用)であるが、大手製造業企業などの場合、これら各フェーズのプロセスを自社内で一貫して実施している場合が多い(近年では一部をアウトソーシングすることも盛んである。本コラム「第4回」参照のこと)。最後に製品開発全体を俯瞰し、無駄のない効率化されたマネジメントの重要性について私見を述べたい。
(2)研究開発フェーズにおける「絞る」プロセスについて
以下は「展望論文:日本の技術経営」(榊原[2003])の内容の一部をまとめたものである。
慶應大学榊原清則教授は、日本の研究開発プロジェクトマネジメントについて、目的志向というよりはプロセス志向であるということ、ステージゲートモデル(注1)にみられるようなシステマティックな手法よりも「目利き」と呼ばれる特定個人の判断を重視しがちであること、外部資源重視というよりは社内資源重視(NIH:注2)であるということなどを挙げ、その最も特徴的な最重要項目として、北米に見られる「多産多死」的な研究開発マネジメント方法に対して日本の「少産少死」的なマネジメント方法について述べている。同教授は、研究開発のプロセスをパイプラインの形状に例え、前者を「漏斗型」、後者を「ストロー型」と表現している。
(注1) 「ステージゲートモデル」:McMaster大学のCooper 教授によって提唱された技術マネジメント手法で、研究開発から製品開発に至るプロジェクトを効率的、効果的に管理するためのプロセスを示す。ステージゲートには基本的に4から6のステージとゲートから成る。各ステージ内は機能横断的である。
(注2) 「NIH」:Not Invented Hereシンドロームのこと。"我々のところで発明されたものではない"とする考え方で、自社の研究開発結果だけに価値を認め、他からの技術、ノウハウを導入することを拒む傾向にあること。
つまり、研究開発プロジェクトを進める上では、「幅広く」プロジェクトに着手し、ある一定期間後に「絞る」プロセスが必要で、これをパイプラインの形として「漏斗型」であるとしている。これに対して日本の研究開発スタイルは、プロジェクト着手を慎重におこない、一旦プロジェクトが進み出した後は、できるだけ止めないという取り組み方が多い。この場合パイプラインの形状として「ストロー型」であるとしている。
【図表】 プロジェクトマネジメントの特徴、研究開発のパイプライン 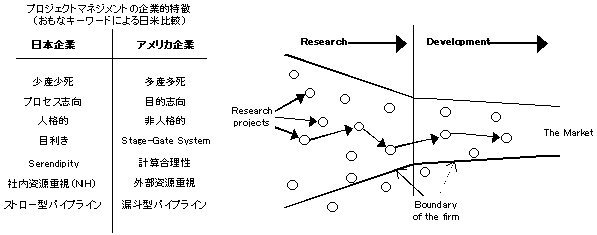
(出所) 技術革新型企業創生プロジェクト(ルネッサンスプロジェクト)「10・15シンポジウム」慶應大学榊原清則教授発表資料から抜粋
この形状の違いは、イノベーション的要素が重要となるような「技術フロンティア領域」では深刻な問題であることを指摘している。
(3)製品開発フェーズにおける「絞る」プロセスについて
以下は『製品開発の変革ソリューション、IPD革命』(廣瀬他[2003])の内容の一部をまとめたものである。
IPD(Integrated Product Development)とは、1993年から始まったIBMの企業変革における再生戦略の一つとして実践された統合製品開発プロジェクトのことである。IBMは90年代初期に起こった3年連続赤字という経営危機を脱出すべく、リストラクチャリングに始まり、すべてのビジネスプロセスを対象としたリエンジニアリング、そしてネットワークを最大限活用するeビジネストランスフォーメーションなど、様々な変革を実施してきた。IPDもこれら変革の中の重要なプロセスの一つとして機能してきた。開発投資、開発体制、開発プロセス、プロジェクト管理、業務の仕方、ITツールなど、製品開発プロセスに欠かすことのできない重要な要素を一つのプラットフォーム上で実現し、さらには開発組織文化および開発技術者の意識を根本的に変えることを目的とする。
『市場で最も受け入れられる商品領域の開拓を決定し、商品の開発を企業にとって事業の視点で最も迅速、かつ効率よく行うために、製品の構想化から終了までの期間にわたり、開発投資・開発プロセス・開発体制・ITを統治する統合マネジメントシステムである』(廣瀬他[2003])
IPDの開発プロセスは6つのフェーズと4つの意思決定チェックポイントからなる。各チェックポイントにおいて継続の可否(GOまたはNO GO)が判断される。つまり、ある程度早い段階(構想DCPや計画DCP)で有望なプロジェクトのみに淘汰される(絞られる)仕組みが構築されており、全体として開発効率の向上に大きく寄与するシステムとなっている。また、プロジェクト一連の流れを製品ライフサイクルとして管理することが可能となり、全体的な開発スピードの短期化にも寄与する。
【図表】 IPDの開発プロセス 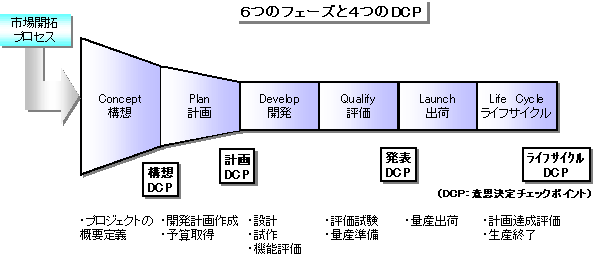
(出所) 廣瀬貞夫、日本IBM㈱IPD研究チーム編『製品開発の変革ソリューション、IPD革命』(2003年、工業調査会)から抜粋
(4)マーケティングフェーズにおける「絞る」プロセスについて
以下は『コア・コンピタンス経営―未来への競争戦略』(ゲイリー・ハメル他[2001])の内容の一部をまとめたものである。
将来性のある市場を切り開くにはどのように製品やサービスの特徴を形づくり、どのような価格設定でどの販売チャンネルを通せばよいのか、これらを事前に知ることは非常に難しい。いずれもマーケティング戦略を検討する際には非常に重要な情報である。一方で、新製品や新サービスのコンセプトに基づいて行われた市場調査が不正確なことは良く知られている。市場調査は既存の製品コンセプトを改良するにはとてもよいツールだが、企業が新しい市場をターゲットとして開発を進めているときには、ほとんど役に立たないことが多い。
ではいったいどのようなアプローチが新しい市場を切り開くために有効なのであろうか。ゲイリー・ハメルらは『コアコンピタンス経営』の中で、「探検的マーケティング」という手法について述べており、できるだけ早く市場理解を深めていきたいならば、コストを抑えながらペースの早い市場参入を繰り返さなければならない重要性を示唆している。
「探検的マーケティング」とは「霧の中で矢を射る」ことをイメージすると理解しやすい。はるか先の霧の中の的にめがけて矢を射る場合、2つの選択肢が考えられる。
◇ 霧が晴れるまで待ち、的が見えてから矢を放つ
◇ 霧中であっても複数の矢を放ち、毎回どこにあたったかフィードバックを得てから次の狙いを定める
前者は、新市場が本当に存在していることをライバル会社が証明してくれるまで待つことを示す。この場合、霧が晴れ、的が見えた時にはすでに多くの矢が的に刺さっている場合が多い(つまり手遅れの状況)。後者が探検的マーケティングのアプローチに相当する。この場合、ある程度手探り的なアプローチとなるため「無駄な矢」というコストが生じてしまう。しかしながら、できるだけ早期に矢を放つ方向性が定まる(絞られる)ため、先行者受益が大きいような市場では有効な手段となりうる(下図表参照)。
【図表】 探検的マーケティングのイメージ 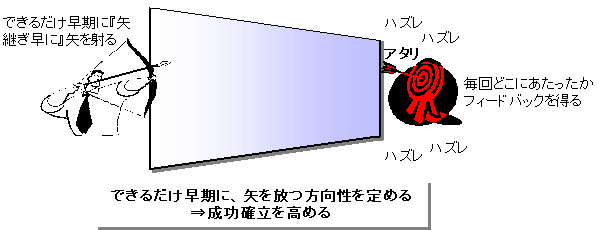
(出所) ゲイリー・ハメル他『コアコンピタンス経営』の内容を基に日本総合研究所作成
手探り的なアプローチとはいえ、探検的マーケティングは信念を支えに盲目的にジャンプすることでは決してない。製品化の反復を通じて、顧客の需要や真の欲求を取り込んでいくことに重点を置いたアプローチである。「研究所や製品開発プロジェクトの会議で学ぶことはあまり多くはない」、「本当にわかってくるのは、仮に不完全であったとしても製品やサービスが市場に出されたときからである」といった声はよく聞かれる。全ての市場に探検的マーケティング手法が適応可能とは限らない。しかしながら、製品反復の時間とコストが抑えられるのであれば、ライバルに先んじて矢を射る事が有効となろう。
(5)製品開発全体を俯瞰した「絞る」マネジメントの重要性について
ここまで「研究開発」、「製品開発」、「マーケティング」の各フェーズにおける「絞る」アプローチの事例を紹介した。これらは製品開発一連の流れの中における重要なフェーズのうちのいくつかを取り上げたものであるが、ここに取り上げた以外のフェーズにおいても「絞る」アプローチが重要となる場面は多々存在するはずである。さらには、大手製造業企業の場合、これらの各フェーズを自社内で一貫して実施しなければならない場合が多い(下図表参照)。
【図表】 一貫した「絞り」 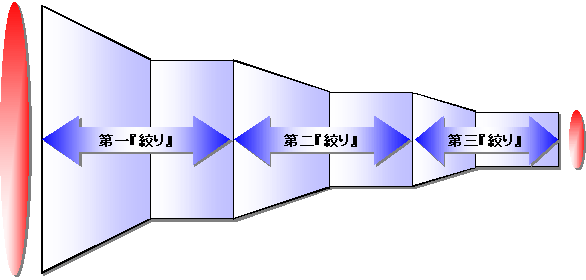
(出所) 日本総合研究所作成
このような一貫した「絞り」のプロセスにおいては、研究開発段階から市場化へ至るまでの全体の流れを俯瞰し、無駄なく効率化されたマネジメントの中で実施されているかどうか、ということが重要となる。例えば、研究開発フェーズでの「絞り」と、製品開発フェーズでの「絞り」が全く独立に実施されているようでは全く意味がない。
【図表】 うまく連鎖されていない「絞り」 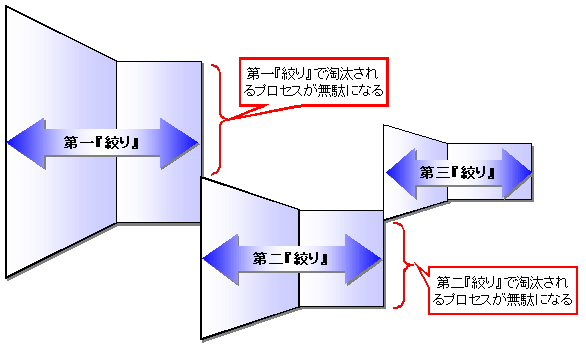
(出所) 日本総合研究所作成
第一段目で淘汰されるプロセスが次の第二段目に全く反映されていないことになる。理想的には、第一段目で絞られた項目を対象として、第二段目の「絞り」が実施され、さらに第三段目では第二段目に絞られた項目を対象とする、という具合に上流で淘汰されるプロセスを無駄にしないマネジメントが必要となる。
(6)上流の「絞り」プロセスほど重要
このような、上流で淘汰されるプロセスを無駄にしないマネジメントがなされた場合、上流の「絞り」ほど重要度が高くなる。例えば、A~Eまでの5つの項目から、第一段目の「絞り」でA、B、Cの3つに絞られたと仮定する。この場合、第二段目以降の下流プロセスでは、この3つの項目A、B、Cのみが対象となる。仮に、第一段目の「絞り」プロセスが不十分で、真の解がD、Eに含まれていたとするならば、第二段目以降の下流域においてA、B、Cを対象にどのような精緻な「絞り」を実施したところで、真の解には到達できないことになる。ある程度直前の「絞り」プロセスであれば、さかのぼって絞り直すことも可能であろうが、はるか以前に実施された上流の「絞り」プロセスの再実施は難しい。
近年、日本における研究開発の効率性について議論されることが多く、その効率性が低下していることを指摘する議論が盛んである。これは製品開発プロセスの中で上流に位置する研究開発の対象を「絞る」ことがいかに難しいか、ということを如実に表している。
このように、「絞る」プロセスが非常に重要となる研究開発フェーズにおいては、「真の解」を見過ごさないためのなんらかの工夫が必要となる。例えば、下流のプロセスの選択肢として、一度上流で淘汰された(除外された)項目の一部を再検討するといった方法(敗者復活のプロセス)も考えられる。これ以外にも、研究開発における不確実性に動的に対応し、対象となる技術の重要度を柔軟に認識することにより「絞る」プロセスを効率的に実施する、という方法も考えられる。
後者の方法は、技術そのものに関連する不確実性だけでなく、周囲のビジネス環境など様々な要素を考慮することにより、対象となる技術の重要度を時間軸に沿って動的に捉えることを特徴とする(詳細は(浅川[2004])参照のこと)。従って、ある時点で完全に絞ってしまうという危険を回避することができる(下図表参照)。
【図表】 ダイナミックな「絞り」 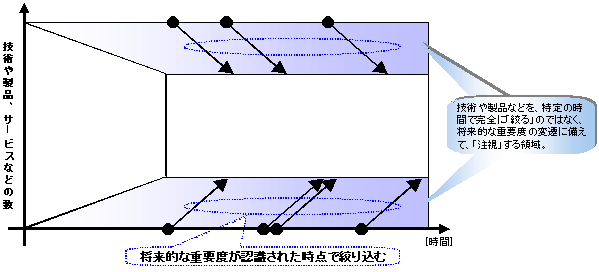
(出所) 日本総合研究所作成
(7)まとめ
製品開発の各フェーズにおいて、効果的に「絞り」を実施することが重要となる。また、大手製造業企業のように一貫した「絞り」プロセスが全体にわたって必要な場合は、研究開発段階から市場化へ至るまでの全体の流れを俯瞰し、無駄なく効率化されたマネジメントの中で「絞り」が実施されているかどうか、ということが重要となる。さらに、「絞り」のプロセスは上流で実施されるほどその重要度が増すため、対象となる技術の重要度を「動的に扱う」といったような対応が必要となる。
「動的に扱う」ためには、技術的な側面だけから当該技術の重要度を判断するだけではなく、その製品がリリースされる予定の市場状況はもちろんのこと、その他のビジネス環境なども含めた総合的な判断を下していかなくてはならない。このためには、技術部門(研究開発部門や製品開発部門など)のみといった狭い範囲内で当該技術を判断するのではなく、営業部門をはじめ、製品開発に携わる幅広い関係者の意見を取り入れることが重要となる。そのためには具体的な「仕組み」が必要となり、さらにはその「仕組み」を効率的に運用するための「組織作り」が必要不可欠となる(「仕組み」や「組織作り」については、以降の本コラム内で紹介予定)。
● 参考文献
◇ 榊原清則「展望論文:日本の技術経営-研究開発は経営成果と結びついているか-」技術革新型企業創生プロジェクトDiscussion Paper Series#03-01(2003年10月)
◇ 廣瀬貞夫、日本IBM IPD研究チーム編『製品開発の変革ソリューション、IPD革命』(2003年、工業調査会)
◇ ゲイリー・ハメル、C.K.プラハラード『コア・コンピタンス経営―未来への競争戦略』(2001年1月、日経ビジネス人文庫)
◇ 浅川秀之「シンクタンクの目(研究開発の不確実性に動的対応)」『日本工業新聞』(2004年1月23日記事)

