第6回 「同一組織内における競争的開発環境づくりのすすめ」
2004年4月2日 浅川秀之
(1)インテルのマイクロプロセッサ企業としての成り立ちは輝かしい成功か!?
「インテルをDRAM企業からマイクロプロセッサ企業に変身させたのは、資源配分プロセスだった。インテルの目覚しい戦略転換は、重役たちが練り上げた意図的な戦略の所産ではなく、中間管理職が日常的に資源配分を行ううちに下した、数々の決定を通じて明らかになったのである。」
―クレイトン・クリステンセン、マイケル・レイナー『イノベーションへの解』(2003年12月、玉田俊平太監修、翔泳社)P.266から抜粋―
インテルの一例は、特に日本の一般的な製造業企業の研究開発戦略に関する組織論的な考察を行う際に、非常に示唆的である。インテルのDRAM企業からマイクロプロセッサ企業への変遷は、成功例として称えられることが多い。しかし、少し厳しい見方をすると、DRAMの基礎技術が発見されてからその真の重要度が認識されるまでに長い年月を要したことに対して、「15年もの間なにをもたもたしていたのか」という捉え方もできる。もう少し具体的にいうと「もっと早くマイクロプロセッサへの変革ができたのではないか(機会損失の問題)」、「この間有力な競合他社がたまたま登場しなかっただけではないか(競争環境の問題)」といった考え方である。
約15年という長い歳月を要した理由はなにか。それはまさに上記抜粋中の「資源配分を行ううちに下した、数々の決定」、つまり「資源配分のプロセス」に起因するところが大きいのではないかと推測される。
(2)「資源配分のプロセス」とは
資源配分のプロセスによって当該組織に何ができるか、できないかが篩(ふるい)にかけられる。この際に重要となるのが篩で選別する際に用いられる「価値基準」である。特に規模の大きな製造業企業における価値基準は次の2点に起因するところが大きいとされる。「粗利益率が許容範囲にあるかどうか」および「事業規模が許容範囲にあるかどうか」という2点である。
新規にリリースされる製品などのように、製品ライフサイクルの初期に位置する製品の場合、垂直統合的な開発体制がとられることが多い。また、部品の汎用化や標準化が進んでいないことなどに起因して、粗利益率が低いことが一般的である。このような利益率の低い新規事業に対して経営陣がなかなかGOサインを下せない状況は容易に想像できよう。
また、企業の株式総額は、予想される将来収益を現在価値に割り引いて判断されることが多い。例えば、25%という成長率を謳う年間売上が4,000万円の企業は、翌年の売上を1,000万円伸ばすだけでよい。しかし、年間売上が4,000億円の企業が25%成長するためには、1,000億円の増収が必要となる。従って、経営陣が旨みを感じるのは1,000億円の増収に直接的に貢献する事業である。必要とされる増収額に対してほとんど貢献できないような新規事業に対して経営陣がGOサインをなかなか下せない状況も容易に想像できよう。
上記の2点が一般的な大企業の「資源配分プロセス」における価値基準であるとされている。2つの価値基準をクリアするためには、高利益率でかつ売上の数十%に貢献するような新製品を、開発当初からリリースしなくてはならないことになる。
インテルの場合、新技術であるマイクロプロセッサが、開発当初から高利益率を誇っていたわけではない。当時は、コア事業であったDRAMの方がより魅力的な利益率や売上比率を持っていた。従って、当時の「資源配分プロセス」においては(2つの価値基準に照らし合わせてみても)、マイクロプロセッサを魅力的な事業と判断することは難しかった。しかしながら、PCを牽引役とし、マイクロプロセッサ市場の環境が徐々に変化していき、やがてはマイクロプロセッサの方がより魅力的な利益率かつ高売上比率を達成するに至った。資源配分プロセスは、この間約15年という長い歳月を要し、ようやくマイクロプロセッサを魅力的な事業と判断するに至ったことになる(下図表参照)
【図表】 新しいS字カーブへの移行の難しさ 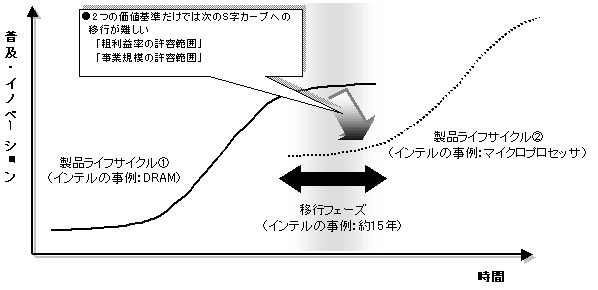
(出所) マイケル・L・タッシュマン他『競争優位のイノベーション』(1997年、ダイヤモンド社)を基に日本総合研究所作成
当初のインテル経営陣はDRAMが技術の牽引役であり、DRAM市場で競争力を維持することが、その他の製品ラインで競争力を保つために不可欠だと確信していた。つまり、当時はマイクロプロセッサを魅力的だと経営陣は考えていなかった。1984年になるとインテルは財政危機に陥り、インテルの総生産に占めるDRAMの割合はほんのわずかにまで落ち込み、このような状況になって初めてインテルの経営陣は自社を「マイクロプロセッサ企業」であると認めたのである。
(補足) ここまでの「資源配分プロセス」に関する記述は、クレイトン・クリステンセン、マイケル・レイナー『イノベーションへの解』(2003年12月、玉田俊平太監修、翔泳社)の内容を一部抜粋、もしくは要約したものである。
「粗利益率が許容範囲にあるかどうか」および「事業規模が許容範囲にあるかどうか」という資源配分プロセスにおける価値基準が不必要であるといっているわけではない。一企業体として粗利益率や事業規模を無視したような研究開発に対して巨額の投資を施すことは許されない。特に、既存製品群の漸進的な機能向上に寄与するような開発においては、粗利益率が適正かどうか、事業規模が適正かとうかといった判断は非常に重要となる。しかしながら、全くの新規開発製品が、リリース当初から高い利益率や大きな事業規模を実現できることは通常ありえない。従って、将来的に可能性を秘めた新技術に対してはある程度と開発投資を続けなければならないにもかかわらず、この2つの価値基準だけでは、破壊的な新技術を涵養することができないことになる。2つの価値基準だけでは、次のS字カーブへのスムーズな移行が実現しにくいということである。
(3)新しいイノベーションへの移行がなぜできないのか
なぜ新しいS字カーブへの移行が難しいのであろうか。その理由は実は簡単で「次のS字カーブが的確に見えていないから」ということではないかと思われる。ただし「的確に見えている」ということは、「合理的な裏付けや理由付けが成された次のS字カーブが見えている」ということであり、単純な類似ケースの外挿や安易な推測だけで、将来のS字カーブを見定めるということではない。当該技術や製品に関する技術的な知識はもちろんのこと、市場動向や競合他社状況、さらには社会・経済・政治的な要因(いわゆるSEPTEmber[Society、Economy、Politics、Technology、Ecology]のこと。世の中の変化動向を読み取る際の標準的なフレーム)も考慮し、総合的な判断によってKSF(キー・サクセス・ファクター)を見極め、新しいS字カーブを決定していかなければならない。
当然のことながら、下図表中の左側のように次のS字カーブがはっきりと見えている、つまり将来の普及の様子が明確かつ的確に分かっているのであれば、次のS字カーブへの移行を躊躇する人はいない。しかしながら、同図表中の右側のように次のS字カーブが定かではない、つまり将来その技術や製品は普及するのかしないのか不明確な状態である場合は、次のS字カーブへの移行に反対する人が大多数であろう。
【図表】 新しいS字カーブの将来性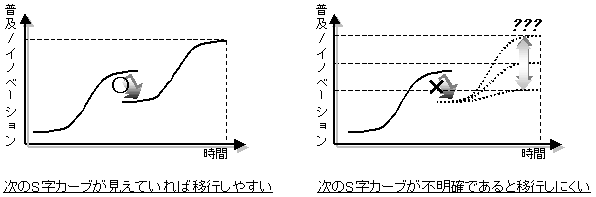
(出所) 日本総合研究所作成
それでは、新しいS字カーブは誰がどのように描くべきなのであろうか。まずは、当該技術や製品を開発した張本人が描くべきであろう。しかしながら、これまでの一般的な日本の研究開発環境化下においては、自らが開発した技術や製品をエンジニアや研究員が積極的に売り込んでいくといった習慣はほとんどみられない。近年では、自らの研究開発成果の対価を積極的にアピールする事例も増えている。しかしながら、研究開発者自らが積極的にS字カーブを描き、その有望な将来性をアピール習慣はまだ十分に浸透していないのではないであろうか。これは、ひと昔前までは「研究開発部門は神聖な場であり、経営陣ですらその内部事情を完全に把握することができない閉ざされた環境である」といったような状況が続いたことが影響を及ぼしていると考えられる。近年は、研究開発の効率性や技術評価手法などといった、研究開発そのもののあり方やそのアウトプットのについての議論が盛んになってきており、ようやく「閉ざされた環境」が開放されようとしている。このような閉ざされた研究開発環境からの開放に伴い、研究開発者担当者自らが積極的に新しいS字カーブを描く必要性がよりいっそう増してくるであろう。
(補足) 全ての研究開発対象に対して「S字カーブ」を描くべき、といっているわけではない。研究開発とはいっても、学術的に重要なもの、科学の進歩に貢献するもの、自然の摂理を解明するものなどのように、いわゆる基礎研究的分野に属するものから、具体的な製品開発に至らしめることを目的とした応用研究分野に属するものなど、その分類は様々である。本稿において対象としている研究開発とは、主に後者の応用研究分野に属するものを想定している。
新しいS字を描く際に重要となることは、開発担当者だけで判断を下すのではなく、関係するマーケターや経営陣などの判断も取り入れた上でS字カーブを描くということである。開発担当者が描いたS字カーブは、当該製品市場に明るいカリスマ的マーケターにとっては「絵に描いた餅」であるかもしれない。また経営陣の目からみた場合、全社的計画やビジョンなどからは遠く逸脱したものであるかもしれない。同一組織内においても、当該技術や製品の将来動向については、それぞれの立場から様々な意見や予見が持たれることが推測される。このような様々な立場からの意見や予見を酌みした上で、次のS字カーブを描き、その上で移行の可否を判断することが重要ではないであろうか。
一般的に、当該技術や製品を開発した開発担当者自身は、なんとか自分の開発した技術が普及するようにと、「上向き(過大)評価」しがちである。これに対して経営陣(CTOなども含め)やマーケターをはじめとする経営側スタッフは、数々の失敗例に遭遇した経験や、近年のような市場の不確実性や厳しさなどを痛感していることから、当該製品や技術に対しては「下向き(過小評価)」しがちである。これら相対する両意見を取り入れることにより、より精度の高い真のS字カーブを描くことができる。
【図表】 真のS字カーブを描く 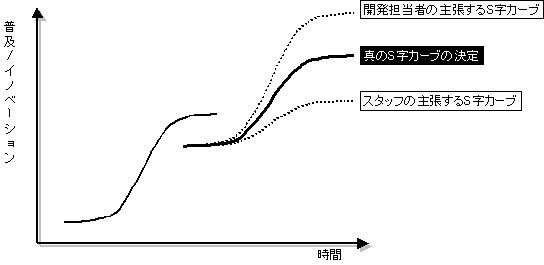
(出所) 日本総合研究所作成
現在の日本における製造業企業の一部は、このような「真のS字カーブを描くプロセス」が非常に曖昧であると考えられる。このような企業では、開発担当者だけでなく、マーケターなどのスタッフも交えた徹底的な議論の後に真のS字カーブを描くという習慣がほとんどない。この「プロセスの曖昧さ」がまさに、新しいS字カーブへの移行を阻害する原因であり、既存の技術や製品への非効率な固執を生み出す要因の1つとなっている。
(4)「真のS字カーブを描くプロセス」が曖昧であることの弊害
新しいS字カーブが描けていないということは、同一組織内において「この技術、製品は有望である」という意見と「この技術、製品は有望でない」という2つの相反意見が共存したままの状況を表す。このような曖昧な状況では新しいイノベーション、破壊的な技術への移行は難しい。これはまさに「【図表】新しいS字カーブの将来性」の右側に示すように「次のS字カーブが見えていない」状況である。「見えていない」ということは、経営陣にとっては新しい技術や製品に関する情報が十分でない限定された状況であることに他ならず、このような限られた状況の中で新しいS字カーブへの移行判断を下していかなければならない。
菊澤研宗[2000]は、人間はこのような限定された情報の中においては意図的に合理的にしか行動できないという「限定合理性」について述べている。人間は情報収集能力に限界があるため、ある判断を下す際には、その判断に必要な全ての情報を完全に獲得することはできないことを前提とし、このような前提のもとには、人間は意図的に合理的にしか行動できないとしている(新制度派経済学アプローチの特徴)。さらに、この限定合理性に起因し、例え現状の既に施行されている戦略や行動が非効率で不正であったとしても、組織や個人はなおその戦略や行動をとり続けることが合理的になるといった不条理に導かれることを指摘している。今現在選択している戦略よりも、より良い戦略が見つかったとしても、容易に乗り移ることができないということである。研究開発戦略においては、今現在のS字カーブから次の新しいS字カーブへ「移るに移れない」というジレンマに相当する。
この「移るに移れない」という状況は、新制度派経済学を構成する理論の1つである「取引コスト理論」によって説明が可能となる。
【図表】 不条理に陥るパターン、不条理を回避するパターン 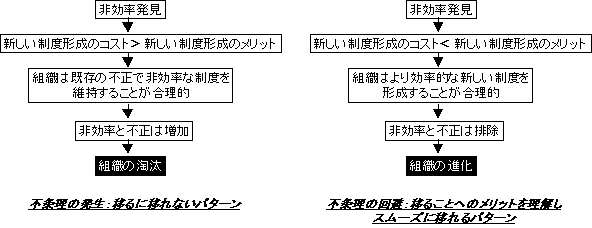
(出所) 菊澤研宗『組織の不条理』(2000年11月、ダイヤモンド社)から抜粋
現在進行している戦略を変更するためには一般に多大な「取引コスト」がかかる。新しい戦略に変更することによって得られるメリットよりも、変更に必要なコストの方が大きいならば、たとえ現在の戦略が非効率で不正であったとしても組織はなおその行動をとり続けることが合理的になる(不条理の発生:移るに移れないパターン)。さらに、この場合組織内部で発生する非効率や不正は排除されず、時間とともに絶えず増加し続けることになり、結果的にこのような組織は淘汰されることになる。
反対に、新しい戦略に変更することによって得られるメリットが、変更する際に必要なコストに比して明らかに大きいような場合は、スムーズに新しい戦略への移行が可能となる(不条理の回避:移ることへのメリットを理解しスムーズに移れるパターン)。
次の新しいS字カーブが見えていないという状況は、人間や組織のもつ限定合理的であるがゆえに発生する状況と考えられる。このような状況下においては新しいS字カーブへ移行するためのコストが非常に大きく、結果として現在のS字カーブから抜け出すことができなくなってしまう。
(5)不条理を回避する組織とは
菊澤研宗[2000]は、組織が不条理を回避するためには、人間が限定合理的であり、人間が常に誤りうることを自覚しているかどうかが重要となるとしている。人間は限定合理的であり、それゆえに常に非効率や不正が発生しうることを意識し、絶えずその非効率や不正を排除するような流れを作る「批判的合理的構造」を組織が具備することが重要であると指摘している。
「批判的合理的構造」を図式化すると下図表(上段)のようになる。批判的合理的構造を具備する組織では、どんな戦略も決して完全なものではないというスタンスをとる。したがって、既存の戦略をめぐって常に批判的議論が展開され、もし既存の戦略に非効率や不正な行動が多く発生しているならば、それが問題として取り上げられる。その結果、問題を解決するための新たな複数の戦略が考案される。新しい戦略のうちどれを選択するかは、再び「新しい制度形成のコスト」と「新しい制度形成のメリット」を天秤にかけることにより判断される。このように、組織は常に非効率や不正を排除しながら進化していくことが可能となる。それに対して、同一組織内でとられる戦略に対しては常に正当化する傾向のある組織については、結果的に非効率や不正が増大していき、最終的には淘汰されることになる(同図表下段)。
(補足) ここまでの「組織の不条理」に関する記述は、菊澤研宗『組織の不条理』(2000年11月、ダイヤモンド社)の内容を一部抜粋、もしくは要約したものである。
【図表】 進化する開かれた組織と淘汰される閉ざされた組織 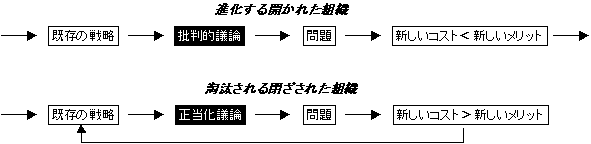
(出所) 菊澤研宗『組織の不条理』(2000年11月、ダイヤモンド社)から抜粋
菊澤研宗[2000]が示すように、常に批判的な環境を作り出すことにより非効率や不正を排除することが可能であるという指摘は、新しい次のS字カーブへスムーズに移行する際には重要となる。しかしながら、批判的議論環境を当該組織が持ち合わせているだけでは、不連続なイノベーションへの対応は十分でない。当該組織の現時点での組織形態や研究開発環境に合わせて、具体な仕組みを構築しなくてはならない。
(6)真のS字カーブを描ける組織とは:同一組織内における競争的開発環境づくりのすすめ
日本の製造業企業に在籍する多くの研究開発者は、その技術力や知識などにおいて、世界的に評価が高い。さらに、特に大企業の研究開発現場では、優秀なエンジニアや研究者が同一組織内においても非常に多く存在する現状がある。しかしながら、優秀な研究開発者が多数存在するような環境下においても、次のS字カーブへスムーズに移行できる企業は非常に少ないという現実が存在する。
次のS字カーブへの移行がスムーズに行われない理由は様々であるが、主な理由の1つに「同一組織内における競争的開発環境の欠如」があげられるのではないであろうか。同一組織内に競争的開発環境を築き上げることにより、必ずしもイノベーションに強い研究開発組織が形成できるというわけではない。競争的な環境以外にも様々な必要条件が存在するであろう。しかしながら、特に従来型の漸進的技術開発を主とする製造業企業や、長年の間ある特定顧客のベンダーとして開発に従事してきた製造業企業などの場合、同一組織内において競争的な環境を築いている可能性は低く、このような企業に対して意識的に競争的な開発環境を構築することは、柔軟な組織造りに大きく貢献すると考えられる。同一組織内において切磋琢磨する競争的開発環境を構築し、菊澤研宗[2000]がいうところの批判的合理的構造を組織に具備させることは、変化の激しし市場に柔軟に対応可能な組織を形成するための有効な手法の1つであると考えられる。
以下において、同一組織内における競争的な開発環境づくりの一例を紹介する。下図表は、その仕組みを模式的に示したものである。
【図表】 同一組織内における競争的開発環境 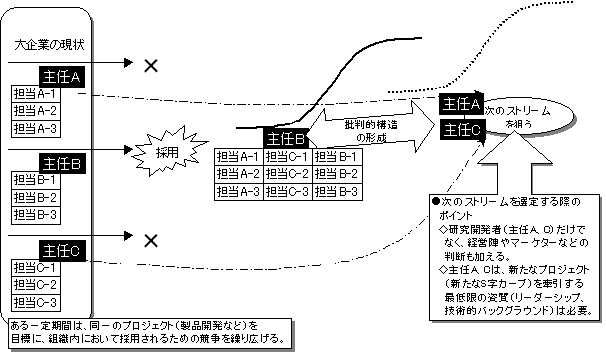
(出所) 日本総合研究所作成
ある製品開発をターゲットとしたプロジェクトを立ち上げることを想定する。基本的な上流仕様の検討から始まり、徐々に開発工程が進んでいくが、この初期の開発段階において、複数のグループによる競争環境を構築する。上図表の例では、主任A~Cまでの3グループが同時に、同一の製品開発をスタートしていることを示す。そして、ある段階でその3つのグループを適切に評価し、実際の製品化に至らしめる1グループを採用する(図中では主任Bグループを採用)。その後、採用されなかった残りの2つのグループ(主任A、Cグループ)に属する担当者は、採用された1つのグループ(主任Bグループ)に合流し、採用された開発の推進に加勢する。採用されなかったグループのこれまでの工数は無駄になるではないかという意見もあるであろう。しかし、合流する担当員は、リーダーは違えども、これまで同一の目標のもとに基礎的な研究開発に従事してきているので、キャッチアップは容易である。さらに主任Bグループにはない新たな視点で開発に携わることができるというメリットもある(以前のグループで培われた良い部分のみ反映できる)。採用されなかったグループのリーダー(主任A、C)については、一部は採用された研究開発グループに合流することもあるが、基本的には次のS字カーブ(ストリーム)を狙うことに注力する。この際にポイントとなるのが、採用されなかったグループのリーダー(主任A、C)は、採用された既存のS字カーブに対して批判的評価が可能な素地を持っているということである。さらには、主任AおよびCの意見のみだけでなく、経営陣やマーケターなど競争の外部的な環境(市場環境など)を熟知した有識者の意見も交えて、真のS字カーブを決定することが可能となる。
ここまで述べてきた仕組みは、新しいイノベーションへスムーズに移行するための組織論的な手法の1例を、そのアウトラインについてのみ示したにすぎない。実際にこのような仕組みを導入する際には、各個別の企業に適した施策を綿密に検討する必要がある。特に、研究開発におけるリソースのアサイン判断を行う場合(上記の例で主任Bグループの採用を判断するような場合)には、各企業組織の状況に即した「人材ポートフォリオ」的なアプローチを適用することが、変化の激しい研究開発環境下においては今後より一層重要となってくると考えられる。
「人材ポートフォリオ」的なアプローチについては第7回のコラムを参照頂きたい。
(7)最後に
ここまで、国内外の有識者の理論や示唆などを引用し、同一組織内における競争的開発環境の有効性について述べてきた。本稿における分析は「一部の製造業の研究開発部門には、同一組織内における競争的な環境が少なすぎるのではないか」という筆者の素朴な疑問に端を発している。勿論、全ての製造業における研究開発部門当てはまることではない。従来型の漸進的技術開発を主とする製造業企業や、長年の間ある特定顧客のベンダーとして開発に従事してきた製造業企業の一部に見受けられる現象である。このような企業においては、同業他社を意識した「外部との競争」は日常茶飯事であっても、同一組織内における「内部での競争」は意識されていないことが多い。「身内との競争を意識する余裕などない」という意見もあるだろうが、「身内との競争にすら勝てないのに、世界中の競合他社を相手に打ち勝てるわけがない」という考え方もある。日本の製造業の研究開発部門には1企業内においても非常に優秀なエンジニア、研究者が数多く存在する。このような環境の中で競争的に開発を進めること自体、その開発の質的な向上に貢献すること多大であろう。
● 参考文献
◇ クレイトン・クリステンセン、マイケル・レイナー『イノベーションへの解』(2003年12月、玉田俊平太監修、櫻井裕子訳、翔泳社)
◇ マイケル・L・タッシュマン他『競争優位のイノベーション』(1997年11月、斎藤彰悟監訳、平野和子訳、ダイヤモンド社)
◇ 菊澤研宗『組織の不条理』(2000年11月、ダイヤモンド社)

